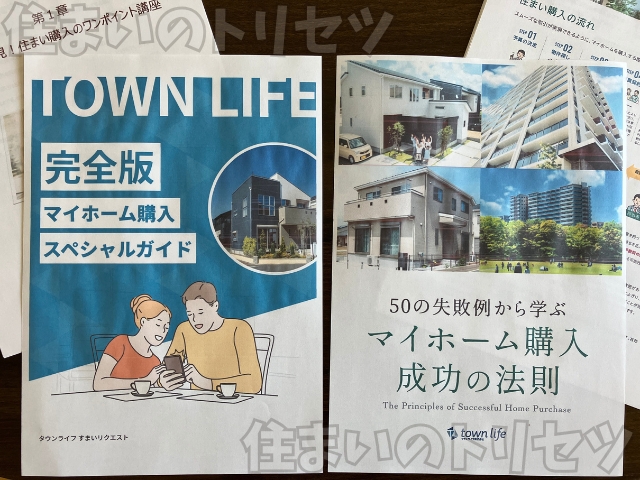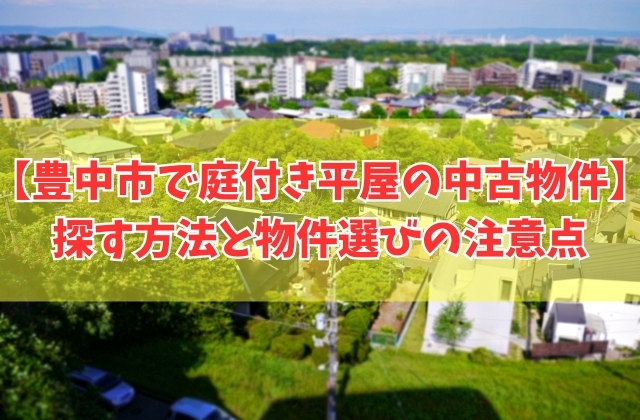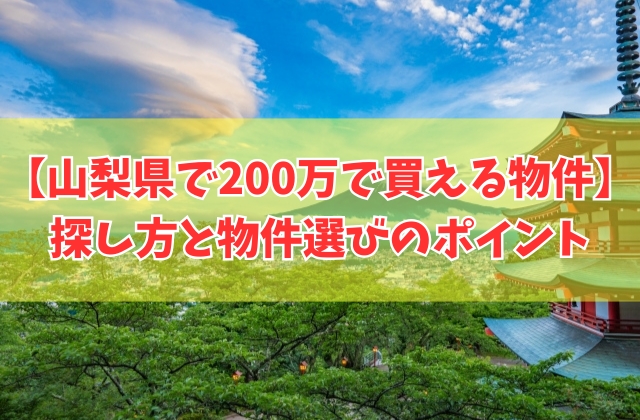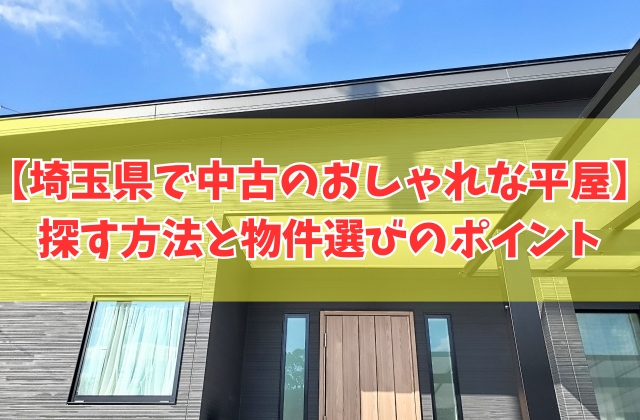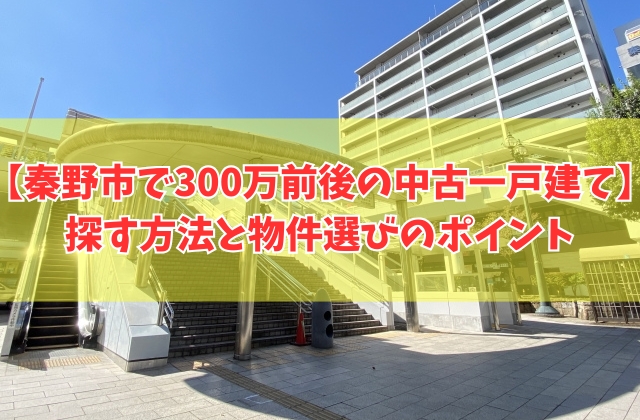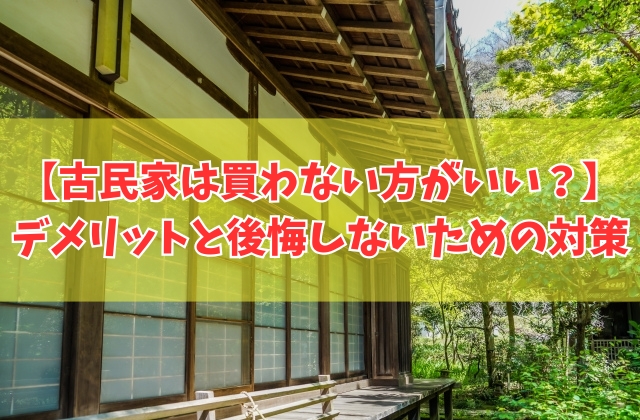
「古民家は買わない方がいいってホント?」
「買った後にもリスクがある?後悔しないためにはどんな対策が必要?」
「古民家でのんびり暮らしたい」と憧れつつも、「本当に買って大丈夫なのか…」と不安に感じてはいませんか?
実際、雰囲気や価格の魅力に惹かれて購入したものの、思わぬ出費や暮らしにくさに後悔するケースも多く見られます。
なぜなら、「古民家は買わない方がいい」と言われる理由には、きちんとした根拠があるからです。
この記事では、古民家の購入前に知っておくべき注意点や判断材料を具体的に解説していきます。
古民家の購入検討、中古の物件を探している方は、ぜひ物件選びの参考にお役立てください。
- 耐震性や断熱性能が低く、安全面と快適性に不安がある
- 修繕やリフォームに高額な費用と専門的な知識が必要になる
- 立地や周辺環境によっては生活利便性が大きく損なわれる
古民家に憧れる気持ちは自然なものですが、「古民家は買わない方がいい」と言われる背景には、現実的な理由があります。
特に築年数が長い物件は、耐震性の不足や断熱材の未整備、さらにはシロアリや腐食といった目に見えない問題を抱えていることもあります。
購入を検討する際は、理想だけでなく現実的な維持管理コストや性能、立地面のリスクを事前に見極めておくことが大切です。
では、古民家や中古物件を買って後悔しないためにどんな対策が必要なのか?できれば物件情報を集めて比較できる方法があれば安心ですよね。
そんな物件を買って失敗したくない方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用する方法です。
「タウンライフすまいリクエスト」とは、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
- 非公開物件&値下げ物件の情報がもらえる!
複数社への一括依頼により、広告掲載前や値下げ前の“掘り出し物件”に出会える可能性が高まる - 物件探しの手間・時間を大幅に削減できる!
60秒の簡単入力だけで、複数の不動産会社から資料・提案が一括で届くので、自分で探す手間が省ける - 信頼できる複数の不動産会社の中から選べる!
登録企業は全国170社以上、独自基準をクリアした優良な不動産会社に限定。安心して比較・選択ができる
さらに!タウンライフすまいリクエスト利用者限定で2つの特典が必ずもらえるプレゼントを実施中!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、40ページを超える読み応えありの内容で、今後の物件探しのヒントが満載でした。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
【結論】古民家は買わない方がいい?
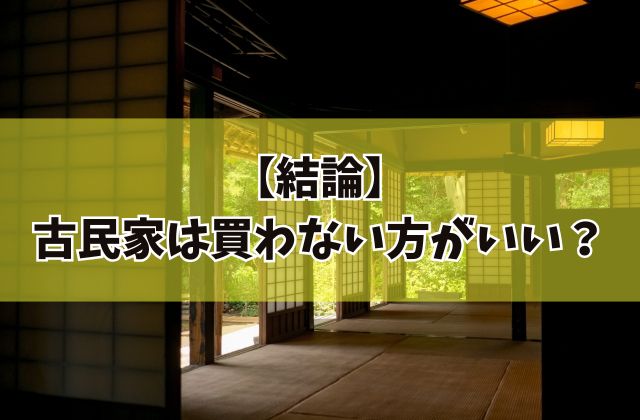
古民家は買わない方がいいのかどうか?
古民家に憧れを抱く人は多いものの、結論からいうと、現実を見れば「やめておいたほうがいい」と感じる場面が少なくありません。というのも、見た目の趣や雰囲気に惹かれて購入しても、住み始めてから次々と問題が浮き彫りになるケースが非常に多いからです。
まず知っておきたいのが、古民家の多くは断熱材が入っていません。つまり、冬は底冷えし、夏は蒸し風呂のように暑くなりがちで、エアコンの電気代が跳ね上がる要因になります。また、建築当時の耐震基準が現代と異なるため、地震が起きた際の倒壊リスクも無視できません。実際に専門家による診断で、耐震補強が必要とされる物件は珍しくないのが現状です。
さらに問題なのが、住める状態に整えるまでの手間とコストです。屋根の修繕、水回りの配管交換、柱の補強、そしてシロアリ被害の確認まで、ひとつひとつの対応に数十万円、時には数百万円単位の出費が発生します。築年数が長ければ長いほど、その傾向は顕著です。
こうした点から、もし「すぐに住める家」を求めているなら、古民家は選ぶべき物件ではありません。安さに惹かれて手を出してしまうと、後悔する可能性が高いのが現実です。もちろん、時間とお金、そして暮らしを自ら作っていく覚悟がある人にとっては魅力もありますが、万人向けではないことは確かです。
古民家の購入を考えているなら、「理想」ではなく「現実」に目を向けることが、最初の一歩になるはずです。
古民家は買わない方がいいと言われる8つのデメリット

古民家の雰囲気や趣に魅力を感じても、実際に暮らすとなると現代の生活スタイルとは合わない点がいくつも出てきます。
特に、「古民家は買わない方がいい」と言われる理由には、目に見えない構造上の欠点や、維持管理に関する費用負担の重さが深く関係しています。
ここでは、古民家購入前に知っておくべき代表的な8つのデメリットについて詳しく紹介します。失敗を防ぐためにも、一つひとつ確認しておくことが大切です。
断熱材がなく光熱費が高くなりやすい
古民家に住むと、まず感じるのが「寒さ」と「暑さ」の厳しさです。見た目の趣は魅力的でも、室内の快適さには大きな差が出ます。その原因のひとつが、現代住宅では当たり前になっている断熱材がほとんど使われていない点です。
古民家の構造は、風を通して夏を涼しく過ごすために工夫されてきたものです(出典:参考資料)。ですが、それは同時に、冬の冷気や夏の熱気もそのまま室内に入り込んでくるということ。加えて、シングルガラスの窓や隙間の多い建具も冷暖房の効率を下げてしまい、結果として光熱費が想像以上にかさみます。
実際、「断熱性が低い」と感じている古民家居住者は少なくなく、ある調査では全体の約19%がその点に不満を抱いているというデータもあります。冬場はストーブを何台も使っても寒さが残り、夏はエアコンをつけっぱなしにしても涼しさが長続きしない。こうした環境では、電気代が月に2万円を超えることも珍しくありません。
もちろん、断熱リフォームという選択肢もあります。ただ、施工費用は数百万円かかるケースもあり、簡単には踏み出しにくいのが現実です。それでも、実際に断熱工事を行った人の中には、10年~15年のうちに光熱費の削減で費用を回収できたという声もあります。
「古民家は買わない方がいい」と言われる背景には、こうした日常的な不便さや費用面の問題が根強くあります。購入前に、ただの雰囲気や価格だけで判断せず、暮らしのコストも具体的にイメージしておくことが大切です。
耐震性が基準未満で地震に弱い
古民家を買おうと考えるなら、真っ先にチェックすべきなのが「地震にどれだけ耐えられるか」という点です。築年数が古い住宅の多くは、1981年以前のいわゆる旧耐震基準で建てられており、震度6以上の大きな地震には耐えきれない構造であることが少なくありません。
実際、国の耐震診断基準によれば、旧基準の木造住宅の約8割は震度7の揺れで全壊または大破の恐れがあるとされています(出典:参考資料)。古民家は「太い柱で頑丈そう」と感じる人もいるかもしれませんが、実際には基礎が弱かったり、接合部の補強が不十分だったりと、現代の建築基準とは大きく差があります。
たとえば、築80年を超えるある民家では、耐震診断の結果、補強が必要とされ(出典:住宅・建築物の耐震化について)、改修には300万円以上の費用がかかる見積もりが出ました。しかも、こうした補強は見た目には分かりにくく、購入後に発覚するケースも少なくありません。
古民家に住むという選択肢は、ロマンや魅力にあふれている反面、安全性という現実的な課題から目をそらすことはできません。購入前には、見た目の雰囲気だけでなく、構造の中身までしっかり確認することが欠かせません。耐震補強には費用も時間もかかりますが、安心して暮らすためには必要不可欠な投資だと考えるべきです。
修繕に専門職人が必要で費用が高い
古民家の修繕は、新築や築浅の住宅と比べて、明らかにハードルが高いと言わざるを得ません。その理由はシンプルで、直すために「手間がかかる」「職人が限られる」「材料が特殊」だからです。特に、構造を支える太い梁や土壁、瓦屋根など、現代の家ではあまり使われなくなった工法や素材が多く、普通の工務店では対応できないことが珍しくありません(出典:参考資料)。
たとえば屋根。古民家に多い日本瓦の葺き替えは、それ自体が重労働なうえに、経験豊富な職人でなければ綺麗に仕上げられません(出典:かわらぶき技能士)。一部だけでも80~150万円、全体をやり直すと数百万円単位になることも。耐震補強まで含めると、全体で150~300万円ほどかかるケースも実際にあります。また、水回りの改修も油断できません。配管の引き直し、風呂やキッチンの更新まで含めると、150~250万円ほどになることも珍しくないのです。
しかも、古民家特有の“直してみないと分からない”部分が多いのも事実です。表面だけは綺麗に見えても、壁を開けたら柱が腐っていた、配線が古すぎて使い物にならなかった……そんなケースも多く、追加費用が発生する覚悟も必要になります。
つまり古民家は、安く買えても「維持するのが高い家」です。どこにどんな修繕が必要なのか、どんな職人に頼めるのか。購入前にそこまで見通せて初めて、安心して選べる物件だと言えるでしょう。魅力に惹かれる気持ちは分かりますが、工事にかかるお金と手間は想像以上です。買ってから慌てないためにも、現実的な視点での検討を忘れずに。
柱や梁の内部がシロアリに侵されている
古民家の怖さは、見えないところに潜んでいます。中でも深刻なのが、柱や梁の内部までシロアリに食われているケースです。一見すると立派な木材に見えても、いざ調べてみたら中がスカスカになっていた、という話は決して珍しくありません。
実際の調査では、267棟のうち約66%の住宅で何らかのシロアリ被害が確認され、しかもそのうち7.5%は深刻な構造損傷にまで至っていたというデータもあります(出典:日本しろあり対策協会調査)。古民家は築年数が長いぶん、湿気を含みやすい箇所が多く、床下や壁の裏で長年シロアリが活動している可能性があるのです。
被害が進行している場合、単なる駆除では済まず、柱や梁そのものを交換したり補強したりする必要が出てきます(出典:参考情報)。なかには、梁を丸ごと架け替える大規模工事にまで発展することもあります。当然ですが、その費用は高額。しかも、住みながらの修繕は難しく、一時的に仮住まいを探す必要があることも。
だからこそ、購入を検討している段階で、床下や天井裏までしっかりと専門業者にチェックしてもらうことが欠かせません。表面がキレイな古民家ほど、内部の見落としには要注意です。修繕が必要になるかどうかで、総額の見積もりもガラリと変わってきます。魅力ある物件ほど、冷静な目で「中身」を確認することが本当に大切です。
だからこそ、「この古民家、本当に大丈夫かな…」と感じた時点で、プロによるシロアリ調査を依頼するのが何より大切です。
『タウンライフのシロアリ対策』なら、無料で複数の業者から見積もりを比較でき、安心して調査を依頼できます。
将来的な修繕コストを回避するためにも、購入前のチェックが後悔しない第一歩です。古民家購入を検討している今だからこそ、見えないリスクに備えておきませんか?
天井や床下の水漏れや腐食の心配
古民家に暮らすうえで、地味だけど見逃せないのが「水のトラブル」です。特に天井や床下での水漏れは、ゆっくりと、しかし確実に家そのものを傷めていきます。
昔の配管は今と比べて耐久性が低く、しかも素材が古いものだと、知らないうちに床下で漏れが起きていることも珍しくありません(出典:報告書)。その水が木材に染み込めば、腐食やカビが進行し、シロアリの発生を招く原因にもなります。ある水道工事業者の報告では、床下の漏水が放置されていたことで、柱の土台まで柔らかくなり、交換を余儀なくされた事例もあります。
天井も例外ではなく、雨漏りが続けばやがて染みが広がり、最悪の場合は天井板が落ちることも(出典:報告書)。日常生活では見えにくい部分だからこそ、被害が広がってから気づくケースが非常に多いのです。※
こうした修繕は、単に配管を直すだけでは終わりません。傷んだ木材の入れ替え、湿気対策、場合によっては全体の配管工事まで必要になることもあります。当然、費用も数十万円単位では済まず、思わぬ出費に頭を抱える人も多くいます。
古民家を検討するなら、「水まわりは一番最後に壊れる」とは思わない方がいいでしょう。購入前の内見では床下や天井裏の点検をしっかり行い、水の痕跡がないか、腐食臭がしないかを自分の目と鼻で確かめる。これが、後悔しないための第一歩です。
古い配管や設備で水回りが使いにくい
古民家を購入して、いざ住み始めたときに「想像より不便だった」と多くの人が感じるのが、水回りです。キッチンやお風呂、トイレといった生活の基本となる場所が、古い配管や設備のままだと、今の暮らしには正直なところ使い勝手が悪すぎます。
たとえば、戦前に建てられた家では、配管の規格が現在のものと合わず、蛇口一つ交換するにも特殊な部材が必要になることがあります(出典:事例集)。築年数にもよりますが、配管の耐用年数はおよそ15~30年とされており、それをはるかに超えて使われている場合、漏水や詰まりが起きるのも時間の問題です(出典:ガイドライン)。
また、配管の劣化は目に見えない場所で進行します。床下や壁の中で水が漏れ続けて、気づいたときには床が浮いていた、クロスが剥がれていた、という話も現場では珍しくありません。ひとつ直すと別の箇所でトラブルが出てくる。そんな“いたちごっこ”に頭を抱える人も少なくないのです。
こうした水回りの全面リフォームには、部材の入れ替えから配管の引き直しまで含めて100万円を超えるケースもあります。しかも住みながら工事をするのは困難なため、一時的な仮住まいを検討しなければならないことも。。。
古民家の魅力はたくさんありますが、水回りの老朽化は「見落としやすいのに最も生活に直結する問題」です。購入前に配管の状態を確認することは、内見時のチェックポイントとして絶対に外せません。快適な暮らしを求めるなら、目に見えない“古さ”にもきちんと目を向けておくべきです。
虫やムカデが住みつきやすい環境
古民家の暮らしに憧れて移住した人が、最初に直面する現実のひとつ。それが、虫との根気比べです。特にムカデは、田舎の湿った土壌や隙間の多い木造住宅を好み、古民家のような環境には非常に馴染みやすい生き物です。
実際に、築年数の古い住宅では、床下や壁の裏、縁側の下などにムカデが潜んでいたという話も少なくありません(出典:参考資料)。特に湿度が高くなる梅雨時期から夏場にかけては、活動も活発になります。
厄介なのは、ムカデが単体で動いているわけではないことです。エサとなる小さな昆虫が多くいる場所に寄ってくるため、見えないところで他の虫も同時に発生している可能性があるのです。つまり、ひとつの虫を退治しても、環境自体を改善しない限り、根本的な解決にはなりません。
もし古民家を購入するなら、虫は“たまに出るもの”ではなく、“常に出る前提”で考えておく方が賢明です。防虫ネットの設置、隙間の封鎖、基礎の防湿、定期的な点検と駆除……このあたりをルーティン化する覚悟がなければ、快適な生活は難しいかもしれません。自然と共に暮らすということは、人だけの都合では成り立たない現実と向き合うということなのです。
病院やスーパーが遠くて不便な立地
古民家に憧れて地方移住を考えるとき、見落としがちなのが「日常のアクセス環境」です。目の前に田んぼが広がる静かな風景、澄んだ空気、鳥のさえずり——たしかに心は癒されます。でも、現実には「病院まで車で30分」「スーパーは週に1回のまとめ買い」が当たり前という地域も多くあります。
たとえば、研究報告によると、高齢者が自宅から食料品店まで1.8km以上離れて暮らしている場合、買い物へのアクセスが著しく制限され、「買い物困難層」に該当する可能性が高まることが報告されています。実際に移住してから「食材を切らすと、往復1時間」「病院に通うのがしんどくて診察を先延ばし」なんて声も多く、生活に必要なインフラが“遠い”ことは、想像以上のストレスになります。
もちろん、車さえあればある程度は補えますが、それも年齢を重ねるほど厳しくなりますし、免許返納後の移動手段を考えておかないと、途端に「住めない家」へと変わってしまいます。
古民家の魅力は、立地や環境も含めての話です。物件の雰囲気だけで判断するのではなく、「この場所で暮らしが成り立つのか?」という視点で周辺の施設や交通の便も冷静に見極める必要があります。ロマンだけでは暮らしていけない。そう実感するのは、移住後では遅いのです。
買わない方がいい?購入後に古民家に住むリスクとは
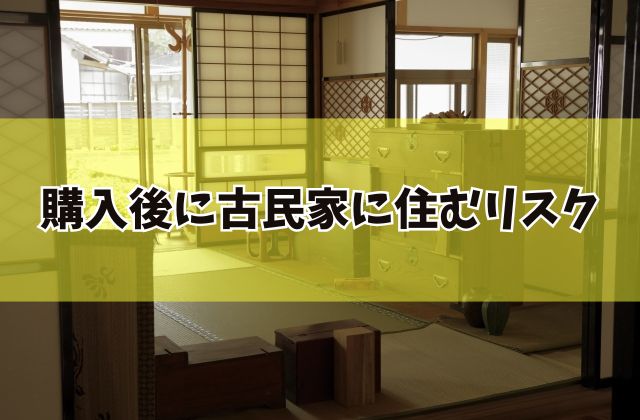
古民家は趣のある佇まいや自然との距離感に惹かれがちですが、いざ暮らし始めると想像とは違う不便さに直面することがあります。
とくに「買わない方がいい?」と悩むきっかけになりやすいのが、住み始めるまでの準備の大変さや、現代の生活に合わない間取り、地域との相性といった部分です。
ここではは、古民家を購入してから見えてくる具体的なリスクについて紹介していきます。
住み始めるまでに時間がかかる場合がある
古民家を購入したあと、すぐに新生活が始められると思っていたら、大きな誤算だった——。こうした声は少なくありません。築年数の長い古民家は、入居前に必ずといっていいほど修繕や改修が必要になります。しかも、簡単な手直しでは済まず、家全体のリノベーションが前提になることも多いのです。
実際、リフォーム工事が始まるまでには現地調査や設計プランの打ち合わせに時間がかかり、着工までに1~2ヶ月。その後の工期も含めると、住めるようになるまでに3~6ヶ月かかるのが一般的です(出典:参考資料)。しかも、古民家ならではの隠れた傷みや構造のクセが途中で見つかり、工期が延びることも珍しくありません。
「のんびり田舎暮らしを始めたい」と思っていても、入居できるまでのこの待ち時間にストレスを感じる方もいます。購入前には「この家、いつから実際に住めるのか?」を冷静に確認し、仮住まいの確保や引っ越し時期の計画もセットで考えることが大切です。
リフォーム済みの物件を選ぶという選択肢も検討してみてください。現実的なスケジュールを持っておくことが、後悔を防ぐ最大のポイントになります。
間取りが現代の生活に合わないことがある
古民家を見に行ったとき、「なんだか不便そうだな」と思った経験はありませんか?理由のひとつが、昔ながらの“田の字型”の間取りです(出典:住宅の間取りと変遷)。
広い続き間に襖や障子で仕切られた造りは、家族が集まって暮らしていた時代には理にかなっていたのでしょう。でも、個室で過ごす時間が増えた現代の生活には、正直なところ噛み合わない部分が多いです。
たとえば、ワークスペースを確保しづらかったり、プライベートな時間を取りにくかったり。実際、「使いたい部屋が廊下でつながっていない」「水回りが離れすぎていて毎日大変」という声もよく耳にします。加えて、キッチンやトイレの位置も非効率で、家事の動線が長くなるのも地味にストレスです。
とはいえ、全てがマイナスというわけではありません。柱や梁を活かしたリノベーションで、間取りそのものを大胆に変えることもできます。実際、リビングを広げたり、水回りをまとめたりして暮らしやすくなった例も少なくありません。
購入を検討しているなら、古民家特有の間取りが「我慢できるレベル」か、それとも「大幅な改修が必要か」を見極めることが、後悔しない鍵になります。
地域の環境や住民との相性に戸惑う可能性
古民家のある地域には、人のつながりを大切にする昔ながらのコミュニティが残っていることが少なくありません。一見すると温かく感じるかもしれませんが、実際にその輪に入るには、想像以上のエネルギーが求められます。
たとえば、年に数回の地域行事への参加や、顔を合わせた際のあいさつの徹底など、日々の何気ないやりとりが信頼関係のベースになる地域もあります(出典:地域住民によるまちづくり活動の継続性に関する研究)。こうした“暗黙のルール”に慣れていないと、どこかよそ者扱いされてしまったり、距離感に悩むことも。
加えて、過疎化が進む地域では住民の高齢化も深刻で、人口の8%未満という例も珍しくありません(出典:環境白書)。移住者を歓迎してくれる一方で、「若い人には分からない」といった価値観のズレに戸惑うケースも見受けられます。
そのため、古民家に惹かれて移住を考えるなら、「この土地で人と心地よく関われるか」という視点は、建物の状態と同じくらい大切です。購入前に、実際に何日か地域で過ごしてみる“お試し移住”を活用して、リアルな空気感を肌で感じることを強くおすすめします。
ホントに買わない方がいい?古民家を買うメリットや魅力

「古民家は買わない方がいい」という声もありますが、すべてがネガティブとは限りません。
実際に、古民家ならではの良さに惹かれて購入を決めた方も多くいます。
この「ホントに買わない方がいい?古民家を買うメリットや魅力」では、価格面の利点や暮らしの楽しみ方など、古民家ならではの魅力に光を当てていきます。
古民家の購入を前向きに検討する判断材料として、ぜひ参考にしてください。
購入価格が新築より安い場合が多い
古民家に惹かれる大きな理由のひとつが「価格の安さ」ではないでしょうか。新築の一戸建てをゼロから建てる場合、土地代込みの全国平均で4,903万円となっています(出典:2023年度フラット35利用者調査)。
ところが、地方の古民家になると話は別。空き家バンクに出ている物件の中には、500万円を下回る価格で掲載されているものも珍しくありません。
もちろん、購入後のリフォーム費用は見込んでおく必要があります。ただ、新築に比べて初期投資をぐっと抑えられる点は、やはり見逃せません。たとえば、予算が2,000万円だった場合、新築なら家だけで予算が消えてしまいますが、古民家なら土地+建物を手に入れたうえで、好みに合わせた改修まで手が届く可能性が高いのです。
「できるだけお金をかけずに家を持ちたい」「自分で手を加えて育てていきたい」という方にとっては、古民家は“予算内で夢を形にしやすい選択肢”として有力だと言えるでしょう。
補助金や税優遇で費用負担を軽減
古民家を購入するとき、ネックになりやすいのがリフォーム費用の大きさです。ただ、それを少しでも軽くしてくれるのが、国や自治体が用意している補助金や減税制度の存在です(出典:住宅リフォームの支援制度)。
たとえば、昭和56年以前に建てられた古民家なら、耐震工事にかかる費用の一部が補助される仕組みがあります(出典:参考資料)。補助率はおよそ工事費の50%、上限は300~500万円ほど(出典:参考資料)。しかもこの制度、全国の自治体で条件が異なるため、該当地域を調べると意外な支援が見つかることもあります。
加えて、改修を通じて「省エネ」「バリアフリー」「耐震」などの基準を満たせば、固定資産税の軽減も。具体的には、改修翌年度の固定資産税が1/2~1/3に減額される制度が活用できます(出典:耐震改修に係る固定資産税の減額措置、など)。さらに、バリアフリー改修などでは、所得税控除が受けられ、最大で25万円の税金が戻るケースも。
正直なところ、最初の見積もりを見た段階では「こんなにお金がかかるのか…」と尻込みする人も少なくありません。しかし、こうした制度をうまく使えば、負担感はぐっと減ります。購入前に地域ごとの補助内容を調べておくことが、あとあと大きな差になります。
天然素材の木や土壁で心地よい空間
古民家に足を踏み入れた瞬間、ふわりと香る木の匂いに包まれた経験はありませんか?目に映る梁や柱には、今の住宅にはない重みと温かみがあり、どこかほっとする安心感を与えてくれます。その理由は、昔ながらの木や土壁といった自然素材の力にあります。
土壁は「呼吸する壁」とも呼ばれ、湿度が高いときには空気中の水分を吸い込み、乾燥してくると吐き出すという調湿機能を持っています(出典:土壁の調湿特性に及ぼす土の寝かしの影響)。
梅雨のジメジメした時期にもカラッと過ごせたり、冬の乾燥した空気が和らいだりするのは、この壁のおかげ。エアコンの効きがよくなって、冷暖房費が抑えられたという声も少なくありません。
木材も同様に、室温を安定させる効果があり、肌ざわりや香りも含めて、五感で快適さを感じられる素材です(出典:木材利用の意義と効果)。
最近では、土壁の空間にいると「心拍が落ち着く」「よく眠れる」といった声も聞かれ、実際に研究でもリラックス効果が示されています。数字や機能以上に、「なんだか気持ちがいい」と感じられる空間というのは、家にとって大切な要素ではないでしょうか。
リノベーションにあたって、この自然素材の魅力を活かすかどうかで、暮らしの満足度は大きく変わります。もし古民家に少しでも興味があるなら、ぜひ一度その空気感を肌で感じてみてください。写真や言葉だけでは伝わらない、穏やかな時間が流れているかもしれません。
縁側や庭で四季を感じられる暮らし
古民家の縁側に腰かけて、ふと目をやると庭の木々が風に揺れ、鳥の声がどこからか聞こえてきます。そんな瞬間こそ、古民家の魅力を実感できるひとときです。
というのも、縁側や庭がある暮らしは、ただ「景色が良い」だけではありません。春は梅や桜、夏はセミの声と木漏れ日、秋には落ち葉が舞い、冬は凛とした冷気の中で静けさを味わえる。季節のうつろいが暮らしに入り込んでくる感覚は、現代住宅ではなかなか得がたいものです。
実際に古民家を購入した方の話では、「毎朝縁側でお茶を飲む時間が一番の癒やし」なのだとか。庭に目をやることで、その日一日の始まりに余白が生まれるといいます。
もし自然の変化とともに過ごすことに憧れがあるなら、縁側のある古民家は大きな選択肢になります。カタログでは伝わらないこの豊かさ、現地で一度体験してみることをおすすめします。
趣味やビジネスに使える活用の幅
古民家には、住むだけにとどまらない魅力があります。たとえば、広い土間や昔ながらの和室を活かして、小さなカフェや雑貨店、陶芸や木工の工房などに作り変えている方が実際に増えています。築100年以上の家に、最新の設備を加えて「自分の城」に仕立てる。そんな生き方に惹かれて移住を決めた人もいます。
あるご夫婦は、長野県の山あいにある空き家を購入し、自ら改修。週末は自家焙煎のコーヒーをふるまうカフェに、平日はオンラインショップの作業場に使っているそうです。SNSで発信するうちに地元の人たちとも自然につながり、気づけばリピーターもできたとか。
古民家の持つ“懐かしさ”や“落ち着き”は、都会ではなかなか手に入らない特別な空気感を生み出します。もしあなたにも「こんな空間を持ってみたい」というアイデアがあるなら、それを実現する場として古民家を考えてみてもいいかもしれません。ビジネスに、趣味に、そして人とのつながりづくりに──可能性は意外と、無限です。
買わない方がいいと言われても古民家購入に向いている人の特徴

古民家は人を選ぶ住宅ともいわれますが、全ての人に向かないわけではありません。
むしろ、住まいに手をかけたり、自然に寄り添う暮らしに価値を見出す方にとっては理想的な選択肢となる可能性があります。
ここでは、「買わない方がいい」との意見があっても、古民家購入に向いている人の特徴を具体的に紹介します。
自然豊かな環境でスローライフを楽しみたい人
都会の喧騒から少し距離を置きたい。そんな想いが心に芽生えたとき、古民家は選択肢として強く浮かび上がります。庭先で草木が揺れ、朝は鳥の声で目が覚める——そんな何気ないひとときが、日常に深い彩りを添えてくれるのです。
たとえば長野や高知の山間部にある古民家では、夏はクーラー要らずの涼風が通り抜け、冬は薪ストーブのぬくもりに包まれながら雪を眺める暮らしが叶います。生活のすぐそばに自然があるというのは、数字や利便性では計れない大きな魅力です。
とはいえ、憧れだけで飛び込むのは危険です。実際にその土地に足を運び、空気を吸い、地域の人と話してみてください。最近では市町村が古民家体験プログラムを用意しているところも多く、数日間の滞在を通じて、自分にその暮らしが本当に合っているかを確かめられます。
自然の中で心から「生きている」と感じられる生活。それを本気で求めている人にこそ、古民家という選択はフィットするのかもしれません。
DIYやセルフリフォームが好きな人
古民家に向いているのは、「自分の手で手直しするのが好きな人」です。というのも、古民家はそのまま住める状態のものは少なく、多かれ少なかれ修繕が必要になります。建具がゆがんでいたり、床がギシギシと鳴ったり。こうした箇所を「味」と受け止めながら、自分で直すことに楽しさを見い出せる人にはうってつけです。
たとえば、土壁を漆喰に塗り替えてみたり、古い窓枠をリメイクして二重窓にしたりといった作業は、見た目以上にやりがいがあります。実際、YouTubeやSNSでもセルフリノベの様子を投稿している人は多く、そうしたコミュニティに加わることでモチベーションも保てます。
ただし、電気や水回りといったインフラは専門性が高いため、無理に手を出すより専門業者に任せた方が安全です。その点を踏まえたうえで、「手を動かすこと自体が好き」な人なら、古民家暮らしはとても楽しいものになるでしょう。
こまめな手入れや庭作業が苦でない人
古民家の暮らしを楽しめるかどうかは、庭や家まわりの手入れを面倒と思うか、ちょっとした楽しみと思えるかで大きく分かれます。正直、築年数の古い家は、放っておくと草が伸び放題、木の枝が屋根にかかるなんてことも珍しくありません。けれど、そうした“ひと手間”を日課のように受け入れられる人なら、古民家はまさにピッタリの住まいです。
たとえば、朝の涼しいうちに落ち葉を掃いて、週末に庭木の剪定をする──そんな生活にわくわくできるなら、維持管理すら暮らしの一部に変わります。手をかけた分だけ庭が応えてくれるのは、マンション暮らしにはない感覚です。
とはいえ、毎日完璧にこなす必要はありません。雑草対策や簡易的な砂利敷きなど、工夫次第で負担を軽くする方法もあります。要は、「自然と共に暮らすこと」を楽しめるかどうか。それが古民家に向いている人の共通点だと言えるでしょう。
【重要】古民家を買って後悔しないための事前対策5選

古民家は魅力的な一方で、住み始めてから「想像と違った」と後悔するケースも少なくありません。
そのため、購入を検討する際には、見た目や雰囲気だけでなく、目に見えない部分までしっかりチェックすることが重要です。
では、古民家を買って後悔しないためにも、どういった対策が必要なのか?
そこでここからは、古民家を買って後悔しないための事前対策5選を詳しく紹介します!
手間やコストを減らし、納得のいく暮らしを始めるための具体的な準備として、ぜひ参考にしてみてください。
信頼できる不動産会社から情報を集める
古民家を購入しようと考えているなら、まず最初に頼るべきは“どんな不動産会社と付き合うか”という点です。
大手の仲介会社にもメリットはありますが、こと古民家に関しては、地元に根を張っている小さな不動産会社の方が圧倒的に頼りになります。地場の空き家バンクや自治体とつながっていたり、地元の地主さんと長年の関係があったりするからです。
例えば、表には出ていない物件情報を持っていたり、「ここは昔から雨漏りがひどい」といった内部事情まで知っていたりと、ネットの検索では到底たどり着けない情報を教えてくれることもあります。
古民家は一軒ごとにクセがある分、不動産会社の“人”を見る目が重要になります。「ここなら任せてもいい」と思える担当者と出会えるかどうかが、その後の満足度を大きく左右するというのが、実際に購入した人たちの本音です。
では、どうやって信頼できる不動産会社から情報を集めればいいのか?できればネットで簡単に、比較検討できる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用する方法です。
「タウンライフすまいリクエスト」は、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
耐震診断を専門家に依頼して調べてもらう
古民家を買うかどうかを悩んでいる段階なら、まず最初に知っておいてほしいのが「耐震性の問題」です。
正直に言うと、築50年、60年を超えるような古民家は、現行の耐震基準を満たしていないことがほとんど。つまり、見た目がいくら立派でも、構造そのものが地震に耐えられない可能性があるというわけです。
そのため、信頼できる建築士や、古民家に強い専門家に耐震診断を頼むことは必須事項といえます。例えば、伝統構法に精通した診断士であれば、壁の土や梁の組み方、床下の状態まで丁寧に見てくれます。
費用は建物の規模や地域にもよりますが、目安として10~20万円ほどかかるケースが多いようです。それでも、構造のクセや弱点が明確になるので、その後のリフォームや補強の計画を立てやすくなります。
「買ってからでは遅い」とよく言われますが、古民家ほどそれが当てはまる住まいはないかもしれません。住み続けるために何が必要かを把握するうえでも、最初に耐震診断を依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。
もし、不動産のプロのアドバイスを貰いながら物件情報を集めたい方は、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』の活用がおすすめです。
「タウンライフすまいリクエスト」は、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
シロアリ被害の有無を事前に点検する
古民家に魅力を感じる方ほど、忘れがちなのが“シロアリのリスク”です。特に築年数が長い建物は、見た目が美しくても床下や柱の内部にシロアリが潜んでいる可能性が高く、実際に築40年以上の木造住宅では、約半数が被害経験ありというデータもあります。
現地見学で気になる兆候があれば、必ず専門業者に床下点検を依頼してください。費用の相場は無料~1万円程度。調査では、土が盛り上がった“蟻道(ぎどう)”や、木材がスカスカと軽く音を立てるなど、経験者ならではの目で確認してもらえます。
万が一、発見が遅れれば、修繕費用は数十万円~100万円単位に膨らむ恐れもあるため、「買ってから後悔」する前に、最低限この確認だけは済ませておくべきです。保証付きの防除処理をしてくれる業者を選べば、5年ほど安心して暮らせます。
とはいえ、「どこに相談すればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そんな時は、複数の優良業者から無料で見積もり・比較ができる『タウンライフのシロアリ対策』が心強い味方になります。
「タウンライフのシロアリ対策」は、現在の状況を入力するだけで、審査済みの優良業者から無料で一括見積もりを取得できるサービスです。
対応エリアも広く、手間なく一括依頼ができるため、初めての方でも安心です。古民家の購入を前向きに進めるためにも、事前チェックという小さな行動が、将来の大きな後悔を防いでくれます。
電気配線と水回り設備をチェックする
古民家に暮らし始めてから「思っていたより修理が多い」と感じる方の多くが見落としていたのが、電気と水回りの設備です。見た目は味のある梁や柱が目を引きますが、生活を支えるのは裏側のインフラ。ここが脆ければ安心して住むことはできません。
特に注意したいのが、築50年以上の物件に多い古い配線や鉛管の存在です。経年劣化で被膜が剥がれた電線は火災を招きやすく、水道管も腐食が進んでいれば水漏れや濁りの原因になります。実際、古民家を購入した人の中には、入居前の点検で数十万円規模の修繕が必要と判明したケースも少なくありません。
そうしたトラブルを避けるためにも、購入前には電気工事士や水道業者など、信頼できる専門業者に調査を依頼するのが賢明です。「古民家を買ったら、まずは裏の設備を疑う」——それくらいの慎重さが、快適な暮らしへの第一歩になります。
将来のリフォーム費用を長期的に試算する
古民家を買ってから「こんなに修繕にかかるとは思わなかった」と後悔する人が後を絶ちません。実は、リフォーム費用というのは思っているよりも高額で、そして終わりがないのが現実です。
築年数の古い物件では、屋根や柱の補修に加え、耐震補強・断熱・水回りの交換と、手を入れる箇所が多岐にわたります。参考までに、最低限のリフォームで300~500万円、内装も含めてしっかり手を入れる場合は1,000万~2,000万円かかるケースもあります。もちろん、どこまでこだわるかによって上限は青天井です。
たとえば、キッチンを現代仕様にして、トイレや浴室も交換、水道管の引き直しまで考えれば、それだけで予算を大きく圧迫します。しかも、購入直後だけでなく10年・20年後にも修繕は必要です。
だからこそ、「今いくらかかるか」だけでなく、「この家に何年住むつもりか」「その間にどんな工事が発生しそうか」まで見据えたうえで、長期的な視点で費用を見積もることが大切です。短期の出費だけで判断すると、後から苦しくなるのは目に見えています。
では、どうやってリフォーム費用を見積もればいいのか?できれば、無料で一括見積もりできる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計利用者数540,000人を超える『タウンライフリフォーム』を活用する方法です。
「タウンライフリフォーム」とは、リフォームの希望を入力するだけで、複数の優良リフォーム会社から無料でプラン・見積もり・提案がもらえる一括見積もりサービスです。
知らずに損する前に。複数社の見積もりを比較して、安心・納得できるリフォームを見つけてみてください。
【Q&A】買わない方がいいと言われる古民家に関するよくある質問
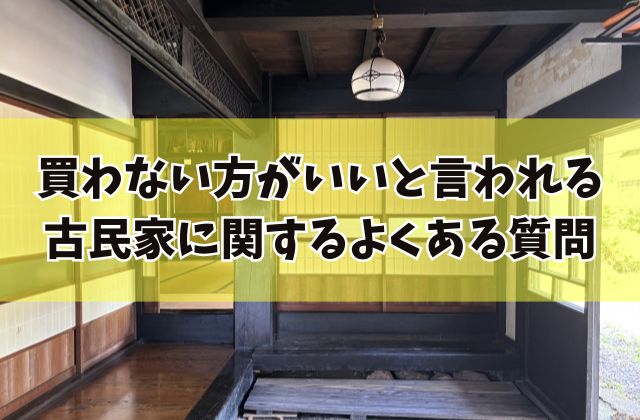
最後に買わない方がいいと言われる古民家に関するよくある質問をまとめました。
検索で多く調べられている具体的な疑問にわかりやすく答えていきます。購入前に知っておきたいリアルな情報が詰まっています。
古民家に暮らす欠点は何ですか?
古民家の生活でまず向き合うことになるのが、寒さや不便さ、そして維持の手間です(出典:伝統民家の冬期の温熱環境を実測・解析)。
築年数が長い分、断熱性能がほぼなく、冬場は室内でも息が白くなるほど冷え込むこともあります。加えて、現代的な住宅設備が整っていない場合が多く、水回りやトイレの使い勝手にストレスを感じる人も少なくありません。購入前には「昔の家」に対する理想と、今の生活とのギャップを冷静に見極めることが必要です。
古民家は何年住めるのでしょうか?
古民家がどれくらい住めるかは、「手入れ次第」と言っても過言ではありません。
築80年、100年の家でも、骨組みがしっかりしていて適切に修繕されていれば、今後何十年も住むことが可能です。たとえば柱や梁に使われている無垢材は、現代の建材よりも耐久性に優れている場合もあります。ただし、定期的な点検と補修を怠ると、想像以上に早く傷むこともあるため注意が必要です。
古民家の耐久性はどのくらいですか?
耐久性という点では、きちんと作られた古民家は驚くほど丈夫です。実際、100年以上経っても住める家は各地に残っています(出典:参考文献)。
特に、土台や梁などが太く立派な構造の場合、耐久年数は非常に長いです。ただし、屋根や外壁、設備類などは経年劣化するので、部分的な修繕は避けられません。見た目が趣深いからといって油断せず、専門家による診断を受けてから判断するのが賢明です。
古民家はお金持ちでないと買えない家ですか?
「古民家=お金持ちの趣味」というイメージを持つ人は多いかもしれませんが、実際には物件価格そのものは意外と安いこともあります。
ただ、ネックになるのはリフォームや修繕費用。全体をフルリノベーションする場合は、1000万円以上かかるケースも珍しくありません。けれど、最低限の修繕に絞ったり、自分でDIYを取り入れたりすれば、費用を抑えて暮らすことも十分に可能です。
住みたくないと思うほど古民家は不便ですか?
たしかに古民家の生活には「不便さ」がつきまといます。水回りの使い勝手、夏の虫、冬の寒さ。こうした点に慣れるまでは、ストレスを感じる人もいるでしょう。
しかし一方で、その不便さを「味わい」や「情緒」として楽しめるようになる人も多いです。昔ながらの暮らしに価値を見出せるかどうかが、満足度を左右する大きな分かれ道になるでしょう。
築100年の古民家のリフォーム費用はいくらですか?
築100年クラスの古民家をきちんと住める状態にするには、リフォーム費用として最低でも数百万円、場合によっては2000万円近くかかることもあります。
たとえば基礎補強、断熱工事、配管の更新などを全て行うと、それなりの費用が必要です。けれど、住まいの一部だけを直して住み始め、少しずつ手を加えていく方法もあります。最初からフルリノベを前提にせず、段階的に整える道もあるのです。
まとめ:古民家は買わない方がいい理由と買って後悔しないための対策
古民家は買わない方がいい理由と買って後悔しないための対策に関する情報をまとめてきました。
改めて、古民家は買わない方がいいと言われる主な理由をまとめると、
- 築年数が古いため断熱性・耐震性が現代基準を満たさず、快適性に欠けやすい
- 修繕や維持に多額の費用がかかるうえ、専門の職人や資材の確保が必要になる
- 構造内部のシロアリ被害や腐食など、目に見えないリスクを抱えている場合が多い
- 水回りや電気配線などの設備が古く、快適に住むには改修が不可欠となる
- 住む地域によっては周辺環境が不便で、日常生活に支障をきたす可能性がある
古民家は魅力的な暮らしを連想させますが、実際には「古民家は買わない方がいい」と言われる理由が多く存在します。
購入を検討する際は、夢だけで判断せず、現実的なリスクや負担をしっかり見極めることが後悔を防ぐ第一歩です。