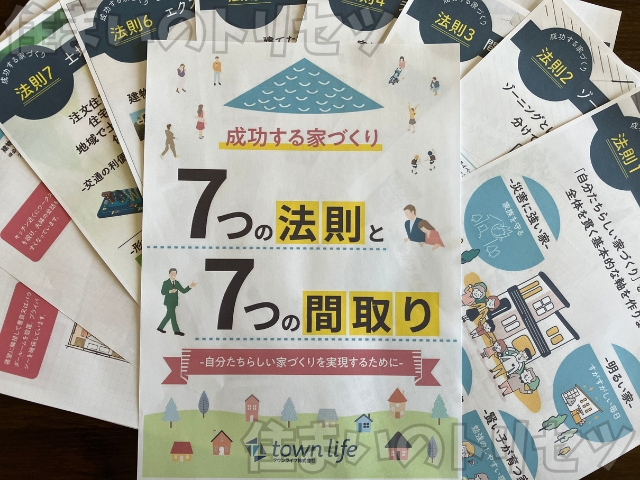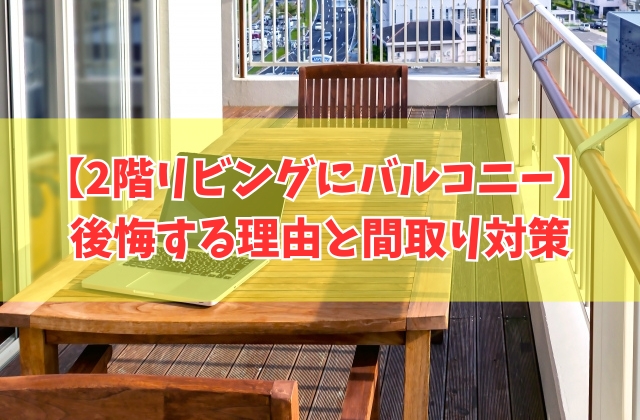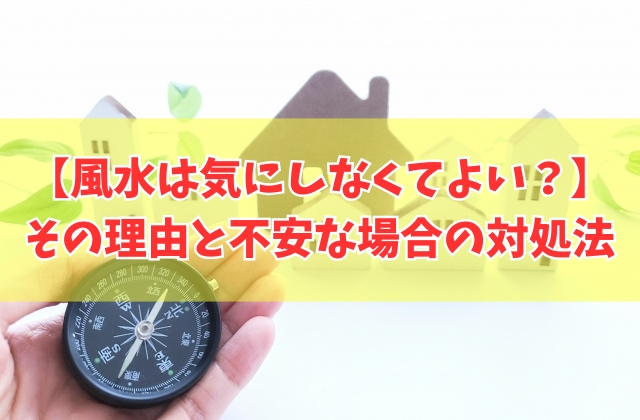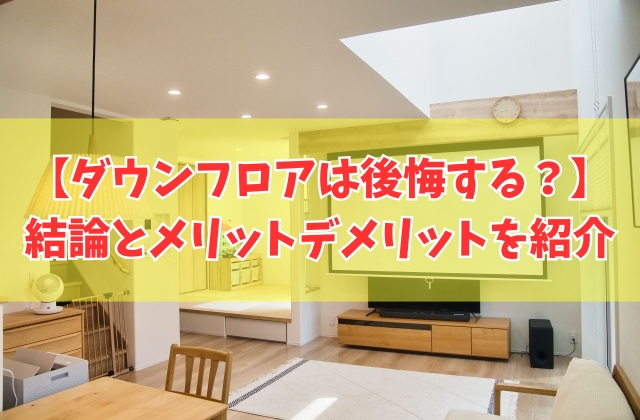
「家づくりでリビングをダウンフロアにすると後悔する?」
「ダウンフロアのメリットデメリットは?後悔しないためにどんな対策が必要?」
開放感があり、空間にメリハリが生まれると人気の“ダウンフロア”。
でも実際に住んでみると「段差につまずいた」「掃除が大変」「寒さが気になる」など、後悔の声も少なくありません。
家づくりを計画中で、リビングに段差を取り入れるか悩んでいる方にとって、「ダウンフロアで後悔した声」は無視できないテーマです。
そこで本記事では、リビングをダウンフロアにするメリットだけでなく後悔しがちな落とし穴や、失敗しないための具体策まで、わかりやすく丁寧に解説します。
人生に一度のマイホーム購入。家づくりで後悔したくない方は、今後の対策としてぜひ参考にしてみてください。
- 段差の高さを抑えて転倒リスクを最小限にすることが重要
- 子どもや高齢者の安全に配慮した設計と対策が欠かせない
- 家具配置や配線計画を事前に決めて動線と快適性を確保する
リビングをおしゃれに演出できる一方で、設計や暮らし方に工夫がないと「ダウンフロアで後悔」につながる可能性があります。
段差の扱いや安全性、レイアウトの計画を丁寧に行えば、後悔を防ぎつつ理想の住まいを叶えることができます。
では、どうやって理想の間取りプランを考えればいいのか?自分で悩み続けるのではなく、ネットからサクッとプロに間取り作成を頼めたら、すごくラクですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。
つまり、「タウンライフ家づくり」を使えば“プロが考えた複数の間取り案を比較しながら、後悔しない家のカタチを決められる”ということ。
同じ要望・条件を入力するだけで、複数の住宅メーカーや工務店から間取りプランやアドバイスが一括で届くため、一人で悩み続けることなく、暮らしやすさや動線を比較しながら自分たちにベストな間取りを選びやすくなります。
- 3つの提案が“すべて無料”で一括入手!
希望に沿った「間取りプラン」「資金計画」「土地探し」の3プランを受け取れ、家づくりが一気に進む! - 複数社の提案を自宅で比較検討できる!
家にいながら、簡単に価格や間取りを“比較”できるので適正価格が分かり、効率よく候補を絞り込める! - 全国の信頼できる住宅メーカーから厳選された提案を受けられる!
全国1,200社以上・大手ハウスメーカー36社以上が掲載&提案するのは国家基準を満たすメーカーのみ!
さらに!利用者の方限定で、プレゼント(成功する家づくりの7つの法則と7つの間取り)も受け取ることができます!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、読み応えあって今後の家づくりを進めるヒントが満載でした。
一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、『タウンライフ家づくり』で複数社の間取りプランを無料で一括比較してみてください。
【結論】リビングをダウンフロアにすると後悔する?

一言で言えば、ダウンフロアのリビングは「人によって後悔するケースもあるが、向いていれば満足度が高い」というのが実情です。
たとえば、段差につまずきやすく小さな子どもや高齢の方がいる家庭では不安材料になります。冬は足元が冷えやすく、ロボット掃除機が段差を越えられないことも。さらに、家具や家電の配置が制限されるという声も少なくありません。模様替えが難しく、レイアウト変更に自由がきかないと感じる人もいるでしょう。
その一方で、「空間に奥行きが出て広く見える」「段差部分がベンチになって来客に好評」「子どもの遊び場が近くて目が届きやすい」など、ダウンフロアならではのメリットも確かに存在します。うまく活かせれば、住まいの魅力はぐんと上がります。
重要なのは、ライフスタイルとの相性です。段差を20~40cm以内に抑える工夫や、床暖房と断熱材を組み合わせて寒さをカバーする設計、暗さを感じさせない採光計画などができていれば、後悔のリスクはかなり減らせます。
バリアフリーや可変性を重視する場合は慎重に。逆に「空間のデザイン性」や「ゆるやかな仕切り」を求める人にとっては、十分に検討の価値がある間取りです。選ぶ側の視点と準備次第で、満足か後悔かは大きく分かれます。家族の将来を見越した判断がカギになります。
ホントに後悔する?リビングをダウンフロアにする8つのメリット

リビングをダウンフロアにすると後悔するのでは?と不安に思う方も多いですが、実はデザイン性や快適性を高める嬉しいメリットもたくさんあります。
空間の使い方や家族との距離感を大切にしたい人にとって、「リビングをダウンフロアにする8つのメリット」は見逃せないポイントです。
家づくり・注文住宅を計画している方や、リビングをダウンフロアにするか悩んでいる方に向けて、暮らしやすさを実感できる魅力を具体的にご紹介します。
目線が下がり天井が高く見えて広々感じる
ダウンフロアのあるリビングに足を踏み入れた瞬間、不思議と「広いな」と感じたことはありませんか?その感覚、実は視線の高さと関係しています。
床が通常より一段低くなることで、人の目線も自然と下がります。すると、同じ天井高でも天井までの距離が広く見え、空間全体にゆとりがあるように感じられるんです。住宅会社の事例紹介でも「天井を高くしたような開放感が得られる」と紹介されているように、視覚効果はなかなか侮れません。
例えば、一般的な天井高が2.4mの住宅でも、床を約30cm下げるだけで、体感的には2.7m~2.8mほどの伸びやかさを感じるケースもあります(出典:参考文献)。吹き抜けのような大掛かりな工事をしなくても、視界に広がりをもたせることができるのがダウンフロアの面白いところです。
限られた間取りの中でも、広がりや奥行きを演出したいという方には、ダウンフロアはとても有効な選択肢だと思います。間違いなく「空間の見え方」が変わり、ちょっとした非日常感すら楽しめるはずです。
段差でリビングとダイニングをゆるく分けられる
リビングをダウンフロアにすると、段差によって空間に自然な境界が生まれます。目に見える壁や仕切りがなくても、「ここからがくつろぐ場所」「そこは食事をするスペース」という認識が、見る人の感覚にスッと入ってくるのです。
なぜこの仕組みが効果的なのかというと、高さの違いが視覚的な区切りになり、ひとつの大きな空間にメリハリを持たせられるからです。
たとえば、住宅デザインを手がける建築事務所でも、ダウンフロアを使ったゾーニングの工夫がよく取り入れられています。「ダウンフロアにすることで空間をゆるやかに区切り、居場所に個性を持たせられる」といった声も紹介されています。
実際にリビングを30cm程度低く設計した事例では、「間仕切りを使わずに家族の動線を分けられて便利」「空間に奥行きが出て広く感じる」という評価が多く見られます。
間取りに迷っている方にとって、段差をうまく活用する方法はとても有効です。視線や動線が自然と切り替わることで、生活にリズムが生まれ、後悔の少ない空間づくりにつながります。
吹き抜けなしでも開放感と明るさを得られる
吹き抜けのある家に憧れはあるけれど、「冬の寒さ」や「掃除の手間」が気になって、なかなか踏み切れない方も多いのではないでしょうか。そんなときに選ばれているのが、リビングを一段低く設ける“ダウンフロア”というアイデアです。
視線の高さが自然と下がるこの工夫だけで、驚くほど空間が広く、明るく感じられるのです(出典:参考文献)。たとえば、天井高をそのままに、床だけを30cm下げてみてください。それだけで視界に抜けが生まれ、圧迫感がすっと消えます。
吹き抜けを設けるほどの天井高が取れなくても、リビングに伸びやかさを与えられるというのは、大きな魅力です。
さらに、ダウンフロアによって窓の位置や壁面の見え方も変わり、日差しの入り方や光の回り方が柔らかくなります(出典:参考文献)。明るさを犠牲にせず、かつ冷暖房効率を落とさずに済むという点も、吹き抜けに代わるメリットとして見逃せません。
住宅情報サイトでも「吹き抜けがなくても、床を下げるだけで空間に変化が生まれ、開放感と快適性を両立できる」といった声が掲載されており、実際に採用されたご家庭からは「天井が高く見えるのに、冬も寒くない」という評価も多く見られます。
吹き抜け=開放感という考えにとらわれなくても、工夫次第で気持ちの良いリビング空間はつくれます。構造的なハードルを感じている方ほど、この選択肢はぜひ一度検討してみてください。
※カタログ
段差をベンチや腰掛けにして座る場所が増える
リビングをダウンフロアにすると、段差の部分が思いがけず便利な「腰掛けスペース」になります。家族や友人が自然に集まる場をつくりたいなら、このちょっとした高低差が心地よい役割を果たしてくれます。
床を30センチほど下げて段差を設けると、その縁がベンチのように使えるんです。住宅メーカーの実例でも「段差を腰掛けとして活用できる」と紹介されており、ダウンフロアが単なるデザインではなく“実用的な家具”のような働きをしていることがわかります。
座る場所が増えるだけでなく、空間全体に奥行きが生まれ、リビングがぐっと立体的に感じられます(出典:参考文献)。
実際に注文住宅で採用した方の声では、「子どもと腰を下ろして遊べる」「来客時に椅子を出さなくても座れる」といった意見が多く見られます。段差の上にクッションを並べるだけで、ちょっとしたくつろぎスペースに早変わり。お茶を飲んだり、話したり、腰を下ろして眺めたり──そんな“人の動き”が自然に生まれる空間になります。
つまり、ダウンフロアを検討している方にとって、この段差は単なる構造ではなく“暮らしを支える居場所のひとつ”になります。デザイン性だけでなく、日常の心地よさを生む工夫として取り入れる価値が十分にあるでしょう。
段差下を収納にして散らかりにくくできる
「リビングって、気がつくと物があふれてる…」そう感じたことがある方にこそ、ダウンフロアの“段差下収納”は心強い味方になります。段差があるからこそ生まれる空間を、ただのデッドスペースにせず、しっかり収納として活用できるのがポイントです。
たとえば床を30cm下げてダウンフロアにすると、その立ち上がり部分に引き出し式の収納を組み込む設計が可能です。実際に、住宅メーカーの実例でも「リビングに物を出しっぱなしにしなくて済むようになった」「おもちゃや雑貨を片づける場所ができて助かっている」といった声が多く見られます。
特にお子さんのいる家庭では、遊び終わったおもちゃをさっとしまえるのは大きな利点です。
収納家具を新たに置く必要がなくなる分、リビングの床も広く使えます。見た目にもすっきりして、急な来客があっても慌てずに済むようになります。
段差という「構造」を、機能的な「価値」に変える発想。これは、ダウンフロアだからこそ実現できる家づくりの工夫です。「散らかりがちなリビングにうんざりしている」「でも収納家具を増やしたくない」という方にとっては、後悔どころか満足感につながるはずです。
子どもの遊び場として目が届きやすい
小さな子どもがいるご家庭では、リビングで過ごす時間が自然と多くなりますよね。そんな中で「ダウンフロアって実際どうなの?」と悩む方におすすめしたいのが、“段差があるからこそ見守りやすい”という視点です。
ダウンフロアにすると、リビングが一段低くなるため、ダイニングやキッチンにいる親から、遊んでいる子どもたちの様子がとてもよく見えるんです。
実際、30cmほどの段差でも視線の角度が変わることで、キッチンで洗い物をしながらでも「あ、いま絵本読んでるな」「ちょっとおもちゃ投げたかも」といった日常の小さな変化に気づきやすくなります。
住宅事例でも、「ピットリビングを遊び場にしてから、安心感がまったく違う」といった声が多く、応じたママさんは、「ダウンフロアにしてから、上の子と下の子が自然と集まる場所になって、ケンカが減りました」と笑って話してくれた内容が紹介されていました。
見た目のおしゃれさだけでなく、子どもが自由に遊べる安心なスペースとしても機能する。それがダウンフロアの隠れた魅力です。遊び場と視線がひと続きになることで、親の心の余裕も増える──そんな実感を得たい方には、きっと後悔のない選択になると思います。
会話が生まれる集いの場になり来客に好評
リビングをダウンフロアにして一番良かったのは、「人が自然と集まる空間」になったことだと話す人が多くいます。少し床が下がっているだけなのに、不思議とそこに座りたくなったり、話したくなったり。段差がベンチ代わりになって、椅子をわざわざ出さなくても、その場に腰を下ろしてくつろげるのです。
実際に、建築会社の事例でも「段差があることで視線に緩やかな変化が生まれ、会話が始まりやすい」と紹介されています。また、木の温もりを生かしたダウンフロア設計では、来客に「おしゃれだけど居心地がいい」と好評だったという声も。
たとえば、リビングを約30cmほど下げたお宅では、ソファ以外にも段差部分にクッションを置いて、友人たちが輪になって座れるように工夫。料理中の奥さんとも自然に会話ができ、まるでカフェのように心地よい空間になっていたそうです。
リビングの中心に段差を設けることは、ただのデザインではなく、人がつながる仕掛けのひとつ。家族や友人との時間を大切にしたい方には、こうした「人が集まるリビング」を目指す間取りもおすすめです。
家具や色分けと合わせておしゃれに魅せられる
ダウンフロアの最大の魅力のひとつが、「段差そのものをインテリアの一部として活かせる」点にあります。段差を境に、床の色や素材を少し変えるだけで、空間にメリハリが生まれ、リビング全体がぐっと洗練された雰囲気に仕上がります。
たとえば、リビング側の床を淡いグレー、ダイニングは温かみのある木目調にしてみる。たったそれだけの工夫で、2つの空間が自然に分かれ、しかもごちゃついた印象がありません。高さを抑えたロースタイルのソファや間接照明を段差部分に組み合わせれば、まるでカフェのような落ち着きが手に入ります。
デザインのプロも「ダウンフロアは“立体的に遊べる空間”。視線の抜けや高さの変化が、おしゃれに見せるための大きな武器になる」と評価しており、平坦な間取りでは出せない立体感が、暮らしに彩りを与えてくれます。
SNSや住宅展示場で目にするような“真似したくなる部屋”には、この段差の使い方が上手に取り入れられていることが多いです。流行りに左右されない個性を持ちつつ、しっかりと機能も果たしてくれる。そんな空間を目指すなら、ダウンフロアは頼もしい味方になってくれるはずです。
後悔した声が目立つリビングをダウンフロアにする8つのデメリット

リビングをおしゃれに演出できる一方で、ダウンフロアには「暮らしにくさ」や「予想外の不便さ」による後悔の声も多く見られます。
そこで「後悔した声が目立つリビングをダウンフロアにする8つのデメリット」をまとめました。
段差の危険性や掃除の手間、冬の寒さなど、実際に暮らし始めてから気づきやすいポイントを詳しくご紹介します。
事前に知っておくことで、後悔を防ぐ判断材料になります。家づくりを計画している人があとで悩まないためにも、事前に知っておきたい注意点を具体的に確認しておきましょう。
冬に足元が冷えやすいことがある
リビングをダウンフロアにすると、冬の冷えを感じやすいという声が少なくありません。
その主な原因として、床を一段下げた分だけ地面との距離が近くなり、冷気がたまりやすい構造になっているからです(出典:参考文献)。とくに断熱や気密が十分でない場合は、暖房を入れても足元だけが冷えることがあります。
実際、国交省の資料(住まいと健康に関するガイドライン)でも「ダウンフロアは床面が地表に近く、冷えやすい傾向がある」と紹介されています。また、床材の種類によっても体感温度が変わり、フローリングは特に冷たく感じやすいという指摘もあります(出典:参考資料)
たとえばリビングを約30cm下げたピットリビングでは、裸足で過ごすと冷気が伝わりやすく、ソファに座っていてもひざ下が冷えるという話も聞きます。逆に、床暖房を入れたケースでは「冬でも快適に過ごせる」との声が多く、施工段階での断熱計画が結果を大きく左右してしまうのです(出典:参考資料)。
家づくりを検討しているなら、「おしゃれさ」と「快適さ」のバランスを意識して設計するのがポイントです。断熱・気密・床暖房の3点をしっかり押さえれば、ダウンフロアでも寒さを気にせず心地よく過ごせる住まいになります。
段差でつまずきやすく子どもや高齢者に不安
リビングを一段掘り下げたダウンフロア。空間に変化が生まれておしゃれな雰囲気になりますが、住んでから気になるのが“段差”です。
小さなお子さんがいる家庭では、ふとした拍子につまずいてしまうことも。高齢の親と同居しているケースでは、夜間の移動や視力の衰えから、段差に気づかず転倒してしまったという声も少なくありません。
実際に国交省の指針では、「段差による事故リスクがあるため、安全配慮が必要」として、高さを20cm以内に抑えることや、照明の工夫、手すりの設置が推奨されています(出典:高齢者が居住する住宅の設計に係る指針)。
たとえば30cm程度の段差を設けた家庭では、2歳の子どもが走っていてバランスを崩し、顔を打ってしまったというエピソードも紹介されています。また、照明が暗い時間帯に親が見えづらく、足を踏み外したという実例も。
段差のある空間は見た目にアクセントがついて魅力的ではありますが、安全面をしっかり考慮しないと、日常生活に不安を抱える原因になります。とくに小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、段差をつくる前にもう一度、その必要性を見直しておいたほうが安心です。
バリアフリーにならず移動が不便になる
リビングを一段下げたダウンフロアは、見た目にはおしゃれで空間に変化をつけられる一方で、暮らしやすさの面では注意が必要です。特に、段差があることで移動がしにくくなり、バリアフリーの考え方とは相反する構造になってしまう点は見落とせません。
実際に、住宅情報を発信するサイトでも「ダウンフロアは段差が生じるため、完全なバリアフリー設計には不向き」と紹介されています。年齢を重ねると、ほんの20~30cmの段差でさえ、昇り降りに手間を感じたり、つまずきのリスクが増すといった声が現実にあります。
たとえば、家づくり当初は「デザイン重視」でダウンフロアを採用したものの、ご両親が遊びに来るたびに「この段差、ちょっと怖いわね」と話すようになり、後から手すりを付けることにした家庭も。転倒防止や安全性の面から見ても、段差のある構造が生活に与える影響は無視できません。
「将来も安心して暮らせる家を」と考えるなら、バリアフリー性の低下というデメリットは見過ごせない要素です。おしゃれさと実用性のバランスをどこで取るか──これが、後悔しない家づくりにおいて大切な判断基準になるのではないでしょうか。
ロボット掃除機が使いにくく掃除が手間
ダウンフロアのある家に住み始めて気づくのが、「ロボット掃除機が思ったように働かない」という現実です。段差があると、掃除機がうまく越えられず、使い勝手が一気に落ちてしまいます。
市販のロボット掃除機は、基本的に高さ2センチほどの段差までしか乗り越えられません(出典:参考資料)。
ところが、ダウンフロアでは一般的に20~30センチほどの段差があるため、掃除機が途中で止まってしまい、フロア間の移動ができなくなります。
実際に「ダウンフロアにしたらロボット掃除機が使えなくなって後悔した」という声は多く、掃除のたびに本体を持ち運んでフロアごとに設置し直す必要が出てくることも。こうなると、ロボット掃除機の魅力である「全自動の掃除」が活かせず、手間もストレスも増えてしまいます。
ロボット掃除機を日常的に使いたい方にとって、段差のある間取りは相性が良くないことが多いです。事前に掃除方法や動線をしっかり考えたうえで、設計に反映させることが後悔を避けるコツといえるでしょう。
家具や家電の置き場所が限られる
リビングに段差を設けたダウンフロアは、見た目こそおしゃれですが、意外な落とし穴もあります。特に家具や家電の配置で悩むケースは少なくありません。
段差によって空間が仕切られるため、平坦なフロアに比べて自由度がぐっと下がります。たとえば、テレビをどこに置くか、ソファとどんな高さ関係になるか、配線はどう通すか──。こうした一つひとつの選択が、段差のせいで難しくなるのです。実際に、家づくり経験者の中には「設置したかった収納棚が高さ的に合わなかった」「段差をまたぐ延長コードが目立って不格好だった」という声も見られます。
しかも、一般的なテレビボードの高さは約40cm。ソファを30cm下げたピットリビングに置くと、自然と見上げる角度になってしまい、目線が合わずに違和感を覚える人もいます(出典:参考資料)。これは図面上では気づきにくい問題で、実際に暮らし始めてから後悔する原因になりがちです。
だからこそ、ダウンフロアを採用するなら、設計段階から「何を・どこに・どう置くか」を具体的に考えておく必要があります。家具の高さ、家電のコードの取り回し、視線の動線まで、できるだけリアルにシミュレーションしておくと、あとから「置きたいのに置けない」と悩まずに済みます。
模様替えやレイアウト変更がしにくい
ダウンフロアのリビングを取り入れたものの、「あとから家具の配置を変えようとしたら意外と難しくて困った」という声は少なくありません。段差があることで、置ける場所や動線が限られてしまうためです。
たとえば、リビングの一部を30cmほど下げたピットスタイルの場合、テレビボードやソファを配置した位置を変えたくても、段差の関係でベストな向きや場所が決まってしまいがちです。段差の縁に家具の脚がかかって不安定になったり、コンセントの位置が合わずコードが邪魔になったりと、自由にレイアウトを変えるにはひと手間かかります。
こうした不便さは、実際に住んでから気づくことが多く、「もっと事前に家具のサイズや動線を考えておけばよかった」と後悔につながるケースも少なくありません。模様替えを楽しみたい方にとっては、ダウンフロアは少し窮屈に感じるかもしれません。
「見た目がオシャレ」と感じて採用する方も多いですが、暮らし始めたあとに不満を感じないよう、配置換えのしやすさや将来の生活の変化も見越して設計することが大切です。
工事費用がかさみ予算オーバーになりやすい
ダウンフロアのリビングに憧れて設計に取り入れたものの、いざ見積もりを出してみて「えっ、こんなに高くなるの?」と驚いた…そんな声は少なくありません。段差をつくるためには、通常の床よりも複雑な施工が必要になり、どうしても工事費が上乗せされてしまうのです。
実際のところ、1畳分を15~20cm下げるだけでも5万円~8万円ほどの費用がかかるケースが多く、建材価格の高騰により10万円近くに達することも報告されています(出典:参考資料)。そこに造作ベンチや段差収納を加えると、予算はさらに膨らみます。
例えば、6畳分のリビングスペースを一段下げると、それだけで30万円~60万円ほどの追加工事費が発生します。さらに、段差による寒さ対策として床暖房や断熱材の強化を取り入れれば、コストは一気に跳ね上がります。ここまでくると、家全体のプランを見直す羽目になることも。
「おしゃれだから」と軽い気持ちで取り入れると、気づいたときには予算が足りず、他の部分を削らざるを得ないという事態になりかねません。ダウンフロアを選ぶなら、追加費用が必ず発生する前提で、事前にしっかり資金計画を立てておくことが大切です。
長期優良住宅の認定外になる場合がある
リビングをダウンフロアにすると、見た目のデザイン性や空間のメリハリには満足していても、あとになって「長期優良住宅の認定が取れなかった」と悔やむケースも少なくありません。これ、意外と見落としがちなんですが、制度の条件と設計プランが食い違ってしまうことがあるのです。
というのも、長期優良住宅に認定されるには、耐久性や断熱性能といった基本的な性能に加えて、「床下の点検スペースが330mm以上あること」といった細かい技術基準を満たす必要があります(出典:長期使用構造等とするための措置)。
たとえば、ダウンフロアでリビングの床を通常より30cm(300mm)下げた場合、その分床下が狭くなってしまい、基準を下回る可能性が出てきます。実際、三重県の基準書でもこの点は明確に示されています。
QUOホームの施主事例でも、ダウンフロアを採用した結果、「床下高さが足りない」という理由で認定を断られてしまったケースが紹介されていました。設計時点では気づかなかったものの、最終確認で引っかかってしまうというのは、誰にでも起こりうる話です。
家づくりにおいて「長期優良住宅」として認定されることを前提にしている方は、リビングの間取りや段差を決める前に、工務店や建築士としっかり確認しておくことをおすすめします。認定を取ることで、住宅ローン控除や固定資産税の軽減といったメリットも受けられますから、設計の自由度とのバランスを見ながら、後悔のない判断をしていきたいですね。
もし、住宅メーカーのアドバイスを貰いながら家づくり計画をを集めたい方は、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』の活用がおすすめです。
「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。
一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、複数社に相談してプランを比べてみてください。
リビングをダウンフロアにして後悔しない・向いている人の特徴とは
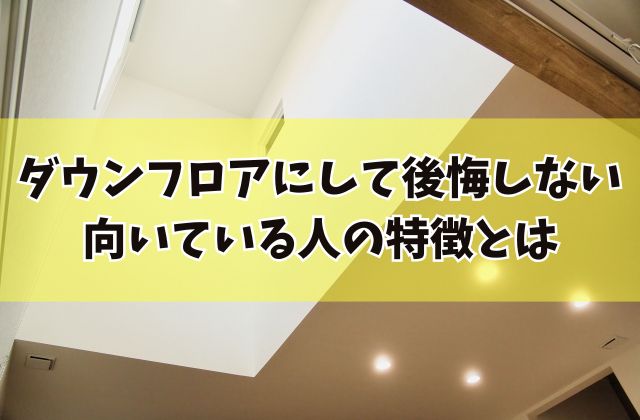
リビングをダウンフロアにすることで「後悔した」という声もある一方で、満足して暮らしている家庭も少なくありません。
実は、ダウンフロアの特性を理解し、住まい方に合った考え方を持つことで、快適に暮らせるケースが多くあります。
ここでは、「リビングをダウンフロアにして後悔しない・向いている人の特徴とは」何かをわかりやすくご紹介していきます。
掃除や段差の安全対策に手間をかけられる人
リビングをダウンフロアにするなら、少しの手間を惜しまない人の方が向いています。段差のある空間は見た目こそおしゃれですが、その分、掃除や安全対策で意外と気を使う場面が多いからです。
たとえば段差の角や溝にはホコリが溜まりやすく、ロボット掃除機がうまく動けないこともあります。結局、モップやハンディクリーナーを持ち出して細かいところを掃く――そんな日常が現実的です。
他にも、床に照明を仕込んだり、滑り止め加工を施したりといった工夫も必要になります。設計時に「どこまで手をかけるか」を考えておくと安心です。
実際、30センチほどの段差を設けたリビングを採用した家庭では、子どもが夜に段差を見落として転びそうになった経験から、後から間接照明を追加したという声もあります。
結局のところ、ダウンフロアの魅力を楽しめるのは、掃除や安全面にしっかり気を配れる人です。段差のある暮らしは、ほんの少しの工夫と気遣いで快適さがまったく変わります。手間を惜しまない人ほど、きっとその空間を長く愛せるはずです。
コストや断熱の工夫を事前に計画できる人
リビングをダウンフロアにしたいと思っているなら、「費用」と「断熱対策」をあらかじめしっかり考えておく人が向いています。逆に言えば、この2つを後回しにしてしまうと、住み始めてから「想定より冷える」「予算をオーバーした」と後悔するケースが多く見受けられます。
ダウンフロアは床を下げる分、基礎の掘削や補強工事が必要になります。加えて、冷気が溜まりやすいため、断熱材を増やしたり床暖房を組み込んだりと、通常より費用がかさむ傾向があります。
実際に住宅情報サイトでも「ダウンフロア+断熱仕様にすると想定以上のコストがかかる」と注意を促しています。
ただ、計画段階で断熱やコスト配分をしっかり組み込んでおけば、結果は大きく変わります。たとえば床暖房と基礎断熱を同時に導入した家では、「冬も足元が冷えず快適」といった満足の声も多く聞かれます。
ダウンフロアの魅力を活かすには、見た目のデザインだけでなく「費用と断熱」をセットで考えることが欠かせません。
もし「多少の手間や費用がかかっても、納得の空間をつくりたい」と思えるなら、ダウンフロアのあるリビングはきっと後悔しない選択になるはずです。
壁なしでリビングとダイニングを分けたい人
リビングとダイニングを、仕切りの壁なしでうまく分けたい。そんな希望があるなら、ダウンフロアという設計手法がぴったりかもしれません。段差を活かして、空間を“ゆるく”切り替える感覚です。
実際、床の高さを20~30cmほど下げてリビングをつくると、視線の段差が生まれて、同じ空間にいながらも「別の場所にいるような落ち着き」が得られます。しかも壁がない分、光や風が遮られず、LDK全体に開放感が残ります。これは住宅デザインの現場でもよく活用されている工夫です。
たとえば、ある設計事例ではキッチンからダイニング、そしてリビングへと視界が自然につながっていく中で、リビングだけがひと段下がった設計になっていました。わざわざ仕切らなくても、ダイニングは食事の場、リビングはくつろぎの場と、過ごし方が自然に切り替わる。そんな心地よい「境界線」が生まれていたのです。
壁をつくらず、でも空間の役割ははっきり分けたい。そう思うなら、ダウンフロアはとても賢い選択肢です。間取りの自由度を高めながら、後悔のない家づくりにつながっていくはずです。
ほどよい囲われ感で落ち着く空間が好きな人
「ゆったりと心を落ち着けて過ごしたい」。そう感じる人にとって、ダウンフロアのあるリビングは一つの理想形かもしれません。床が少しだけ下がっていることで、空間にゆるやかな境界が生まれ、まるで安心できる“くぼみ”に身を預けるような心地よさが得られます。
実際に住宅設計を手がける工務店の事例でも、「段差による囲まれ感が、気持ちをふっと緩めてくれる」という声が紹介されていました。壁を建てて仕切らなくても、視線の高さが変わるだけで空間に役割が生まれるのは不思議なものです。
ある家では、リビングの床を30cmほど掘り下げ、段差部分に腰掛けられるように仕上げていました。お子さんはそこを遊び場として使い、大人はソファに沈み込みながら、ほどよく“包まれるような空気感”を楽しんでいるとのこと(参考:トヨタホーム施工事例)。
「籠っているけれど、閉じ込められてはいない」──そんな絶妙な距離感が、心地よさの理由なのかもしれません。
もしあなたが、開放感よりも“静かに落ち着ける居場所”を求めているなら、リビングに段差をつけるアイデアを一度検討してみてはいかがでしょうか。暮らし方に寄り添う形で設計できれば、「ダウンフロアで後悔した」という声とは無縁になるはずです。
目線が合い家族の様子を見守りたい人
「子どもがリビングで遊んでいる間も、キッチンからそっと様子を見ていたい」。そんな想いを持つ人にとって、ダウンフロアという選択は想像以上にフィットします。
実際に床を一段下げたリビングでは、ダイニングやキッチンから自然に視線が届きます。段差があることで空間はゆるやかに仕切られながらも、声や気配は遮られません。まるで半地下のような落ち着きがありつつも、完全に閉じられていない。だから、家族の距離感がちょうどいいのです。
新潟の住宅事例では、同じフロア面積でも段差を活かしたレイアウトによって「子どもが何をしているのか一目で分かって安心」という声が挙がっています。また、別の家づくり相談サイトでは「家事をしながらも、ソファに座る家族と自然に目が合う」といったリアルな感想が掲載されており、実際の暮らしの中での満足度も高いことがうかがえます。
「家族とのつながりを感じられる家にしたい」「でも全部を見渡すのは少し落ち着かない」。そんな人にこそ、ダウンフロアはひとつの答えになるかもしれません。空間を完全に区切らず、それでいて安心感のある間取り。このちょうどよさが、後悔のない選択へとつながります。
リビングをダウンフロアに決めて後悔しないための間取りづくりのポイント5選

リビングをダウンフロアにすると空間が引き締まり、おしゃれで個性的な印象になりますが、一方で「暮らしにくい」と後悔する人も少なくありません。
特に段差の扱いや冷え対策、動線の工夫が足りないと、不便さが目立ちやすくなります。
そこで、リビングをダウンフロアに決めて後悔しないための間取りづくりのポイント5選を紹介します。
快適な住まいを実現するための重要な視点として、ぜひ参考にしてみてください。
床暖房や断熱を強化して冬の冷えを防ぐ
冬になると、「せっかくのダウンフロアなのに、足元がひんやりする」と感じる人は少なくありません。
リビングの床を一段下げると、どうしても基礎部分に近くなるため、冷気が伝わりやすくなります。家づくりの段階で断熱や暖房を強化しておくことが、後悔を防ぐ大切なポイントです。
たとえば、ヤマダホームズの施工事例では「ダウンフロアでは冷気の滞留が起きやすく、断熱材の厚みを増やすことで快適性が大きく変わる」と紹介されています。また、リビング全面に床暖房を入れた住宅では「冬でも靴下を履かずに過ごせるほど暖かい」と好評です。
一方、断熱対策を軽視したケースでは「暖房をつけても底冷えする」「もっと考えておけばよかった」との声も多く見られます。
ダウンフロアの快適さは、見た目のデザインだけで決まりません。床下の断熱材の種類、施工の精度、床暖房の配置など、細部の積み重ねが暮らし心地を左右します。
「デザインも快適さも両立したい」と思うなら、設計段階で“冬の足元”までしっかり想像しておくことが、後悔しない家づくりの近道です。
採光と通風を意識して暗さとこもりを避ける
リビングにダウンフロアを採用する場合、「なんだか薄暗くて息が詰まりそう」という声が意外と多いのをご存知でしょうか。段差がある分、窓から入る光や風が届きづらくなり、居心地が悪く感じてしまうこともあるのです。
実際に、「南向きの窓があるのに日中も薄暗く、後悔している」といった住まい手の声もありました。段差によって、思った以上に光や空気の流れが遮られてしまうのですね。とくに冬場は日差しの入り方がシビアになるため、計画段階での工夫が欠かせません。
その対策として有効なのが、吹き抜けを設けて上から光を取り入れる方法や、高い位置に窓を設けて空気を循環させる工夫です。ある家では、リビングの上部に横長の高窓を設けたことで、午後の時間帯も自然光がやわらかく差し込み、「薄暗さから一転、穏やかで気持ちのよい空間になった」といった声も聞かれます。
ダウンフロアのある空間を快適に保つためには、単に見た目のデザイン性だけでなく、光や風の通り道にまで意識を巡らせることがとても大切です。間取りの自由度が高い注文住宅だからこそ、こうした点まで丁寧にプランニングしておくと、住み始めてからの満足度が大きく変わってきますよ。
段差の高さを抑えてつまずきにくくする
リビングをダウンフロアにするなら、段差の高さは“ほんの少し低め”を意識しておくと失敗がありません。
段差が高いと、日常の中でふとした拍子に足を引っかけやすく、暮らしの快適さを損ねてしまうことがあるためです。特に小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では、安全性を優先した設計が欠かせません。
住宅メーカーの設計担当者によると、20センチ以内の段差がもっとも移動しやすく、見た目のアクセントとしてもバランスが良いとのことです。実際、15センチ前後に設定したお宅では「段差が自然で違和感がない」「掃除のときもラク」という声が多く聞かれます。
一方で、30センチ以上の深い段差にしたケースでは「夜に踏み外しそうになった」「模様替えのときに家具の脚がぶつかる」といった後悔も少なくありません。
家づくりを進める際は、図面だけで判断せず、モデルハウスや完成見学会で実際の段差を体感してみることをおすすめします。歩いたときの感覚や視線の変化を確認すれば、自分たちの生活に合った“ちょうどいい高さ”が見えてきます。
小さな段差の違いが、暮らしやすさと安心感を大きく左右するポイントになるのです。
※カタログ?
子どもや高齢者に配慮し安全対策を徹底する
ダウンフロアのあるリビングは見た目におしゃれですが、小さな子どもや高齢の家族がいる場合は、段差による転倒のリスクを軽視できません。実際、20cm前後の段差であっても、高齢者にとってはつまずきやすく、思わぬケガにつながる可能性があります。
安全性を考えるなら、設計の段階で対策を織り込んでおくのが鉄則です(出典:高齢者が居住する住宅の設計に係る指針)。たとえば、段差の角を丸くして滑りにくい素材を選んだり、手すりや足元を照らす照明を設置するだけでも安心感が違います。特に夜間は視界が狭まるため、ほんのり光るフットライトがあると、移動中の不安がぐっと減ります。
ある家庭では、段差部分にクッション性のある素材を取り入れ、子どもが遊んでいても安心できる工夫をしていました。「万が一ぶつかっても心配ない」という声は、まさにリアルな住まい手の実感です。
ダウンフロアは暮らしに個性を与えてくれますが、家族の安全があってこそ成り立つもの。見た目やデザイン性に心が惹かれても、安全対策への配慮を最優先にすることで、将来的な後悔を避けられます。段差の魅力を活かしつつ、住まいとしての安心感も忘れずに整えておきましょう。
家具の置き場と配線コンセント位置を先に決める
リビングにダウンフロアを取り入れるとき、意外と見落としがちなのが「家具の置き場」と「コンセントの位置」です。
段差のある空間は視覚的におしゃれですが、その分レイアウトの自由度は下がります。「どこにソファを置くか」「テレビ周りの配線はどうするか」といったことを後から考えると、うまくいかないケースも少なくありません。
特に困るのが、コンセントが欲しい位置にない、という声。段差部分に家具をかけて配置するのが難しかったり、掃除機のコードが届かなかったりと、細かい不便が積もることで「ちょっと失敗だったかな」と感じる原因になります。
実際、床用コンセントを設けた家庭では「コードが見えずにすっきり暮らせる」といった満足の声がありました。一方で、計画を後回しにしてしまった方からは「延長コードだらけで見た目が台無し」「ソファの位置が制限されてしまった」といった声も聞かれます。
デザイン性だけに目を奪われず、「暮らしてからの動き」を一度シミュレーションしてみてください。日常のちょっとした不便は、設計の段階でほとんど防げます。家具と配線の位置、少し早めに考えておくだけで、リビングの満足度は大きく変わってきます。
【安心】リビングの間取りプランや家づくりのアドバイスを無料でもらえる裏ワザ

家づくりの間取りプラン作成でリビングをダウンフロアにしたいと考えていても、
「本当にこの間取りで良いのか?」「断熱性や段差の安全面は大丈夫?」と不安を抱える方は多いものです。
そんなときに頼れるサービスが『タウンライフ家づくり』です。プロの建築士やハウスメーカーが、希望条件に沿ったオリジナル間取りプランと見積もりを、完全無料で作成してくれます。
このサービスの魅力は、なんといっても“複数社の提案を簡単に比較できる”という点にあります。
例えば「ダウンフロア+床暖房でどの程度の費用がかかるか」「段差のあるリビングでもロボット掃除機を使いやすくできるのか」といった細かい要望にも、各社が異なるアプローチで応えてくれるため、納得いく形で選べるのです。
しかも提携している住宅会社は全国1,200社以上。大手から地域密着の工務店まで幅広く参加しているため、選択肢も豊富。実際の利用者からも「最初の希望を入力しただけで3社から間取りと資金計画が届き、比較しやすかった」という声がありました。
申し込みはすべてオンラインで完結し、希望エリアや家族構成、建てたい家のイメージを入力するだけ。営業電話の心配も少なく、自分のペースでじっくり検討できます。
改めて『タウンライフ家づくり』を利用するメリットをまとめると、
- 3つの提案が“すべて無料”で一括入手!
希望に沿った「間取りプラン」「資金計画」「土地探し」の3プランを受け取れ、家づくりが一気に進む! - 複数社の提案を自宅で比較検討できる!
家にいながら、簡単に価格や間取りを“比較”できるので適正価格が分かり、効率よく候補を絞り込める! - 全国の信頼できる住宅メーカーから厳選された提案を受けられる!
全国1,200社以上・大手ハウスメーカー36社以上が掲載&提案するのは国家基準を満たすメーカーのみ!
さらに!利用者の方限定で、プレゼント(成功する家づくりの7つの法則と7つの間取り)も受け取ることができます!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、読み応えあって今後の家づくりを進めるヒントが満載でした。
家づくりにおいて、最初の間取り設計こそが成功のカギ。
「ダウンフロアで後悔しない間取り」にたどり着くためにも、プロの視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
「無料でここまでしてくれるの?」と驚く人が多い、お得で心強いサービスです。ぜひ活用してみてください。
【Q&A】後悔する声も目立つリビングのダウンフロアに関するよくある質問

最後に後悔する声も目立つリビングのダウンフロアに関するよくある質問をまとめました。
ダウンフロアの後悔の理由やその対策方法、赤ちゃんや高齢者がいる家庭、老後の暮らしを見据える方にとっても役立つヒントを、解説していきます。
スキップフロアが得意なハウスメーカーは?
スキップフロアを得意とするのは、構造計算や動線設計まで一貫して提案できる大手メーカーや、空間設計に強い工務店です。
実際に評判が高いのは、住友林業やユニバーサルホームなど。前者は「床を掘り下げたピットリビング」事例を多数公開しており、後者は「ほっとピット」という専用プランを展開しています。こうした企業は、段差の高さ・視線の抜け・空調効率などを考慮した提案が得意です。公式サイトで実例や間取りを比較し、自分の暮らしに近い提案をしてくれる会社を選ぶと失敗が少なくなります。
ダウンフロアは赤ちゃんに危ないけど対策できる?
段差のあるリビングは赤ちゃんには少し心配…そう感じる方は多いかもしれません。でも、工夫しだいで安全に暮らすことは十分に可能です。
例えば、段差の前に市販のベビーゲートを取り付けるだけでも、転落のリスクはかなり減ります。さらに、段差の角をクッション素材で保護したり、床材を滑りにくいものにしたりといった対策も効果的です。実際に厚生労働省の調査でも、家庭内の事故で多いのは「転倒」や「転落」なので、段差をどう扱うかは設計時に意識したいポイントです。目が届きやすいレイアウトにしておくことも安心につながります。
ブログではスキップフロアのどんな点に後悔してる?
スキップフロアに憧れて取り入れたけれど、「やっぱり失敗だった」と感じる人も少なくありません。
多くの後悔の声に共通しているのが、掃除やレイアウト、寒さ、そして段差による不便さです。「ロボット掃除機が使えない」「家具の配置が制限されて模様替えがしづらい」といった日々のストレスが蓄積し、次第に後悔につながってしまうのです。また、「床が冷える」「小さな子どもや高齢者に危険」など、暮らしの安全面への不安も挙げられています。こうした声から見えてくるのは、「見た目だけで決めると生活のしづらさに悩まされる」という現実です。だからこそ、設計段階で不便さやコスト面を想定し、しっかりと対策を立てておくことが後悔を防ぐポイントになります。
ピットリビングは老後の暮らしに向いている?
段差のあるピットリビングは、年齢を重ねた暮らしには少し不向きかもしれません。
バリアフリーが重要視される中、段差があることで移動が大変になったり、転倒の危険が高まるといった懸念が残ります。もし将来的な不安を感じるなら、あらかじめ手すりの設置や段差を低くする設計を取り入れておくと安心です。また、段差を埋めてフラットに戻せるような構造にしておくと、ライフステージが変わっても住み続けやすくなります。
ピットリビングに合うソファの高さはどれ?
ピットリビングに置くソファは、高さ選びがとても大事です。
一般的には、座面の高さが38cm~40cm前後のものが使いやすいとされています。この高さは、日本人の平均身長を基準にしたとき、立ち座りの負担が少なく、姿勢も安定しやすいちょうどよいバランスだからです。ただし、ピットの床面から見たときの“目線の低さ”や“圧迫感”にも配慮して、ローテーブルや照明との相性も一緒に考えると快適さが変わってきます。インテリアショップで実際に座って確かめるのが一番確実です。
まとめ:リビングをダウンフロアにすると後悔するのかをメリット・デメリットで紹介
リビングをダウンフロアにすると後悔するのかをメリット・デメリットで紹介してきました。
改めて、ダウンフロアのメリット・デメリットをまとめると、
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| ダウンフロア |
|
|
そして、ダウンフロアで後悔しないための5つの結論もまとめると、
- 段差の高さは低めに設計してつまずきにくくすることが大切
- 子どもや高齢者が安心して使えるよう安全対策を徹底することが必要
- 家具の置き場とコンセントの位置を事前に明確に決めておくことが重要
- 事前に複数の間取りプランや費用を比較することで後悔を防げる
- 無料で間取り提案がもらえる「タウンライフ家づくり」の活用がおすすめ
ダウンフロアにすると空間にメリハリが生まれおしゃれになりますが、使い方次第で「ダウンフロア 後悔」につながることもあります。
段差の高さや安全性、レイアウト計画をしっかり考え、プロのアドバイスを活用することで、暮らしやすく満足度の高いリビングを実現できます。