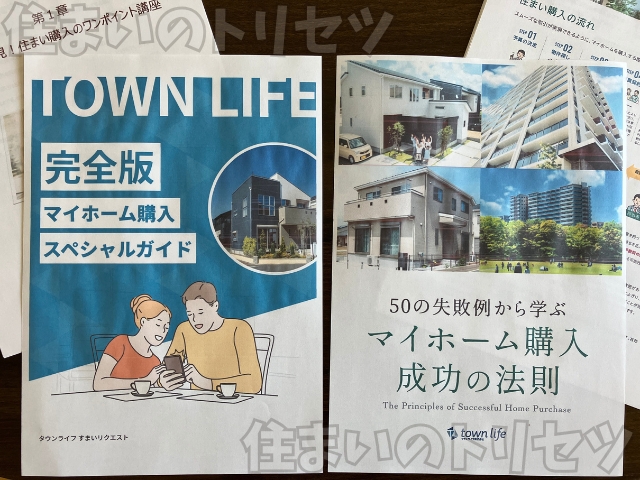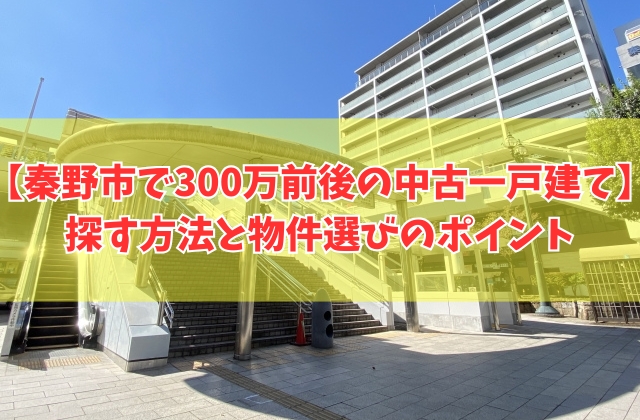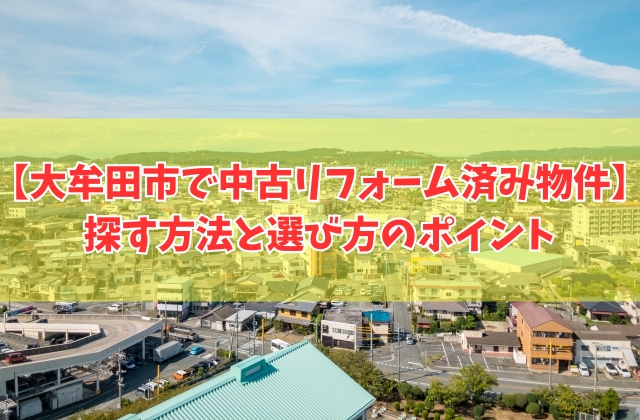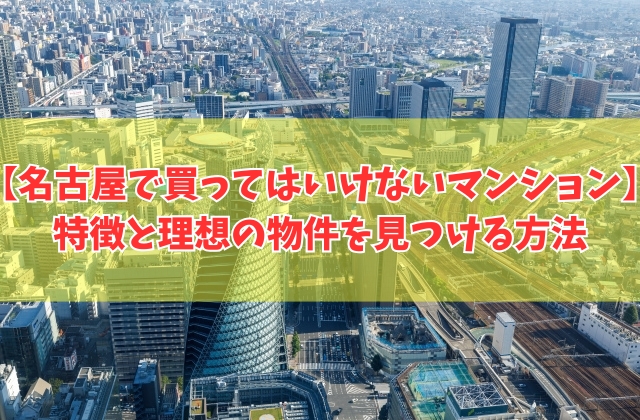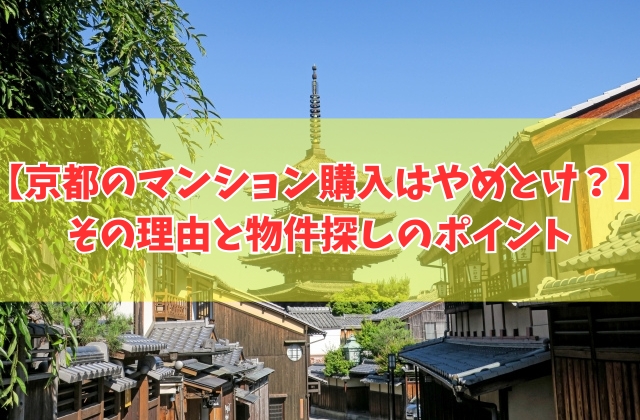
「京都のマンションは買わない方が良いってホント?」
「物件探しのポイントは?買って後悔しないためにどんな対策が必要?」
京都でマンション購入を検討していると、「本当に買っても後悔しないのか…」と不安になる方は少なくありません。
観光地としての魅力がある一方で、住環境としては一筋縄ではいかない現実もあります。
ネット上では「京都のマンションは買わない方が良い」といった声も多く見かけますが、その背景には明確な理由が存在します。
この記事では、購入を検討している方に向けて、メリットとデメリットの両面から京都のマンション事情を丁寧に解説します。
- 景観規制や建築制限により自由度が低く、将来の資産価値に不安が残る
- 観光地特有の騒音や混雑、ゴミ問題が生活の質に影響する可能性がある
- 供給が少なく価格が高止まりしており、割高な物件を掴みやすい
「京都のマンションは買わない方が良い」と言われる背景には、景観保全の縛りや観光都市特有の課題、そして需給バランスの崩れによる価格高騰など複数の要因があります。
購入を検討するなら、十分な下調べと事前対策、そして慎重な判断が必要です。
では後悔しないためにも、どうやって物件情報を集めればいいのか?できれば、ネットで簡単に物件情報を受け取れる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用する方法です。
「タウンライフすまいリクエスト」とは、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
- 非公開物件&値下げ物件の情報がもらえる!
複数社への一括依頼により、広告掲載前や値下げ前の“掘り出し物件”に出会える可能性が高まる - 物件探しの手間・時間を大幅に削減できる!
60秒の簡単入力だけで、複数の不動産会社から資料・提案が一括で届くので、自分で探す手間が省ける - 信頼できる複数の不動産会社の中から選べる!
登録企業は全国170社以上、独自基準をクリアした優良な不動産会社に限定。安心して比較・選択ができる
さらに!タウンライフすまいリクエスト利用者限定で2つの特典が必ずもらえるプレゼントを実施中!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、40ページを超える読み応えありの内容で、今後の物件探しのヒントが満載でした。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
【結論】京都のマンションは買わない方が良いってホント?

京都のマンションは買わない方が良いのかどうか。
結論からいうと、「京都のマンションは買わない方が良い」という意見には、一理あります。もちろん全ての物件がそうだとは言いませんが、注意して見極めないと“高い買い物で失敗した”と感じるリスクがあるのは事実です。
たとえば京都では、古都ならではの景観保全のルールが非常に厳しく、マンションの高さや外観のデザインに多くの制限がかかります。その影響で、建築コストや維持費が割高になるケースも少なくありません。さらに観光都市という特性上、繁忙期には周辺の騒音やゴミの問題も顕在化しやすく、住環境としては落ち着かないエリアもあります。
また、京都は地理的に見ても地震の揺れが強く出やすい地盤が多く、液状化のリスクもゼロではありません。国や自治体が出しているハザードマップを見れば、地震や浸水リスクの高い地域が市内にも点在しているのが分かります。
こうした現実を知ったうえで、それでも京都に暮らしたい、資産として持ちたいという人であれば、物件選びさえ間違えなければ満足できる可能性は十分あります。逆に、「なんとなく京都って良さそう」で買うと、後悔するかもしれません。
京都のマンション購入を検討するのであれば、メリットだけでなく、デメリットにもちゃんと目を向けておくべきだといえます。
京都のマンションは買わない方が良いと言われる5つの理由
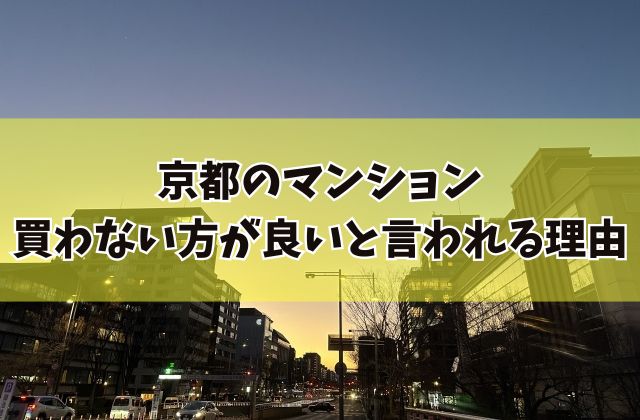
京都でマンション購入を検討する際、多くの人が「京都のマンションは買わない方が良い」と耳にしたことがあるのではないでしょうか。
たしかに、魅力的な街である一方で、購入後にギャップを感じやすい落とし穴も存在します。
実際に後悔の声が上がる背景には、地域特有の事情や不動産市場の傾向が関係しています。
ではどういった理由で「買わない方が良い」と言われているのか。
ここでは、その具体的な京都のマンションは買わない方が良いと言われる理由を5つの観点で考察していきます。
京都の景観保全規制で自由な設計が難しいから
京都でマンションを購入しようとする際、多くの人がまず直面するのが「景観保全の壁」です。外観や高さに対する制限があまりに細かく、自由な設計を望む人にとっては、思っていた以上にハードルが高いと感じるかもしれません。
実際、京都市では「新景観政策」によって市内全域で建物の高さに上限が設けられ、美観地区や歴史的建造物周辺ではさらに厳しくなります。たとえば、ある地域では建物の高さが10メートルまで、屋根は必ず切妻型、外壁は彩度4以下の落ち着いた色合いしか認められないなど、条件が極めて細かく指定されています(出典:京の景観ガイドライン)。
こうしたルールがある背景には、千年の都としての景観や文化を守る意図があることは理解できますが、その分だけ、購入者や設計者にとっての自由度はどうしても狭まってしまいます。気に入ったデザインの物件があっても、許可が下りなかったり、建て直しやリノベーションが思うようにできないケースも多々あるのが実情です。
「京都らしさ」を守る街だからこそ、マンションの選び方にも柔軟性が求められます。建築の自由を求める人にとっては、こうした規制が「京都のマンションは買わない方が良い」と言われる大きな理由の一つになっているのは間違いありません。とはいえ、制限の中でも工夫された魅力的な物件も存在します。ルールを知った上で、納得して選べるかどうかが鍵になるでしょう。
観光客増加による騒音やゴミが問題になりやすいから
京都でマンションを検討する際に、意外と見落とされがちなのが「観光公害」の問題です。住み始めてから「思っていた以上にうるさい」「ゴミが多くて清潔感がない」と感じる人が少なくありません。
京都市が行った調査によれば、宿泊施設周辺に暮らす住民のうち約37%が「騒音やゴミ、車の混雑に困っている」と回答しています。特に祇園や四条周辺、京都駅の近くなどは外国人観光客や国内旅行者で常に賑わい、夜遅くまで人の声が響き、歩道には持ち込んだ軽食のゴミが散乱している場面もしばしば見受けられます。
実際、マンションのベランダで洗濯物を干しても、風に乗ってたばこの煙が漂ってきたり、深夜まで近くの飲食店から話し声が聞こえたりすることも。便利さと賑わいが魅力の一方で、静かに暮らしたい人にはストレスに感じられる場面も多いのが現実です。
京都の中心部に住むということは、風情ある街並みと同時に、人が多く集まる“観光都市”の一角に暮らすということ。だからこそ、「京都のマンションは買わない方が良い」と言われるのも無理はありません。物件を選ぶ際には、パンフレットの立地情報だけで判断せず、昼と夜、それぞれの時間帯に実際の周辺環境を自分の目と耳で確かめておくことを強くおすすめします。
マンション供給が少なく価格が高騰しやすいから
京都でマンションを探している人の中には、「そもそも選べる物件が少ない」と感じたことがあるかもしれません。実はそれ、気のせいではありません。実際、京都市内の新築マンションの供給数は年々減少傾向にあり、2024年はわずか2,002戸。これは近畿全体の約13%ほどで、大阪や兵庫に比べて圧倒的に少ない水準です(出典:Kantei Eye)。
数が少なければ、当然価格も上がります。全国的にマンション価格は上昇していますが、京都も例外ではありません。2024年の近畿圏における新築マンションの平均価格は6,200万円を超え、前年比で20%以上も上昇しています(出典:マンション・一戸建て住宅データ白書2024)。特に京都は「土地が限られ」「景観規制がある」など、供給そのものにブレーキがかかりやすい地域です。
たとえば、烏丸御池や岡崎といった人気エリアでは、売りに出る物件数がそもそも少なく、出たとしてもすぐに売れてしまう状況が続いています。そのため、価格が多少高くても「今買わないともう出てこないかも」という心理が働き、相場がさらに押し上げられるという悪循環が起こりがちです。
こうした背景を知らずに物件探しを始めると、「こんなに高いとは思わなかった」「選択肢が少なすぎる」と感じてしまうことになります。だからこそ、「京都のマンションは買わない方が良い」と言われる理由のひとつとして、この“供給の少なさと価格の上昇”があるのです。焦って決めず、タイミングと情報収集をしっかりと見極めることが、後悔しない買い方につながります。
中古マンションの再生や修繕費が読みにくいから
中古マンションを検討しているなら、価格の手頃さだけで決めてしまうのは少し危険です。というのも、物件の表面からは見えにくい「修繕費のリスク」が後からのしかかってくることがあるからです。
実際、京都市内の中古マンションでも、築20年を超える物件では外壁や共用部分の大規模修繕が迫っているケースが多く、一戸あたりの負担が100万円を超えることも珍しくありません(出典:令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査)。足場の設置だけでも30万円前後がかかることがあり、積立金だけでは足りず追加徴収が発生する場合もあります。
とくに築年数が古くなると、見た目では分からないような配管の劣化や防水工事の必要性なども出てきます。リフォームを始めたあとに「思った以上に傷んでいた」と分かり、想定外の出費が発生する…という話は、実際の購入者からもよく聞かれます。
この“読めなさ”が、京都のマンションは買わない方が良いと言われる理由の一つです。マンション選びの段階で、過去の修繕履歴や管理組合の積立状況までしっかり確認しておかないと、後悔する可能性があります。見た目や立地の良さだけに惑わされず、数字や裏側までチェックしてこそ、本当に安心できる住まい選びにつながります。
京都の地震や液状化リスクが他地域より高いから
京都でマンションを選ぶときに、地震のリスクを軽く見てしまうのは危険です。実は京都市は地震の揺れが強く出やすい地盤が多く、しかも液状化の危険性がある地域も少なくありません。
京都市のハザードマップを確認すると、鴨川や桂川周辺、埋立や低地エリアの一部では「液状化の恐れ・中~大」とされる場所が点在しています。阪神淡路大震災クラスの地震が直下型で発生した場合、地下インフラや建物基礎に深刻なダメージが出ると想定されており、京都府の想定では最大4,000人以上の死者が出る可能性があるとの報道もあります。
たとえば、マンホールが浮き上がったり、道路が波打つように沈下したりといった現象は、過去の大地震でも現実に起きたことです(出典:液状化によるマンホールの最大浮上量の推定法)。そして、それが「買ってから知った」では済まされない話なのです。
だからこそ、京都のマンションは買わない方が良い——とする声が一定数あるのも無理はありません。ただし、全域が危険なわけではありません。地盤調査が明確にされている新築や、過去に大きな被害が報告されていないエリアを選べば、リスクを避けながら安心して暮らせる選択肢もきちんとあります。購入前には、見た目だけでなく「足元の安全」までしっかり調べておくことが、後悔しない第一歩になります。
買わない方が良いと言われても京都でマンションを買うメリット

「京都のマンションは買わない方が良い」と言われる理由には確かに一理あります。
ですが、それでも購入する価値があると感じる人がいるのも事実です。
なぜなら、京都ならではの魅力や不動産としての希少性は、他の地域ではなかなか得られないものだからです。
その具体的な京都でマンションを買うメリットとはなにか。
「買わない方が良いと言われても京都でマンションを買うメリット」では、そんな前向きな理由を整理して紹介していきます。
資産価値が落ちにくく希少性が高い
「京都のマンションは高いだけで割に合わない」と感じている人も多いかもしれませんが、実は資産として見ると意外な強さを持っています。その理由は、物件そのものの“数の少なさ”にあります。
たとえば、地下鉄「京都市役所前」や「烏丸御池」周辺の中古マンションでは、過去に比べて価格が落ちにくく、むしろ購入時より高く売れる例もあります。調査データによると、これらのエリアでは新築価格に対して中古でも1.1~1.2倍、中には特定の人気マンション・立地・築浅の場合で1.5倍といった水準で取引されているケースが報告されています。これは他の都市と比べてもかなり高い比率です。
なぜここまで高値が維持されるのか。その背景には、京都市が景観保全を重視し、高層建築や無秩序な開発を厳しく制限している事情があります(出典:景観政策による建築活動等への影響)。つまり、「欲しくてもなかなか手に入らない」からこそ、資産としての希少性が際立っているのです。
もちろん、すべての物件が高騰するわけではありません。ただ、長く住むつもりで買っても、将来手放すことになったときに値崩れしにくいという点で、京都の物件には他地域にはない強みがあります。「買わない方が良い」という意見がある一方で、こうした資産価値を重視する人にとっては、むしろ“選ぶ理由になる”のが京都のマンションなのです。
観光地ゆえ賃貸ニーズが強く高利回り
京都でマンションを買うメリットのひとつが、「貸しやすさ」と「収益の安定感」です。観光地という特性から、住まいとしてだけでなく投資対象としても注目されています。
実際、中心部ではAirbnbのような民泊が年間の稼働日数で約300泊という高い数字を叩き出しており、稼働率にして80%前後。これはホテル並みの回転率で、需要がいかに安定しているかを物語っています。
収益面でも、480万円台の中古ワンルームで月4万円の賃料が見込める例があり、表面利回りはざっくり計算して10%近く。これが首都圏ならせいぜい5~6%ということを考えると、京都の物件は利回りという点で非常に優秀です。
もちろん、民泊運用には法律の制約やエリア指定がありますし、管理の手間もゼロではありません(出典:住宅宿泊事業法(民泊新法)とは)。ただ、そういったハードルを乗り越えてもなお「回す価値がある」と感じさせるのが、京都の不動産です。
「京都のマンションは買わない方が良い」と言われる背景には、住まい目線の懸念が多いのも事実ですが、賃貸・投資目線で見れば評価はまったく変わってきます。資産を活かすという視点で見れば、むしろ選びたくなる立地が、京都には確かに存在しています。
企業や大学が多く、転勤者・移住者が多い
京都の街には、ひっそりとした町家や観光地のイメージが強いかもしれませんが、実は“働く人”と“学ぶ人”が常に流動している都市でもあります。そのことが、マンション需要を底支えする大きな力になっています。
たとえば任天堂、京セラ、島津製作所など、全国区の大企業の本社や研究所が京都市内に点在しており、転勤でこの街にやってくる単身者や家族も少なくありません。加えて、京都大学や同志社大学など名の知れた大学も多く、学生や教職員、研究者といった“住まいを必要とする人”が、毎年一定数流入してくるのが特徴です。
こうした背景があるため、エリアによっては「転勤者向けの賃貸はすぐ埋まる」「大学近くのワンルームは常に需要がある」といった声を、地元の不動産会社からよく聞きます。住む人が常に入れ替わる分、賃貸市場が活発で、空室リスクが低く保たれているのです。
「京都のマンションは買わない方が良い」という意見には一理あるものの、こうした継続的なニーズがある場所なら、むしろ“買って貸す”という戦略が成立します。観光や歴史だけではない、暮らしと働きが交差する都市・京都だからこそ成立する需要といえるでしょう。
交通利便性の良いエリアが多い
京都の暮らしで魅力的なのは、何といっても“移動のしやすさ”です。街全体がコンパクトにまとまっていて、電車・地下鉄・バスが無理なく共存している都市は、全国でもそう多くありません。
たとえば、地下鉄烏丸線を使えば、京都駅から北の今出川まで一直線でつながっており、通勤・通学にも観光にも使いやすい路線です(約6分~7分程度)。さらに、阪急京都線の桂や西院といったエリアでは、大阪・梅田方面へのアクセスもスムーズ(約42~46分程度で直通)。西院に至っては阪急と嵐電(京福電鉄)が交わるジャンクションのような立地で、地元の人たちからも「車がなくても不便しない」と評判です。
駅周辺の便利さにも注目したいところです。烏丸御池や四条烏丸、西院といった駅前には、日用品が揃うスーパーや商業ビルが密集していて、帰り道に買い物を済ませられるのも大きな魅力のひとつです。こうした日常の“ラクさ”は、数字には見えないけれど、住む人にとってはとても大切です。
「京都のマンションは買わない方が良い」という声も聞かれますが、交通の便という視点から見れば、話はまったく別です。暮らしやすさを左右する“足回りの良さ”が、京都の強みであることは間違いありません。どこに住んでも、どこへ行くにも困らない——そんな安心感が、京都の街にはしっかり根づいています。
景観規制で将来の競合が増えにくい
京都の街には、時間が積み重なっています。歴史ある町並みを守るために、建物の高さや色、外観のデザインまで厳しく規制されているのはご存じでしょうか。たとえば、五条通周辺や東山エリアでは景観条例によって、建て替えや新築すら簡単にはできません(出典:京の景観ガイドライン)。
これはマンション市場にとって、実は非常に大きな意味を持ちます。なぜなら、新築物件の供給が限られるということは、既存物件の価値が相対的に下がりにくいことを意味するからです。競合が増えづらい環境は、結果的に空室リスクの低減にもつながります。
不動産投資家の間では「京都の物件は出口戦略が立てやすい」との声もあります。供給が絞られるからこそ、買い手がつきやすい。そんな“市場構造そのもの”が他のエリアにはない強みになっています。
派手さはなくても、じわじわと効いてくる——。京都の景観規制は、そんな堅実な安心を物件価値に与えてくれる存在なのです。
京都で買わない方が良いマンションを見抜く物件探しのポイント
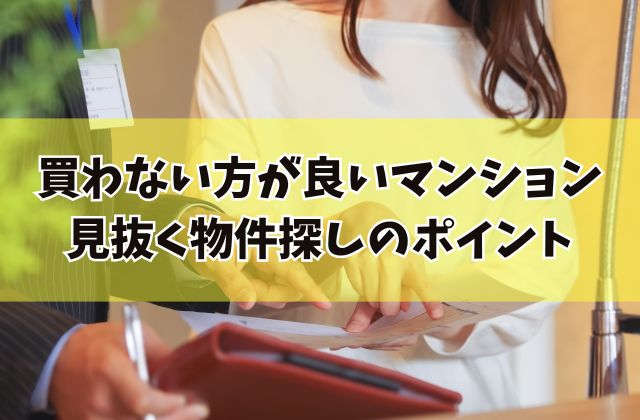
ここまで、京都のマンションは買わない方が良いと言われる理由と購入メリットを整理してきました。
京都でマンション購入を考える際には、「京都で買わない方が良いマンションを見抜く物件探しのポイント」を知っておくことが重要です。
立地や価格だけで判断すると、後々後悔することも少なくありません。
見逃しやすいチェックポイントを押さえながら、長く安心して住める物件かどうかをしっかり見極める目が求められます。
共用部の管理状態を目で見て確認する
どれだけ立地が良くても、エントランスをくぐった瞬間に「うーん」と眉をひそめてしまうマンション、意外とあります。共用部は、その建物がきちんと手入れされているかどうかが如実に現れる場所。つまり、ここを見れば、管理が機能しているかどうかがわかるのです。
たとえば、
- ゴミ置き場に悪臭が漂っていたり、分別が適当だったりする
- 廊下や階段に私物が放置されている
- 掲示板が古いまま、何ヶ月も更新されていない
こうした状態が見受けられる物件は、住民のマナーや管理組合の活動状況にも不安が残ります。日々のメンテナンスが行き届いていないマンションは、資産価値もじわじわ下がりやすく、いざというときに売りにくいという事態にもつながりかねません。
実際に物件を見に行った際は、室内の広さや間取りだけでなく、共用部分にも目を配ってください。派手な設備はなくても、清掃がきちんとされ、掲示板に新しいお知らせが貼られているようなマンションなら、管理がしっかりしている証拠。そうした小さなサインを拾えるかどうかが、良い買い物につながるかどうかの分かれ道になります。
建物外観や内装の劣化をしっかり見る
京都で中古マンションを購入する際に見落としがちなのが、建物の外観や内装の“細かな傷み”です。見た目はきれいでも、よく観察すると修繕が必要なサインが潜んでいることは少なくありません。
たとえば外壁。タイルの剥がれや細かいヒビ、白い粉のような汚れ(白華現象)が出ている場合は、内部のコンクリートにまで水分が染み込んでいる可能性があります。ひびから雨水が侵入していれば、鉄筋が錆びて建物の寿命に関わる事態も起こり得ます。
室内では、床のきしみや傾き、天井の染み、クロスの浮きなどが要チェックポイントです。一見すると小さな問題に見えても、水漏れが原因だった場合はリフォーム費が跳ね上がることもあります。
内見時には以下を確認しておくと安心です:
- 外壁:ヒビ割れ、タイルの浮き・剥がれ、白い粉状の汚れ(白華)
- 雨樋や鉄部:錆びや変形の有無
- 室内:床のたわみ、天井や壁のシミ・カビ跡、壁紙の浮きや剥がれ
物件の第一印象に惑わされず、細部をしっかり見ることが失敗しない購入のカギです。見えないところにこそ、本当のコストが潜んでいます。
管理費や修繕積立金の積み立て状況を確認する
中古マンションを検討するうえで見落としがちですが、管理費と修繕積立金の状況は、その後の暮らしや資産価値に直結します。「なんとなく大丈夫そう」では済まされません。
とくに修繕積立金。これはマンション全体の将来の大規模修繕に備えて、住民全員で少しずつ積み立てていく“共通のお財布”のようなものです。ところが実際には、全体の約35%ものマンションで積み立てが不足しているという調査結果もあり、油断できません。
内見時には室内の状態ばかりに目が向きがちですが、重要なのは「数字」。購入前には「重要事項調査報告書」や長期修繕計画書をしっかり見てください。残高の少なさや、滞納住戸の有無、今後の値上げ予定などを確認すれば、「思ったより出費がかさむ」と後悔するリスクをぐっと減らせます。
ちなみに、京都市内のマンションなら、月額の修繕積立金は15,000~25,000円ほどがひとつの目安。高すぎても安すぎても注意が必要です。価格だけに目を奪われず、こうした“見えにくい出費”にこそ目を光らせてください。
最寄り駅まで実際に歩いて利便性を確認する
不動産広告に「徒歩10分」と書かれていても、それを鵜呑みにするのは危険です。住み心地や通勤のストレスを大きく左右するのが“駅までの道のり”。だからこそ、物件を見に行く際は、駅から実際に歩いて確認するのが鉄則です。
というのも、徒歩時間の目安は「1分=80メートル」で算出されていますが、地図上の距離と実際の所要時間は必ずしも一致しません。信号の多さ、坂の有無、街灯の明るさ、舗装の状態など、歩いて初めてわかる要素がたくさんあります。特に京都のような歴史ある街では、細くて入り組んだ道や観光客でにぎわうエリアを通る場合も多く、時間と体力の感覚がズレやすいのです。
たとえば、ある中古マンションの資料には「駅徒歩9分」と記載されていても、実際に歩いてみると信号待ちが多く、朝の通勤時には15分近くかかるケースも。そうなると、購入後に「想像と違った」と後悔しかねません。
物件探しでは間取りや築年数も大切ですが、毎日の通勤や生活を支える“駅までの距離”は、思った以上に暮らしやすさと資産価値を左右します。数字ではなく、自分の足で体感してこそ、本当に納得のいく判断ができるのです。京都でマンションを探すなら、紙の情報だけでなく、自分の歩幅と感覚を頼りにすることも忘れないでください。
換気や風通しの良さも内見時にチェックする
住み心地を大きく左右するのが「風の通り道」です。どんなに設備が整った物件でも、空気がこもる部屋では快適に暮らせません。実際、湿気が抜けない住まいは、カビや結露、ニオイの原因になり、体調を崩す原因にもなります。
特に京都のように四季がはっきりしていて、梅雨や冬場に室内干しをすることが多い地域では、空気の流れは軽視できません。現地での内見時には、窓の位置や数、換気扇の場所をしっかり確認しておきましょう。
窓が東西にひとつずつあれば理想的ですし、ワンルームであってもドアやサッシの開閉で空気が抜ける導線が確保されているかを目で確かめるのが鉄則です。
目に見えない「空気の通り道」は、実際に現地で体感しないと判断できません。チェックを怠ると、入居後にジメジメした空気と一緒に後悔がついてくるかもしれません。細かいことに見えるかもしれませんが、風通しの良さは“快適な暮らし”を左右する本質です。
京都のマンションを買うならどのエリアがおすすめ?厳選3つ

「京都のマンションは買わない方が良い?」と悩んでいる方でも、場所次第では十分に魅力的な投資先や住まいとなるエリアがあります。
そこで、今回は“京都のマンションを買うならどのエリアがおすすめ?厳選3つ”という視点から、生活のしやすさや将来的な資産価値にも注目しながら、買って後悔しにくい地域をピックアップしました。
通勤や買い物の利便性、住環境の快適さなど、実際に暮らすことをイメージしながら参考にしてみてください。
烏丸御池エリアは交通・買い物利便性が高い
「便利に暮らしたい」と考えるなら、京都市内でまず候補に入れたいのが『烏丸御池』です。
理由はシンプルで、地下鉄烏丸線と東西線の2路線が交差する要所であり、京都駅・三条・河原町などの主要エリアまで一本で行ける好立地だからです。LIFULL HOME’Sのエリア評価では、交通利便性がなんと4.6点/5点満点。数字で見ても、この街の「通いやすさ」は頭ひとつ抜けています。
さらに魅力的なのが、生活のしやすさです。駅周辺には「新風館」をはじめ、スーパーやおしゃれなベーカリー、日用品店など、日常の買い物に困ることはまずありません。実際、駅徒歩圏にある築浅の1LDKマンションの賃料は月13~14万円前後と、中京区の中でも需要の高さがうかがえます。住環境に対する期待値がそのまま価格に表れていると言ってよいでしょう。
交通も買い物も、どちらも妥協したくない方にとって、烏丸御池はまさに“ちょうどいい街”。利便性だけでなく、京都らしい街並みもほどよく残っているので、生活に潤いを感じられるのも大きな魅力です。
桂エリアは特急停車駅で大阪方面にもアクセス良好
『桂エリア』が注目を集めている理由のひとつが、「アクセスの良さ」です。阪急京都線の桂駅には、通勤特急や快速急行など、すべての電車が停車します。
これが何を意味するかというと、例えば朝の通勤時でも、乗り換えなしで大阪の梅田まで出られるということ。実際、特急を使えば桂駅から阪急大阪梅田駅まで約34分。京都市中心部の四条河原町へも10分ほどでアクセス可能です。
しかも、桂駅は始発・終着の電車も多く、帰宅ラッシュ時でも座れる確率が高いというメリットも。日々の通勤でのストレスが少なく、家に着いたときに「やっと帰ってこられた」と感じられるのは、実はとても大きなポイントです。
こうした背景から、桂エリアは大阪方面に通勤・通学する人にとって、非常にバランスの取れた居住地と言えます。生活の拠点を京都に置きつつ、大阪へのアクセスもスムーズにこなしたいなら、桂のマンションは候補に入れておいて損はありません。
西院エリアは交通・商業利便性が抜群で賃貸需要も安定
京都で「ここなら買ってもいい」と思える場所を探すなら、『西院(さいいん)』は候補に入れて損はありません。阪急・京福・地下鉄の3路線が乗り入れ、どこへ出るにもアクセスがスムーズ。朝の通勤ラッシュでも、烏丸や河原町、大阪方面へ乗り換えなしで行けるのは大きな強みです。
駅前には、イオンモール京都五条や西友、ドラッグストア、チェーン系飲食店が揃い、生活に必要なものは一通りそろいます。利便性だけでなく、住む人の回転も早い地域なので、賃貸需要が常に一定しており、築浅物件では利回り9%前後の事例も確認されています。
利便性・収益性・資産性、その全てがバランスよく備わっているのが西院です。京都でのマンション購入に迷ったら、まずはこの街を実際に歩いてみる価値があります。
京都のマンションを買って失敗しないための事前対策3選
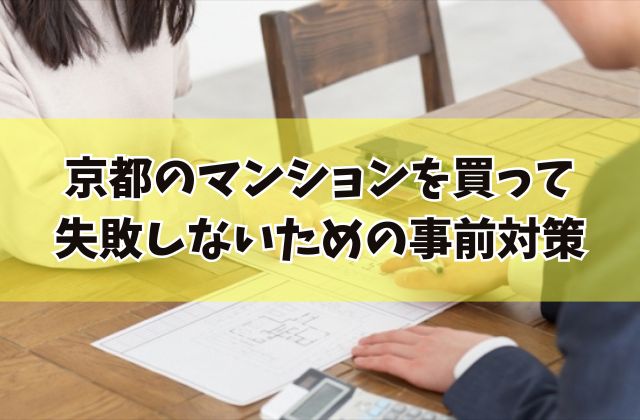
京都でマンション購入を検討する際、住環境の特性や将来のリスクを見落とすと、後悔する結果になりかねません。
特に「京都のマンションを買って失敗しないための事前対策」を把握しておくことで、購入後のミスマッチを防ぎやすくなります。
ここからは、京都で慎重にマンションを選ぶための具体的な視点を3つご紹介します。
信頼できる不動産会社から情報を集めて比較検討する
マンション購入を考えるとき、最初に頼るのが不動産会社という人は多いはずです。だからこそ、どこから情報を得るかはとても重要です。京都市内には地元密着型の不動産会社から全国展開の大手まで数多くありますが、同じ物件でも提案内容や条件、対応の丁寧さには驚くほど差があります。
例えば、京都駅周辺の物件を探すなら、「京都ライフ」や「アパマンショップ 京都駅前店」などは対応が早く、取り扱い物件数も豊富です。一方、売買の相談なら「三井のリハウス 京都四条センター」や「東急リバブル」などの大手が持つ情報網や安心感は見逃せません。口コミやオリコンなどの顧客満足度ランキングも、会社選びのひとつの目安になります。
実際に店舗に足を運んで、話してみてください。「この担当者なら安心して任せられる」と思える相手に出会えるかどうかで、その後の流れが大きく変わります。情報を比較検討するのは手間がかかりますが、急がず慎重に動いた方が、結果的に後悔のない選択につながるはずです。
では、どうすれば信頼できる不動産会社から情報を集めることができるのか?できればネットで簡単に、家にいながら情報を集める方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用する方法です。
「タウンライフすまいリクエスト」は、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
現実的な資金計画を立てて無理のないローンにする
住宅ローンは、額面ではなく「返せる金額」で考えることが大切です。京都府内の平均借入額はおよそ3,564万円で、月々の返済は約11万5,000円(出典:フラット35利用者調査)。これは近畿エリアの中でもやや高めの水準です。年収が500万円程度であれば、手取り月収は約30万円。そこから家賃やローンに充てられる金額は、せいぜい月12万円前後が限度だと感じる人が多いはずです。
たとえば、3,000万円を金利1.4%、35年ローンで借りると、月々の返済はおよそ9万円程度。生活にゆとりを持たせたいなら、このぐらいに抑えておくのが安心です。しかも京都は都市部より物価が安定しているとはいえ、修繕積立金や管理費、固定資産税なども忘れてはいけません。
無理なく返していくためには、手取りの25~30%以内に返済額を収めるのが現実的。金利の変動や将来的な収入の増減も見込んで、余裕を持ったプランを組むことが、住宅購入で後悔しないための土台になります。
管理組合の議事録や修繕履歴を事前にチェックする
マンション購入を検討しているなら、物件の状態だけでなく「その建物がどんな風に管理されてきたか」も見逃してはいけません。特に重要なのが、管理組合の議事録と過去の修繕履歴です。
議事録には、住民同士でどんな課題を話し合い、どう対応してきたかが率直に記されています。たとえば「修繕積立金の不足が深刻」だとか「エレベーター更新の意見が割れている」といった内容があれば、それは将来的なトラブルの火種かもしれません。
修繕履歴も同じく大切です。外壁塗装や屋上防水といった定期的なメンテナンスが計画的に実施されているなら安心材料になりますが、長年手つかずだった場合は、次に購入する人に大きな負担が回ってくる可能性もあります。
不動産会社に頼めば、これらの資料は事前に見せてもらえることがほとんどです。見た目のきれいさや立地の良さだけでは分からない「そのマンションの本質」を知るために、購入前のひと手間として必ずチェックしておきましょう。
【無料】未公開物件の情報を複数社から一括で受け取れる方法

「ネットに出ている物件ばかりで、本当に良いマンション情報が見つからない」
「京都のマンション価格が高すぎて、今の相場が適正なのか判断できない」
「購入前にもっと多くの選択肢を見て、後悔しない判断をしたい!」
あなたも、上記のように悩んではいませんか?
理想の物件を探すのは至難の業。まして、人生で一番高い買い物で失敗なんて、笑えませんよね。
でも実は、そんな悩みを解決する未公開物件の情報を複数社から一括で受け取れる方法があります!
それが、540,000人以上が利用した“一番いい”物件情報がもらえる『タウンライフすまいリクエスト』です。
「タウンライフすまいリクエスト」とは、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
- 非公開物件&値下げ物件の情報がもらえる!
複数社への一括依頼により、広告掲載前や値下げ前の“掘り出し物件”に出会える可能性が高まる - 物件探しの手間・時間を大幅に削減できる!
60秒の簡単入力だけで、複数の不動産会社から資料・提案が一括で届くので、自分で探す手間が省ける - 信頼できる複数の不動産会社の中から選べる!
登録企業は全国170社以上、独自基準をクリアした優良な不動産会社に限定。安心して比較・選択ができる
さらに!タウンライフすまいリクエスト利用者限定で2つの特典が必ずもらえるプレゼントを実施中!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、40ページを超える読み応えありの内容で、今後の物件探しのヒントが満載でした。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
【Q&A】買わない方が良い京都のマンションに関するよくある質問

最後に買わない方が良い京都のマンションに関するよくある質問をまとめました。
実際に多く寄せられているリアルな疑問にわかりやすく答えていきます。購入判断の参考材料として、ぜひチェックしてみてください。
京都のマンション価格は今後上がるのでしょうか?
マンションの購入を検討している方にとって、今後の価格動向はどうしても気になるところです。結論から言えば、京都のマンション価格は今すぐ劇的に下がる兆しは見えず、当面は高止まり、もしくは緩やかな上昇が続くと見られています。
実際、京都府内の中古マンション価格はこの10年で約43%も上がっており、例えば2020年の平均価格は2,853万円でした(出典:京都府の中古マンション価格推移)。中心地や駅近エリアでは、過去10年で価格が50%以上上昇したエリアもあるほどです。さらに、将来予測を見ても京都駅周辺のように「2030年までに+20%」と評価されている地域もあります。
ただし、エリアによっては今後10年で価格が1割ほど下がるとする予測もあります。今後の動きを読みつつ、立地や築年数、再販時の需要まで見据えた物件選びが鍵になりそうです。資産性を重視するなら、駅近や人気エリアを検討する価値は十分あります。
京都で一人暮らし用マンションの購入はアリ?
「一人暮らしだけど、買ってしまってもいいのかな?」そう迷っている方に伝えたいのは、「アリかナシか」で言えば、十分アリです。むしろ将来を見据えるなら、早めの購入が賢い選択になる場合もあります。
というのも、自分名義でマンションを持っていれば、住宅ローン控除などの制度が使えるほか、老後の住まいとしても安心材料になります。家賃を払い続けるより、いずれ持ち家になるほうが長期的に見るとお得になるケースも少なくありません。
実際、京都は大学や企業が多く、単身者向けの賃貸ニーズが根強い地域です。将来的に住み替えを考える場合でも、貸し出して家賃収入を得る選択肢があるのは大きな強みでしょう。
もちろん、ローンの返済計画やライフスタイルの変化を見越した上での判断が必要ですが、「一人暮らしだから買うべきではない」という時代ではなくなっているのは確かです。
京都市で1000万円以下の中古マンションは狙い目?
「1000万円以下でマンションが買える」と聞くと、正直「大丈夫?」と身構える方もいると思います。けれど、京都市内でも伏見区や東山区などでは実際にそうした価格帯の物件が流通しています。
たとえば、淀のあたりなら60平米超・3LDKで980万円前後の部屋があったり、東山区では清水五条駅近くのワンルームが800万円台から手に入ることも。
もちろん築年数はそれなりに経っていますし、リフォーム前提のものも多いですが、住むだけでなく「賃貸に出して利回りを狙う」という視点で見ると、思わぬ掘り出し物が見つかる可能性もあります。条件と目的がハマるなら、検討して損はありません。
京都のマンションは今後値下がりする可能性ある?
今の京都のマンション市場は堅調に見えますが、「このまま値上がりが続く」と楽観視するのはちょっと危険かもしれません。
不動産価格研究所のデータによると、京都府の中古マンション相場(約2853万円)は、今後10年で1割以上下がる可能性も指摘されています。実際、西京区の予測では6~7%の下落が見込まれているようです。
もちろんエリアや立地、マンションの条件によって大きく変わりますし、一概には言えません。ただ、金利の動きや供給過多といった外部要因も影響するため、「今買えば必ず値上がる」という保証はないのが実情です。将来的な売却や資産価値を気にする方は、慎重に見極めたいところです。
京都で売れ残り物件に手を出すのは危険?
「なんとなくお得そう」と思って売れ残りのマンションに手を出すのは、正直おすすめしません。
というのも、なかなか売れない物件には、何かしらの“理由”が潜んでいるからです。たとえば立地が中途半端だったり、価格が周辺相場に比べて高すぎたり、修繕積立金がほとんど貯まっていなかったり──。実際、東日本不動産流通機構の統計では、中古マンションは掲載から平均79日ほどで売れるのが一般的(首都圏不動産流通市場の動向)。
それを過ぎて半年以上売れていないとなると、資産価値や流動性に疑問を持たざるを得ません。もちろん、掘り出し物の可能性もゼロではありませんが、慎重な見極めが必要です。価格だけで飛びつかず、なぜ残っているのか“裏側”までチェックすることが大切です。
京都にマンションバブル到来って本当?
最近「京都にもマンションバブルが来ている」という声を耳にすることがありますが、実際は“部分的な高騰”にすぎません。
特にインバウンド需要が強い一部のエリアでは、新築・中古問わず価格が異常に上がっているのは事実です。しかし、全体で見ればそこまで極端な状況ではなく、高値がついているのは主に富裕層向けや希少価値の高い物件に集中しています。
不動産コンサルタントの長嶋修氏も「上位15%が突出して高い一方、多くの物件は価格が落ち着き始めている」と指摘しています(出典:朝日新聞)。
つまり“誰にでも恩恵があるバブル”とは違い、あくまで局所的な現象。買うタイミングとしては、勢いに惑わされず、自分の資金計画とライフスタイルにフィットするか冷静に見極めるべきでしょう。
中古マンションを買ってはいけない時期はいつですか?
中古マンション購入で最も慎重になるべきタイミング、それは「築25年を過ぎた頃」です。
というのも、この時期は建物の老朽化が目に見えて進み、エレベーターや給排水管の更新、大規模修繕といったコストの大きい工事が控えていることが多いからです。現に、首都圏データを例に挙げると、築21~25年の平均価格が約4,887万円だったのに対し、築26~30年では一気に約3,344万円まで下がっています(出典:首都圏の不動産流通市場)。
価格が安いぶん「買い得」と思われがちですが、実は修繕積立金や維持費など“見えない出費”がどんどん増えていく落とし穴があります。築年数だけで決めず、管理組合の体制や修繕履歴、積立状況などもしっかりチェックしておくのが失敗しないコツです。
まとめ:京都のマンションは買わない方が良い理由と物件探しのポイント
京都のマンションは買わない方が良い理由と物件探しのポイントをまとめてきました。
改めて、京都のマンションを買わない方が良いと言われる理由をまとめると、
- 景観保全の厳しい規制により、建物の自由な設計が制限されやすい
- 観光地ならではの騒音・ゴミ問題が日常生活に影響する可能性がある
- 供給が限られており、価格が高騰しやすく割高感がある
- 築年数の古い中古物件は、修繕コストの見通しが立てにくい
- 地震や液状化などの自然災害リスクが地域によっては高い
「京都 マンション 買わない方が良い」と検索する方の多くは、失敗したくないという不安を抱えています。
確かに京都には独自の規制や環境上のデメリットが存在します。ただ、正しい知識と事前準備があれば、後悔のない選択は可能です。購入前にしっかり見極める目を持ちましょう。