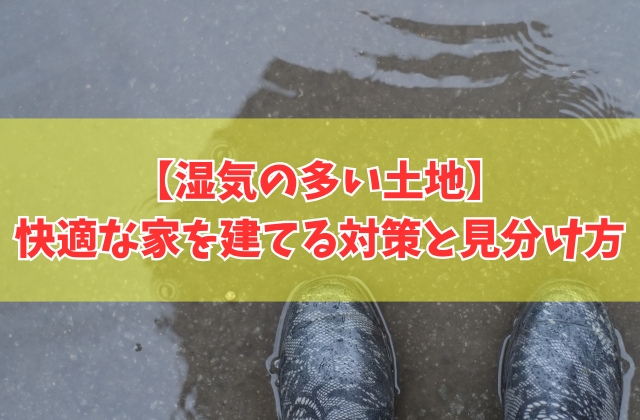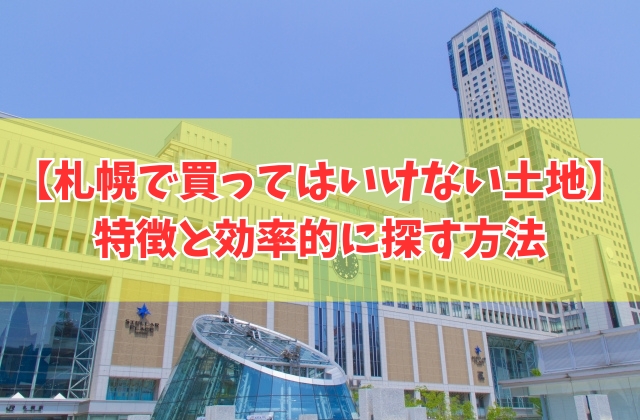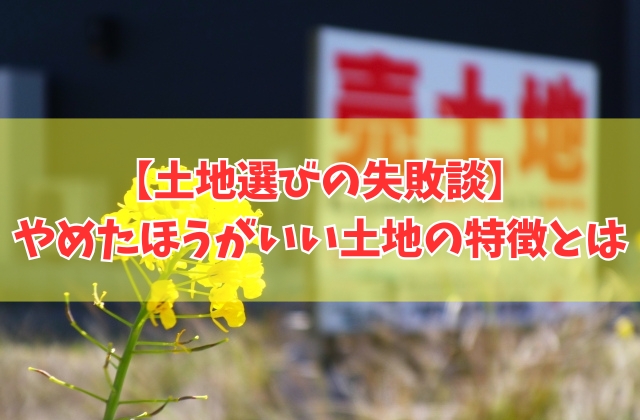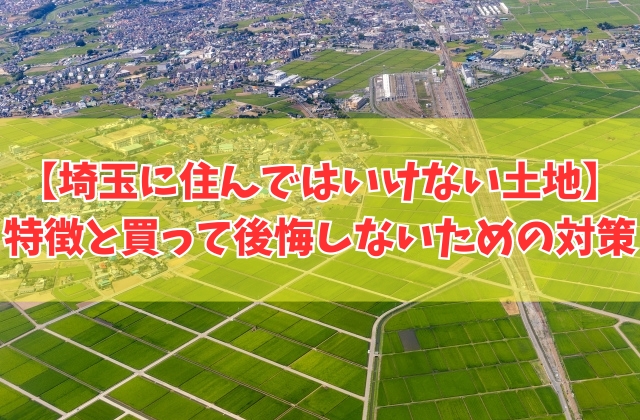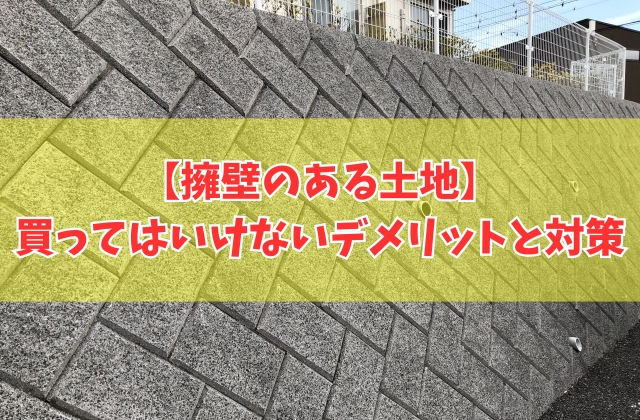
「擁壁のある土地は買ってはいけないってホント?」
「買うメリットはない?買って後悔しないための必要な対策は?」
「擁壁のある土地は危ない」と耳にしたことはありませんか?
価格の安さや眺望の良さに惹かれて検討しているのに、「本当に買って大丈夫なのか」と不安を感じている方は多いはずです。
特にネット上では、「擁壁のある土地は買ってはいけない」とネガティブな声も少なくありません。
では、具体的にどのようなリスクが潜んでいるのでしょうか?
この記事では、擁壁付きの土地購入にあたって注意すべきポイントや、安全性を見極めるコツをわかりやすく解説します。
- 老朽化や不適合な擁壁は倒壊リスクが高く、命や資産に危険を及ぼす可能性がある
- 法規制や検査済証の有無によって、建築や修繕の手間とコストが大きく変わる
- 擁壁の状況によっては、将来的な資産価値や売却のしやすさに悪影響を与える
「擁壁のある土地は買ってはいけない」とされる最大の理由は、安全性と費用面での不安にあります。
購入前に擁壁の状態や法的な整合性を細かく確認することで、リスクを最小限に抑えることができます。慎重な判断が、安心できる住まいへの第一歩です。
では、土地購入で後悔しないためにどうやって情報を集めればいいのか?できれば、ネットで簡単に情報がもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
【結論】擁壁のある土地は買ってはいけない?
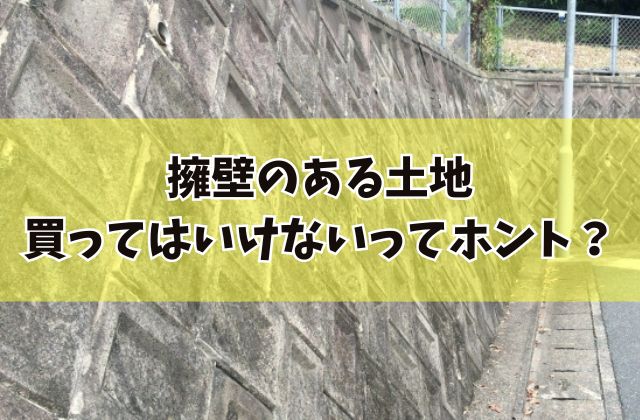
擁壁のある土地は買ってはいけないのかどうか?
結論から言えば、擁壁のある土地がすべて危険というわけではありません。ただし、「状態の悪い擁壁」がある土地については、できれば避けた方が安心です。
なぜそう言えるのかというと、まず安全面の不安が拭えないからです。例えば、建築基準法に基づいた確認申請がされていない擁壁や、古くてひび割れ・傾きのある擁壁は、地震や大雨の際に崩れるリスクがあります。これは見た目だけでは判断しづらく、素人が見ても「どれくらい危ないのか」がわかりません。
さらに、こうした擁壁の補修や建て替えには、100万円~数百万円単位の費用がかかることもあります。しかも、2メートル以上の擁壁は「がけ条例」や「工作物確認申請」などの法的手続きが必要になるケースが多く、時間も手間もかかります。
実際、不動産業界の現場では「擁壁のある土地は売れ残りやすい」と言われることも珍しくありません。買い手が躊躇しやすい理由が、それだけ多いのです。
とはいえ、すべての擁壁付きの土地が悪いわけではありません。しっかりと検査済証があるもの、専門家のチェックで安全性が確認できるものであれば、高台の立地を活かして快適な暮らしができることもあります。
大切なのは「擁壁がある」こと自体ではなく、「その状態が適切か、安全が保証されているか」です。気になる土地があれば、必ず事前に専門家の調査を依頼し、納得のいく判断をしましょう。土地選びは、将来の安心にもつながる重要な選択ですから。
擁壁のある土地は買ってはいけない7つのデメリット
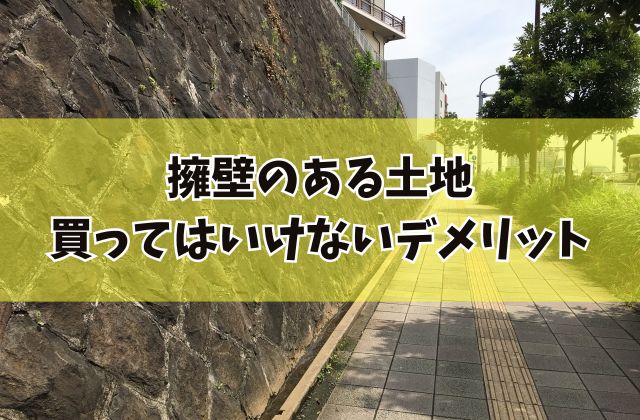
一見便利に思える擁壁付きの土地ですが、購入後に後悔する人も少なくありません。
擁壁があるだけで建築の自由度が下がったり、想定外の出費が発生することもあります。
中でも注意したいのが「擁壁のある土地は買ってはいけない7つのデメリット」と呼ばれる要因です。
安全性や法的な問題だけでなく、税金や売却のしづらさにもつながるため、事前の理解がとても重要になります。
ここでは、それぞれのリスクについて具体的に解説していきます。
倒壊や崩落事故の危険性がある
擁壁がある土地を選ぶ際、いちばん気をつけたいのが「崩れるリスク」です。見た目に異常がなくても、ひとたび地震や大雨に見舞われれば、擁壁が突然崩れる——そんな事例は全国で何件も報告されています。
たとえば熊本地震では、住宅地に設けられていたブロック製の擁壁が次々に崩落。避難通路がふさがれたり、隣家に被害が及ぶケースも発生しました(出典:参考資料)。また、2023年の北海道登別市では、長く降り続いた雨の影響で古い擁壁が崩れ、住宅そのものが傾くという深刻な事故も起きています(出典:北海道新聞)。
これらのケースに共通するのは、「擁壁の劣化」や「構造上の問題」が、見えにくいまま放置されていた点です。崩れるとわかっていれば誰も住まない——でも、多くの人は、倒壊の兆候を見逃したまま住んでしまうのです。
だからこそ、擁壁がある土地は慎重すぎるほど慎重に選ぶべきです。ほんの少しのひび割れや傾きが、数年後に命に関わるリスクへと変わるかもしれません。購入前に「安全確認を済ませておく」という意識が、これ以上ない安心材料になります。
補修や建て替えに高額な費用がかかる
擁壁つきの土地に興味があっても、気をつけたいのが「後からかかる費用」です。特に、古い擁壁やヒビ・傾きがある擁壁は、見えないところで深刻な問題を抱えていることが少なくありません。
たとえば、見た目では小さなヒビでも、職人に依頼してモルタルを詰めるだけで1㎡あたり1~2万円程度が相場です。これだけならまだ軽いほうですが、もし擁壁そのものを撤去して造り直すとなると、話は別。撤去費用に加えて、造り直しは1㎡あたり3~13万円と幅があり、場所や条件によってはもっと高くなるケースもあります。
実際、擁壁を20㎡ほど建て直すと、ざっと見積もっても60万~260万円。擁壁の高さや構造、地盤によっては300万円以上かかることもめずらしくありません。現場によっては、家を建てる前の段階で土地代とほぼ同じ費用が発生することさえあるのです。
見えない費用ほど怖いものはありません。安いと思って購入した土地でも、擁壁の修繕や建て替えで資金計画が崩れてしまう——そうなる前に、現地調査と事前の見積もりは必須です。土地の購入費だけで考えるのではなく、「擁壁にかかるお金」まで含めた判断が、後悔のない選択につながります。
検査済証なしだと安全性に不安が残る
土地に擁壁があるなら、まず「検査済証があるか」を確認してください。見落とされがちですが、これはその擁壁がルールに沿って作られ、きちんと検査を通っている証です。
逆に言えば、検査済証がない擁壁は、誰にも安全性を保証されていないということ(出典:既存擁壁の安全性について)。少し大げさに思えるかもしれませんが、実際にトラブルの原因になるケースは少なくありません。
たとえば、高さ2メートルを超える擁壁を作る場合、建築基準法上「確認申請」と「完了検査」が必要です(出典:工作物(擁壁)の確認申請と検査等)。ところが、過去には無届けで施工され、そのまま放置されてきた擁壁も多く存在します。これが「既存不適格」とされ、建築時の手続きが煩雑になったり、最悪の場合には擁壁を作り直さないと建築できないケースすらあります。
また、たとえ検査済証が発行されていたとしても、それが10年、20年以上も前のものであれば安心とは言い切れません。排水機能の劣化や、周囲の地盤の変化によって、擁壁そのものが弱っている可能性もあるからです(出典:宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル)。
つまり、「検査済証があるかどうか」は出発点にすぎず、本当に大事なのは、現時点でその擁壁が安全かどうかを、自分の目と専門家の視点で確かめることです。土地の見た目や価格だけで判断するのではなく、こうした“裏のリスク”に目を向けることが、あとあと後悔しない土地選びにつながります。
がけ条例や法規制で手続きが複雑になりやすい
擁壁のある土地に家を建てようとすると、避けて通れないのが「がけ条例」。これが意外と曲者です。自治体ごとに基準が異なるうえ、内容もなかなか専門的。初めて土地を買う人にとっては、理解するのも一苦労です。
たとえば東京都では、「高さ2m以上のがけ」に建築を計画する場合、安全を確保するために擁壁の設置や補強が義務づけられています(出典:参考資料)。しかも「上に建てるのか」「下に建てるのか」で条件も異なり、横浜市のように3mを超えるとさらに厳しくなる地域もあります(出典:横浜市建築基準条例)。擁壁の構造、施工方法、距離の制限…そのすべてに法的な裏付けが必要になります。
では、実際にどうすればよいのか。結論から言うと、建築士や造成に詳しい専門家に相談しながら進めるしかありません。申請書類の作成、構造計算、行政とのやり取り——個人で対応しようとすれば、時間も手間も膨大になります。そして何より、申請が通らなければ、家を建てることさえできないという事実があるのです。
つまり、がけ条例を軽く見ると、あとで動けなくなる可能性があるということ。土地選びの時点で「ここ、条例の対象じゃないか?」と気づけるかどうかで、住まいづくりの難易度がまったく変わってきます。
擁壁付きの土地を検討するなら、まず市区町村の担当窓口に一度問い合わせる。そのひと手間が、安心と後悔の分かれ道です。
擁壁の影響で固定資産税が高くなる場合がある
「擁壁があると固定資産税が高くなることがある」。そんな話を聞いたことがある方もいるかもしれません。実はこれ、場合によっては本当に起こり得る話です。
たとえば、200㎡の土地があったとして、そのうち30㎡が擁壁や急斜面などで使いにくい場所だったとします。感覚的には「この30㎡分は評価から除かれるだろう」と思いがちですが、実際には土地全体が“均一に使える”と見なされて評価されることがあります。つまり、使えない土地に対しても税金が課されてしまうわけです(出典:参考資料)。
もちろん、すべてが不利になるわけではありません。自治体によっては「傾斜地補正」という制度があり、がけや擁壁部分の評価を20~30%程度下げてくれる場合もあります。ただ、この補正は自動的に適用されるとは限らず、自分で申請する必要があることも多いのです。
税金というのは見落とされがちですが、毎年かかるものだからこそじわじわ効いてきます。土地を買う前に、「擁壁部分の評価はどうなるか?」「傾斜地補正は適用されるのか?」を、事前に税務課や土地家屋調査士に相談しておくことをおすすめします。
知らずに買ってあとから気づくと、意外な出費に後悔しかねません。土地選びの判断材料として、固定資産税の影響もきちんと織り込んでおきたいところです。
土地の売却時に敬遠されがちで売れないこともある
擁壁がある土地というだけで、「買い手が見つかりにくい」。不動産業界では、そんな声が現場でよく聞かれます。
理由は単純で、「あとからお金がかかりそう」「崩れたら怖い」──そんなイメージを持たれるからです。特に古い擁壁や、見た目に劣化があるものだと、購入検討者の心はどうしても後ろ向きになります。擁壁の補修や作り直しにかかる費用は、場合によって1㎡あたり3万~15万円ほど。20㎡の工事だけでも数十万円から数百万円という単位になります。
もちろん、すべての擁壁が問題というわけではありません。ただ、建築基準法に適合していない、検査済証がない、排水がされていない──そんな状態だと、住宅ローンが通らなかったり、建築が制限されたりと、買い手側の選択肢も限られてしまいます(出典:参考資料)。
こうした背景から、擁壁付きの土地は「価格を下げても売れ残る」ケースが珍しくないのです。とはいえ希望はあります。事前に点検・補修を済ませたり、専門家による診断結果を提示できれば、安心材料となり売却につながることも十分あります。
つまり、擁壁があるからといって売れないわけではなく、“どう見せるか”“どう伝えるか”が大事。買主の不安を、こちらがどれだけ先回りして取り除けるかにかかっています。土地を売るなら、その工夫こそが一番の武器になります。
古い擁壁は新築時につくり直しが必要になることもある
擁壁がある土地に家を建てたい。そんな希望を持って現地を見に行っても、「このままじゃ建てられません」と言われて戸惑う方は意外と多いです。というのも、古い擁壁のままでは新築の許可が下りないことがあるからです。
実際、築40~50年以上前に造られた擁壁は、今の基準に合っていないケースが多くあります。たとえば、当時は許されていた自然石や大谷石の積み方が、現在の建築基準法では「安全性に問題がある」と見なされることも(出典:擁壁のはなし)。さらに、古い擁壁は「確認申請がされていない」ことが珍しくなく、それだけで再建築がストップしてしまうこともあるのです。
擁壁のやり直しとなると、話は簡単ではありません。構造計算、設計申請、施工の手間、そして費用。たとえば鉄筋コンクリート製の擁壁であっても、20㎡ほどの再構築で100万~300万円かかるのはよくある話です。土地価格に加えてこの出費が乗るとなれば、資金計画にも大きな影響を与えかねません。
「擁壁がある=すぐに建てられる土地」とは限らないのが、現実です。だからこそ、古い擁壁付きの土地を検討するときは、事前に専門家に見てもらうことを強くおすすめします。
「見た目は立派」でも「中身は再施工必須」なんてことは、決して珍しくありませんから。購入前に“その擁壁は本当に使えるか”を見極める——それが安心して家づくりを始めるための第一歩です。
特に擁壁のある土地の中でも買ってはいけない擁壁の特徴
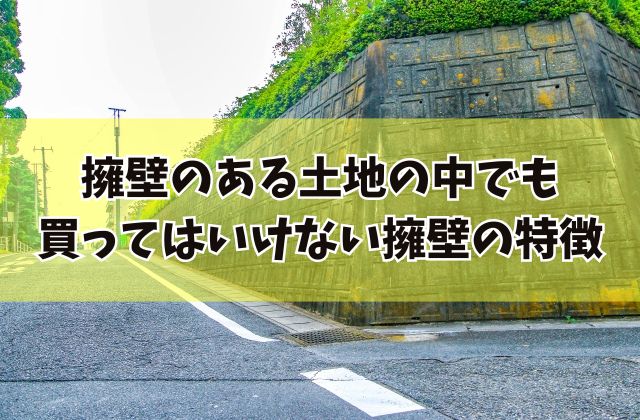
擁壁のある土地を検討する際に注意したいのは、すべての擁壁が危険というわけではないということです。
問題なのは、「擁壁のある土地の中でも買ってはいけない擁壁の特徴」に当てはまるようなケース。
安全性や管理体制に不安がある擁壁は、将来のトラブルや余計な出費につながる可能性があります。
ここからは、具体的にどのような擁壁が避けるべき対象なのかを解説します。購入前の判断材料として、しっかり押さえておきましょう。
高さ2m以上で確認申請されていない擁壁
見た目はしっかりしていても、擁壁の高さが2メートルを超えているのに「確認申請」がされていない土地は、正直なところ避けるのが無難です。というのも、建築基準法施行令138条では高さ2m以上の擁壁には設計の届け出と審査が義務づけられており、それが済んでいない擁壁は“違法建築物”とみなされる可能性があるからです(出典:参考資料)。
実際、過去に確認申請をしていなかったことで、家を建てようとしても「擁壁の安全性が確認できないため許可できない」と自治体に言われ、土地の活用自体がストップした事例もあります。また、検査済証がない場合、後から擁壁の補強工事を求められることも少なくありません。
土地の見た目や価格だけで判断してしまうと、思わぬ工事費や申請の手間がのしかかってくることになります。購入前に市区町村で確認申請の記録が残っているかどうか、しっかり調べておくことが、将来の後悔を防ぐ第一歩です。できれば建築士や不動産の専門家にも相談して、書類や現地状況の確認を怠らないようにしましょう。
築年数が古く劣化が進んでいる擁壁
見た目にはまだしっかりしていそうな擁壁でも、築年数が古いものには思わぬ落とし穴があります。特に注意したいのは、昭和の時代に造られた擁壁の多くが、現在の安全基準を満たしていない可能性があるという点です。
たとえば、古い石積みやコンクリートブロック製の擁壁は、使用から20~50年ほどで構造的な劣化が進みます。排水口が詰まっていたり、表面にひび割れがあったりすれば、それはすでに「寿命のサイン」(出典:参考資料)。放置すれば、雨による土圧で崩れやすくなり、土地全体の安全性に関わります。
しかも、築年数が経った擁壁がある土地に家を建てようとすると、自治体から「擁壁の再施工」を求められることも。そうなれば、解体費から再築費まで数百万円単位で出費がかさむケースも出てきます。
土地を安く買えたと思っても、後で高くつくのでは意味がありません。古い擁壁のある土地は、購入前に必ず専門業者に診てもらいましょう。費用と安全、どちらも見逃せない大事なポイントです。
自然石や大谷石を積んだ不安定な擁壁
一見すると風情があって立派に見える自然石や大谷石の擁壁。しかし、それが数十年前のものなら、むしろ警戒が必要です。なぜなら、こうした石積み擁壁は、見た目とは裏腹に構造的な弱点を抱えているケースが非常に多いからです。
とくに大谷石は、柔らかく加工しやすい反面、雨風にさらされると表面からボロボロと崩れやすく、時間とともに強度が落ちていきます。1970年代以前に建てられたものは、構造計算や耐震基準を満たしていないことがほとんど。風化が進みやすく、地震や豪雨のたびにヒヤッとするようなリスクを背負うことになります。
横浜市の公式資料でも、「大谷石を使った擁壁は風化が進行しやすく、倒壊の危険性が高い」と明記されています。しかも、昔ながらの空積み(モルタルなどの接着材を使わない積み方)は、見た目は立派でも強度面では脆く、崩れるリスクが高まります。
つまり、「古くて趣があるから安心」と思うのは大きな誤解。実際には、メンテナンスや補強がなされていない限り、専門家のチェックなしでは手を出さないほうが無難です。購入前には、必ず現場を見て、擁壁の材質と築年数、劣化具合を細かく確認してください。
不安があれば、専門の建築士や地盤調査のプロに相談するのが確実です。土地選びは、見た目より中身が大切です。
水抜き穴がない擁壁
「水抜き穴がない擁壁」は、一見して問題がなさそうでも、実は内側に大きなリスクを抱えていることがあります。擁壁の背後には、雨水や地下水が日々少しずつ溜まっていきます。これをうまく逃がしてやらないと、水の重みがじわじわと擁壁を押し、ある日突然“崩れる”こともあるのです。
法律でも、擁壁には3平方メートルごとに直径7.5cm以上の水抜き穴を1つ以上設けることが義務付けられています(出典:参考資料)。これは土木工学の基本とも言える設計ルールですが、古い擁壁や違法に造られたものには、そもそもこの穴がないケースもあります。
水の逃げ場がないということは、擁壁が常に「押されている」状態にあるということ。これでは、たとえコンクリートでしっかり固められていても、時間が経てばひび割れが起きたり、最悪の場合は倒壊してしまったりという危険すらあるのです。
土地を選ぶとき、「水抜き穴があるか?」なんて、つい見落としがちかもしれません。でも、そこにこそ、その土地の“安全”が詰まっています。見に行ったときは、壁の下の方をよく観察してください。もし穴が見当たらなければ、専門家の点検を依頼するなど、慎重すぎるくらいでちょうどいいと思います。
私設で管理者が不明な擁壁
誰が持ち主かも分からない擁壁がある土地、正直いって、手を出すのはおすすめできません。というのも、擁壁って見た目以上に責任が重たい存在なんです。
たとえば、古い擁壁が敷地の境目にあって、登記にも名前が出てこない──そんなケース、実は珍しくありません。いざ崩れでもしたら「誰が直すの?」という問題が、思いのほか深刻になります。
管理者が不明だと、行政もすぐには動けません。所有者不明のままでは、修繕にも時間がかかり、場合によっては裁判所に“管理人”を立ててもらう必要が出てきます(出典:参考情報)。もちろん、そんな手続きに関わる費用も、労力もバカになりません。
つまり、誰の持ち物かあいまいな擁壁がある土地を買うというのは、見えない火種を抱え込むようなもの。買う前に必ず、名義や管理状況を確認しておくべきです。調べれば案外シンプルに解決できることもあるので、不安があれば専門家の力を借りてください。トラブルを未然に防げば、その土地も悪くない選択肢になるかもしれません。
本当に買ってはいけない?擁壁のある土地を買うメリット

「擁壁のある土地は危ないから買ってはいけない」といった声を耳にしたことがあるかもしれません。
確かにリスクは存在しますが、一方で無視できないメリットもあるのが実情です。
本当に買ってはいけないのかどうかは、その土地の状態や活かし方によって判断が分かれます。
ここでは、擁壁のある土地ならではの利点について具体的にご紹介していきます。
高台による眺望や開放感が得られる
擁壁のある土地は敬遠されがちですが、立地によっては思わぬ魅力もあります。たとえば、高台にある土地なら、目の前に広がる景色をひとり占めできます。マンションの15階相当、標高50メートル前後の場所なら、街の夜景や遠くの山並み、海までも見渡せることも珍しくありません。
景色だけではありません。高台は風通しも良く、朝から夕方までたっぷりと日が入るため、家の中が明るく保たれます。とくに周囲に建物が少ない場合、窓を開けるだけで心地よい風が通り抜け、夏場でも比較的涼しく過ごせるのが利点です。
見晴らし、風通し、日当たり。こうした条件がそろう高台の土地は、住まいに開放感やゆとりを求める人にとって大きな価値があります。「擁壁=マイナス」と決めつけず、ロケーションがもたらす恩恵にも目を向けてみると、理想の暮らしに一歩近づくかもしれません。
日当たりが良く明るい住まいを建てやすい
高台にある土地は、なんといっても陽当たりの良さが魅力です。周囲よりも一段高い位置に家が建てられるため、周辺の建物に光を遮られにくく、朝から夕方までしっかりと自然光が入ります。これは実際に暮らしてみると、想像以上に大きな差になります。
特に南向きに窓を設けると、リビングやダイニングにやわらかな光が差し込み、室内が明るく暖かく保たれます。洗濯物もよく乾きますし、日中は照明いらずで過ごせることも少なくありません。
擁壁があると聞くと構えてしまう方もいるかもしれませんが、地盤が高い分、採光や通風といった住宅性能の面ではむしろ有利に働くケースもあります。日当たりを重視する方にとっては、こうした土地がかえって理想に近い選択肢になることもあるのです。
水害や浸水リスクが低減される
「高台にある土地は、水害に強い」。これは不動産業界ではよく知られた話です。大雨のたびにニュースで流れる冠水被害。低地ではちょっとした雨でも道路が川のようになり、床上浸水にまで至るケースも珍しくありません。
一方で、擁壁によって地盤が高くなっている土地では、家の基礎が水につかりにくくなります。国土交通省や各自治体のハザードマップを見れば一目瞭然ですが、周囲が浸水エリアに指定されていても、擁壁上の敷地だけは安全圏、ということも実際にあります。
たとえば、50cm~1mの浸水が予想されている地域でも、擁壁でしっかり盛土されていれば、建物内部まで水が上がってくる可能性はぐっと下がります(出典:研究資料)。もちろん、擁壁の高さや構造が適正であることが前提ですが、それが確認できれば「水害に強い家」を手に入れることも夢ではありません(出典:新築木造戸建て住宅の浸水対策に関する検討)。
土地選びでは眺望や価格ばかりに目が行きがちですが、こうした災害リスクへの備えも、大切な判断材料のひとつです。
土地価格が相場より安く抑えられる
擁壁がある土地は、見た目のインパクトとは裏腹に、意外な“掘り出し物”であることも少なくありません。というのも、購入者側にとっては造成費や補修のリスクがある分、売主側は価格を下げて販売せざるを得ないケースが多いのです。
たとえば、高さ2メートルを超える擁壁がある土地では、専門業者による補強や申請手続きが必要になることがあり、その費用は場合によっては100万円を超えることも。そうした背景を考慮して、最初から近隣の平坦地よりも200~300万円ほど安く設定されている例も珍しくありません。
もちろん、安いからといって即決するのは危険です。ただ、土地にかかるコスト全体を見積もったうえで、擁壁の有無による価格差と、修繕費や安全性を天秤にかけて判断すれば、結果的に満足度の高い買い物になる可能性も十分あります。
プライバシーが守られやすい環境になる
道路よりも一段高く造成された擁壁のある土地は、外からの視線を自然に遮ってくれるという思わぬメリットがあります。たとえば、リビングや庭でくつろいでいても、通行人や近隣の家からジロジロ見られる心配が少なくなります。
これは単なる気分の問題ではありません。高さがあることで、そもそも目線が合いにくくなるため、常時カーテンを閉める必要がなくなり、開放感のある暮らしが実現しやすくなるのです。住宅密集地では、ちょっとした目線のストレスが毎日の積み重ねになってしまいますから、これが解消されるだけでも随分と気持ちがラクになります。
実際、購入者の中には「同じ予算で検討した土地の中でも、擁壁があったことで室内の視線ストレスが格段に減った」と感じている人もいます。外から見えにくいだけでなく、防犯面でも安心感を得やすいというのも嬉しいポイントです。
もちろん擁壁のある土地には注意点も多く存在しますが、ことプライバシーの観点でいえば、非常に理にかなった構造だと言えるでしょう。
買ってはいけないと言われる擁壁のある土地購入に向いてる人
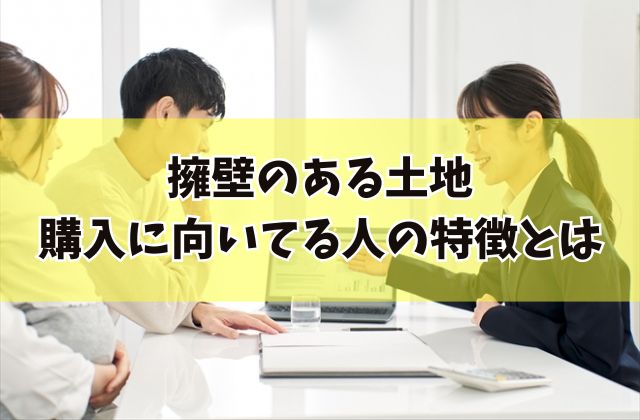
擁壁のある土地は一見リスクが多く、「買ってはいけない土地」として避けられることもあります。
ですが実は、向いている人にとっては条件に合った掘り出し物となる可能性もあります。
ここでは、買ってはいけないと言われる擁壁のある土地購入に向いてる人の特徴を具体的に紹介していきます。
リスクと向き合えるかどうかが、購入判断の分かれ道となります。
安く土地を手に入れたい人
「どうにかして予算内でマイホームを建てたい」と考えているなら、擁壁のある土地は意外と見逃せない選択肢です。理由は明快で、平坦な整地済みの土地に比べて、同じエリアでも価格が抑えられていることが多いからです。
実際、造成費用や将来的なメンテナンスの懸念があるため、市場価格よりも2~3割ほど安く売りに出されることも珍しくありません。住宅ポータルや不動産会社のデータを見ていると、こうしたケースはよく見かけます。
たとえば、都市部で予算が厳しいなか、希望のエリアに手が届かないとあきらめていた人が、擁壁付きの傾斜地を選ぶことで建築費に余裕を持たせられたという話もあります。差額を家の内装や断熱性能の向上にあてるという発想も十分現実的です。
もちろん、購入後に必要となる補修費や安全確認には備えておく必要がありますが、それらを見込んだうえで納得して選べば、「安く買える」という強みは大きなメリットになります。
購入予算に補修費を含めて計画できる人
擁壁のある土地を検討しているなら、土地代だけで判断するのは少し危ういかもしれません。というのも、古くなった擁壁の補修や建て替えには、思った以上に費用がかかるケースがあるからです。
例えば、小規模なクラックの補修で済むなら1㎡あたり1~2万円前後で済むこともありますが、老朽化が進んでいて擁壁そのものを造り直すとなれば、工事の規模によっては総額で200万円~300万円を超えることも珍しくありません。
だからこそ、擁壁のある土地を前向きに検討するなら、こうした補修費を最初から予算に組み込んでおくことが重要です。実際に購入を進める段階では、信頼できる施工会社に現地調査を依頼し、複数社から相見積もりを取って、必要な費用を具体的に把握しておきましょう。
土地を安く買えたとしても、その後の出費が想定を大きく超えてしまっては元も子もありません。補修費込みでトータルの予算計画が立てられる方であれば、擁壁のある土地でも十分に検討に値します。
高低差を活かした家を設計したい人
平坦な土地に建てる家にはない、立体的な面白さ——それが、高低差のある土地を選ぶいちばんの醍醐味です。擁壁があるというだけで避けられがちなこのタイプの土地ですが、設計の自由度を武器にできる方にとっては、むしろチャンスです。
たとえば、高台の敷地から広がる眺望を活かして、2階にリビングを配置すれば、外からの視線も気にならず、昼間はたっぷりの自然光に包まれた空間が生まれます。反対に、低い部分を地階として利用すれば、ガレージや収納、趣味の部屋など、用途に応じた多機能なスペースを作ることもできます。
実際、傾斜地を活用した住宅事例では、スキップフロアや中2階を取り入れて、家全体にリズムを与える間取りが人気です。建築費用は平地よりかさみますが、その分、個性と実用性を兼ね備えた住まいが実現しやすくなります。
設計を楽しみたい方、住まいに“らしさ”を求める方にとって、擁壁のある土地は決して「買ってはいけない土地」ではなく、可能性に満ちたフィールドです。
地盤や擁壁の専門家に相談できる人
擁壁がある土地に「ちょっと不安…」と思うのは、当然の感覚です。だからこそ、その不安をプロの目で解消できる人は、土地選びで大きなアドバンテージを持てます。というのも、素人目には何の問題もなさそうな擁壁でも、内部にひびが入っていたり、水抜きが不十分だったりするケースが実際に多いのです。
国土交通省や複数の不動産関連団体も、「擁壁を含む土地の購入前には、必ず専門家に確認を」と注意喚起しています(出典:不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン)。
たとえば、地盤調査会社や構造設計士は、土の締まり具合や排水の状態、擁壁の強度などを総合的に診断し、補修が必要か、建て替えが必要かまで踏み込んだアドバイスをしてくれます。東京都や神奈川県などの自治体では、がけ地に関する独自の条例もあり、法律的なチェックも欠かせません。
費用は内容にもよりますが、地盤調査が5~10万円、擁壁診断が10万円前後というのが一般的です。ただ、後から数百万円の修繕費がのしかかることを思えば、事前のこの出費はむしろ“保険”に近いものです。
「よくわからないから後回し」ではなく、「今のうちに聞いておく」という判断が、将来の安心を守ってくれます。少しでも迷いがあるなら、土地に詳しい建築士や不動産鑑定士に一度相談してみると良いでしょう。
地盤や擁壁は、家を支える“見えない土台”。そこにしっかり目を向けられる人こそ、後悔しない土地選びができるはずです。
手続きや工事の手間を受け入れられる人
擁壁のある土地を買う場合、一番ネックになるのが「手続きの多さ」と「工事の煩雑さ」です。そう聞くと不安に思うかもしれませんが、実はそこを冷静に受け止めて動ける人こそ、こうした土地と相性がいいんです。
たとえば、擁壁の高さが2mを超えていれば、建築確認申請や宅地造成等規制法に基づく届け出が必要になります(出典:宅地造成等規制法の概要)。
これ、簡単に言えば「行政にOKをもらわないと工事ができない」ということ。しかも、図面を出して、場合によっては自治体や専門家と何度かやりとりしなければなりません。特に都市部では、がけ条例の絡みで想像以上に時間も手間もかかります。
それでも「どうせやるなら最初にちゃんとやっておきたい」「後でトラブルになるよりはマシ」と割り切れる方には向いています。近隣住民への挨拶や工程説明も含めて、地道な段取りを楽しめる人なら、むしろやりがいすら感じるかもしれません。
要するに、書類仕事や現場とのやりとりが苦にならず、「しっかり整えた土地で家を建てたい」という意識がある方にとって、擁壁のある土地は悪くない選択肢です。大事なのは、“多少の手間も家づくりの一部”と受け入れられる柔軟さです。
擁壁のある土地を買って後悔しないための事前対策5選
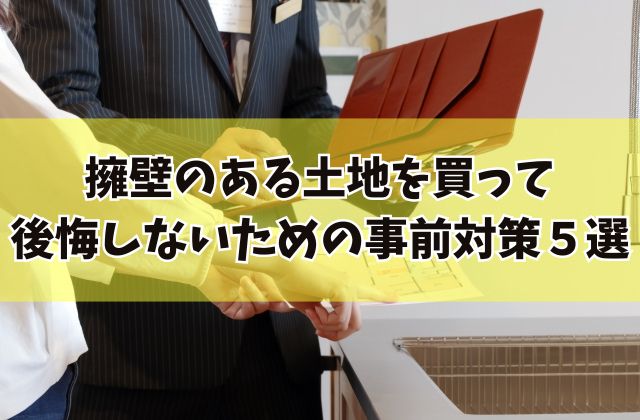
擁壁がある土地には注意点が多く、「買ってはいけない土地」と言われがちです。
しかし、事前に押さえるべきポイントを確認しておけば、大きなトラブルを防ぐことも可能です。
そこでここからは、擁壁のある土地を買って後悔しないための事前対策5選として、実際に購入前に行っておくべきチェック項目を具体的に解説します。
購入を検討する方にとって、失敗しない判断材料になります。ぜひ、参考情報としてお役立てください。
専門業者による地盤調査と擁壁点検を依頼する
擁壁のある土地を買って失敗しないためには、最初の一歩で「プロに見てもらう」ことが欠かせません。たとえば、古い擁壁の多くは一見問題がなくても、中では水がたまっていたり、構造にゆるみが出ていたりします。自分の目で見ても、正直わからないものです。
実際の調査は、最初に目視や簡単な打音検査などを行い、その後に専門の機器を使った測定に進むことが一般的です(出典:参考資料)。費用は内容によってまちまちですが、簡易調査なら5万円前後、本格的な構造診断になると10万円以上かかることもあります。場合によっては100万円近くかかるケースもあり、事前に見積もりを取って比較するのがおすすめです。
信頼できる業者を選べば、擁壁の傾きや排水の状態、地盤の強さなど細かく確認してくれますし、不安がある場合は補修や補強の提案までしてもらえます。「見た目は問題なさそう」と感じた土地でも、後から数百万円単位の修繕費がかかるケースは少なくありません。
だからこそ、購入前に専門家のチェックを受けることが、もっとも安心できる方法です。
もし、不動産のプロのアドバイスを貰いながら土地探しを進めたい方は、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』の活用が便利です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
検査済証の有無と法適合性を必ず確認する
擁壁のある土地を検討しているなら、まず確認してほしいのが「検査済証」の存在です。これがあるかないかで、その土地の安全性や将来のトラブルリスクが大きく変わってきます。
たとえば、高さ2メートルを超える擁壁は、建築基準法に基づいて確認申請と完了検査が義務づけられているのですが、実際には無申請や未検査の擁壁も少なくありません。検査済証がないということは、「きちんと安全確認されていない可能性がある」ということ(出典:参考資料)。
つまり、万が一の事故が起きたときに、責任の所在が曖昧になり、補修や再工事の費用が購入者にのしかかるケースもあるのです。
物件を紹介してくれる不動産会社が「大丈夫です」と言っていても、鵜呑みにしてはいけません。市区町村の建築指導課などで検査済証の写しや確認申請の記録を調べられますし、不明点があれば専門の建築士に相談するのが得策です。
見落としがちなポイントですが、だからこそ慎重にチェックしておきたいところです。
擁壁の耐用年数と劣化状況を事前に調べる
擁壁がある土地を検討するとき、見た目だけで「頑丈そうだから大丈夫」と判断するのはとても危険です。コンクリートやブロックでつくられた擁壁でも、築年数が30年を超えている場合は劣化のリスクが一気に高まります。石積みやブロックタイプなら、20~30年ほどで補修の必要が出てくるケースも少なくありません。
たとえば、表面のひび割れ、水抜き穴の詰まり、ブロックのずれや浮き上がりといった症状は、劣化のサインです。さらに深刻なのは、内部に鉄筋が入っている擁壁で中の鉄が錆びて爆裂している場合。こうしたトラブルは外から見えづらく、専門家の診断なしでは見逃されがちです。
後々になって「建て替えが必要だった」「大規模な補修費がかかった」と後悔しないためにも、購入前にしっかりと耐用年数と劣化状況をチェックしておきましょう。目視だけで判断せず、必要に応じて専門業者に依頼して調査してもらうのが安心です。
少し手間をかけるだけで、あとから背負う大きなリスクを避けることができます。
自治体のがけ条例や確認申請の要否を確認する
擁壁のある土地を検討しているなら、まず真っ先に確認しておきたいのが「がけ条例」と「確認申請の必要性」です。これは軽視すると後でかなり痛い目に遭います。なぜなら、がけ条例は自治体ごとに内容が異なり、場合によっては思った以上に厳しい建築制限がかかってくるからです。
たとえば、東京都内では「高さ2メートル以上」の擁壁がある場合、崖から建物を2倍以上離さなければ建てられないことがあります。さらに、そうした擁壁には建築基準法に基づく「確認申請」が必要で、これを怠るとそもそも建築許可が下りないケースも珍しくありません。
現地を見ただけでは分からない点も多いので、「この土地良さそう」と思った段階で、役所の建築課などに電話一本でもいいので早めに相談するのがおすすめです。実際、現場で「申請してなかった擁壁だった」と判明し、建築計画が白紙に戻った事例もあります。
安心して土地を買いたいなら、こうした基本的な確認作業こそが一番の“近道”かもしれません。
修繕費用や維持管理費を契約前に見積もる
擁壁のある土地を買うときに見落としがちなのが、「将来かかるお金」です。外から見ただけではわからない劣化や老朽化が進んでいた場合、購入後すぐに補修が必要になるケースもあります。その費用、意外とかさみます。
たとえば、表面のひび割れや簡単な補修なら1㎡あたり1~2万円程度で済むこともありますが、擁壁全体の再施工となると話は別です。場所や構造にもよりますが、1㎡あたり最大で10万円超えになることもあり、工事費用が100万円を超えるのも珍しくありません。参考までに、LIFULL HOME’Sやリフォームナビではそうした目安が紹介されています。
大切なのは、契約前に必ず現地を確認し、専門業者から詳細な見積もりをとること。複数社に相談すれば、価格の比較もできますし、必要な補修内容も明確になります。可能なら、自治体の補助制度についても事前に調べておくと、負担を軽くできるかもしれません。あとから困らないためにも、先に手を打っておくことが肝心です。
【無料】自宅にいながら効率よく希望に合った土地が見つかる方法

「どの擁壁が安全で、どこに問題があるのか判断する基準がわからず悩んでいる」
「土地選びの手間や失敗を避けたいが、信頼できる情報源や探し方が見つからない」
あなたも、上記のように悩んではいませんか?
条件に合う土地を探すのは至難の業。しかも土地は“見えないリスク”が多く、買ってから失敗に気づいても手遅れ。
でも実は、そんな悩みを解決する自宅にいながら効率よく希望に合った土地が見つかる方法があります!
それが、540,000人以上が利用した“複数社から一括で”土地情報をもらえる『タウンライフ家づくり』です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
【Q&A】買ってはいけない擁壁のある土地に関するよくある質問
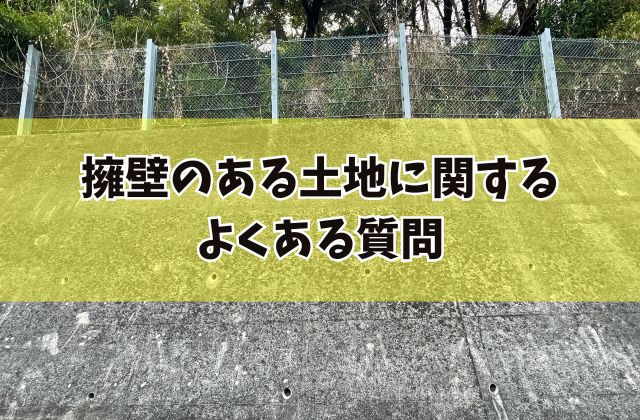
最後に買ってはいけない擁壁のある土地に関するよくある質問をまとめました。
誤解されやすいポイントや見落とされがちな部分を、ひとつひとつ丁寧に解説していきます。
擁壁がある土地の所有者はどちらになりますか?
土地に擁壁があると、その“持ち主”が誰になるのか気になる方は多いのではないでしょうか。基本的には、その擁壁がある側の土地の所有者が責任を持つとされています(出典:擁壁(ようへき)の安全に関すること)。
たとえば、崖下に擁壁があって、土が流れてこないように支えているなら、その下側の土地の所有者が管理すべき、というのが法律上の考え方です。
ただし例外もあります。擁壁がちょうど境界線上にまたがっていたり、明確な設計図や登記記録がある場合は、どちらの所有か判断が分かれることもあります。実際、こうした線引きでトラブルになることも少なくありません。
つまり、目の前の擁壁が誰のものかを正確に知るには、現地の調査だけでなく、役所や法務局で書類を確認する必要があるということです。見た目だけで決めつけないことが大切です。
境界の擁壁の費用は誰が負担するのでしょうか?
境界にまたがっている擁壁の工事費は、一体誰が払うべきなのでしょうか。この疑問は、土地の購入者にとって避けて通れない重要なポイントです。
一般的には、高い場所にある土地の所有者が費用を負担するのが基本とされています。なぜなら、土の重みを支えるために擁壁が必要になるのは、主にその高い土地の安全のためだからです。
ただ、例外もあります。たとえば擁壁が共有物と見なされる場合は、隣地の所有者と費用を分担するケースもあるのです。どちらにしても、境界の擁壁に関しては「見た目」ではなく「契約書や図面」で判断することが重要になります。
後になって揉めないよう、契約前に専門家に相談して、しっかり確認しておくことをおすすめします。
擁壁以外に代表的な買ってはいけない土地の形は?
「土地は四角が基本」。不動産に詳しい人がよく口にする言葉です。実際、土地の形がいびつだと、家を建てる段階から悩みの種になります。
たとえば、よくあるのが「旗竿地」と呼ばれるタイプ。道路から敷地までが細い通路でつながっていて、奥に本体部分がある形です。見た目は包丁に似ていて、間取りや駐車場の設計で無理が出ることも。加えて、隣家に囲まれるため日当たりや風通しに難があります。
似たような例では、三角地や台形地もあります。一見「おしゃれな設計ができそう」と感じるかもしれませんが、設計や工事費用がかさみやすく、最終的に割高になる傾向があります。見た目のインパクトに惑わされず、冷静に建築条件を見極めることが大切です。
風水的に買ってはいけない土地の特徴は?
家を建てる場所を決めるとき、風水を気にする方も少なくありません。実際、古くから語り継がれている“よくない土地”には、一定の共通点があります。
たとえば「T字路の突き当たりにある土地」。これは「気」が一直線にぶつかってくるとされ、落ち着かない暮らしになると言われています。また、旗竿地のように入口が狭く奥まった形の土地も、「良い気が入りづらい」として避けられる傾向があります。
さらに、三角形や不規則な形状の土地も、気の流れが乱れるとされ、運気が安定しにくいと考えられています。もちろん、風水をどこまで重視するかは人それぞれですが、「なんとなく気持ちが乗らない」と感じる土地には、無意識にこうした影響があるのかもしれません。
関連記事:不幸になる土地は存在する?結論と縁起が悪い土地の特徴10選と失敗しない選び方
地名で買ってはいけない土地はある?
少し意外に思われるかもしれませんが、地名にはその土地の“過去”が刻まれています。
たとえば「川」「池」「沼」「潟」など、水にまつわる漢字が使われている場所。かつて湿地帯だったり、氾濫の多い川沿いだったりと、水害の履歴がある地域であることが少なくありません。実際に、昔の地図や地質調査を見ると、こうしたエリアは地盤が軟弱だったり、水はけが悪かったりするケースが目立ちます。
また、「窪」「谷」などの地名も、低地であることを意味する場合があります。もちろん、今ではしっかりと整備されている場所も多いですが、「なぜこの名前がついているのか?」という視点で、土地の来歴をたどってみるのは、失敗しない土地選びにおいて重要なアプローチです。
まとめ:擁壁のある土地は買ってはいけないデメリットと購入前の対策
擁壁のある土地は買ってはいけないデメリットと購入前の対策をまとめてきました。
改めて、擁壁のある土地に関する重要な5つのポイントをまとめると、
- 検査済証のない擁壁は、安全性の裏付けがなくリスクが高い
- 築年数が古く劣化が進んでいる擁壁は、補修費用が高額になりがち
- 自然石や大谷石の擁壁は構造が不安定で倒壊リスクがある
- がけ条例の対象となると、建築許可や手続きが煩雑になる
- 修繕費や維持費の見積もりを契約前に把握することが重要
擁壁のある土地は一見魅力的に見える場合もありますが、見えないコストや法的リスクが潜んでいます。
特に「買っては いけない 土地 擁壁」という視点で考えると、専門家による調査と正確な情報収集が後悔を避けるカギとなります。購入前に慎重な判断をおすすめします。