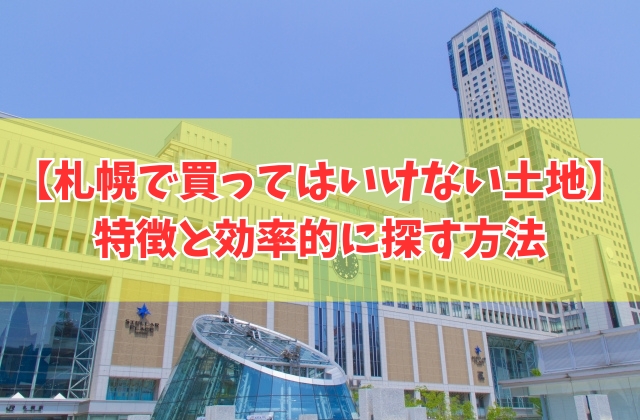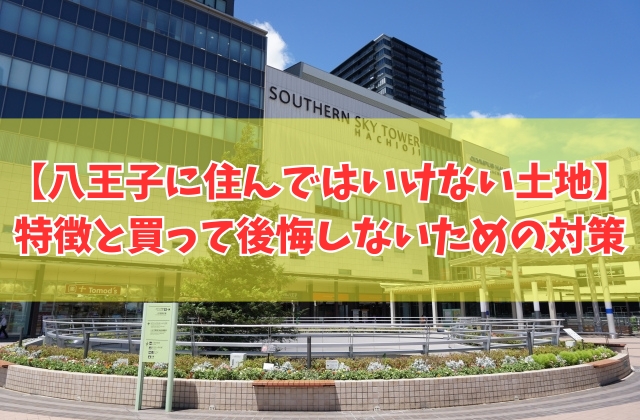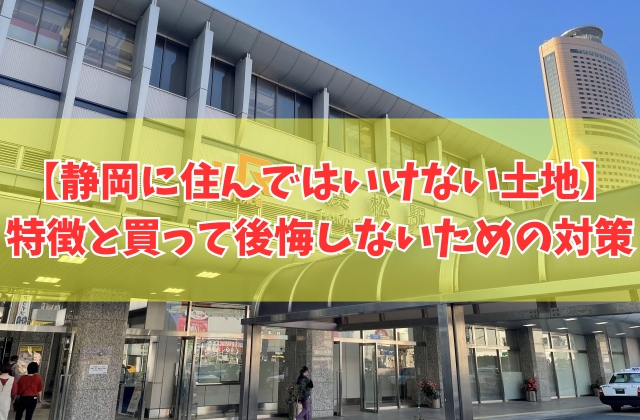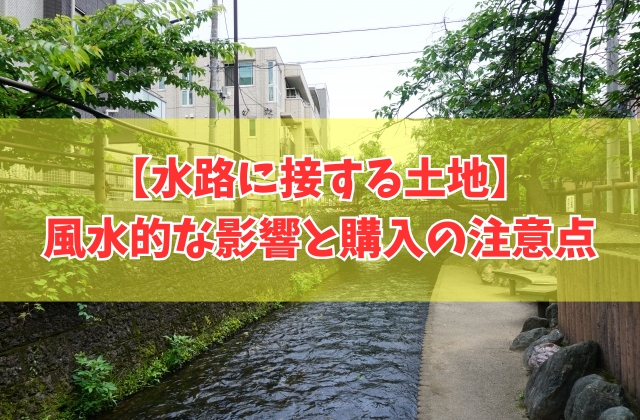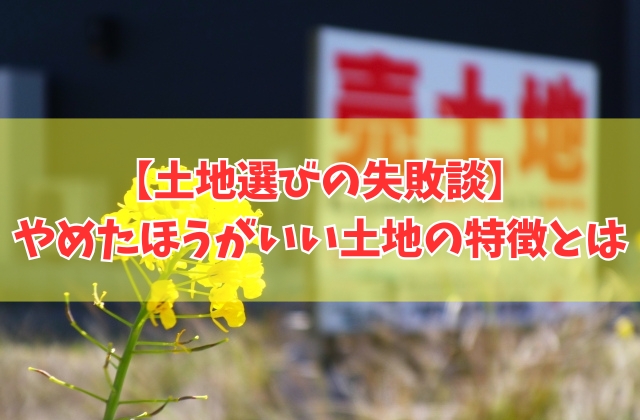
「土地選びの失敗談にはどんな共通点がある?」
「後悔しないための土地選びのポイントは?どうすれば失敗せずに土地探しは進められる?」
家づくりの第一歩となる土地選び。
しかし、希望にぴったりだと思って購入した土地が、後になって「こんなはずじゃなかった…」と後悔の元になることも少なくありません。
実際に多くの人が経験している「土地選びの失敗談」には、共通する落とし穴があります。
建築できなかった、思ったより日当たりが悪かった、追加費用がかさんだ──そんなリアルな声に触れることで、見えてくるものがあります。
この記事では、そんな土地選びの失敗談の具体例を交えながら、やめたほうがいい土地の特徴と後悔しないための土地選びのポイントをわかりやすく解説していきます。
後悔のない土地選びを目指すなら、まずは知ることから始めてみませんか。家づくりを計画している方は、ぜひ参考にお役立てください。
- 用途や法的制限を確認せず購入すると建築できないリスクがある
- 地盤や災害リスクを見落とすと想定外の費用や安全性の問題が生じる
- 専門家の助言を得ずに進めると後悔やトラブルの原因になりやすい
「土地選びの失敗談」に多く見られる共通点は、情報不足と準備不足です。
間取りの自由度、土地の安全性、将来のリスクまでしっかり見極めることが、後悔しない土地選びのカギになります。プロの意見を取り入れながら慎重に進めていきましょう。
では、失敗しないためにもどうやって土地情報を集めればいいのか?できればネットで簡単に、情報がもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
土地選びの失敗談20選

家を建てるために土地を購入したものの、思いもよらないトラブルに直面して後悔するケースは少なくありません。
「土地選びの失敗談20選」では、実際に多くの人が経験したリアルなエピソードをもとに、どんな点に注意すべきかを紹介しています。
土地選び・土地探しを進めている人や、土地選びの失敗談を知りたい人にとって、後悔しないための大切なヒントが詰まった内容です。
購入前に確認すべきポイントを、具体例を交えながら一つひとつ見ていきましょう。
用途地域の制限で希望の間取りが不可能だった
「まさか法律で間取りまで制限されるなんて、思いもしませんでした」──そう話すのは、郊外に土地を購入し、2階リビングの家を建てようとしていたAさんです。土地自体に問題はなく、価格も予算内。ただ、購入後に建築士へ相談した際、用途地域の高さ制限と北側斜線の影響で、希望していた2階の天井高が確保できないと告げられました。
用途地域というのは、その土地で建てられる建物の種類や大きさ、形などを行政があらかじめ決めている区分のことです。例えば「第一種低層住居専用地域」は、建物の高さが10メートル以下と定められていたり、北側の隣家への日照を守るために、屋根の勾配に厳しい角度制限がかかることがあります。このため、設計の自由度はかなり限られてしまうのです。
Aさんのケースでは、図面上では開放的だった吹き抜けが、法規に沿って修正された結果、天井は低く、採光も十分に取れないものになってしまいました。「間取りの大幅な見直しを余儀なくされ、結果的に妥協の連続でした」と振り返ります。
見た目や立地だけでなく、法律による制限があるかどうかを購入前に必ず確認しておくべきです。土地は自由なキャンバスではありません。可能なら購入前に建築士や不動産のプロに相談し、その場所に“自分たちの家”が本当に建てられるのかを具体的に確かめること。それが、後悔のない土地選びの第一歩だといえます。
市街化調整区域で建築許可が取れなかった
「ここなら静かだし、広さもあるし、価格もちょうどいい」──そう思って購入した土地が、市街化調整区域だったというBさん。ところが、家を建てようと申請を出したところ、建築許可が下りなかった。どうして?と驚いたそうです。
市街化調整区域というのは、ざっくり言えば「勝手に家を建ててはいけない地域」。将来的な都市の広がりを制限するために指定されている場所で、基本的に住宅建築は禁止とされています。ただし、例外があって「農業を営む人の家」や「すでに宅地だった土地への建て替え」など、一定の条件を満たせば許可される可能性はあります。
とはいえ、この条件がややこしい。自治体によって基準も違えば、審査のハードルも高いんです(出典:市街化調整区域における立地基準)。
Bさんの場合、祖父の名義で残っていた土地に「分家住宅」として家を建てる予定でした。ところが、「その土地は実質的に農地で、既存宅地ではない」と判断され、申請は却下。しかも、住宅ローンの手続きも先に進んでいたため、建てられないとわかったときには多くの手続きがすでに動いており、金銭面のダメージも大きかったといいます。
市街化調整区域の土地は、表面上はとても魅力的に見えることが多いです。価格が手頃で、面積も広く、自然も多い。でもその裏には、建てられない・使えないリスクが潜んでいます。
不動産会社から「大丈夫です」と言われても、まずは自治体の都市計画課などに直接問い合わせてください。そして、少しでも疑問が残るなら、建築士か行政書士に一度見てもらうことを強くおすすめします。そうしないと、「買ったけど建てられない」という、取り返しのつかない後悔につながります。
接道義務を満たしておらず建築が不可能だった
「ちゃんと道路に面してるし、まさか建てられないなんて思いませんでした」──購入後に建築許可が下りないと知らされたCさんの話は、決して他人事ではありません。
問題は“接道義務”。これは建築基準法で定められているルールで、簡単に言えば「建物を建てる土地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければいけない」というものです。
Cさんが選んだのは、いわゆる旗竿地。通路のように見える細長い部分がわずかに道路に触れていましたが、その幅が1.9メートル。わずか10cm足りない。それだけで建築不可と判断されてしまったのです。
図面上では微妙な違いでも、現地で確認した役所の担当者は厳格でした。塀が張り出していた分を差し引いて「実質的に2メートルに満たない」とされ、建築確認が通らなかったそうです。もちろん、後からどうにもできません。土地を買ってから気づいたときには、時すでに遅し。
土地を選ぶとき、価格や立地ばかりに目を奪われがちですが、本当に見なければいけないのは「建てられるかどうか」。道路との関係が曖昧な土地を検討する場合は、不動産会社だけでなく、行政や建築士と現地を一緒に見て判断するくらい慎重でも遅くありません。見逃しがちな条件こそが、後々最大の落とし穴になります。
建築条件付きで自由な設計ができなかった
「自由設計って書いてあったから、うちは好きな間取りでいけると思ってたんです。でも、ぜんぜん自由じゃなかったですね」──そんな悔しさをにじませながら話してくれたのは、ある30代のご夫婦。理想のマイホーム計画は、思わぬところでブレーキがかかりました。
きっかけは、「建築条件付き土地」という文字。土地と建物のセット販売で、決められた工務店で家を建てなければならない、という条件付き。しかも契約から3ヶ月以内に建物の契約を結ばなければいけない決まりがあり、ろくに比較検討する余裕もなかったそうです。
最初に出されたプランを見て、あれ?と思ったそうです。収納が少ない、日当たりも微妙、なにより「子ども部屋の広さ」がどうしても希望通りにいかない。でも、間取りの修正をお願いしても「その仕様は対応していません」とあっさり断られました。
最終的に建った家は、悪くはない。でも、決して“自分たちが考えた家”ではなかった──そんな後味の悪さが今も残っているそうです。
建築条件付きの土地は、値段や立地が魅力的に見える反面、設計の自由度には限りがあるという現実があります。「自由」と書いてあっても、どこまで自由なのか。その線引きを、購入前にしっかり確認することが、本当に納得できる家づくりには欠かせません。
焦らず、必ず確認を。それが、後悔しない土地選びへの第一歩です。
間口が狭く希望の家が建てられなかった
「土地自体はきれいな長方形で、価格も手ごろ。これでマイホームが建てられると思っていました」
そう語るDさんは、旗竿地に近い間口の狭い土地を購入した直後から、設計の自由度に壁を感じることになります。
間口、つまり敷地が道路に接している幅が狭いと、思った以上に設計の選択肢が狭まります。たとえば、間口が4メートル前後しかないと、玄関の位置ひとつ決めるのにもひと苦労。左右どちらにリビングを配置するか、窓をどこに開けられるか、耐震のための壁がどこに必要か…。細かいパズルのような設計作業が待っていました。
複数の住宅メディアでも、間口が5.5~6メートル未満の土地では「自由設計」はかなり難しいとされています(出典:参考資料)。見た目には広く見えても、壁芯や建ぺい率、セットバックの制限を引くと、実際に“使える”幅はかなり小さくなるからです。
Dさん夫妻も「子ども部屋を南側に」とか「アイランドキッチンにしたい」といった希望を出しましたが、建築士からは「幅が足りず難しい」と何度も頭を下げられたといいます。最終的に、間取りはすべて“寸法ありき”で決まり、理想とはかけ離れた住まいになってしまいました。
土地を見るとき、多くの人は面積や価格にまず目がいきます。でも、本当に確認すべきは“間口の実寸”です。その幅が家づくりの自由度を決めると言っても過言ではありません。購入前に建築士と一緒にその土地に立って、「どこに玄関をつけて、どんな光が入るのか」まで想像しておくことが、後悔しない第一歩です。数字では測れない“住みやすさ”が、そこにはあります。
旗竿地を選んで日当たりと通風が悪かった
「値段も立地も条件に合ってたし、迷わず決めました。でも、暮らしてみたら…こんなに陽が入らないなんて思いませんでした」
そう話すのは、旗竿地にマイホームを建てたEさんご夫婦。購入当初は、駅から近いわりに手頃な価格が決め手だったそうです。
けれど、実際に暮らしてみてわかったのは、隣の家にぐるりと囲まれた敷地の“奥”にある家が、朝も昼も薄暗いという現実でした。通路部分が細く、家が建っているのはその奥まった場所。午前中こそかろうじて陽が入るけれど、午後からは日差しが完全に遮られ、リビングでも照明なしでは過ごせない日が続いたそうです。
Eさん宅では、湿気の逃げ場もなく、窓を開けても風が通らない。特に梅雨時期になると、窓ガラスにびっしりと結露。洗濯物が乾きづらいのはもちろん、小さな子どもの咳が止まらなくなり、病院の先生からも「換気不足かもしれないですね」と言われたことで、ようやく自分たちの家の“欠点”に向き合うことになったといいます。
旗竿地は確かに整形地より安く手に入ることが多く、うまく設計すれば快適に暮らすことも可能です。でもそれは、通風や採光まで計算し尽くされた設計あっての話。安さや立地だけに目が向いているうちは、こうした盲点に気づけません。
購入を検討するなら、午前・午後の陽の入り方、風の抜け方、隣家との距離や高さまで、現地で必ず確認してください。図面の中に「暮らしやすさ」は載っていません。土地選びに必要なのは、“暮らしの想像力”です。
土地の方角を確認せず日当たりが悪かった
「南向きなら間違いないと思ってたんですよ。でも、実際に住んでみたら、陽がほとんど入らないんです」
こう話してくれたのは、南道路に面した土地を購入し、マイホームを建てたFさん。図面上では“理想的な日当たり”のはずでした。
ところが、リビングの窓を開けても隣家の影が大きくかかっていて、特に冬場は午前中を過ぎると部屋がぐっと暗くなる。洗濯物が乾きづらく、エアコンの使用頻度も増えたせいで、電気代もじわじわ上がっていったそうです。
「南向き=明るい」は、多くの人が信じがちな“住宅あるある”ですが、実際はそんなに単純じゃありません。たとえ南側に道路があっても、その向こうに3階建てが建っていたらどうなるか。建物の高さ、隣地との距離、道路の幅、窓の配置。どれが欠けても“明るさ”は失われます(出典:研究資料)。
不動産サイトや図面の「方角」の表記だけでは、暮らしの光は見えてきません。購入を考えている土地があるなら、午前と午後、それぞれ実際に現地に立って太陽の動きを確かめてください。できれば、冬の日にも一度見ておくと安心です。数字じゃない「光の質感」を、目で肌で感じること。それが、土地選びの見落とされがちな盲点を防ぎます。
方角は“目印”にはなっても、“保証”にはならない。これは、経験者が口をそろえて語る真実です。
高低差が大きく設計費が予算を超えた
「この土地、予算内で買えるし、眺めもいいし、いいことだらけだと思ったんです」
Gさんがそう話すとき、表情は少し硬くなっていました。見学のときにはワクワクしていたその土地は、実は“設計費が予想外に膨らむ落とし穴”を抱えていたのです。
土地には隣地との間に約2.5メートルの高低差がありました。傾斜をうまく活かせば開放感が出る──そんなふうに前向きに捉えていたものの、現実は甘くなかったそうです。実際に工事が始まると、まず必要になったのが擁壁の再施工と排水処理。業者から提示された見積は、当初の予算を70万円以上オーバーする内容でした。
「造成でここまでかかるとは想像してませんでした。最初は“ちょっと盛土すれば済むかな”くらいの感覚でしたね」とGさん。けれど、現場はそんなに単純ではありません。法律に適合させるためには鉄筋入りのコンクリート擁壁が必要で、しかも隣地の土砂が流れ込まないよう追加対策まで必要になったとのこと。
土地代が安く見えた理由、それがまさに“高低差”。整地や排水、基礎のやり直しが必要な土地は、購入価格が安くても結局、全体コストで見れば割高になるケースが多いのです。
もし高低差のある土地を検討するなら、「土地+建物」ではなく「土地+造成+建物」で見積もること。現地をプロと一緒に歩いて、見た目だけではわからない工事の手間まで想像しておくこと。それが、家づくりの後悔を防ぐための大事な“初期投資”です。安さに飛びつく前に、一度深呼吸して確認する。Gさんのような経験者が口をそろえて言う、大切なアドバイスです。
擁壁の補修義務があり想定外の出費になった
土地選びで「擁壁」に目を向ける人は、そう多くありません。けれど、まさにその見落としが、あとあと大きな痛手になることがあります。
実際に、神奈川県で中古住宅付きの土地を購入したTさんは、入居前に自治体から「擁壁の安全性に問題がある」と指摘を受けました。擁壁といっても、高さが2メートルちょっとあるだけ。見た目は特に問題なさそうだったといいます。でも、築30年以上が経ち、劣化したコンクリートの内側はひび割れや排水管の詰まりが進行していたのです。
自治体の要請を受け、業者に見積を依頼したところ、補修費用はなんと約45万円。「土地の価格でちょっと得した気分だったのが、一気に冷めましたね。想定していなかった支出でした」と、Tさんは苦笑いを浮かべていました。
実は擁壁には、所有者が管理・補修する義務があります(出典:参考資料)。安全性が確認できなければ再建築もできず、放置して崩落すれば、損害賠償の対象になることもあるのです。
新しく土地を探すなら、擁壁の有無だけでなく、その構造や劣化の程度まで確認すること。特に高さが2メートル以上ある場合や、古いブロック積みの擁壁は注意が必要です。地盤の安定性や排水設計まで含めて、専門家のチェックを受けてから購入を決めましょう。
価格が安い土地には理由があります。擁壁の管理義務もそのひとつ。「こんなことになるなら、もう少し高くても平坦な土地にしておけばよかった」。Tさんの言葉には、土地選びの現実がにじんでいました。
関連記事:擁壁のある土地は買ってはいけない?それはなぜ?7つのデメリットと後悔しないための事前対策
セットバック義務で建てられる面積が減った
「土地は100㎡って聞いてたんです。けど、いざ図面を引いてみたら、実際に建てられるのは90㎡。思ってたよりもずっと狭くなってしまいました」──都内で土地を購入したIさんが、図面を前にぼそりとこぼした言葉です。
原因はセットバック。前面道路が4mに満たないと、中心線から2m下がって建物を建てなければならないという決まりに引っかかっていたんです(出典:建築基準法第42条2項)。後退した部分は建築面積からも容積率からも除外。広告には100㎡と堂々と書かれていたのに、実質は10㎡分使えない“幻の面積”でした。
「まさかたった数メートルの道路幅で間取りが左右されるなんて…」。Iさんが希望していたのは広めの4LDK。でも、その10㎡が削られたことで、間取りは3LDKに収まり直すことに。加えて、舗装や登記の手続き、分筆費用などで予想外に30~80万円ほどの追加出費がかかり、予算はギリギリに膨らんだそうです。
これ、決して珍しい話じゃありません。測量図を見るだけでは見落としがちですが、建築の許可を取る際にセットバックが必要なことはよくあります。見た目の土地の広さだけで判断してしまうと、家づくり全体の計画に大きなズレが生じてしまいます。
土地選びの際は「面積」だけでなく、「有効面積がいくつになるか」も冷静に見ておくこと。不動産会社任せにせず、自分で役所に問い合わせるのも一つの手です。あとになって、「最初に聞いておけばよかった」と後悔する人は、驚くほど多いのです。
地盤調査前に契約し改良費が大幅にかかった
「この土地なら大丈夫だと思ってたんです。見た感じはしっかりしていたし、周囲にも家がたくさん建っていたので」。そう語るのは、千葉県内で土地を購入した40代のご夫婦。しかし、契約後に地盤調査をしてみると、そこに大きな落とし穴がありました。
結果は「柱状改良が必要」。しかも、その工事にかかる費用は約70万円。住宅ローンの融資額はすでに決まっており、思わぬ出費に頭を抱えることになったそうです。調べてみると、地盤改良には種類があり、表層改良なら30万円程度で済むこともありますが、柱状改良や鋼管杭になると100万円以上になるケースもあります。
地盤調査を契約前にしておけば、その土地の「隠れたリスク」を見抜くことができます。にもかかわらず、多くの人が「見た目」や「価格」だけで判断してしまいがちです。Iさんご夫婦も「もっと早く調べておけば、選択肢も違ったはず」と悔やんでいました。
地盤の強さは、図面では見えません。契約を急がず、まずは調査。これが、あとあと泣かない土地選びの基本です。家づくりの第一歩を踏み出す前に、ぜひその一歩を丁寧に見極めてください。
浸水想定区域と知らず水害リスクが高かった
「引っ越して1年目の梅雨に、あの光景を目にしたとき、正直、買う前にもっと調べておくべきだったと後悔しました」
あるご家族は、駅近で価格も手ごろな土地を見つけ、迷わず契約しました。ところが暮らし始めてすぐ、大雨で周囲の道路が膝の高さまで浸水。慌てて自治体のハザードマップを確認すると、そこは“浸水想定区域”で、最悪の場合は3メートルもの浸水リスクがあるエリアだったのです。
国土交通省のデータによれば、こうした想定浸水区域は全国の都市部にも広く存在し、約790万人がその範囲内で生活していると言われています。見落としがちな内水氾濫(下水からの逆流)リスクも含めると、影響の範囲はさらに広がります。
購入した土地自体に問題がなくても、災害への備えがないまま住み始めると、住宅設備や家財が被害を受け、余計な出費を招くおそれがあります。このご家族も、浸水に備えるために床を高くする工事や防水ドアの取り付けを行い、結果的に追加で100万円近い費用が発生しました。
土地の見た目や条件が良くても、災害リスクの確認を後回しにしてはいけません。とくに都市部では、思わぬエリアが被害想定区域に入っていることもあります。土地を選ぶ際は、必ずハザードマップで浸水深や避難経路を確認し、「暮らしてから気づく後悔」を防ぐことが大切です。
土砂災害警戒区域にあり想定以上の制限があった
「まさか、こんなに手間がかかるとは…正直、甘く見ていました。」
神奈川県の山沿いに土地を購入した50代ご夫婦。周囲は緑が多く、静かで理想的に思えたそうです。ところが契約後、そこが“土砂災害特別警戒区域”、いわゆるレッドゾーンに該当していたことを知ります。
問題は、ただの災害リスクだけではありません。レッドゾーン内では、建物の構造に厳しい安全基準が課され、普通の住宅では許可が下りないケースもあります(出典:参考資料)。例えば、がけ崩れの力に耐える構造計算書の提出が必要になり、補強設計や特注の基礎工事が必要になることも珍しくありません。結果、当初見積もっていた建築費用を大きく上回ることになってしまいました。
「まさかハザードマップの色で人生が狂うとは…」と、奥様は漏らします。不動産会社は区域の存在を説明していたものの、“具体的に何が問題になるか”までは把握していなかったとのこと。情報の“伝え方”と“受け取り方”の両方に落とし穴がありました。
こうした後悔を防ぐには、土地選びの段階で市町村が公開しているハザードマップを自ら確認し、その区域に該当していたら「どこまで建てられるのか」「追加で何が必要になるのか」を行政窓口や設計士に直接相談することが欠かせません。
「自然が多い場所には、自然ゆえの制限がある」──その視点を持つだけで、土地選びの精度はぐっと上がります。静かで緑豊かな土地も魅力的ですが、見た目の良さだけで決めてしまうと、後から高い代償を払うことになりかねません。
崖に近くて安全対策費が必要だった
一見すると風情があって、「ここに家を建てたら気持ちよさそう」と思ったその土地。でも、崖が近いというだけで、話は大きく変わってきます。あるご夫婦は、自然豊かな立地に惹かれて購入を決めましたが、後になって“擁壁の新設”が必要と判明。これが大きな落とし穴でした。
実際、崖下や崖上の土地には安全性を確保するための制限が法律で定められていて、地域によっては建築そのものが難しくなることもあります。東京都や神奈川県の一部では、崖から5m以内に建てる際、鉄筋コンクリートの擁壁を築く必要があり、工事費用は内容によっては300万円以上に膨らむことも珍しくありません。
このご夫婦も見積もりを取った時点で予算オーバーが確定し、設計プランを大幅に見直すことになったそうです。しかも、行政の許可を取るのに時間もかかり、スケジュールはズレにズレて、完成は半年以上遅れてしまいました。
「もっと早く地盤や法規制を確認しておけば…」と悔やんでも後の祭り。土地の見た目に惑わされず、購入前に法的リスクや地形の特性まで細かく調べておくことの大切さを、痛感したそうです。
都市計画道路にかかっていて将来の移転が不安
土地を買ってから「この場所、実は道路になる予定です」と知る──そんな冷や汗ものの話、意外と少なくありません。
現に、都市計画道路の予定地にかかる土地は、将来的に道路整備のために買収される可能性があり、「ずっと住める」と思っていたマイホームが数年後には立ち退き対象になるかもしれないのです(出典:参考資料)。
たとえば、あるご家族が購入した土地は、建築時には何の問題もないように見えました。でも後で調べてみると、20年以上前から“都市計画道路”に指定されていた場所。今すぐ工事が始まるわけではないとはいえ、「何十年先に突然移転を迫られるかも…」という不安は、生活をじわじわ蝕んでいきました。しかも、売却時の価格も思うように伸びず、資産価値の面でも厳しい状況に。
こういった事態を避けるには、土地を選ぶ段階で“用途地域”や“都市計画図”をしっかり確認しておくことが大切です。「決定済みかどうか」「事業化の見込みがあるか」といった進捗まで、自治体の窓口で直接チェックすることを強くおすすめします。
不確かな未来を抱えて土地を選ぶのは、理想の家づくりを建てるにおいて、あまりに大きなリスクです。こういった土地の購入は、注意することを強くおすすめします。
隣接道路が狭く車の出入りに支障が出た
家を建てるには土地が必要。でも、その土地が「道路に面しているからOK」と思い込んで契約すると、あとで痛い目を見ることがあります。実際、ある方が選んだのは、幅およそ3メートルの路地に面した土地。周囲は住宅に囲まれ、トラックはもちろん、普通車でも切り返しなしでは入れないほどの狭さでした。
引っ越し当日は、引越業者の大型トラックが侵入できず、途中で荷物を積み替える羽目に。建築中も資材の搬入が難航し、工程がずれ込み、予算もオーバー。しかも後から「この幅だと救急車も通れませんよ」と知って青ざめたそうです。
土地選びでは「家が建てられるか」だけでなく、「車が問題なく出入りできるか」も必ずチェックしてください。特に道路の幅と車の動線は、暮らしの快適さを左右する重大なポイントです。
電柱や支線が敷地内にあり設計が制限された
まさか、電柱ひとつでここまで悩まされるとは思いませんでした──。ある夫婦は、ようやく見つけた土地にワクワクしながら理想のマイホームの設計を進めていました。ところが、敷地内に立つ1本の電柱と、それに伸びる支線が設計の邪魔をしてしまったのです。
「駐車スペースが想定より狭くなって、ミニバンがギリギリ。バックのたびにヒヤヒヤする」「リビング前に支線が走っていて、窓を大きくできなかった」。こうした声は珍しくありません。電柱の存在は、設計図面では見落とされがちですが、実際の暮らしに直結するストレスになりえます。
電力会社に相談すれば移設できるケースもありますが、費用は10万円~20万円ほどかかる場合もあります。しかも、すべての電柱が移動可能とは限りません。だからこそ、土地を選ぶ段階で「電柱の位置」や「支線の向き」までチェックすることが大切です。
不動産屋の言葉だけを鵜呑みにせず、現地をよく観察してください。ほんの少しの見落としが、後悔の原因になりかねません。
古い構造物が残っていて撤去費用がかかった
「この金額、完全に予想外でした」
実際に土地を購入したある方がそう語ってくれました。見た目にはただの空き地だったものの、いざ契約後に調査してみると、古い基礎やコンクリート塀が地下に埋まっていたのです(出典:参考資料)。
しかも、古家の解体は終わっていたように見えて、地中の浄化槽や配管の一部がそのまま。結局、撤去費用だけで100万円近くかかってしまったそうです。(※ただし売主に瑕疵担保責任が認められるケースあり、(出典:契約不適合責任(地中埋設物)))
撤去費用は構造物の種類や状態、作業環境によって大きく変わります。特に鉄骨やコンクリート造は高額になりがちですし、道路が狭ければ重機が入らず手作業になるため、さらに費用がかさみます。
土地を見に行くときには、地上だけで判断しないこと。契約前には、古い構造物の有無について売主や不動産会社に確認し、できれば専門業者に現地を見てもらっておくと安心です。見えない「地中リスク」は、費用面でも精神的にも後悔のもとになります。
隣地との境界が曖昧で購入後に揉めた
家を建てる準備が整い、ようやく理想の土地を見つけたと思った矢先、思わぬ落とし穴がありました。それが「境界がはっきりしていない土地」だったのです。
書類上では問題なさそうに見えても、実際の現地では境界杭が見当たらず、隣の家の方と「どこからがうちの土地?」という話に。結果、土地家屋調査士を呼んで測量をやり直し、数十万円の追加費用が発生しました。
こうした境界トラブルは、決して珍しくありません。特に古い住宅地や、相続で持ち主が変わっているような場所では、土地の境界があいまいなまま放置されているケースも多いのです。
土地を探す段階で「境界確定図」や「筆界確認書」などをきちんと確認し、必要であれば買う前に現地で境界杭の有無を確かめておく。このひと手間を惜しまなければ、あとあと心身をすり減らすこともありません。土地選びで後悔しないための、意外と見落としがちな注意点のひとつです。
仲介業者の説明不足で重要事項を見落とした
土地を買うときに、「そんなの聞いていない」となるトラブルは意外と多いです。特に厄介なのが、仲介業者からの説明が不十分だったために、あとになって重大な事実を知るパターン。例えば、「この土地は浸水履歴があります」といった話が一言もなく、契約後に役所で調べて初めて分かったというケースもあります。
建築に制限のある地域だったことを知らされず、希望していた間取りが法律上建てられなかった——という声も実際にあります。重要事項説明書に小さく書かれていたとしても、購入者側が内容を完全に理解していなければ意味がありません。
しかも、説明は一度限り、しかも短時間。法律で「説明したことになっている」から、あとは自己責任という空気があるのも問題です(出典:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
こんな失敗を防ぐには、自分の目と耳を信じて、気になることは納得できるまで確認することが大切です。「よくあることです」「みなさん気にされませんよ」と流されそうになったら、いったん立ち止まりましょう。不安が残るなら、セカンドオピニオンとして不動産に強い専門家に一度目を通してもらうのも有効です。
失敗談に共通するやめたほうがいい土地の特徴
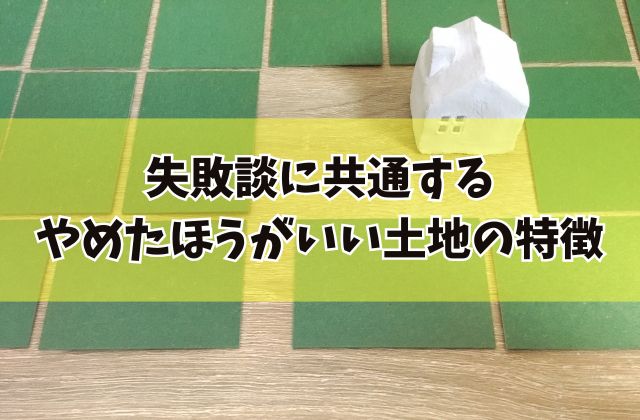
土地選びの失敗談を振り返ると、いくつかの共通点が見えてきます。
「なんとなく安いから」「場所が良さそうだから」といった感覚だけで決めてしまうと、見えないリスクに後から気づくことになります。
ここでは、実際の体験談をもとに、購入前に注意したい「失敗談に共通するやめたほうがいい土地の特徴」について紹介します。
後悔のない土地選びのために、避けたほうが良いポイントを押さえておきましょう。
急斜面や崖に近く災害リスクが高い土地
「値段も手頃だし、眺めも悪くないし…ここで決まりかな?」──そんな直感だけで選んでしまうと、後から取り返しのつかない後悔を抱えることになります。特に注意すべきなのが、崖や急斜面に隣接する土地です。
土砂災害が起きやすい地域では、ちょっとした大雨でも地盤が緩み、がけ崩れや土石流が発生する危険があります。国土交通省の統計によると、2023年には全国で1,471件もの土砂災害が発生(出典:報道発表資料)。これは過去10年の平均を上回る件数です。特に傾斜のきつい場所では、滑り出した土砂が2~3倍もの距離にまで及ぶこともあるといいます。
実際、千葉県内のある住宅地では、造成時に急斜面を十分に補強していなかったことで、雨のたびに土が流れ出し、近隣住民とのトラブルにも発展しました(出典:参考資料)。「まさか自分の家が…」という想定外を避けるには、購入前に必ず自治体のハザードマップを確認し、専門家に相談するくらいの慎重さが必要です。
安さや眺望の良さに気を取られて、命や財産を危険にさらすような土地を選ばないようにしましょう。家は建てた後が本番。安心して住み続けられるかどうかこそが、本当の“良い土地”の条件です。
ハザードマップで浸水深が深い土地
購入後に後悔する例として多いのが、水害リスクを見落とした土地選びです。たとえば、ハザードマップで「浸水深1メートル以上」と示されていたエリア。ここに家を建てた方の中には、床上浸水で家財道具がすべてダメになり、家そのものの修繕費もかさみ、大きな負担を抱えることになった方もいます(出典:水害による被害)。
特に注意すべきは、浸水深が「3メートル以上」とされている場所。国の資料によれば、これは2階まで浸水する可能性があることを意味しており、避難すら難しくなるおそれがあります(出典:参考資料)。こうした場所では建て替えや売却すらままならず、身動きが取れなくなる可能性も。
大事なのは、「水害なんて滅多にないでしょ」と油断しないこと。ハザードマップを開いて、浸水リスクを事前に確認するのはもちろん、実際に現地を歩いてみたり、近隣住民に話を聞いたりすることも非常に有効です。情報を鵜呑みにせず、肌感覚で確認する。この一手間が、後悔のない土地選びを左右します。
日当たりが悪く洗濯や生活に影響する土地
家を建ててから気づいた、という声がとても多いのが「日当たりの悪さ」です。実際に暮らし始めてみると、洗濯物はいつまでも乾かず、生乾きのにおいが部屋に残ってしまう。そんな状態が毎日続くと、ストレスも溜まります。
ある方は、周囲を高い建物に囲まれた北向きの土地を購入。日中でも薄暗く、結局、リビングでは昼間から照明を点けっぱなし。冬場は陽が入らず部屋が冷え込み、暖房代も思った以上にかかったそうです。さらに、湿気が逃げずに結露がひどく、窓や壁にカビが発生。掃除に追われる毎日だったといいます。
「日当たりなんて気にしすぎだと思っていたけど、ここまで生活に影響するとは…」と、土地選びの判断を悔やむ声は少なくありません。現地を訪れたときに天気が悪かったり、朝夕の時間帯だけを見て判断してしまうと、実際の陽当たり具合は見落としがちです。
土地選びの際は、太陽の動きや周囲の建物の影をしっかり確認し、時間帯ごとの光の入り方まで意識してチェックすることが大切です。
交通量が多く騒音や排気が気になる土地
大通りに面した土地は便利に見えても、実際に暮らすとなると話はまったく変わってきます。うるさい、汚れる、落ち着かない。この3つが揃ってしまうと、家にいるのに心が休まりません。
特に車の往来が激しい道沿いでは、窓を閉めてもエンジン音やクラクションが響きます。寝ていても耳に入る音はなかなか遮れず、結果として睡眠の質が下がることも。厚生労働省も騒音による健康リスクを指摘しており、長期的には高血圧やストレスの原因になると言われています(出典:参考資料)。
しかも、車の排気ガスは目に見えづらい厄介者。洗濯物は外に干せず、せっかくの新築の外壁がすぐに黒ずんでくる、なんてケースも少なくありません。あるご家族は「住んで初めて、静かさと空気のきれいさがどれほど大事だったか気づいた」と振り返っていました。
「駅に近いから」「値段が手頃だったから」といった理由で飛びつくと、あとで住みにくさに悩まされます。音や空気は、写真にも図面にも載っていません。現地見学では、必ず平日・週末・昼・夜と時間帯を変えて、自分の五感で確認することを強くおすすめします。
雰囲気が暗く雰囲気が良くないと感じる土地
土地の購入前、「なんとなく気が進まない」と感じる場所には、何かしらの理由が潜んでいるものです。実際に「駅から近い」「価格も条件に合っている」と思って見学に行ったのに、現地に立った瞬間、妙な圧迫感や静まり返った空気に胸がざわついた経験はないでしょうか。
その“直感”は、決して気のせいではありません。街の空気感には、景観や建物の古さ、手入れの行き届かなさ、防犯面の不安、あるいは通りすがる人の雰囲気までが影響しています。都市整備局の調査でも、地域の印象が住環境の満足度に大きく関係するという報告があります。
たとえば、ある夫婦は中古住宅付きの土地を購入する予定でした。駅にも近く、価格も手頃。しかし内見の帰り道、薄暗い路地、古びた看板、閉まりきったシャッター街の寂しさに不安を感じて見送ったそうです。夜に再訪してみると、街灯が少なく視界が悪く、人通りも皆無。「ここでは安心して暮らせない」と判断したといいます。
こうした失敗を避けるには、日中の見学だけで判断せず、朝・夕・夜の様子を自分の足で確かめることが大切です。地図や数値では拾えない“肌で感じる違和感”こそ、住まい選びの重要なサインになることがあります。
予算に合わず建物費用を削る必要がある土地
「安い土地を見つけた!」と飛びついたものの、あとで建築費を削る羽目に──。これはよくある話です。土地価格に惹かれて予算の大半を使ってしまい、いざ家を建てる段階になって「お金が足りない」と気づく。結果として、理想の間取りや仕様をあきらめるしかなくなります。
というのも、土地には建物以外にかかる“見えないコスト”が潜んでいるからです。たとえば、地盤が弱ければ改良工事が必要になりますし、上下水道やガスが引き込まれていなければ、その整備にも数十万円以上かかります(出典:参考資料)。こうした費用は土地によって大きく異なるため、建物にかけられる金額を圧迫する原因になるのです。
実際、当初は「坪単価が安くてお得」と思って契約した土地が、いざ工事段階で地盤改良費や外構費がかさみ、建築費を200万円以上削る結果になったケースもあるほど。仕方なく設備グレードを下げたり、収納を減らしたりして、当初思い描いていたマイホームからは大きくズレてしまうことも。
こうした事態を避けるためには、土地価格だけでなく「トータルでいくらかかるか」をシミュレーションしておくことが欠かせません。土地+建物+諸費用のバランスを俯瞰し、余裕のある資金計画を立てることが、後悔のない家づくりの第一歩です。
隣地境界が不明確で後で揉める可能性ある土地
「まさか土地を買ったあとに隣人と境界線のことで口論になるなんて…」。これは実際によくある話です。境界杭がなかったり、昔の慣習であいまいなまま使われてきた土地では、いざ工事に入ろうとしたときに「ここはうちの敷地じゃないの?」と相手から言われて、建築が止まってしまうケースもあります。
このようなトラブルは、事前にきちんと測量しておけば防げるもの。公図と現況のズレは意外と多く、専門家に依頼して現地を確認してもらうことで、見落としがちなリスクにも気づけます(出典:筆界特定制度)。もし曖昧なまま進めてしまえば、後から境界確認のために訴訟や調停が必要になり、金銭的にも精神的にも大きな負担です。
土地選びの時点で「境界はハッキリしていますか?」と仲介業者に聞くことは、最もシンプルで大切な確認事項のひとつです。見えない境界線が、見えるトラブルを生むこともあると、どうか覚えておいてください。
前面道路に上下水道が未整備の土地
一見すると静かで整った環境に見える土地でも、目に見えないインフラの整備状況によっては、後から大きな出費が発生するケースがあります。特に気をつけたいのが、前面道路に上下水道が整っていない土地です。
「引き込みがないから工事をすればいい」と簡単に考えがちですが、実際にはそう単純ではありません。上下水道の本管が通っていない場合は、そもそも引き込み工事自体ができないこともありますし、仮に引けるとしても工事費が想像以上に高額になります。
実際、60万~100万円程度かかるという声は珍しくありません。中には、自治体の加入金や道路の掘削費用も重なって、200万円近くかかったという話もあるほどです(出典:参考資料)。
たとえば「道路までは水道が来ているけれど、自分の敷地までの配管は未整備だった」というケース。引き込み工事費だけで数十万円、そこに水道局への加入金や、場合によっては舗装の復旧費まで発生します。知らずに契約してしまい、後悔する方が後を絶ちません。
土地を購入する前に必ず、自治体や上下水道局に確認を入れてください。前面道路に本管が通っているか、敷地内に引き込み済みかどうか、工事費の目安はどれくらいか——少しでも不明な点があれば、専門家に同行してもらって調査することを強くおすすめします。
土地選びは「見えない部分」で差が出ます。あとから泣かないように、事前の確認が何より大切です。
形がいびつで設計が難しく建築費が高くなる土地
一見すると広さに問題のなさそうな土地でも、輪郭がガタついていたり、三角やL字などの不整形だと、建てる家の自由度が一気に狭まります。
経験者からよく聞くのは「土地代は安かったけど、家の設計で泣いた」という声。実際、そうした形状だと一般的なプランが使えず、特注の設計が必要になります。その分、設計料も工事費もジワジワ跳ね上がるのが実情です。
たとえば、直線の多いシンプルな四角い家なら、外壁や屋根も効率的に施工できますが、角が多いと職人の手間も増え、材料の無駄も出やすくなります。
海外の事例では、外壁の長さが増えることで施工コストが約6%上がるケースも見られました。しかも、形が複雑になるほど雨仕舞いや断熱の工夫が必要になり、結果的に予算を1.2~1.3倍見ておかないと足りなくなるという話も珍しくありません。
土地選びの段階では、つい「安さ」や「場所の良さ」に目が行きがちですが、設計の自由度が低い形状は、結果的に“高い買い物”になります。家を建てる前提なら、土地の形がスムーズな設計と予算管理に直結すること、ぜひ覚えておいてください。
抵当権が残っていて将来トラブルの可能性がある土地
「安くて条件もいいじゃないか」と飛びついた土地、実はあとから“抵当権付き”と発覚。もし前の持ち主がローンを滞納したら、購入者である自分が何の落ち度もなく競売の巻き添えになるかもしれません。
抵当権とは、ざっくり言えば「お金を借りた側が返せなくなった時、土地を処分して回収するための銀行側の保険」のようなもの。つまり、まだ完済されていないローンがくっついた状態の土地を買うと、見えないリスクを抱え込むことになります。
たとえば購入後に「実は売主の借金が残っていて、銀行から差し押さえ通知が届いた」なんてトラブルも現実に起きています。特に個人間売買では、契約書をよく確認せずに進んでしまう人が多いので要注意です。
土地を購入するときは、登記簿謄本の「権利部(乙区)」に目を通し、抵当権の記載があれば必ず「抹消して引き渡す」ことを契約条件に盛り込んでください。安心して家を建てるためにも、このひと手間は決して省けません。
失敗談を踏まえて後悔しないための土地選びのポイント
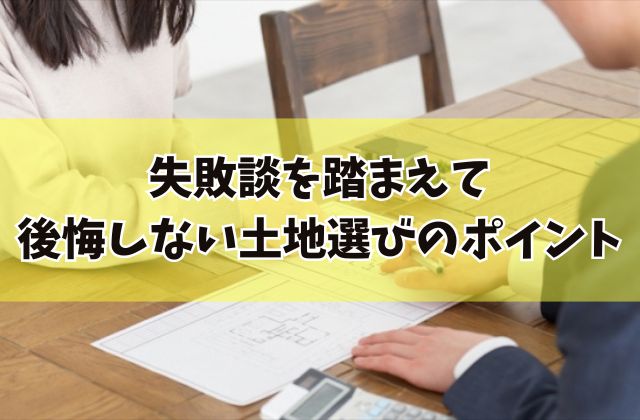
土地選び・土地探しで後悔したくない方にとって、「土地選びのポイント」を知ることは非常に重要です。
間取りが制限された、地盤改良に思わぬ費用がかかった、境界トラブルに巻き込まれたなど、実際の失敗例から学べることは多くあります。
ここでは、購入前に必ず押さえておきたい確認事項や判断基準を、具体的にわかりやすく紹介します。土地購入を成功させたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
条件の優先順位を家族で明確に決めておく
理想の土地なんて、探せば探すほど「どこかしら足りない」ものです。そんな中で後悔しない選び方をするには、「家族で何を一番大事にしたいのか」を最初に話し合っておくことが、何よりも大切です。
たとえば「駅からの距離」「学区」「日当たり」「予算内で建てられるか」など、譲れない条件は家庭によってまったく違います。これを曖昧なままにしてしまうと、内見や検討のたびに意見がブレて、時間も労力も無駄になります。しかも、肝心の「納得感」まで失ってしまいがちです。
実際、多くの住宅相談に携わるプロも、最初にやるべきは「希望条件の棚卸し」と断言しています。リスト化して、必須/希望/妥協可という3段階に整理しておけば、迷ったときに立ち返る基準ができるのです。
家族それぞれの希望を丁寧に聞き取って、最終的に「この条件は絶対」「これは妥協できる」と線引きしておく。それが、土地選びを後悔しないための土台になります。
もし、不動産のプロのアドバイスを貰いながら土地情報を集めたい方は、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用するのがおすすめです。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
法的制限(用途地域や建ぺい・容積率)を確認する
「理想の家が建つはずだったのに、建てられなかった」──実はそんな声、土地選びの失敗談では珍しくありません。その原因の一つが、法的な制限を見落としていたこと。
たとえば第一種低層住居専用地域では、建ぺい率が60%、容積率が200%といったルールが決まっています(出典:都市計画制度)。これが何を意味するかというと、100㎡の土地に対しては建築面積60㎡、延べ床面積200㎡以内でしか家を建てられないということ。もし二世帯住宅や広めの平屋をイメージしていたなら、希望はすっぱり断たれてしまいます。
この制限、ネットで調べれば出てきますが、正直読み解くのは難しいです。だからこそ、土地を選ぶときには、役所の都市計画図で用途地域を調べたり、信頼できる建築士や不動産会社に相談して「どこまで建てられるか」を必ず確認しておきましょう。
間取りで妥協したくない人ほど、先にこの点をクリアにしておくべきです。ぜひ、参考にしてみてください。
上下水道や電気などインフラ整備状況を確認する
どんなに理想的な土地に見えても、水道・電気・ガスといったインフラが通っていなければ、そこに暮らすための準備は一から始めなければなりません。引き込み工事にはまとまったお金がかかり、思いがけない出費に後悔する人も少なくありません。
たとえば、水道が道路から引かれていない場合、20~30メートルの引き込み工事で30~60万円ほどの費用がかかることがあります(出典:参考資料)。電気はポールの位置次第で10万円以上、ガスが都市ガスではなくプロパンしか使えない地域だと、ランニングコストも割高です。
土地価格だけを見て飛びついた結果、インフラ整備に数十万円もかかり、予算オーバーになる——こうした失敗談はよく耳にします。購入を検討する段階で、不動産会社や自治体の窓口、またはハウスメーカーにインフラの状況を細かく確認し、必要な工事と費用の見積もりをとっておくことが何より大切です。
災害リスク(浸水や崖崩れ)を事前に把握する
家づくりを始めるとき、つい見落とされがちなのが“土地そのものの安全性”です。中でも厄介なのが、自然災害のリスク。浸水や崖崩れといったトラブルは、起きてからでは手遅れです。たとえば、購入した土地が土砂災害警戒区域だった——これ、実際によくある話なんです。
だからこそまずやるべきは、ハザードマップの確認。国交省が出している「重ねるハザードマップ」なら、洪水・土砂・津波など、リスクを重ねて見られます。また、各自治体が公開している「わがまちハザードマップ」も要チェック。地域ごとの避難経路や危険ゾーンが細かく載っています。
リスクがあるとわかったら、「やめておこう」と判断するのも一つの手ですし、建物の床を高くする、擁壁を設けるといった防災設計で対応することも可能です。不安があるなら、資料を持って専門家に見てもらうのが賢明です。安心して暮らせる土地かどうか、見た目だけでは判断できませんから。
土地選びに困ったらプロに相談しながら進める
「この土地で本当にいいのか…」と迷ったとき、一人で判断しようとすると、意外な落とし穴にハマりがちです。理想の家を建てるために選んだ土地でも、いざ設計となると「想定していた間取りが入らない」「擁壁の補強が必要で数百万円かかる」なんて事例も少なくありません。
そこで、不動産業者や住宅会社、建築士といった専門家に相談することで、目に見えにくい土地のリスクまで洗い出してもらえます。たとえば、ハウスメーカーであれば、土地の条件をもとに建物のプランや予算配分を具体的にシミュレーションしてくれますし、建築士であれば、複雑な地形でもうまく活かせる設計の可能性を探ってくれます。
実際に、「旗竿地しか選べなかったけど、建築家と相談しながら進めたら光と風の通りを工夫した素敵な間取りになった」という声もあります。土地選びに迷ったときは、勇気を出してプロに相談してみる。そのひと手間が、後悔しない住まいづくりに繋がっていきます。
そして、不動産のプロのアドバイスを貰いながら土地情報を集めたい方は、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用するのがおすすめです。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
失敗した!土地を買って立ち直れないときの最適な対処法
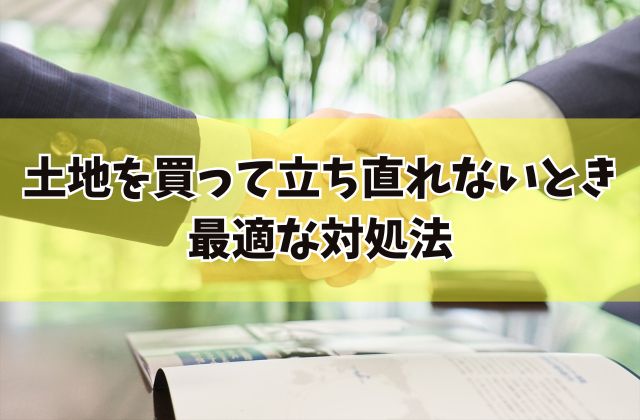
理想の住まいを夢見て選んだ土地が、思わぬトラブルの連続だった…。そんな深い後悔を抱える方も少なくありません。
実際に「失敗した!土地を買って立ち直れない」と感じてしまったとき、どうすれば前を向けるのか。
その状況から抜け出すためにできる現実的な対処法を、3つの視点からご紹介します。購入後に頭を抱える前に、解決の糸口を見つけるヒントとして役立ててください。
専門家に土地活用プランを相談する
土地を買ったのに使い道がなくて困っている──そんな時は、一人で悩まず、土地活用に詳しい専門家に相談するのが正解です。
というのも、土地の活用方法は一つじゃありません。住宅を建てるだけでなく、アパート、駐車場、太陽光発電施設など、選択肢は意外と多岐にわたります。ただし、どの方法がベストかは、その土地の立地や広さ、周辺環境、将来の見通しなどによって大きく変わってきます。
実際に、ある相談者は自宅用の土地として購入したものの、建築にかかる費用が予想以上に膨らみ断念。その後、専門の土地活用プランナーに相談したことで、駐車場としての運用に切り替え、安定した収益を得られるようになったそうです。
素人判断ではどうしても視野が狭くなりがちです。第三者のプロに話を聞いてもらうことで、新たな選択肢が見えてくることもあります。後悔を少しでも減らすために、活用に行き詰まったら、まず専門家の意見を取り入れてみてください。選択肢は、思ったより広がっているかもしれません。
※
購入した土地をすぐに売りに出す
「しまった」と思ったら、迷っている暇はありません。購入した土地に後悔が残るなら、早めに売却を検討するのが得策です。とくに「住む予定がない」「使い道がない」といった場合は、不動産会社による買取サービスを利用すれば、数週間~1か月程度で現金化できるケースもあります。これは仲介で買い手を探すよりも圧倒的に早く、手間も少ないのが特徴です。
とはいえ、売却価格は相場の6割~7割になることが多く、納得できるかは人それぞれ。焦って手放すと後悔するので、まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、価格感を把握してから決断しましょう。数十万~数百万円単位の差が出ることもあります。
「失敗した土地を持ち続けるストレス」と「やや安くてもスパッと手放して気持ちを切り替える決断」──どちらが自分にとって良い選択なのかを冷静に考えることが大切です。
※
自治体への寄付を検討する
「どうしても活用できない」「売るあてもない」そんな土地を抱えて困っているなら、自治体に寄付できないか相談してみる価値があります(出典:相続土地国庫帰属制度)。ただし、どんな土地でも受け入れてもらえるわけではないのが現実です。
実際のところ、多くの自治体は“管理に手間がかかる土地”や“公共利用の見込みがない土地”については慎重です。たとえば、山林や狭小な旗竿地、アクセスが極端に悪い土地などは断られるケースが多いと言われています。一方で、駅から近い立地や、公園や施設などに転用できるような条件の良い土地であれば、前向きに検討してもらえることもあります。
たとえば、ある自治体では「通学路に面していて地域整備に活用できそうな土地なら検討の余地あり」と明言している例もあるほど。とはいえ、受け入れの可否は役所ごとに違いがあるため、まずは都市計画課や資産管理課などの窓口に問い合わせてみましょう。
土地に見切りをつけるのは簡単ではありませんが、維持費や固定資産税をこれ以上抱えたくないなら、自治体への寄付という道もひとつの選択肢です。判断に迷ったら、不動産や法務の専門家に相談しながら進めていくのがおすすめです。
【Q&A】気になる土地選びの失敗談に関するよくある質問

最後に気になる土地選びの失敗談に関するよくある質問をまとめました。
多くの人がつまずいたポイントや、事前に知っておくべきチェック項目についてわかりやすく解説。土地選びの参考としてぜひ活用してみてください。
買わない方がいい土地の条件は?
「買ってはいけない土地」には、いくつかの共通点があります。
たとえば、法的な制限が厳しくて思い描いていた建物が建てられない場所。あるいは、災害リスクが高くて住んだあとも不安が残る場所です。都市計画道路にかかっていたり、浸水想定が2メートル以上だったりすると、建築や生活そのものに大きな影響が出かねません。
こういった土地は一見お得に見えることもありますが、長い目で見るとトラブルの元になるケースが少なくありません。購入を検討する際は、ハザードマップや自治体の計画図をよく確認し、「安いには理由がある」と心得て選ぶことが大切です。
こんな土地は買うな!と言われる注意点は?
「その土地、買わない方がいい」とプロに言われるのには理由があります。
たとえば、水道や下水道が整っていない土地。あとから工事するとなると、平気で100万円以上の費用がかかることもあります。また、境界線があいまいな土地は、後で隣人と揉める原因になりやすく、場合によっては裁判沙汰になることも。
実際、インフラの整備に120万円かかって予算オーバー、隣人との境界トラブルで1年以上も話し合いが続いたという体験談も見られます。土地の価格だけで判断せず、契約前に専門家のチェックを受けるのが、失敗を防ぐ大きな鍵になります。
住んではいけない土地の特徴は何があるの?
「この土地に住んでいいのか?」そんな直感が働いたら、一度立ち止まってみるべきです。
災害の多い地域や、条例で建築が厳しく制限されている場所には注意が必要です。崖の近くや土砂災害警戒区域に指定されている土地では、安全対策に多額の費用がかかったり、そもそも建築許可が下りにくかったりします。風致地区のように景観保護のルールがある場所では、設計の自由度が大きく制限されることも(出典:東京都風致地区条例)。
地図や現地の雰囲気だけではわからないことが多いので、必ず自治体の資料を確認し、不安があれば専門家に相談するのが賢明です。「知らなかった」では済まされないのが土地選びの難しさです。
いい土地と悪い土地の違いはどこで見分けるの?
「この土地、良さそう!」と第一印象で決めてしまうと、あとで痛い目を見るかもしれません。良い土地とそうでない土地には、素人目にもわかるポイントがいくつかあります。
たとえば、境界線がはっきりしているか。道路との接し方に問題はないか。上下水道やガスが整備されているか。そして、敷地の形状や周囲の環境も見逃せません。こうした条件がひとつでも欠けていると、住んでから後悔する可能性が高くなります。
実際に、地盤が弱くて追加の改良費がかかったり、日当たりを気にせず購入した結果、冬場は室内が極端に寒かったという声もあります。
不安があるなら、信頼できる不動産会社や建築士と一緒に現地確認をするのが一番。プロの目を借りて、後悔のない土地選びを進めてください。
土地選びで後悔した人のブログはある?
ネット上には、土地選びに失敗した人たちのリアルな体験談が多く公開されています。じっくり読んでみると、見逃しがちな落とし穴に気づかされることが多いのです。
たとえば「仮契約を急いで結んだ結果、周辺環境の確認が不十分だった」という話や、「仲介業者に任せきりにしたせいで、重要な説明がなかった」というものもあります。いずれも、ほんのわずかな油断が取り返しのつかない後悔につながっています。
ブログの魅力は、書き手の感情や思考の過程が生々しく伝わるところ。自分の価値観に近い人のエピソードを見つけると、より参考になるはずです。
土地選びの準備段階でこうした体験談に触れておくと、判断の精度がぐっと上がりますよ。
土地購入に失敗したブログはどんな内容?
検索してみると、土地購入の失敗談を綴ったブログがいくつも見つかります。その内容はというと、「ほんとにそんなことあるの?」と驚くようなリアルなエピソードばかり。
ある方は、駅から近い立地に惹かれて購入したものの、実はその駅が高架工事中で、数年後に電車の音が想像以上にうるさくなったと後悔しています。別の方は、土地そのものは良かったのに、隣地の所有者と境界でもめてしまい、引っ越し後も気疲れが絶えないと綴っていました。
多くのブログで共通しているのは、「もっと調べておけばよかった」「誰かに相談しておけば防げたかも」という後悔の言葉です。
こうした声は、まさに“失敗の先輩”たちからの貴重なアドバイス。これから土地を探す人には、何よりの教科書になるでしょう。
まとめ:土地選びの失敗談からNGな土地の特徴と選び方のポイント
土地選びの失敗談からNGな土地の特徴と選び方のポイントをまとめてきました。
改めて、土地選びの失敗談20選をまとめると、
- 用途地域の制限で希望の間取りが不可能だった
- 市街化調整区域で建築許可が取れなかった
- 接道義務を満たしておらず建築が不可能だった
- 建築条件付きで自由な設計ができなかった
- 間口が狭く希望の家が建てられなかった
- 旗竿地を選んで日当たりと通風が悪かった
- 土地の方角を確認せず日当たりが悪かった
- 高低差が大きく設計費が予算を超えた
- 擁壁の補修義務があり想定外の出費になった
- セットバック義務で建てられる面積が減った
- 地盤調査前に契約し改良費が大幅にかかった
- 浸水想定区域と知らず水害リスクが高かった
- 土砂災害警戒区域にあり想定以上の制限があった
- 崖に近くて安全対策費が必要だった
- 都市計画道路にかかっていて将来の移転が不安
- 隣接道路が狭く車の出入りに支障が出た
- 電柱や支線が敷地内にあり設計が制限された
- 古い構造物が残っていて撤去費用がかかった
- 隣地との境界が曖昧で購入後に揉めた
- 仲介業者の説明不足で重要事項を見落とした
そして、土地選びで後悔しないために押さえておきたい重要ポイントもまとめると、
- 建築に支障が出る土地(市街化調整区域・接道なしなど)は事前確認が必須
- 高低差や日当たり、方角といった土地形状が暮らしやすさに直結する
- 擁壁や地盤など目に見えない要素が後々の大きな出費につながる
- 災害リスクや都市計画に関わる情報は自治体のハザードマップ等で調査を
- 迷ったときは不動産や建築の専門家に相談するのが失敗回避の近道
「土地選びの失敗談」は、購入後に後悔する前に知っておくべき教訓が詰まったテーマです。
用途地域や災害リスク、地盤の状態など、見落としがちなポイントが意外と多く存在します。
後悔しないためには、冷静な情報収集と専門家のアドバイスを活用する姿勢が何より重要です。