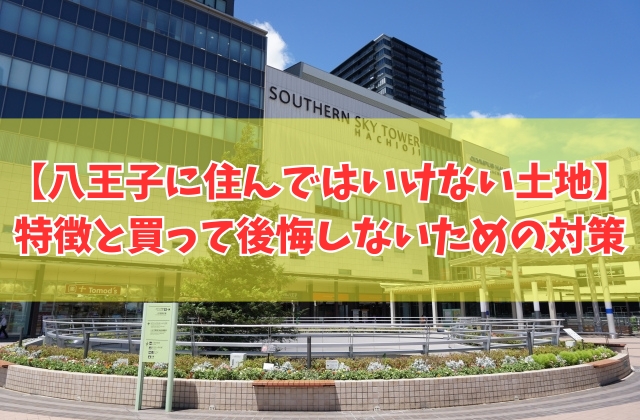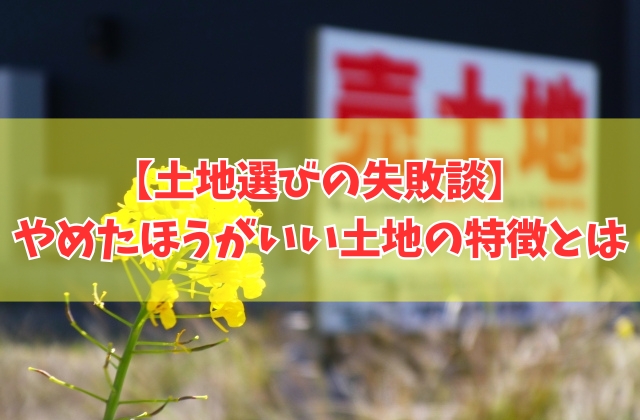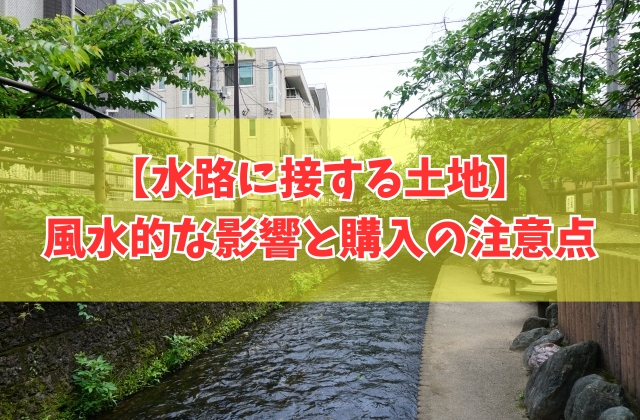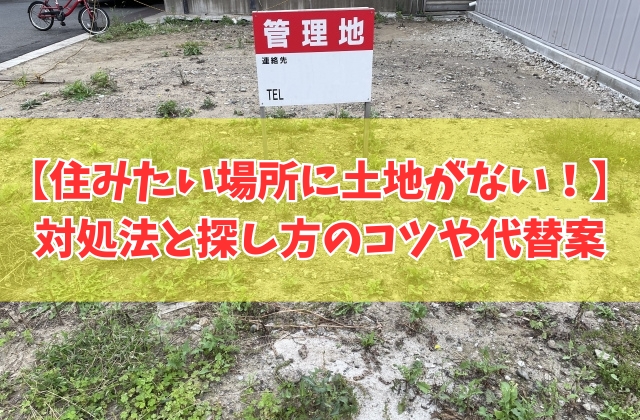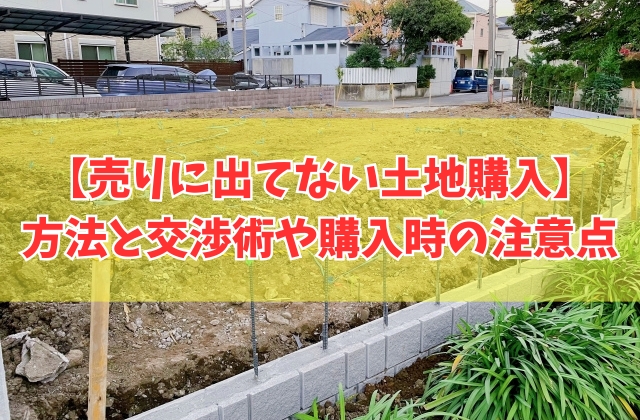
「売りに出てない土地を購入する方法はあるの?」
「土地購入時の注意点は?家で非公開土地の情報は探せないのかな?」
「空き地があるのに、なぜ売りに出ていないのだろう」と感じたことはありませんか?
希望のエリアで条件に合う土地がなかなか見つからず、行き詰まりを感じている方は少なくありません。
でも実は、売りに出ていない土地にも購入のチャンスはあります。
そこで本記事では、売りに出てない土地の購入を検討している方に向けて、情報の見つけ方や注意すべき落とし穴を丁寧に解説します。
「売りに出てない土地購入」を成功させるには、事前の知識と戦略がカギです。ぜひ最後までご覧ください。
- 売りに出てない土地は不動産会社や工務店から非公開情報を得るのが効果的
- 登記簿の取得や現地調査で所有者を特定し直接交渉に進めることもできる
- 法的リスクや物理的な問題を事前に調べて慎重に判断することが重要
売りに出てない土地を購入するには、表に出ない情報をつかむ工夫と、慎重なリスク確認が欠かせません。手間こそかかりますが、選択肢を広げたい方にとって価値ある手段といえます。
では、どうやって土地情報を集めればいいのか?できれば、家にいながらネットで簡単に情報がもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
売りに出てない土地を購入する方法5選

誰もが狙える「売りに出ている土地」とは違い、表に出ていない「売りに出てない土地」には、思わぬ掘り出し物や希望エリアの好条件物件が眠っていることがあります。
ですが、こうした土地は普通の検索ではなかなか見つかりません。
そこで今回は、売りに出てない土地の購入を検討している人や、土地の探し方や購入時の注意点を調べている人に向けて、売りに出てない土地を購入する方法5選を紹介します。
各方法のメリットや実践ポイントもあわせて解説しますので、気になる土地を見つけたい方はぜひ参考にしてみてください。
不動産会社に未公開土地の相談をする
売りに出されていない土地を探しているなら、まず一度、不動産会社のドアをノックしてみてください。実は、一般の物件情報サイトに載っていない「未公開土地」というものが存在しており、信頼できる不動産会社を通じてしか出会えないケースが多々あります。
こうした物件は、売主の事情で公にせず水面下で話が進むものもあれば、売却準備中の段階だったり、売主が“信頼できる相手にだけ売りたい”と考えていることも少なくありません。つまり、情報を「持っている人」と直接つながることが鍵です。
たとえば、オープンハウスの調査によると、実際に物件を紹介する前に顧客の希望条件を細かくヒアリングし、条件に合致した土地が見つかれば、広告を出す前に声をかけるケースが多いといいます。さらに、複数の会社に声をかけておけば、それぞれが持っているネットワークから独自の未公開情報を得られるチャンスも広がります。
地域密着型の不動産会社であれば、地主との直接的なつながりを持っていることもあります。「◯◯エリアで、これくらいの広さ、予算はこのくらい」といった希望を正確に伝えれば、「実は来月売りに出る予定の土地がある」といった話がポロッと出てくることもあるのです。
土地探しというと、どうしてもネット検索に頼りがちですが、未公開土地のような情報は、人とのつながりから始まる場合がほとんどです。だからこそ、気になるエリアがあるなら、まずは不動産会社を訪ね、丁寧に希望を伝えておく。地道な一歩ですが、これが結果として理想の土地と出会うための最短ルートになるかもしれません。
とはいえ、不動産会社にひとつずつ問い合わせて情報を集めるのは億劫。。できればネットで簡単に、情報を一括取得できる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
法務局で登記簿を取得して所有者を調べる
気になる空き地を見つけたのに、売りに出されていない——そんなときこそ、頼りになるのが「登記簿」です。
最寄りの法務局へ行けば、その土地の所有者が誰なのか、現在の権利関係まできちんと確認できます。しかも、手続きはとても簡単。必要なのは「地番」だけ。これは住所とは異なるため、ブルーマップや固定資産税の通知書などで事前に調べておくとスムーズです(出典:参考資料)。
登記事項証明書の請求は、法務局の窓口なら600円、オンラインで事前申請すればたった480円で取得できます。待ち時間も10~15分程度と短く、郵送でも対応可能。誰でも請求できるので、気になる土地があれば遠慮せず調べてみましょう。
「まだ売りに出ていないから」と諦める必要はありません。登記簿を手に入れれば、交渉への第一歩を踏み出せます。土地探しは情報戦——まずは、確かな情報を自分の手でつかむところから始めてみてはいかがでしょうか。
買付証明書を作って所有者に交渉の意思を示す
「本気で買いたい」と思っている土地があるなら、その気持ちはできるだけ“形”にして伝えるのが効果的です。実際、不動産業界では「買付証明書」という書類が、買い手の意思表示としてごく一般的に使われています。これは簡単に言えば、「私はこの条件でこの土地を買いたいと思っています」という内容を記載する書面です。
正式な契約ではないので法的な拘束力はありませんが、それでもこの一枚があるだけで、売主や不動産会社の対応が大きく変わることも。たとえば「現金一括で購入可能」「ローン特約なし」と書き添えるだけで、他の買い手よりも優先されるケースも珍しくありません(出典:不動産売買契約書)。買い手の“本気度”が見えるからです。
提出の方法も難しくありません。あらかじめフォーマットを用意してくれる不動産会社もありますし、手書きで気持ちを込めて作成しても構いません。内容は、購入希望価格、支払い方法、希望する契約日など。書いたらそのまま送るだけでなく、一報を入れておくと丁寧です。FAXやメール、郵送、持参など、どの方法でも構いません。
こうして買付証明書を通じて誠意を示すことで、売りに出ていない土地でも話が動くことがあります。相手が一般の所有者であっても、不動産会社を介していても、「この人なら安心して売れそうだ」と思わせるだけの材料になる。それだけで、あなたの手元に巡ってくるチャンスが一歩近づくのです。
工務店やハウスメーカーから未公開土地情報を得る
実は、誰にも知られていないような“穴場の土地”を見つけたいなら、不動産会社よりも先に相談すべきなのが、地元の工務店やハウスメーカーかもしれません。彼らは「建てること」が本業ですが、実は「土地の情報」も静かに抱えている存在です。
なぜなら、工務店やハウスメーカーは、家を建てる前提で土地を押さえていたり、地主とのつながりが深くて表に出ない情報を握っていたりします。分譲予定の土地を「建築条件付き」でセット販売するケースも多く、そうした情報はポータルサイトには出回りません。早ければ、造成前に話が聞けることもあるくらいです。
たとえば、「このエリアで、予算はこのくらい」と希望をざっくばらんに伝えておけば、条件に合う未公開の土地を提案してくれることがあります。場合によっては仲介手数料がかからなかったり、家づくりまで一貫してサポートしてもらえたりと、金額面でも気持ちの面でも安心できる選択肢になることがあるのです。
もちろん、「建築条件付き」に抵抗がある人もいるでしょう。でも、話を聞くだけでも構いません。土地だけ探しているというスタンスでも、きちんと対応してくれる業者はたくさんあります。売りに出ていない土地を本気で探したいなら、住宅会社の窓口にも、ぜひ一度足を運んでみてください。地味だけど確実に、情報の扉が開く瞬間があります。
とはいえ、ハウスメーカーにひとつずつ問い合わせて情報を集めるのは億劫。。できればネットで簡単に、情報を一括取得できる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
市役所や自治体の土地支援制度を利用する
「土地を買いたい」と思ったとき、真っ先に不動産サイトを開く人は多いと思います。でも、実は市役所や自治体にこそ、まだ誰も気づいていない“売りに出てない土地”のヒントが転がっていることがあります。
たとえば、京都府長岡京市では、「事業用地マッチング支援制度」という仕組みを導入していて、市民が希望する土地の条件を登録しておくと、それに合った未利用地や空き家の情報を、市が間接的に紹介してくれるんです。特徴的なのは、登録者の個人情報が不動産業者に直接渡らない点。市役所が仲介役としてそっと橋渡しをしてくれる、ちょっと珍しい制度です。
千葉県柏市では、自治体が持つ未利用地の情報をウェブサイトで公開していて、購入希望や賃貸活用の相談も受け付けています(出典:未利用地(市有地)の公開)。こうした制度は静かに運用されているため、大手ポータルサイトでは見つかりません。でも、“地元ならでは”の土地に出会えるチャンスでもあるんですよね。
正直、自治体の制度は少し分かりづらいこともあります。ただ、問い合わせればきちんと教えてくれますし、自分の希望を届けておくことで、眠っていた土地の情報がぽろっと出てくることもあるんです。「売りに出ていない土地を買う」という少し難しそうなテーマに、行政という味方をつけるのは、思った以上に心強い手段になります。
土地が不動産市場に売りに出てない主な理由
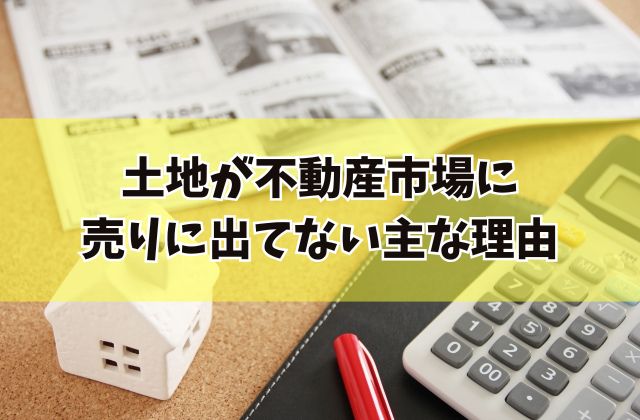
ここまで、売りに出てない土地を購入する方法を紹介してきました。
「売りに出てない土地購入」を目指すなら、そもそもなぜ市場に出回っていないのか、その背景を知ることも大切です。
土地には売れない事情があるケースもあり、理由を理解しておくと交渉や判断がしやすくなります。
ここでは、土地が不動産市場に売りに出てない主な理由をいくつか紹介していきます。
購入の可能性を見極めるための視点として、しっかり押さえておきたいところ。ぜひ参考にしてみてください。
境界が確定しておらず売れにくいから
売りに出ていない土地の中には、「売りたくても売れない」事情を抱えたものが少なくありません。その一つが、境界がまだきちんと確定していない土地。実際、測量図がないだけで、買い手がつかないケースは想像以上に多いのです(出典:参考資料)。
土地の売買には、境界が明確になっていることがほぼ必須です。もし隣地との境界線があいまいなままだと、購入後に「ここからはウチの土地ではなかった」と判明するようなトラブルにつながりかねませんし、住宅ローンも通りにくくなります。金融機関も「担保として不安がある」と判断してしまうからです(出典:筆界特定制度)。
こういった土地を相手に交渉するなら、まず確認したいのが「確定測量が済んでいるかどうか」。もし済んでいなければ、買主側が測量費を一部負担する提案をすることで、交渉が前に進むこともあります。おおよその費用感としては、土地家屋調査士に依頼して30~80万円、期間は3~4ヶ月前後が一般的とされています。
境界問題は面倒に思われがちですが、逆に言えば、ここを解消できれば「他の人が手を出しにくい土地」を狙うことができます。売りに出ていない土地を購入したい人にとって、こうした“ひと手間の交渉余地”こそが、希望の土地と出会うチャンスになるのです。
土地所有者が高齢または遠方で対応できないから
気になる土地があるのに、売りに出ていない。問い合わせ先も見つからない。その背景には、所有者がすでに高齢だったり、遠方に住んでいて管理できていない──そんな事情が隠れていることがあります。
実際、国土交通省の資料でも、空き地や放置された土地の約60%が65歳以上の高齢者世帯によって所有されているというデータが報告されています。地方に残した土地を手放したいと思っていても、登記の手続きがわからない、足腰が不自由で相談窓口に出向けない。あるいは、「売るほどの価値はないだろう」と判断され、完全に意識の外に置かれているケースも少なくありません。
一方、都心から遠く離れた場所に移住してしまったため、所有していることすら忘れかけていた──というケースもあります。とくに親から相続したまま、そのまま…という土地。買う側が動かなければ、永遠に売りに出ないまま埋もれてしまいます。
だからこそ、「売りに出てない土地購入」を本気で狙うなら、登記簿を確認して手紙で一報入れてみるという小さな行動が、大きな突破口になることもあるのです。人の手に渡るきっかけを待っているだけの土地は、実は意外なほど多い。話が動き出すのは、いつも“こちらから声をかけた瞬間”なのかもしれません。
所有者が亡くなり相続人が管理できていないから
その土地に家族がいたのは、もう何十年も前の話。今は誰が持っているのかさえ分からない──そんな土地が、街の片隅にぽつんと残っているのを見かけたことはありませんか?
実は「売りに出てない土地」の多くが、まさにこうした相続放置の状態にあるのです。所有者が亡くなったあと、登記の名義変更もされないまま、次の相続人が誰なのかすら不明なケースも少なくありません。
2023年からは「相続登記の義務化」が段階的に始まり、放置された土地の管理問題にようやくメスが入ろうとしています。また、「相続土地国庫帰属制度」のスタートにより、管理しきれない土地は国に引き取ってもらえる道もできました。
けれど、これらの制度は始まったばかりで、運用にはまだハードルがあります。つまり、いま目の前にあるその空き地は、「売りたくても売れない」「持ち主が動けず、動かせない」という事情を抱えている可能性が高いのです。
売りに出ていない=興味を持たれていない土地、とは限りません。視点を変えれば、買い手の“能動的なひと声”が、動けなかった土地に風を通すきっかけになるのです。
売りに出てない土地購入で交渉するときのコツ
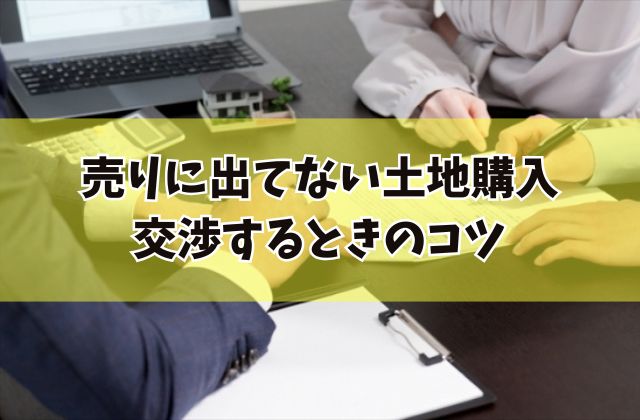
売りに出てない土地を見つけたとき、交渉の仕方次第で購入できる可能性がぐっと高まります。
たとえ市場に流通していなくても、アプローチの方法や言葉の選び方ひとつで、持ち主の心が動くことは十分にあり得ます。
「売りに出てない土地購入で交渉するときのコツ」を押さえておけば、無駄な時間や手間を減らしながら、スムーズに話を進めるきっかけがつかめます。
ここでは、その実際に活用できる交渉の工夫を紹介していきます。
複数の不動産会社に相談して情報の幅を広げる
売りに出ていない土地を探すなら、不動産会社は「一社だけ」ではもったいない。たとえばA社では紹介されなかった物件が、B社では「ちょうど条件に合う空き地がありますよ」と紹介されるケースも珍しくありません。未公開の土地情報は表に出ていないからこそ、どこでどう出会えるかは運と人脈の勝負です。
実際、未公開物件を扱っている会社は複数あり、「本気で探している」と伝えると、それに応じて情報を教えてくれる可能性も高まります。さらに、会社によって得意エリアや仕入れルートが違うため、視点の違いが土地探しの幅をぐっと広げてくれるのです。
ただし、やみくもに数だけ増やせばいいというものでもありません。3社ほどに絞っておけば、連絡の手間も減り、比較検討もしやすくなります。信頼できる担当者と出会えるかどうかも、土地選びの大切なポイントになります。
とはいえ、不動産会社にひとつずつ問い合わせて情報を集めるのは億劫。。できればネットで簡単に、情報を一括取得できる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
最初に具体的な価格を示し意思を明確に伝える
「この土地、もし○○万円なら買いたい」——そんな率直な一言が、売主との距離を一気に縮めてくれることがあります。未公開の土地を相手に交渉するなら、まずはあなたの本気度を示すことが肝心。曖昧な姿勢では、そもそも話が進みません。
たとえば、買付証明書に希望金額や希望条件を書き添えて提出すれば、「この人は本気で探しているんだな」と売主側も感じてくれます。ときには、こちらから声をかけなくても、不動産会社のほうから「売却予定の情報が入ったのでご連絡しました」と教えてくれることもあります。価格提示は、信頼のスタートラインです。
とはいえ、安すぎる金額を提示すれば、当然ながら「話にならない」と門前払いを食う可能性もあります。市場相場や類似物件の成約価格など、ある程度の相場観を持ったうえで、現実的な数字を出すようにしましょう。価格の提示は単なる金額ではなく、「この土地を本当に必要としている」というあなたの姿勢そのものを映す鏡です。
そして、土地の相場を調べるには、情報収集と比較が欠かせません。
そこでおすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
測量費負担や手数料免除を交渉材料にする
未公開の土地を購入する際、価格交渉に入る前に少しだけ知恵を使いたい場面があります。たとえば、「測量費はこちらで持ちますので、その分だけ仲介手数料を調整いただけませんか」と静かに切り出す。そんなひとことが、交渉を一気に前へ進めるきっかけになることもあります。
測量費用は売主側の負担が原則とされていますが、話し合いによっては買主が一部負担することで交渉がまとまりやすくなるケースも少なくありません(出典:不動産売買契約書)。現況測量でおよそ10~20万円。境界確定測量に進めば、費用は一気に数十万円~100万円を超えることもあります。
一方、仲介手数料は法律で「物件価格の3.3%+6万6,000円まで」と上限が定められています(出典:参考文献)。ただ、購入意欲を明確に示しつつ、将来の取引を匂わせるような関係構築ができれば、柔軟な対応をしてくれる不動産会社も実際にあります。
つまり、測量や手数料の“お金の話”をただの費用ではなく、「誠意と交渉の材料」として差し出せるかがカギです。お金を出す=損をする、という見方だけでなく、そこに信頼を添えられるかが勝負の分かれ目です。
売りに出てない土地を購入する際の8つの注意点

売りに出てない土地は、一般の不動産市場に出回っていないため、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。
しかし、その一方で見えにくいリスクも多く潜んでいます。
たとえば建築ができない土地や、権利関係が複雑な土地など、慎重な確認が必要なケースも珍しくありません。
ここでは、売りに出てない土地を購入する際の8つの注意点を紹介します。
事前に押さえておくことで、後悔しない土地選びがしやすくなります。ぜひ、土地購入の対策としてお役立てください。
再建築不可の土地に注意する
「再建築不可」と聞くと、ピンと来ないかもしれません。でも、実はこれ、不動産を買ううえでの“落とし穴”のひとつです。たとえば、「この場所、安いし便利そう」と思って手を出してしまうと、あとで「建て替えできません」と言われて青ざめる、なんてことも珍しくありません。
この問題、建築基準法が関係しています。幅4m以上の道路に2m以上接していないと、建て替え許可が出ない決まりがあるのです。とくに古い住宅地や細い路地裏に多く、見た目には気づきにくいのが厄介です(出典:参考資料)。
さらに注意したいのは、再建築不可の土地だと住宅ローンが組みにくくなること(出典:対象となる住宅・技術基準)。仮に家が老朽化や災害で壊れた場合でも、新しい家を建てられないため、資産価値が大きく下がるリスクもあります(出典:無道路地の評価)。
でも、すぐに候補から外すのは早計です。自治体で接道義務の確認をして、隣地との交渉や「セットバック」という手法で建築可能になる場合もあります。購入前にじっくり調べておくことで、“安いけど失敗”という後悔を避けることができます。
災害リスクの高い土地は避ける
いくら安くても、「なんで売りに出ていないのか?」という視点は、土地選びでとても大事です。中でも気をつけたいのが、災害リスクが潜んでいる場所。値段が魅力的だからといって飛びつくと、あとで後悔する可能性があります。
たとえば、国や自治体が出しているハザードマップを見れば、その土地が浸水想定区域にあるかどうかはすぐにわかります。近年はゲリラ豪雨や大型台風が増えていて、「昔は大丈夫だった場所」が今は危ない、なんてことも普通に起きています。
また、地盤がゆるい場所や、もともと湿地だったところ、山のふもとで土砂崩れの危険がある場所なども要注意。不動産会社が「この辺は人気です」と言っていても、災害リスクまでは触れないことが多いので、自分で調べて判断する姿勢が必要です。
災害に強い土地を選ぶのは、家を建てたあとの暮らしの安心に直結します。価格や立地の良さだけで決めず、「この場所に長く住めるか?」という目線で見てみてください。
相場より高額な土地は慎重に判断する
「ちょっと高い気がするな…」そう感じた時点で、一度冷静になるべきです。土地の価格が周辺相場を大きく上回っている場合、なぜその金額なのかを深掘りして確認しないと、あとで後悔しかねません。
不動産市場では、売り出し価格はあくまで“希望”にすぎません。実際の取引ではそこから値下げされるケースが大半で、統計によると売出価格の93%程度で成約されるのが平均的な流れです。
にもかかわらず、最初から割高な価格設定になっている場合は、売主の事情か、買い手の目を試すような戦略か、あるいはその土地に何らかの“クセ”がある可能性も考えられます。
相場を無視した価格で焦って購入するのはリスクが高すぎます。近隣の取引事例や公示地価を調べ、不動産会社に複数確認を取るなど、納得できるだけの根拠が見えてから判断するようにしましょう。
境界や権利関係があいまいな土地を避ける
「ちょっと気になる空き地を見つけた。でも、どこまでが敷地かはっきりしない」。そんな土地に出会ったときは、一度立ち止まる勇気が必要です。というのも、境界や権利の確認が曖昧なままだと、後で面倒なトラブルに巻き込まれる恐れがあるからです。
実際、土地の“線引き”には2種類あります。ひとつは法務局に登記されている「筆界」、もうひとつは現地で人が認識している「所有権界」。このふたつがズレている土地は意外と多く、「塀の向こうはうちの土地だ」と隣人から主張されるケースも珍しくありません(出典:参考資料)。
特に「売りに出ていない土地」の場合、以前からの持ち主が境界確認をしていないケースも多く、測量図がなかったり、登記簿が古かったりと、情報の不備が目立ちます。こうした土地に安易に手を出すと、引っ越した後に境界をめぐって近隣と揉めるリスクが生まれます。心地よい暮らしを思い描いていたのに、現実は話し合いと書類の山──そんな事態は避けたいものです。
対策としては、専門家に依頼して境界をはっきりさせておくことが肝心です。土地家屋調査士による測量や、隣地所有者との立ち会いによって作成される「確定測量図」があれば、境界線を明確にでき、後々の不安を取り除くことができます。
「買ってから後悔したくない」。そう感じたら、見た目の条件よりもまず“線”を疑ってみてください。境界が曖昧な土地には、必ずその裏に複雑な事情が眠っているものです。
所有者が不明で手続きが煩雑な土地を避ける
「ここ、いい場所だな」と感じても、いざ調べてみると“誰の土地か分からない”。そんなケースは少なくありません。所有者不明の土地は、見えないハードルがいくつもあります。
たとえば、相続登記が放置されていたり、所有者が亡くなっていたり。昔は登記を義務にしていなかったため、家族間で口約束のまま名義が動かず、現在の所有者がはっきりしない土地が全国に点在しています。国交省の推計(参考資料)では、そうした土地がすでに国土の約2割を超えているとも言われています。
では、買いたいと思ってもどうなるか。登記簿からたどれる相手がいなければ交渉すらできません。しかも、どうしても買いたい場合は、家庭裁判所に申立てをして「財産管理人」を選任してもらう必要があり、手続きは長期化します。費用も時間も、相応に覚悟しなければなりません。
土地選びの第一歩は、「手続きの壁がないか」を見極めることです。見た目や立地だけで飛びつくと、あとで取り返しがつかなくなるリスクがあります。所有者不明の土地には、慎重に距離を取るのが賢明です。
隣地との高低差がある土地は慎重に判断する
「土地の形よりもまず価格だろう」と思って見に行った物件。ところが、現地に立ってみた瞬間、道路との間に大きな段差があるとわかった時の違和感——それ、正解かもしれません。
土地に高低差があると、見落としがちな問題がいくつも出てきます。たとえば、がけ条例。地域によって違いはあるものの、高低差が2メートルを超えるような場合には建築制限がかかることがあり、最悪「建てたい家が建てられない」という事態になることも(参考文献:東京都建築安全条例)。
また、古い擁壁(ようへき)が残っている場合、安全基準を満たしていないと補修ややり直しが必要になり、その費用が数百万円単位になるケースも珍しくありません(出典:宅地造成等規制法の概要)。
さらに、造成や排水計画、隣地とのトラブル防止のための工事など、購入価格とは別に費用がどんどん積み上がっていくのも、見落とされがちなポイントです。
価格が安く見えても、「理由がある安さ」かもしれない。だからこそ、現地を必ず見て、自分の目で“土地の癖”を知ること。不動産業者だけでなく、建築士や地元の工務店にも相談して、第三者の視点を交えて判断する。それが、後悔のない土地選びに必要なステップです。
個人間売買で法的リスクの高い手続きを避ける
気になる空き地が見つかって、相手も「売ってもいいよ」という雰囲気。となれば、「不動産会社を通さずに直接やり取りすれば安く済むかも」と思うのは自然な流れです。ただ、土地の売買は、想像以上に「落とし穴」が多い世界です。
実際、個人同士のやり取りでは、売買契約書に不備があったり、境界や権利関係をしっかり確認しないまま手続きを進めてしまうケースが後を絶ちません(出典:参考資料)。とくに厄介なのが、土地に抵当権が残っていた場合。買ってから「銀行がまだ権利を持っていた」と発覚することもあるんです。これでは自由に使えず、手続きがストップすることも。
また、知人や親族間での売買だからといって相場より大幅に安い金額で取引すると、税務署に「これは贈与だね」と判断され、贈与税を請求されるケースもあります(出典:参考資料)。実際にあったトラブルとして、土地を100万円で譲り受けたはずが、あとで数百万円の贈与税がかかったという話も耳にします。
安く手に入れるつもりが、手続きや税務の問題で数十万円、いや数百万円の損になったら本末転倒です。もし個人間売買を進めるなら、契約書の作成や登記は司法書士へ、税金の確認は税理士へ。信頼できる専門家のサポートを部分的にでも受けながら、「安心できる取引」に変えることが重要です。
未公開だからといって必ずしも優良とは限らない
未公開物件と聞くと、「掘り出し物に出会えるかも」と胸が高鳴るかもしれません。ですが、実際には必ずしもそうとは限りません。むしろ、見えないからこそ冷静な判断が求められます。
たとえば、未公開の理由が「相場より割高だから」「事情が複雑だから」というケースも少なくありません。市場に出すと売れ残る可能性があるため、あえて内々で情報を止めていることもあります。ほかにも「売主が知人だけに売りたい」「価格を周囲に知られたくない」といった思惑が背景にある場合もあります。
とはいえ、全ての未公開物件が問題を抱えているわけではありません。中には、市場に出す前の段階で良質な土地が手に入ることもあるのです。ただしそのチャンスをものにするには、周辺の土地価格や条件をきちんと比較し、「なぜ未公開なのか」を見極める目が欠かせません。
見えないものほど、慎重に。未公開という言葉だけで飛びつかず、まずは一歩引いて冷静に。信頼できる不動産会社と一緒に、事実を積み重ねながら判断していくことが、後悔しない土地選びにつながります。
では、どうすれば理想の土地情報は見つかるのか?できれば無料で簡単に、ネットでもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
【安心】家にいながら売りに出てない土地を探せる裏ワザ

「不動産会社に聞いても“売り物ではない”と断られてしまう土地が気になって仕方ない」
「登記簿を調べたり現地で所有者を探すのは手間も時間もかかって現実的ではない」
「そもそも、どこに未公開の土地情報があるのか見当もつかず動き出せずにいる」
あなたも、上記のように悩んではいませんか?
条件に合う土地を探すのは至難の業。しかも土地は“見えないリスク”が多く、買ってから失敗に気づいても手遅れ。
でも実は、そんな悩みを解決する家にいながら売りに出てない土地を探せる裏ワザがあります!
それが、540,000人以上が利用した“複数社から一括で”土地情報をもらえる『タウンライフ家づくり』です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
【Q&A】売りに出てない土地の購入に関するよくある質問

最後に売りに出てない土地の購入に関するよくある質問をまとめました。
気になる疑問に答え、購入前に知っておくと安心できるポイントを、わかりやすく解説していきます。
非公開土地とは何ですか?
「非公開土地」と聞くと、なんだか特別な物件のように感じるかもしれません。広告に出ていないからこそ、掘り出し物のチャンスかも…と期待する方も多いでしょう。ですが、ちょっと立ち止まってください。実は“非公開”とされている理由は、必ずしも良いことばかりではありません。
例えば、売主が「近所に知られたくない」と思っていたり、「まだ本格的な売却準備が整っていない」ケースだったりします。あるいは、境界の問題や法的な手続きが未完了で、まだ売り出すには難がある物件かもしれません。
つまり、非公開だからお得、というわけではなく、「情報が出ていない=理由がある」という視点を持っておくことが大切です。非公開物件には魅力もありますが、見えない事情が隠れている可能性もある。だからこそ、情報を自分で深掘りして判断する姿勢が欠かせません。
持ち主不明の土地を買いたいときどうすればいい?
「この空き地、ちょっと気になるな」──そんな風に思って調べてみたら、持ち主が分からない。誰が所有しているのか分からない土地を、果たして買うことなんてできるの?と不安になるのも無理はありません。
でも、方法はあります。まず、法務局で登記簿を取得して、登記上の所有者を調べてみましょう。もし登記が古くて所有者が亡くなっていたり、相続が進んでいなかったりした場合でも、諦める必要はありません。2023年に本格始動した「所有者不明土地管理制度」を活用すれば、家庭裁判所に申立てを行い、管理人を選任してもらうことで、購入へと道を開けます。
もちろん、手続きには専門的な知識が必要な場面もあるので、司法書士や弁護士に相談するのが安心です。手間はかかりますが、何十年も放置されてきた土地を活用する第一歩になります。「誰のものか分からない土地は買えない」と思い込まず、制度と専門家を味方にして一歩踏み出してみてください。
売りに出ていない空き家は誰にどう交渉する?
人通りの少ない住宅街の一角に、長年放置されているような空き家。草木が伸び放題で、明らかに人の気配がない。ふと「ここを買って再生できたら面白いかも」と思ったとき、最初に立ちはだかるのが、「持ち主にどうやってアプローチするのか?」という壁です。
基本的には、法務局で登記情報を取得すれば、所有者の名前と住所が分かります。そこから、手紙や訪問などで交渉を始めることは可能です。ただし、いきなり見知らぬ相手から連絡が来れば、相手も構えてしまいます。
そんなときは、地元の不動産会社に間に入ってもらうのが現実的です。彼らは地域のネットワークを持っていて、直接コンタクトが難しいケースでも、うまく橋渡ししてくれることがあります。また、空き家バンクに登録されていないか、自治体の窓口に相談するのも手です。
「交渉=難しい」と思われがちですが、正しい段取りと信頼できる仲介者がいれば、想像よりずっと前向きに進みます。気になったその瞬間の気持ちを、ぜひ形に変えてみてください。
近所の空き地を買いたいとき最初に何をする?
ご近所にぽっかり空いた空き地があって、「あそこ買えたらいいのに…」なんて思ったことはありませんか?
まず最初にやるべきことは、所有者を正確に突き止めることです。方法としては、法務局でその土地の「登記簿謄本」を取得します。住所ではなく「地番」で調べるのがポイントで、費用は数百円ほど。所有者の名前や住所が分かるはずです。
とはいえ、個人でいきなり連絡するのはちょっとハードルが高いですよね。そんなときは、地域に強い不動産会社や自治体の空き家バンクに相談するのが安心です。実際、そういった専門家に仲介してもらうことで、話がスムーズに進むケースも多いです。まずは“所有者を知ること”、ここがすべてのスタートです。
売りに出てない空き地の持ち主はどう探す?
「ずっと空き地のままなのに、誰のものなの?」と疑問に思う土地、見かけますよね。売りに出ていないとはいえ、必ず誰かの所有物です。
まず調べるべきは、やはり法務局の登記簿。地番を調べて、そこから所有者情報を確認します。ただし、登記が古かったり、亡くなった方の名義のままというケースも珍しくありません。そんなときは相続が未了で所有者が事実上不明という状況かもしれません。
こうした場合、不動産会社や行政が運営している「空き家・空き地バンク」に情報がないか確認したり、自治体の固定資産課で調査できることもあります。表に出てこない持ち主を探す作業は地道ですが、意外と“ご近所ネットワーク”が手がかりになることもあるので、地域とのつながりも大切にしたいところです。
隣の土地は買ってはいけないって本当?
「隣の土地が空いてる。手に入れば広く使えるのに」と思ったことがある方、少なくないはず。でも、“隣地は買わない方がいい”なんて噂を耳にして、不安になることもあるかもしれません。
実はその噂、完全に間違いではありません。たとえば、道路に接していない土地は「再建築不可」とされる場合があり、建物を建てられないケースも。その土地が袋小路にある、幅員が狭いなど、法的制限があると、希望どおり使えないことがあるんです。
さらに注意したいのは、隣人との関係。過去にトラブルがあったり、境界が不明確なままだと、購入後に思わぬ問題が発生することも。とはいえ、リスクをしっかり調べて納得したうえで進めるなら、理想の住まいづくりの第一歩になる可能性も十分あります。「隣だからこそ」慎重に。これが答えです。
まとめ:売りに出てない土地を購入する方法と購入時の注意点
売りに出てない土地を購入する方法と購入時の注意点に関する情報をまとめてきました。
改めて、売りに出てない土地を購入する方法をまとめると、
- 不動産会社に未公開土地の相談をする
- 法務局で登記簿を取得して所有者を調べる
- 買付証明書を作って所有者に交渉の意思を示す
- 工務店やハウスメーカーから未公開土地情報を得る
- 市役所や自治体の土地支援制度を利用する
そして、売りに出てない土地を購入する際に知っておくべきポイントもまとめると、
- 不動産会社や工務店から非公開の土地情報を積極的に集めることが重要
- 法務局で登記簿を取得すれば、所有者に直接アプローチする手がかりが得られる
- 買付証明書を使い、購入意思を明確に伝えることで交渉が進みやすくなる
- 個人間売買には法的リスクが多く、契約手続きは専門家を介して慎重に行う
- 未公開だからといって必ずしも優良物件とは限らず、冷静な見極めが必要
売りに出てない土地の購入には、通常の不動産取引では得られない情報収集力と判断力が求められます。
「売りに出てない土地購入」を調べている方にとって、交渉方法や注意点を把握することが、理想の土地を手に入れる近道です。