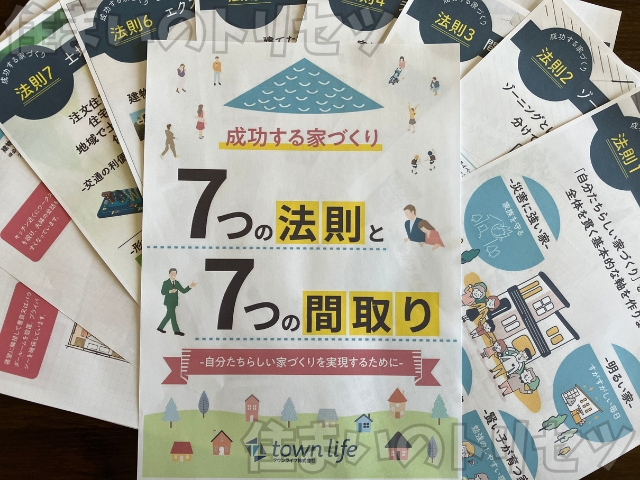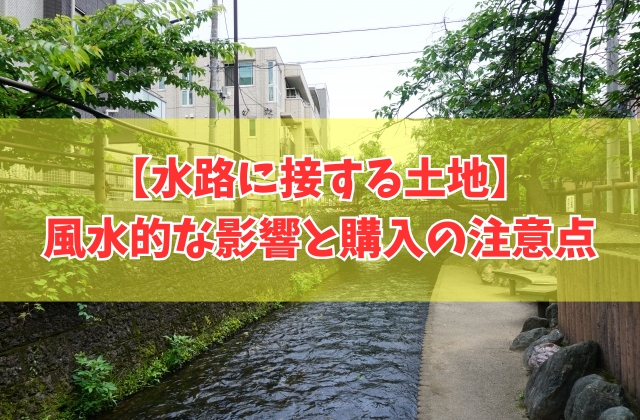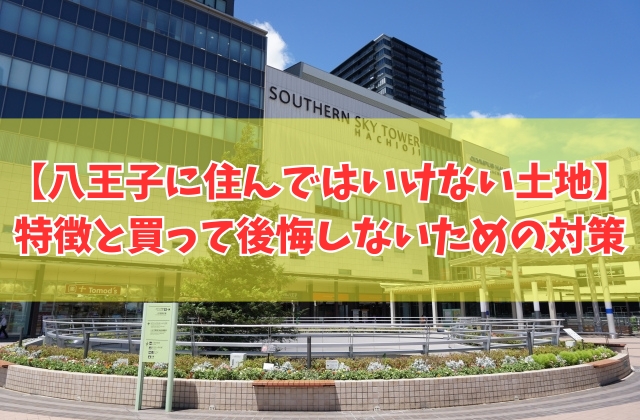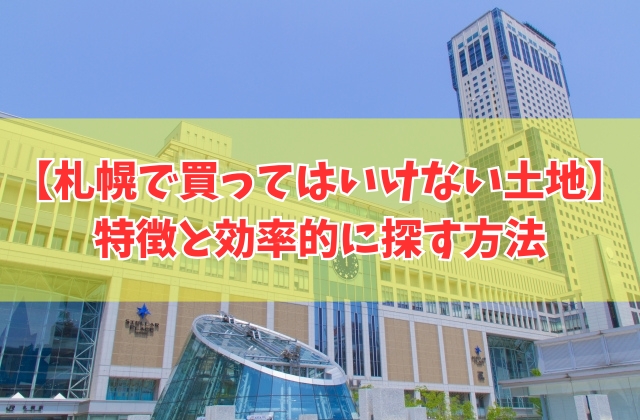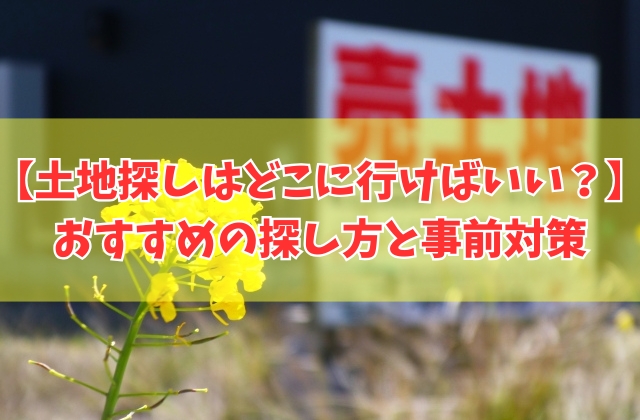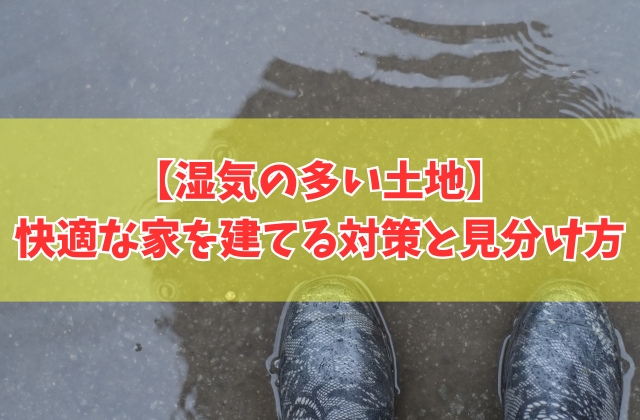
「湿気の多い土地に家を建てる際の対策は?」
「湿気の多い土地の見分け方は?無料で対策できる方法はないの?」
家を建てるなら、家族が安心して長く暮らせる住まいにしたい──そう思う方がほとんどでしょう。
しかし、土地選びの段階で「湿気が多そう…」と不安に感じる場面もあるのではないでしょうか。
特に低地や日当たりの悪い場所では、湿気が住環境に悪影響を与える可能性があります。カビやシロアリ、さらには建物の劣化につながることもあるため、見過ごせません。
そんな不安を解消するために大切なのが、事前にしっかりとした「湿気の多い土地でも快適な家を建てるための対策」を知っておくことです。
この記事では、快適で長持ちする家を実現するための具体的な対策をわかりやすくご紹介します。
- 湿気が多い土地でも正しい対策を行えば快適な家づくりは可能
- 通気・排水・防湿の工夫が家の寿命と資産価値を守る鍵になる
- プロの知見を活用することで土地選びと家づくりの失敗を防げる
湿気の多い土地対策を理解し実践すれば、安心して快適な暮らしを叶えることができます。
事前調査や専門家の力を借りながら、湿気に強い住まいをしっかり計画しましょう。通気性や排水性を意識した設計や素材選びが、長く安心して暮らせる家づくりの要になります。
とはいえ、素人にはどんな土地が良いのか?どうやって選べばいいのか?分からないのが本音。
正直、条件に合う土地を探すのは至難の業。しかも土地は“見えないリスク”が多く、買ってから失敗に気づいても手遅れ。
でも実は、そんな悩みを解決する希望に合った土地情報を無料で効率よく集める対策があります!
それが、540,000人以上が利用した“複数社から一括で”土地情報をもらえる『タウンライフ家づくり』です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
【先に結論】湿気の多い土地に家は建てられる?
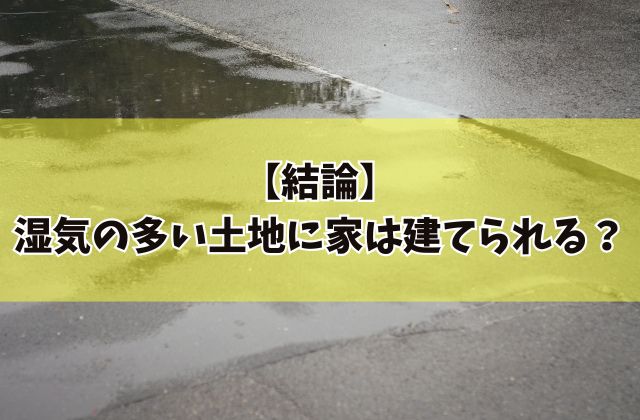
結論から言ってしまえば、湿気が多い土地でも家は問題なく建てることが可能です。ただし、「そのまま建てていい」という話ではありません。ちゃんと対策をしてあれば、という前提がつきます。
たとえば、床下の湿気対策。これは本当に基本でありながら、家の寿命に関わるほど大切です。今どきの家づくりでは「ベタ基礎」という工法が主流になっていて、地面全体をコンクリートで覆ってしまいます。そうすることで、地面からの湿気をしっかり遮断できるんです。
さらに、防湿シートと呼ばれる0.1mm以上の厚さを持つシートを敷き込むことで、さらに湿気をブロック。この方法は、国土交通省の評価方法基準でも示されています。
でも、床下だけでは終わりません。実は壁の中も湿気がこもりやすい場所なんです。そこで「通気層」といって、壁の中に空気が流れる空間をつくります(出典:長持ち住宅ガイドライン)。これにより、もし壁の中に湿気が入り込んだとしても、風で抜けていく仕組みになっているんですね。あわせて、雨は通さず湿気だけ逃がす“透湿防水シート”を使うのも、もはや定番です。
そして、見落とされがちなのが敷地全体の排水計画。湿気の多い土地というのは、つまり水がたまりやすい土地とも言えます。そこで、敷地の表面にほんのわずかな傾斜をつけたり、地中に排水管を通したりして、雨が降っても家の周りに水がとどまらないようにすることが大切です(出典:参考資料)。これ、専門家に任せるべきポイントですが、施主側も知っておくと打ち合わせがスムーズになります。
もちろん、完璧な対策なんてありません。でも、ベタ基礎+通気層+排水計画の3点をしっかり押さえておけば、「湿気のせいで家がカビだらけ」「床下がジメジメして白蟻が…」なんてことはまず起きません。
「この土地、湿気が多いからやめた方がいいかな」と悩む気持ちはわかります。でも、その悩み、実は“建て方”で解決できることが多いんです。
湿気の多い土地でも快適な家を建てるための対策7選

湿気の多い土地に家を建てる場合は、湿気がこもらない設計や設備選びがとても重要です。
放っておくと、カビや腐食、結露による健康被害につながることもあります。
そこで「湿気の多い土地でも快適な家を建てるための対策7選」を厳選してまとめました。
土地環境に合った構造や建材、換気の工夫など、家づくりを成功させるための基本ポイントをわかりやすく紹介します。
快適な暮らしを実現するために、対策の内容をしっかり確認しましょう。
土地探しの段階で水位や周辺環境を専門家とチェックする
湿気が多い土地に家を建てるとき、一番初めに注意すべきなのは「その土地自体、本当に暮らしやすい環境か?」という視点です。見た目が良さそうでも、地盤がゆるかったり、水はけが悪い場所では、暮らし始めてからジメジメに悩まされることも少なくありません。
実際、川の近くや昔水田だった場所などは、地面の中に水分がたまりやすく、湿気や水害のリスクも高まります。特に、国土交通省や自治体が出しているハザードマップでは、浸水の恐れがある地域が明記されていて、地域によっては最大で3m以上の浸水が想定されているところもあるんです(出典:参考資料)。
たとえば、埋立地や低地に家を建てる場合、床を高く設計したり、排水経路をしっかり確保したりすることで、被害を避けられた事例もあります。実際にそうした工夫を取り入れて、快適に暮らしているご家庭もたくさんあります。
こうした背景から、土地探しの段階で建築士や地盤の専門家に相談しながら、「地盤の強さ」「水のたまりやすさ」「周辺の地形」などを細かく見ておくことが大切です。ハザードマップを確認するだけでなく、現地に足を運び、雨上がりにぬかるんでいないか、排水溝の位置はどうかなど、自分の目でもチェックしておきたいところです。
あとになって「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、家を建てる前の“土地選び”こそ、最も重要な湿気対策の一つなのだと、意識して進めていきましょう。
雨水や地下水の流れを整える排水・暗渠処理を行う
湿気が多く、水はけが悪い土地に家を建てると、室内がなんとなくジメジメしたり、カビが出やすくなったりと、住み始めてから困る場面が出てきます。
そうならないために、建築前にやっておきたいのが「排水計画」の見直しです。特に、地下に水がたまりやすい場所では、暗渠(あんきょ)と呼ばれる水抜き管を設置して、地中の水の通り道をきちんと整えることが大切です(出典:参考資料)。
暗渠というのは、雨や地下水を地中で集めて、決まった排水ルートへ流す仕組みのこと。見えないところで働いてくれる“水はけの道筋”のような存在です。
実際、埼玉県のある住宅では、裏山から水が染み出す土地に建てられていたため、床下に湿気がこもり、住人が悩んでいました。そこで、砕石を敷いて水はけをよくしつつ、暗渠管を埋設して水の流れをコントロールしたところ、湿気がぐっと減り、カビの発生も抑えられたという報告があります。
このように、湿気の影響を減らすには、ただ土地を選ぶだけでなく、「水がどこから来て、どこへ逃げていくか」をあらかじめ想定しておくことが重要です。家づくりの最初のステップとして、信頼できる施工会社や地盤の専門家に相談し、排水のプランをしっかり立てましょう。
建てた後に「もっと考えておけばよかった」と後悔しないためにも、目に見えない“水の動き”こそ、慎重に向き合っておきたいポイントです。
床下に風が抜けるように高基礎を採用する
湿気が多くて地盤が水を含みやすい土地に家を建てるなら、「床下に風が通る設計」は最初から検討しておきたい基本中の基本です。中でも高基礎構造は、地面との距離をしっかり取ることで、床下に湿気がこもりにくくなります。
特に日本のように梅雨があり、夏の湿度が高くなる気候では、家の下に空気の通り道をつくるだけで、住み心地がぐっと変わります(出典:住宅の省エネルギー 設計と施工 2023)。逆に風通しが悪い床下だと、木材が常に湿った状態になり、知らぬ間にカビやシロアリの温床になってしまうことも少なくありません。
たとえば、床下に十分な高さを確保し、通気口や換気設備を設けた住宅では、梅雨時でも床下の湿度が60%台に抑えられたという記録があります(出典:参考文献)。これは通常の基礎構造よりも10~15%ほど低い値で、長期的に見ても家の寿命に大きく影響する差です。
「基礎を高くするだけで、そんなに違うの?」と思うかもしれませんが、実際に施工された住宅では、ジメジメが解消されただけでなく、室内全体の空気もカラッと快適になったという声が多く上がっています。
もし家を建てる予定の土地が、少しでも湿気が気になる場所なら──。高基礎の採用を、オプションではなく“前提”として考えてみてください。設計士や工務店と相談すれば、基礎の高さや換気口の配置、さらには基礎パッキンなどの組み合わせで、風の通り道を最大限に活かすプランを提案してくれるはずです。
数十年住み続ける家だからこそ、目に見えない部分への配慮が、暮らしやすさを大きく左右します。地面からの湿気に悩まない、そんな未来をつくるために、床下の風通しを侮らないでください。
窓や換気口を工夫して屋内に風の通り道をつくる
湿気の多い土地で家を建てるとき、見落としがちだけど意外と大切なのが「風の通り道」をどう確保するかという点です。窓や換気口の位置をちょっと工夫するだけで、家全体の空気の流れが大きく変わり、室内に湿気がこもりにくくなります。
実際、YKK APが紹介している事例では、南北に対面する窓を配置するだけで、自然換気の回数が1時間あたり約10倍(1.7回 → 16.6回)に増加するという結果が出ています。これは、対角に風の入口と出口があることで、空気が家の中をスムーズに抜けていくからです。
例えば、南側の大きな窓から風を取り入れ、北側の小さな窓や高い位置の換気口から風を抜くようにすると、特に梅雨や夏の湿度が高い時期でも、空気がよどまずカラッとした空間を保てます。風がしっかり抜けるだけで、結露やカビの心配がぐっと減るのは大きなメリットです(出典:参考文献)。
設計の段階で「風はどう流れるか?」という視点を持つだけで、湿気対策は大きく変わります。窓のサイズや位置、換気口の高さや配置に少し気を配ることで、何年経っても気持ちのいい家にできます。特に湿気が気になるエリアでの家づくりでは、この通風設計が「後悔しない家づくり」のカギになるはずです。
防湿シートやコンクリートで地面からの湿気を遮る
湿気が多い土地に家を建てるなら、まず意識したいのが「地面から上がってくる湿気」への対策です。床下の湿気がたまると、ジメジメとした空気が室内にまで届いてしまい、カビやシロアリの温床になることも。そこで役に立つのが、防湿シートやコンクリートによる湿気の遮断です。
実際、多くの施工現場では、基礎工事の段階で防湿シートを地面に敷き、その上からコンクリートを打つ「防湿土間コンクリート」という方法が取り入れられています(出典:住宅外皮重要ポイントチェックリスト)。
これは、シートが湿気を跳ね返し、コンクリートがそれを押さえる、という二重構えのような仕組み。ある現場ではこの方法を取り入れたことで、床下の湿度がぐっと安定し、結果としてカビの発生が抑えられたという報告もありました。
さらに古い民家のリノベーションであっても、防湿シートとコンクリートの組み合わせによって、湿気とともにシロアリ被害のリスクも減らせたという声が上がっています。
家づくりの初期段階で、地盤調査とあわせて湿気対策の有無を施工会社に確認するのが理想です。そして設計時には「うちは湿気の多い土地だから、防湿シートを入れてもらいたい」と、きちんと希望を伝えておくことが大切です。たったそれだけで、住まいの快適さが長持ちする。そんな小さな工夫が、のちの暮らしやすさを左右してくれます。
しかし、どれだけ湿気対策をしても、シロアリへの不安は完全には拭えません。特に床下が湿りがちな環境では、目に見えないリスクが潜んでいるかもしれません。
そこで検討したいのが信頼できる専門サービスの活用です。たとえば『タウンライフのシロアリ対策』なら、複数の優良業者から無料で見積もりが取れ、自宅に合った最適な対策がわかります。
「湿気の多い土地でも安心して暮らしたい」と考えるなら、今すぐチェックしておいて損はありません。将来の安心を手に入れるために、今の一歩がとても大切です。
調湿建材を活用して室内の湿度を自然に整える
「なんとなく空気が重い」「押し入れの中がいつもジメジメしてる」──湿気の多い地域に住んでいると、そんな悩みがつきものです。除湿機を動かす手もありますが、できることなら住まいそのものに湿度を調整する力があれば理想的。そこで注目したいのが“調湿建材”という選択肢です(出典:住宅の省エネルギー設計と施工2023)。
この建材、実はかなり賢くて、空気中の湿気が多いときには水分を吸い取り、乾燥すると少しずつ放出するという性質があります。まるで空気と会話するかのように、自然な状態を保とうとしてくれるんです。例えば、昔から親しまれてきた珪藻土や漆喰の壁材。これらには優れた調湿効果があり、室内のムレ感を和らげてくれます。
さらに、最近では「さらりあ~と」などの高機能パネルも登場しており、デザイン性と性能を兼ね備えた製品も増えてきました。データによると、こうした調湿建材を取り入れた空間では、室内湿度が40~60%程度に収まるケースが多いとされており、これはカビやダニの繁殖を防ぐうえでも理想的な数値です。
導入は意外と手軽で、壁全面ではなく、一部の部屋や収納スペースだけに取り入れるという方法もあります。施工の際には、どの素材をどの場所に使うか、建築士や工務店としっかり相談すると失敗がありません。カタログだけではわかりにくい吸放湿量や効果の持続性も、事前にチェックしておくと安心です。
「湿気は我慢するもの」なんて思っていませんか? 家そのものが湿度と付き合えるようになれば、日々の暮らしが見違えるようにラクになりますよ。自然の力を味方に、ムレない、カビない、心地よい空間をつくってみてください。
除湿器や床下換気扇などでこもった湿気をしっかり除く
湿気の多い土地に家を建てるなら、忘れてはいけないのが「湿気の逃げ道」をどうつくるかということ。特に床下や部屋の隅など、空気がよどむ場所に湿気はたまりやすく、放置するとカビやシロアリ、さらには木材の劣化などにつながってしまいます。
こうした悩みを未然に防ぐには、除湿器や床下換気扇をうまく活用することが効果的です。
例えば、床下換気扇を設置して、湿気がこもりやすい北側や水回りの下に風の通り道を作った住宅では、「梅雨でも床下がさらっと保てている」と実際に住んでいる方の声もあります。また、室内で使う除湿器に関しても、湿度が60%を超えるような日には効果を感じやすく、ジメジメ感の軽減に役立っています(出典:参考資料)。
そもそも日本の家屋は、昔から通風を大切にしてきました。けれど、近年の高気密・高断熱の家では湿気が逃げにくくなっているのも事実。だからこそ、機械の力を上手に借りて空気を動かす工夫が必要になってくるわけです。
これから家づくりを始める方は、建築士に「湿気対策として換気扇の設置は可能か」相談してみることをおすすめします。後からの工事よりも初期設計の段階で取り入れた方が効率的で、費用も抑えやすいからです。さらに、完成後も湿度計を設置して、空気の状態を日々チェックしていく習慣を持てば、家全体の快適さを維持しやすくなります。
家は、建てたら終わりではありません。湿気に悩まされない暮らしのために、こうした小さな工夫の積み重ねこそが、将来の安心につながっていくのです。
家づくり計画に欠かせない湿気の多い土地の5つの見分け方
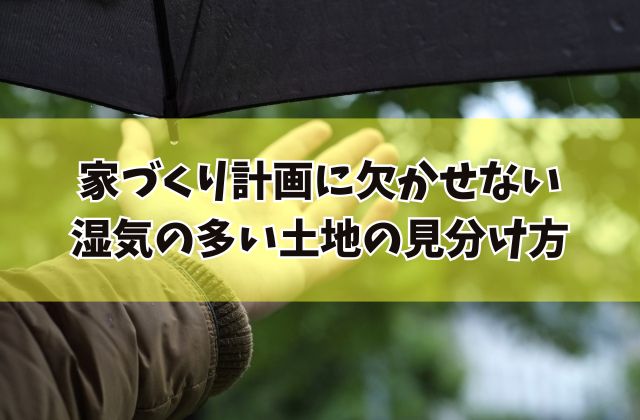
家づくりを進めるうえで、建てる土地が湿気の多い環境かどうかを見極めることは非常に重要です。
湿度の高い場所に家を建てると、室内の快適さや建物の耐久性に影響を与える可能性があるため、事前の確認が欠かせません。
そこで、家づくり計画に欠かせない湿気の多い土地の5つの見分け方について、具体的なチェックポイントをご紹介します。
「田」「沢」「谷」など水を連想させる地名が付く土地
「地名って、そこまで気にしないかも」──土地探しでそう思っている方は、少なくないかもしれません。ですが、意外なところにヒントが隠れているのが、家づくりの奥深さです。
たとえば「○○田」「○○沢」「○○谷」。そんな名前を見かけたら、ほんの少し注意を向けてみてください。こうした地名の多くは、昔そこが水田だったり、沢が流れていたり、谷地だったことを示している場合があります(出典:参考文献)。土地の性質は、見た目が整っていても、地中に長年の記憶を残していることがあるのです。
もちろん、すべてが湿気に悩まされる土地というわけではありません。でも、住宅街を歩いていて、基礎のあたりに黒ずみがあったり、庭の土がいつまでも乾かない家が多かったりするなら、何かしら共通点があるのかもしれません。
地名の由来は、地図や市区町村のWebサイトで簡単に調べられます。「沼」や「池」「潟」など水にまつわる漢字が入っていたら、一度その意味を知っておくと安心です。
土地の履歴書は、名前のなかにそっと綴られています。見えないリスクを減らすには、見過ごされがちな小さな手がかりに目を向けることが、なによりの対策になるのかもしれません。
かつて田んぼや湿地であった履歴のある土地
土地選びの段階で見落としがちなのが、「その場所がどんな地歴を持っているか」という視点です。特に注意したいのが、昔、田んぼや湿地として使われていた場所。これは想像以上に、湿気との戦いを強いられる土地だったりします。
たとえば、購入した土地が実は水田の埋め立て地だったと後で知った、というケース。こういった土地は、見た目には問題がなくても、地中に水分が多く含まれていることがよくあります(出典:被災宅地復旧の手引き)。
その結果、床下に湿気がこもりやすく、カビが発生したり、構造材が傷むスピードが早まったりするリスクが出てくるのです。
実際、調査によれば、かつて湿地帯だった場所では地下水位が高く、水はけが悪い傾向があります。地盤もやわらかく、住宅の沈下や傾きの原因になることも。だからこそ、土地が少し安めに感じたときは、一度立ち止まって「なぜ安いのか」を疑ってみることが重要です。
見極めのヒントとしては、「田」「沼」「沢」「谷」といった水にまつわる漢字が地名に含まれていないかを確認してみてください。もちろんそれだけでは判断できませんが、過去の利用状況を調べるきっかけになります。
もしどうしても気になる土地であれば、購入前に地盤調査を依頼し、防湿シートや床下換気設備の設置、高基礎設計などをあらかじめ検討しておくことで、長く快適に暮らせる家づくりが実現できます。
家は一生ものの買い物です。だからこそ、「目に見えない過去」が、暮らしの安心を左右することを、ぜひ覚えておいてください。
隣地や道路よりも明らかに低い位置の土地
家を建てる前に見逃してはいけないのが、土地の高さです。もしも購入を検討している土地が、隣の家や前の道路よりも明らかに低い場所にあるなら、注意が必要です。なぜなら、そういった土地は雨が降ったときに水が流れ込んできやすく、地面に湿気がたまりやすいからです(出典:住宅・まちづくりにおける水害リスクの考慮と実例)。
たとえば、実際にあった相談で「隣の土地より低くて、雨が降るたびに水が敷地に流れ込む」といった声があります。実際、国交省の「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」でも、そのまま家を建ててしまうと、床下の湿気が抜けにくくなり、シロアリやカビの原因になることも。特に、湿度の高い地域ではこのリスクがさらに高まります。
こうした場所に家を建てる場合は、土地をかさ上げしたり、高基礎にしたりといった対策を初めから考えておくと安心です。また、敷地の周りに排水溝や雨水を流す設計を取り入れると、湿気がこもりにくくなります。少しの勾配をつけるだけでも、水はけの効果は大きく変わってきます。
湿気の多い土地対策をしっかり行えば、たとえ土地が低くても快適に暮らせる家はつくれます。ただし、購入前に現地を必ず見て、雨のあとに水たまりが残っていないか、自分の目で確認することがとても大切です。
雨が降った後に水たまりが長く残る土地
家を建てる土地を見に行くなら、できれば「雨の翌日」を選んでください。少し面倒に思えるかもしれませんが、そのひと手間が、後々の湿気トラブルを避ける大きな判断材料になります。
というのも、雨上がりに地面に水たまりが残っている土地は、水はけが悪いサインです。水たまりが乾くまでに時間がかかるということは、地中の水分が抜けにくく、湿気がこもりやすい地質の可能性が高いのです(出典:参考資料)。
実際、外構や地盤の専門家たちも「排水性を見極めるには、晴れの日より雨上がりのほうが良い」とよく口にします。
ある住宅情報サイトでは「雨の翌日、庭に入れないほど水たまりが残っていた」という相談がありました。その家庭では、床下に湿気がたまり、カビが出てきてから対策に追われたとのこと。
こうしたトラブルを防ぐには、候補地の周囲と比べて明らかに低い場所や、地面がいつまでも濡れている場所は要注意です。どうしてもその土地を選びたい場合は、排水を改善する暗渠(あんきょ)工事や、床下の湿気を防ぐ防湿シート、高基礎などの対策を建築計画に盛り込むのが現実的な方法です。
見えにくい湿気ほど、暮らし心地を左右します。土地探しでは「価格」「駅距離」だけでなく、「雨が降ったあとの顔」もチェックしてみてください。その視点が、快適な住まいづくりの土台になります。
日当たりが悪く日影が多く風通しに欠ける土地
住宅を建てる際に、見落とされがちな「湿気のたまりやすさ」。じつは、日差しがほとんど入らず風が通りにくい土地ほど、この湿気が家全体にじわじわと影響してきます。
というのも、太陽の光や風は、自然の“乾燥機”のような役割を果たします。ところが、建物が密集していたり、高い塀や木々に囲まれていたりすると、敷地が一日中じっとりしたままになることも。これは、家の中の空気だけでなく、床下や壁の内部までジメジメが染み込んでいく原因になります(出典:省エネと結露)。
ある外構業者の事例では、「北側の敷地で常に日陰、風も抜けないため床下が常に湿っている」という報告も。風が通らず、陽も当たらない。そんな環境では、いくら見た目の設計にこだわっても、住んでからの快適さは大きく損なわれてしまいます。
では、どうすれば良いのか。
土地選びの時点で、「午前中だけでも日差しが入るか」「風の抜け道があるか」はぜひ確認しておきたいポイントです。仮に条件が厳しい場所であっても、建物の配置を工夫したり、窓の数や高さを調整することで、風通しを改善する余地はあります。
また、風が通らない分を機械的に補う方法として、床下換気扇や除湿装置を導入する選択肢も。内装材に調湿性能のあるものを使うのも有効です。
日当たりや風通しは、「見えない快適さ」を決める大切な要素。デザインや立地だけで判断せず、湿気とどう向き合うかまで考えてみてください。それが、長く心地よく暮らせる家づくりにつながります。
湿気の多い土地だけでなく住んではいけない土地の特徴とは

家づくりを検討する際には「湿気の多い土地の対策」だけでなく、建築そのものに向かない土地の特徴も事前に知っておくことが大切です。
安全性や快適性に深く関わる条件が隠れているケースもあるため、慎重な見極めが欠かせません。
ここでは、住まいを建てるうえで避けるべき「住んではいけない土地の特徴」を5つ紹介します。
家づくり計画を始める前の判断材料としてお役立てください。
地盤が軟弱な埋立地や盛土された土地
家を建てるうえで“土地選び”はすべての土台になりますが、とくに気をつけたいのが「埋立地」や「盛土」された土地です。湿気がこもりやすいだけでなく、家そのものの安全性にもかかわってくるため、軽視できません。
たとえば、昔は沼や池だった場所を埋め立ててつくられた住宅地。いまではすっかり街並みが整っているように見えても、実際には地中に締まりきらない柔らかい土が残っているケースがあります(出典:治水地形分類図 利用の手引)。専門家によれば、こうした土地は地盤が不均一になりやすく、雨水や地下水がたまりやすいとのことです。
実際に、埋立地に建てられた住宅で「家が傾いてきた」と相談が寄せられたケースもあるそうです。原因を調査すると、地中の水分と軟弱地盤による不同沈下でした(出典:参考資料)。見た目にはわかりませんが、湿気の影響が地盤全体を緩めていたことがわかったのです。
こうしたリスクを避けるためには、まずその土地の過去の使われ方や造成の履歴を調べてみてください。市役所で地歴図を確認したり、不動産会社に問い合わせたりするだけでも手がかりはつかめます。また、気になる土地が見つかったら、購入前に「地盤調査」を依頼するのも大切なステップです。
もし「どうしてもその場所に家を建てたい」という場合でも、まったく建てられないわけではありません。防湿シートの敷設、排水設備の強化、高基礎構造の導入、地盤改良工事など、湿気と軟弱地盤に備えるための対策はしっかりあります。
土地の表面だけで判断せず、“地面の中の事情”にも目を向けてみてください。見えない部分にこそ、本当のリスクと、暮らしやすさのカギが隠れています。
洪水や内水の危険がある低地の土地
家を建てる場所を選ぶとき、意外と見落とされがちなのが「低地」のリスクです。湿気の多い土地対策を考える前に、そもそもその土地が水害の危険にさらされやすい環境ではないか、一度立ち止まって確かめることを強くおすすめします。
たとえば、川沿いや海に近いエリア、または地形的に周囲より少し低い土地では、大雨のたびに地表水が滞りやすくなります。国土地理院の資料によれば、こうした地域では内水氾濫──つまり、河川があふれなくても排水設備が追いつかずに水があふれる被害は発生しやすいことが報告されています。
実際、近年の都市型豪雨では、河川から離れた住宅街でも床上浸水が相次いでいます。
一度でも水が入り込むと、地面や基礎の中に湿気がこもりやすくなります。乾くまでに時間がかかり、床下の木材が傷むだけでなく、室内にもジメジメした空気が残ってしまうケースもあります。湿気が抜けにくい低地では、排水計画と湿気対策をセットで考えることが欠かせません。
もし気になる土地が低地に含まれている場合は、まず自治体が公表しているハザードマップを確認してください。そのうえで、敷地を少し高く造成したり、排水経路を設計に組み込んだりすることで、被害を大きく減らせます。家の基礎を高くする「高基礎設計」も効果的です。
「湿気の多い土地の対策」というと床下や建材の工夫に目が行きがちですが、実は土地そのものの性質を理解することが第一歩です。地盤が強くても、水が逃げない場所では快適な暮らしは難しくなります。安全で乾いた土地を選ぶ──それが何よりも大切な湿気対策なのです。
急な崖地や土砂災害警戒区域にある土地
家を建てる土地として、急な崖地や土砂災害警戒区域に指定されている場所は、避けたほうが無難です。こうした土地では、湿気への対策以前に、命を守るための備えが必要になるからです。
崖の近くや斜面地では、地盤が不安定なケースが多く、特に大雨の際は土砂崩れや地滑りのリスクが高まります。実際、国や自治体は「土砂災害警戒区域」や「特別警戒区域」として、全国で約60万か所以上を指定しており、これらの地域では建築の制限が課される場合もあります(警戒区域(イエロー)706,273区域、特別警戒区域(レッド)607,422区域。出典:参考データ)。
参考までに、鳥取県の公開資料でも、区域指定の進捗や建築上の注意点が示されています。
具体的には、ある地域では、崖の上に家を建てた結果、連日の雨で地盤が緩み、背後から大量の土砂が流れ込むという被害が起きました。こうした事例は珍しくなく、年々その数も増えています。
もちろん「湿気の多い土地 対策」として換気や防湿施工をしても、地盤そのものが不安定だと、建物へのダメージは避けられません。土地選びの段階で、まずはその場所が土砂災害リスクのある区域かどうかを、ハザードマップや市町村の窓口でしっかり確認しておくことが重要です。
安全な場所に家を建てるという視点が、結果として湿気対策にもつながり、長く快適に暮らせる住まいになります。
水はけが悪く雨が降るとぬかるみやすい土地
雨のたびに庭がぬかるんで靴が泥だらけ、そんな状況を想像すると、暮らしのストレスが増えるのは明らかです。実はこうした土地、湿気の悩みだけでなく、家の構造そのものに悪影響を及ぼすことが少なくありません。
地面に雨水がたまりやすい場所では、地盤が常に湿った状態になりやすく、住宅の土台にじわじわと湿気がしみ込みます。これは放置しておくと、基礎部分のコンクリートが劣化したり、床下の木材が腐ったりする原因になり得るのです。国土地理院の報告によると、水はけの悪い立地では地盤沈下や湿気による劣化が発生しやすいとされています。
実際、ある相談事例では「土地が隣より低く、雨が降るたびに庭に水が溜まり、苔がびっしり生える」といった声が上がっていました(出典:住まいの相談事例データベース。見逃しがちなこうしたサインも、住宅にとっては重要な危険信号です。
では、どう対応すればいいのでしょうか。土地選びの段階で、晴れた日だけでなく雨の翌日にも現地を見に行くこと。水たまりの様子や土の乾き具合を目で確かめておくのが有効です。もし水はけが気になるようなら、建築時に地盤改良や排水管の設置、高基礎構造の採用などを検討しましょう。特に透水性の高い砂利やコンクリート舗装を使うだけでも、地面の湿気は大きく変わります。
「多少ぬかるむ程度なら大丈夫」と見過ごすと、将来のトラブルが一気に押し寄せてきます。湿気の多い土地は工夫次第で快適な住まいに変えられますが、その第一歩は、土地の“素の表情”に目を向けることから始まります。
騒音や悪臭など生活環境が悪い土地
「どれだけ素敵な家を建てても、周囲の環境が悪ければ台無しです」──これは、多くの家づくり経験者が口を揃えて言うことです。とくに注意したいのが、騒音や悪臭が気になる土地。見た目だけでは判断しにくいぶん、あとで「失敗だった…」と感じやすいポイントです。
たとえば、幹線道路のすぐそばや大きな工場の近く。昼間は静かでも、夜になると大型トラックが何台も通ったり、換気扇からの排気が風に乗って臭ってきたりします。実際に「騒音と臭いで窓が開けられない」といった声もありますし、生活の質がじわじわと下がってしまいます。
特に住宅密集地や都市部では、道路沿いや処理施設の近くなど、意外とこうした問題が潜んでいることも。資産価値にも関わるため、注意が必要です。土地選びの段階で「昼」「夜」「平日」「休日」と時間を分けて現地に足を運び、五感でチェックしてみてください。
湿気対策だけに気を取られていると、こうした見えないストレス要因を見逃しがちになります。せっかくのマイホーム、安心して心地よく暮らすためには、“音”と“におい”にもぜひ敏感になってください。
湿気の多い土地に家を建ててしまった場合の想定されるリスク
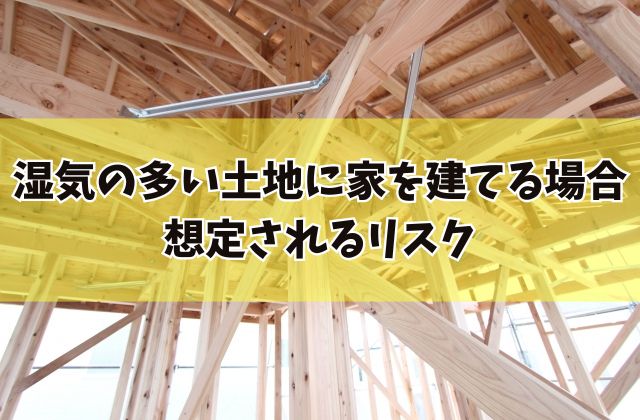
家づくりを進める中で見落としがちなのが、“湿気”による住環境への影響です。
想定されるリスクとしては、健康被害や構造の劣化、さらには資産価値の低下など深刻な問題が挙げられます。
安心して暮らすためにも、どのようなトラブルが起こり得るのかを具体的に知っておくことが大切です。
ここでは、その代表的な湿気の多い土地に家を建ててしまった場合の想定されるリスクについて詳しく紹介します。
カビやダニが繁殖して健康被害につながる
梅雨どきになると、押し入れや家具の裏からなんとも言えないにおいが漂う…。そんな経験、ありませんか? 実はその「におい」、カビが発生しているサインかもしれません。そして、そのカビを好んで集まってくるのが、ダニです。
湿気の多い土地に家を建てると、空気の逃げ場が少ない床下や壁の中に湿気がこもりやすくなります。一般的に、湿度が60%を超えるとカビの繁殖が始まり、75%を超えると一気に増えると言われています。そこにダニが加わると、アレルギーや喘息、肌のトラブルといった健康被害が現れることも少なくありません(出典:参考資料)。
実際、国土交通省の調査報告でも、住宅内のカビやダニが小児喘息の発症と関係しているというデータが公表されています。とくに小さな子どもがいる家庭では、空気の「質」は見えないけれど大きな問題です。
こうした被害を防ぐには、単に除湿器を置くだけでは不十分です。建築段階で、床下に湿気がたまらない構造をつくる、高基礎にする、防湿シートを敷くなど、湿気と向き合う備えが欠かせません。家を快適に保つためには、風通しや日当たりだけでなく、「湿気の流れ」まで読み込んだ計画が必要なのです。
湿気が原因でシロアリなどの害虫被害が起きやすい
湿気の多い土地に家を建てるとき、気をつけたいのが「シロアリの被害」です。実は、シロアリが活発になる条件のひとつが“湿気”。特に床下の湿度が高くなると、木材がジメジメした状態になり、シロアリにとってはまさにごちそうのような環境になります。
というのも、シロアリは乾いた木材よりも湿った木を好みます。床下の相対湿度70〜90%の状態が続くと、被害が一気に進行しやすくなると言われています(出典:参考文献)。
風通しが悪く、暗くて、湿気が逃げにくい場所は、彼らにとって絶好の住みかです。実際に、湿気の多い地域で建てられた木造住宅のなかには、「羽アリが出たと思ったら柱の中がスカスカだった」といった深刻な事例も少なくありません。
こうした被害を防ぐには、家を建てる前に「土地の水はけ」や「床下の通気性」をしっかりと確認しておくことが大切です。加えて、防蟻処理を施したり、高基礎を採用したりすることで、湿気を溜めない構造をつくることも有効です。
そして、完成後も安心せず、定期的な点検を行い、羽アリの兆候や木材の劣化がないかを確認する習慣が安心につながります。
湿気の多い土地には、快適に暮らす工夫と同じくらい、「建物を守る視点」も欠かせません。建てる前の対策と、建てた後の見守り。この2つの積み重ねが、大切な住まいを長持ちさせてくれます。
とはいえ、目に見えない床下の状態を常に管理するのは簡単ではありません。
だからこそ「専門家の力」を借りることが重要です。たとえば、『タウンライフのシロアリ対策』なら、無料で複数の専門業者に相談・見積もり依頼ができ、自宅の状況に合わせた最適な対策が見つかります。
「湿気の多い土地でも長く安心して暮らせる家にしたい」と願うなら、知らないうちに大切な住まいがシロアリの被害を受けてしまう前に、気軽にチェックしておくことをおすすめします。
床下や基礎部分の木材が腐食しやすくなる可能性あり
家の基礎って、普段は気にかけることが少ない場所かもしれません。でも、湿気の多い土地に家を建てるなら、ここを見過ごすのは本当に危険です。というのも、床下の木材は、湿度が高い環境に長くさらされると、気づかないうちにじわじわと傷んでしまうんです。
木材が28%以上の水分を含むようになると、腐朽菌が活性化しはじめます(出典:参考資料)。この菌は一度増えだすと、木材の中に深く入り込み、時間をかけて腐らせていきます。外から見るとまだ大丈夫そうなのに、内部がスカスカだったというケースも決して珍しくありません。
実際に、築10年も経っていない家で「床がなんとなく沈む感じがして調べてみたら、土台の一部がふやけていた」という話を聞いたことがあります。湿った空気がこもる環境は、シロアリにとっても居心地がよく、気づいたときにはすでに被害が広がっていたという例もありました。
こうした事態を防ぐためには、家を建てる段階からしっかりと湿気対策を考えておくことが重要です。具体的には、高基礎を採用して風通しをよくしたり、防湿シートを敷いて地面からの湿気を遮ったりするなどの工夫が効果的です。そして、建てたあとも定期的に床下の状態を確認すること。見えない部分にこそ、家の未来を左右するポイントが隠れているのかもしれません。
地盤が湿ったままになり不同沈下やひび割れが起きる
湿気の多い土地に家を建てると、目に見えないところで“地盤の歪み”が少しずつ進行し、やがて家そのものが傾いたり、基礎にひび割れが生じることがあります。これは「不同沈下」と呼ばれ、住宅の重大なトラブルのひとつです(出典:参考資料)。
原因の多くは、地盤に含まれる水分です。水はけの悪い土は乾湿の差で膨張と収縮を繰り返し、建物の重みを支えきれなくなります。たとえ丈夫なベタ基礎を採用しても、地盤そのものが不安定だと傾きは防げません。
実際、地盤調査の専門会社によると、「水が抜けにくい土地では不同沈下の発生率が高い」と指摘されています(出典:軟弱地盤対策)。
こうした事例は少なくありません。ある住宅では、造成地の低い部分に建てた結果、雨が続くたびに敷地の一部が沈み、数年後には基礎に細かいひびが入ったそうです。原因を調べると、地下水の影響で地盤が常に湿った状態になっていたといいます。
もし湿気の多い土地で家づくりを考えているなら、最初の一歩は“見えない地盤を知ること”です。購入前に地盤調査を依頼し、水位や地質、排水状況を専門家と確認しましょう。そのうえで、高基礎・地盤改良・暗渠排水といった対策を組み合わせれば、不同沈下のリスクは大きく減らせます。費用はかかっても、家全体の寿命を守るための必要な投資と考えるべきです。
湿気がこもることで住まいの資産価値が下がる
家を長く大切に使いたいと考えるなら、「湿気」は見過ごせない要注意ポイントです。実は、湿気の多い土地に建てた家ほど、きちんと対策を取らないと資産価値が落ちやすい傾向があります。
なぜかというと、湿度が高い状態が続くと、カビやダニが増えたり、木材が傷んだりと、目に見えないところで建物が劣化していくからです。専門家も「湿気は家の寿命を縮める大きな要因」と指摘しています(出典:健康・快適居住環境の指針)。
特に中古市場では、湿気や水はけの悪い立地にある住宅が査定で低く見積もられるケースも少なくありません。たとえば、河川沿いや低地に建つ家の場合、「室内のカビ臭さ」や「基礎部分の結露跡」があるだけで、買い手の印象が大きく変わります。
実際に、「湿気による環境リスクを放置した結果、売却時の価格が下がった」という事例も報告されています(出典:参考資料)。
つまり、湿気を甘く見ると、見えない場所でゆっくりと「家の価値」が削られていくということです。
土地選びの段階で地盤や水はけを確認し、設計時に通気・防湿・排水の工夫を取り入れること。そして、もし将来的に売却を考えるなら、ハザードマップや地盤データを整理しておくことも大切です。
家を長持ちさせたい、そして「守る資産」にしたい。そう考えるなら、湿気対策は“快適さ”だけでなく、“価値を守るための投資”でもあります。
間取りプランや土地探しなど家づくり計画を無料で依頼できる方法

家づくりを進めるうえで必ず悩む、
「どんな間取りがいいのか」
「どの土地が暮らしやすいのか」
「全体の費用はどれくらいか」
──こうした悩みを一度に解決してくれるのが、無料サービスの『タウンライフ家づくり』です。
このサービスでは、全国の住宅会社や工務店にまとめて相談でき、希望に沿った間取りプランや資金計画書を自宅にいながら受け取ることができます。もちろん、費用は一切かかりません。
特に便利なのは、ただのカタログ請求ではなく「オーダーメイドの提案」が届く点です。たとえば「湿気の多い土地で快適に暮らせる家を建てたい」という条件を伝えれば、排水計画や基礎構造、通風の取り方まで考慮したプランを複数社から比較できます。
こうした一括依頼の仕組みは、土地探しにも強く、地域の不動産会社や分譲地情報までカバー。公開前の土地データを提案されるケースも少なくありません。
実際に利用者の多くが、「初めてでも家づくりの全体像がつかめた」「複数の会社から比較できて、安心して選べた」といった声を寄せています。
改めて、『タウンライフ家づくり』を利用するメリットをまとめると、
- 3つの提案が“すべて無料”で一括入手!
希望に沿った「間取りプラン」「資金計画」「土地探し」の3プランを受け取れ、家づくりが一気に進む! - 複数社の提案を自宅で比較検討できる!
家にいながら、簡単に価格や間取りを“比較”できるので適正価格が分かり、効率よく候補を絞り込める! - 全国の信頼できる住宅メーカーから厳選された提案を受けられる!
全国1,200社以上・大手ハウスメーカー36社以上が掲載&提案するのは国家基準を満たすメーカーのみ!
さらに!利用者の方限定で、プレゼント(成功する家づくりの7つの法則と7つの間取り)も受け取ることができます!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、読み応えあって今後の家づくりを進めるヒントが満載でした。
間取り・予算・土地という三つの要素を同時に進めるのは大変ですが、『タウンライフ家づくり』なら最初の一歩がスムーズになります。
忙しい方や、家づくりに不安を感じている方ほど、一度利用してみる価値があります。
【Q&A】家づくりに欠かせない湿気の多い土地対策に関するよくある質問

最後に家づくりに欠かせない湿気の多い土地対策に関するよくある質問をまとめました。
庭の湿気対策や地面からの湿気防止策、湿気に強い植物の選び方など、暮らしの中で気になるポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します
湿気が多い庭の対策は?
湿気が多い庭は、放っておくと水たまりができたり、コケや害虫が増えたりと、見た目も衛生面も気になりますよね。
まず意識したいのは「水の逃げ道をつくること」です。地面に傾斜をつけて雨水を外へ流すほか、暗渠(あんきょ)や透水管を入れて地下に排水ルートを設けると効果的です。最近では「浸透トレンチ」や「レインガーデン」といった自然に水を浸み込ませる手法も注目されています。勾配づくりや排水桝の設置など、少し手を加えるだけで格段に改善するケースも多いです。
湿気の多い土地対策の基本は、見えないところで水をコントロールすることです。
地面からの湿気対策には何がありますか?
地面から上がる湿気は、外と内の両方で分けて考えると分かりやすいです。
屋外では、排水と透水の仕組みをつくり、雨水が地中に浸み込みやすい環境を整えます。暗渠排水や透水性舗装を取り入れると、表面の水たまりを防げます(出典:参考資料)。屋内では、防湿シートやコンクリートを床下に敷き、湿気の上昇を遮断。さらに換気口を確保すれば、空気が流れてカビも発生しにくくなります。
湿気の発生源を分けて考え、それぞれに合った対策を講じるのが、最も確実な方法です。
湿気の多い庭に強い植物はどれを選べばいい?
湿気の多い庭には、水気に強い植物を選ぶのがコツです。
水はけの悪い場所では、根が呼吸できずに枯れてしまう植物もありますが、湿地を好む種類ならむしろ元気に育ちます。たとえば、アヤメやミソハギ、セキショウ、イグサ、ヤブランなどは湿気に強く、管理も比較的簡単です(出典:参考資料)。
半日陰ならギボウシやシダ類もおすすめです。葉の緑が濃く、庭全体が落ち着いた雰囲気になります。
植物の力を借りて、自然に湿気と付き合う庭づくりを意識すると、景観と機能の両方が整います。
庭の湿気を取る対策に砂利敷きは本当に効果がある?
砂利敷きは見た目が整い、泥はね防止にも役立ちますが、排水そのものの改善効果は限定的です。地中の水が逃げにくい状態では、表面に砂利を敷いても根本的な湿気対策にはなりません。
より効果を上げるには、透水管を通した暗渠排水や浸透トレンチ、勾配を設けた排水路などと組み合わせるのが理想です。砂利はあくまで補助的な素材。庭全体の湿気を減らすには、構造的な「水の逃げ道づくり」が欠かせません。
庭の湿気対策に消石灰は使っても大丈夫?
消石灰は一時的に湿気を抑える効果がありますが、常用はおすすめできません。
強いアルカリ性を持ち、皮膚や植物への刺激が強いため、扱い方を誤ると土壌のバランスを壊してしまいます。農林水産省の資料でも、腐食性や刺激性への注意が明記されています。
農業では土壌の酸度調整や消毒に使われますが、庭全体の湿気対策としては不向きです。湿りやすい土壌には、砕石やバーク堆肥を混ぜて水はけを良くしたり、浸透桝を設けて水を逃がす方が安全で効果的です。
化学的に湿気を“消す”より、自然に“流す”ほうが持続的で安心です。
まとめ:湿気の多い土地でも快適な家を建てるための対策と見分け方やリスク
湿気の多い土地でも快適な家を建てるための対策と見分け方やリスク情報をまとめてきました。
改めて、湿気の多い土地でも快適な家を建てるための対策をまとめると、
- 土地探しの段階で水位や周辺環境を専門家とチェックする
- 雨水や地下水の流れを整える排水・暗渠処理を行う
- 床下に風が抜けるように高基礎を採用する
- 窓や換気口を工夫して屋内に風の通り道をつくる
- 防湿シートやコンクリートで地面からの湿気を遮る
- 調湿建材を活用して室内の湿度を自然に整える
- 除湿器や床下換気扇などでこもった湿気をしっかり除く
そして、湿気の多い土地対策の重要ポイントもまとめると、
- 湿気の多い土地でも家は建てられるが、適切な対策が必須
- 湿気を防ぐためには地盤調査や排水処理など事前対策が重要
- 高基礎や換気口の工夫で通気性を高め、湿気をため込まない構造に
- 湿気は不同沈下やカビ・害虫・建材腐食を引き起こし、資産価値も下がる
- 無料で家づくり計画を依頼できる「タウンライフ家づくり」などを活用すると安心
湿気の多い土地での家づくりには、早い段階からの対策が必要です。
地盤や排水環境を見極め、通気や防湿の工夫を取り入れることで、住み心地と将来的な資産価値を守ることができます。
「湿気の多い土地対策」を意識した家づくりで、安心・快適な住まいを実現しましょう。