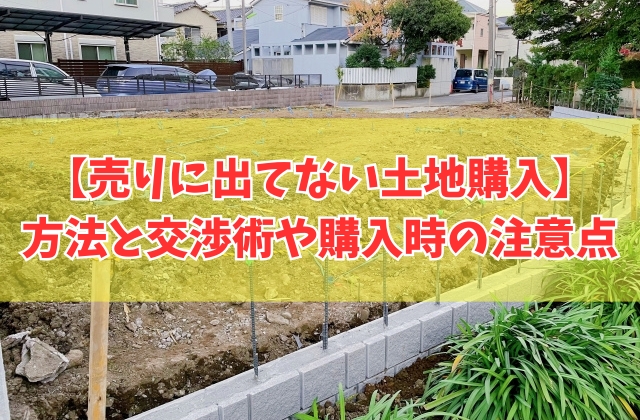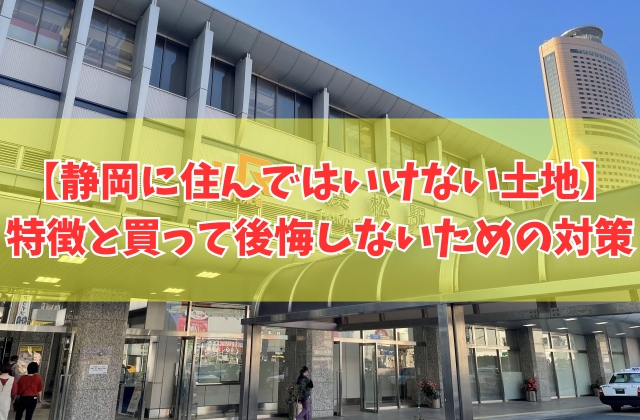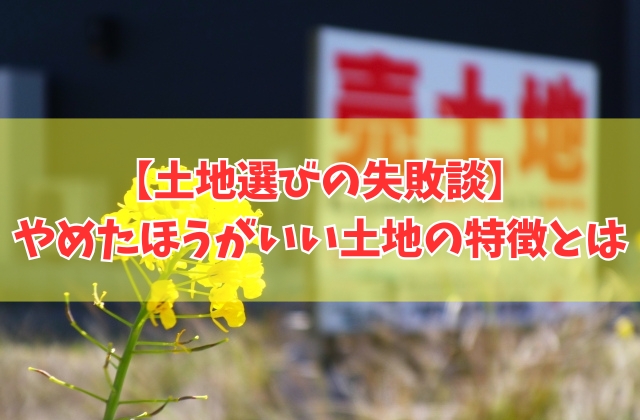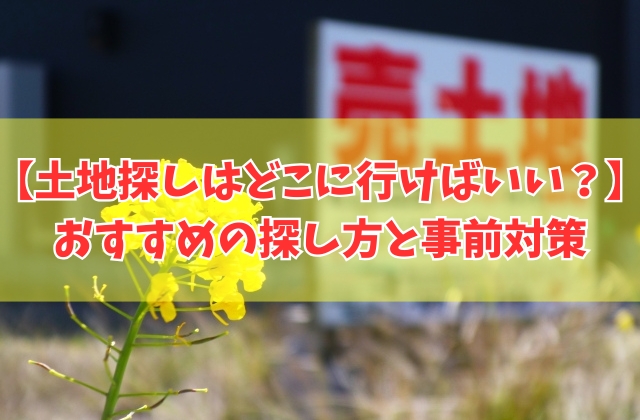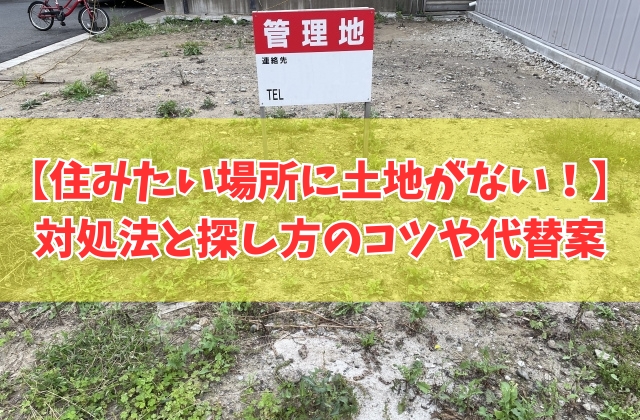
「住みたい場所に土地がない!いったいどうすれば?」
「探し方のコツは?なにか最適な代替案はないの?」
理想の場所に家を建てたいのに、いくら探しても希望の土地が見つからない??そんな状況に焦りや不安を感じていませんか?
「住みたい場所に土地がない」という壁にぶつかると、思い描いた暮らしがどんどん遠のいてしまうように感じるものです。
でも、探し方や考え方を少し変えるだけで、土地探しの選択肢はぐっと広がります。
そこで本記事では、限られた土地事情の中でどのように理想に近づくか、現実的かつ効果的な対処法を具体的に解説しています。
- 希望エリアに固執せず、柔軟に周辺地域も視野に入れることが重要
- 土地探しは複数の手段と関係先を活用し、情報の幅を広げることが鍵
- 理想の条件を整理し、7~8割満たす現実的な土地を検討する視点が必要
住みたい場所に土地がないという悩みは、多くの人が直面する課題です。
ですが、探し方や条件の見直しによって理想に近づく選択肢は確実に存在します。大切なのは情報と視野の広さです。
では、どうやって土地情報を集めればいいのか?できれば、ネットで簡単に情報がもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
住みたい場所に土地がない時の対処法5選
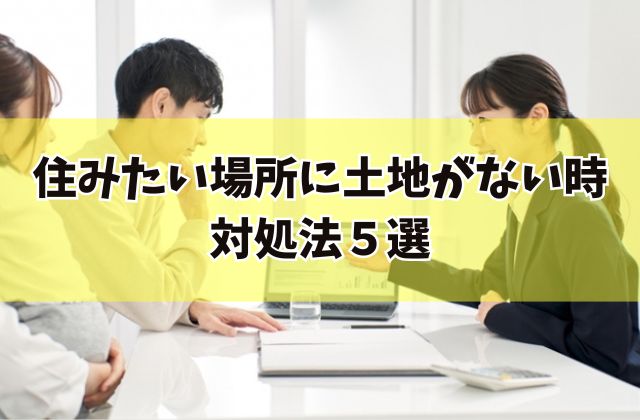
「もう何ヶ月も土地を探しているのに希望の場所が見つからない」
このように悩む方に向けて、今すぐ試せる実践的な住みたい場所に土地がない時の対処法5選を紹介します。
不動産会社の活用法から、探し方の工夫、役所の情報まで、現実的で効果のある対処法を厳選しています。
土地探しに行き詰まりを感じている方でも、行動次第で希望の土地に近づけるヒントが見つかります。ぜひ参考にしてみてください。
複数の不動産会社に同時に問い合わせて情報量を増やす
「なかなか土地が見つからない」と悩んでいるなら、不動産会社を一社に絞っていないか振り返ってみてください。実は、多くの人がやってしまいがちなのが、最初に相談した会社だけに任せてしまうこと。しかしそれでは、得られる情報が限られてしまいます。
不動産業界では、全国の物件をまとめた「レインズ」という共有システムが存在していますが、実際の現場ではそれだけで完結していません。各社が独自に持っている未公開情報や、ネットに出さず顧客にだけ紹介している“水面下の物件”も珍しくないのです。
例えば、A社にしかない登録前の土地情報や、B社が地域の地主と直接つながっていて初めて紹介してくれる物件など、それぞれの会社が持つ強みはバラバラです。実際に、複数社へ同時に問い合わせたことで、1社では絶対に得られなかった好条件の土地に出会えたという声も多く見られます。
「住みたい場所に土地がない」と感じたときこそ、視野を広げてください。複数の会社に問い合わせることは、チャンスを広げるための基本中の基本。時間をかけず効率的に探すなら、遠慮せず、積極的に動くことが大切です。焦りや不安を感じている今だからこそ、情報量を武器にしていきましょう。
では、どうやって複数の不動産会社に同時に問い合わせて情報量を増やせばいいのか?できれば無料で簡単に、ネットでもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
ハウスメーカーや工務店と連携して土地を一括提案してもらう
「土地が全然見つからない」と焦っているなら、ハウスメーカーや工務店に土地探しも含めて相談するという手があります。あまり知られていませんが、彼らは実は土地探しのプロでもあります。
多くのハウスメーカーや地元の工務店は、不動産会社と強いパイプを持っており、一般には出回っていない非公開の土地情報を持っているケースがよくあります。しかも、単に「売地」を紹介されるのではなく、「この土地なら、この家が建てられる」と具体的な建築プランを想定したうえで提案してもらえるのが大きなメリットです。
家を建てるという視点で土地を探すと、予算や理想とのバランスに頭を悩ませがちですが、建築と土地の両方を一括で見てくれるパートナーがいれば、検討がグッと現実的になります。時間も手間も節約でき、理想に近づくスピードも一段と早まるはずです。
土地だけを追い求めるより、住まいづくりの全体像から逆算する方が、結果的に満足度の高い家づくりにつながります。焦らず、まずは一度、家づくりのプロに相談してみてください。
では、どうすればハウスメーカーや工務店と連携して土地を一括提案してもらうのか?できれば、ネットで簡単に依頼できる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。
一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、複数社に相談してプランを比べてみてください。
地域密着型の不動産会社に相談して隠れ物件を紹介してもらう
ネットを毎日チェックしても、住みたいエリアに「これは」と思える土地が全然出てこない——。そんなときは、地域密着型の不動産会社に足を運ぶ価値があります。なぜなら、ネットに出てこない“水面下の土地情報”が、そこに眠っていることがあるからです。
地域に根を張っている不動産会社は、長年の付き合いがある地主さんから直接土地の相談を受けることが多く、物件が広告に出る前に話が決まるケースも珍しくありません。
たとえば、ある不動産会社の事例では、広告に載らないまま売買が進む土地は想像以上に多いと指摘されています。中には「広告費がかけられない」「ネット掲載に抵抗がある」といった理由で、地元の常連客だけに紹介される“知る人ぞ知る物件”も。
こうした隠れ物件を紹介してもらうには、店舗に直接出向き、「こんな土地を探しています」と正直に伝えることが大切です。希望条件を具体的に話せば、営業担当者も「この人なら紹介できる」と感じてくれます。探しているだけでは見つからない土地に出会えるかどうかは、こうした“地元とのつながり”を持てるかどうかが大きなカギになります。
住みたい場所に土地がないと悩んでいるなら、検索ワードよりも、人との会話に可能性を託してみるのも一つの戦略です。机の前では見つからない情報が、意外と近くの不動産屋のカウンターで待っているかもしれません。
とはいえ、地域密着型の不動産会社に1件1件問い合わせるのは億劫ですよね?できればネットで簡単に、情報を一括取得したいのが本音。
そんな効率よく探したい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
条件の7~8割を満たす現実的な土地を候補に入れる
「駅近で、南向きで、広さは100㎡以上。しかも価格は予算内で」——理想を並べるのは簡単ですが、それをすべて満たす土地は、残念ながらほぼ出てきません。むしろ、条件にこだわりすぎるほど、出会いのチャンスはどんどん狭まってしまいます。
実際、住宅業界でも「100点満点の土地は存在しない」と言われることが多く、理想の7~8割を満たす土地を前向きに選ぶ姿勢が大切だとされています(出典:参考資料)。たとえば、徒歩5分にこだわっていたけれど、8分でも落ち着いた環境で日当たりが良ければ十分満足というケースは多々あります。
「少し妥協したはずなのに、住んでみたら逆に良かった」と話す人もいます。100㎡に届かなくても、間取り次第で想像以上に快適になることもあるし、静かな住宅地に惹かれて通勤時間の数分は気にならなくなった、なんて話も珍しくありません。
土地探しで大事なのは、「自分にとって本当に大事な条件は何か」を見極めること。すべてにこだわるよりも、軸を絞って柔軟に考えたほうが、住みたい場所に近づける確率は確実に上がります。完璧を求めすぎないことが、現実的で後悔のない土地選びのコツです。
自治体や市役所の未公開土地情報をチェックする
ネットでも不動産会社でも見つからない——そんな状況が続くと、土地探しに行き詰まった気持ちになるかもしれません。けれど、実は「まだ出回っていない土地」が見つかる可能性のある場所が、ひっそりと存在しています。それが、市役所や自治体の窓口です。
多くの人が見落としがちですが、自治体には「市有地」や「空き家バンク」など、民間のサイトに載っていない情報が保管されています(出典:報道発表資料)。たとえば横浜市のように、市有地を専用ページで公開している自治体もありますし、都市計画課に直接問い合わせれば、分譲予定地や遊休地の情報を教えてもらえるケースもあるのです。
こうした土地はまだ売りに出されていない場合が多く、問い合わせた人だけが得られる“早耳情報”だったりします。
実際に、空き家対策や移住支援に力を入れている自治体では、「空き地・空き家バンク」経由でしか出回らない土地が掲載されていることもあります。一般の不動産サイトでは出会えない、“地元の人しか知らない物件”に触れられる機会です。
「住みたい場所に土地がない」とあきらめる前に、ぜひ一度、市役所の資産活用課や都市整備課を訪ねてみてください。誰よりも早く知ることで、まだ世の中に出ていない一手に巡り合えることがあります。土地探しにおいて「静かに眠る情報」を探りにいく——それも、実はとても有効な選択肢です。
住みたい場所に土地がないし見つからない原因とは

土地探しを続けているのに、なかなか希望に合う物件が見つからない——そんな悩みには、いくつかの共通した原因があります。
その住みたい場所に土地がないし見つからない原因とは何か。
実は、探し方の偏りや条件の設定に問題があることも多く、視点を少し変えるだけで状況が動き出すケースも少なくありません。
ここでは、その具体的な理由を整理しながら、見落としやすいポイントをひとつずつ解説していきます。
不動産会社に依頼するのが一社だけのため
「何社も聞いて回るのは面倒だし、最初に相談したところで十分でしょ」と思っている方は少なくありません。でも実は、それが土地探しを長引かせる落とし穴になっていることもあります。
不動産会社ごとに取り扱っている物件は異なり、なかには自社だけで情報を囲い込んで他社には出さない「未公開物件」もあります。つまり、ある会社にしか出回っていない土地情報があるのです。たとえばレインズという共通データベースを活用していたとしても、会社ごとの紹介力や地域とのつながりには差があります。
実際、複数の不動産会社に声をかけたことで、最初の1社では得られなかった魅力的な土地に出会えたという話もよくあります。「同じエリアでも紹介される物件がまったく違った」というケースもあるほどです。特に、駅近や人気エリアを希望している場合、情報量の差はそのまま選択肢の差に直結します。
住みたい場所に土地がない…と感じたときは、まずは依頼先の見直しから始めてみてください。3社程度を目安に相談してみるだけで、土地探しの景色がガラッと変わることがあります。情報は「待つ」よりも「取りに行く」姿勢が、良い出会いを引き寄せる一歩です。
そして、不動産会社から一括で情報を効率よく集めたい方は、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用するのがおすすめです。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
希望条件が多すぎて探しにくくなっているため
「駅から近くて、日当たりも良くて、100㎡以上で、予算は◯◯万円以内」——そんなふうに、最初はざっくりだった希望条件が、気づけばどんどん細かくなっていませんか?情報収集を続けるほどに理想は膨らみますが、条件を詰め込みすぎると、現実の物件に当てはまる土地はほとんどなくなってしまいます。
実際に専門家の間でも「希望が増えるほど土地探しは難航する」と言われています。すべての条件を満たす土地なんて、そうそう出てこないのが正直なところ。にもかかわらず、「これも違う、あれも違う」と除外を重ねていくと、選べる候補はどんどん減ってしまいます。
「もっといい土地があるんじゃないか」と延々と探し続けていると、どの土地も中途半端に見えてきて、決断のタイミングを逃す人も少なくありません。完璧を目指す気持ちは分かりますが、大切なのは“何を妥協してもいいのか”を自分で理解しておくことです。
まずは条件を3つだけに絞りましょう。「通勤が苦にならない距離」「日当たり」「小学校の学区」など、自分たちにとって本当に優先したいものだけを軸にする。そのうえで、多少の妥協を受け入れる柔軟さを持てば、「住みたい場所に土地がない」と感じていた状況が、意外な形で動き出すこともあります。
土地探しにおいては、譲る力こそが選ぶ力になるのです。
条件をすべて100%満たす土地を追い求めているため
「理想の土地が見つからない」と悩んでいる方の中には、知らず知らずのうちに“完璧な一枚”を探し続けている方が少なくありません。駅から近くて、南向きで、100㎡以上で、しかも予算内——それを全部満たす土地なんて、本当にあるのでしょうか?
実は、土地探しが長引いてしまう大きな原因の一つが、この「100%の理想を求める姿勢」です。不動産の専門家の多くも、「条件に優先順位をつけなければ、土地探しは終わらない」とはっきり言います。現実には、7~8割叶えば“良縁”だと言われるほど。
たとえば、駅徒歩5分を譲れない条件にしていたけれど、7分でも静かで緑が多い場所に出会ったとき、「あれ?こっちのほうが落ち着くかも」と感じることもあります。ほんの少し角度を変えるだけで、“完璧じゃないけど心地いい土地”が見えてくるんです。
すべてを求めすぎると、選択肢はどんどん狭まり、心も疲れてしまいます。「譲れること」と「譲れないこと」を整理することは、妥協ではなく、自分の暮らしに本当に必要な軸を見つける作業。
土地選びが行き詰まってきたら、一度立ち止まって“本当に大事な条件”を見つめ直してみてください。そうすれば、思いがけない形で、理想の暮らしに一歩近づけるはずです。
住みたい場所に土地がない時に意識したい探し方のコツ

「どうしても見つからない」と感じたときは、土地の探し方そのものを見直すタイミングかもしれません。
住みたい場所に土地がない時に意識したい探し方のコツは、情報の集め方や優先順位の付け方、そして理想の暮らし像をどう描くかにあります。
焦る気持ちを落ち着けて、視野を広げながら柔軟に考えることで、思わぬ出会いが生まれることもあります。
ここからは、土地探しを前に進めるための具体的なコツを紹介します。ぜひ、土地探しの参考にお役立てください。
一つに絞らずあらゆる方法で土地を探す
土地がなかなか見つからない…。そう感じているなら、探し方そのものが“偏って”いないかを見直してみてください。よくあるのが、ネットの検索結果だけを頼りにしてしまうパターン。でも、実際のところ、本当に出会える土地は“ネット外”にもたくさん眠っています。
たとえばSUUMOでは、土地探しには「ネット検索」「不動産会社への相談」「自分で現地を歩く」「ハウスメーカーからの提案」など、複数のアプローチを組み合わせることが基本だと紹介しています。実際、希望エリアを歩いていて偶然見つけた“売り出し前の空き地”に一目惚れして購入を決めた、という例もあります。
そして、不動産会社や工務店の担当者と直接話すことで、「今は出していないけど、売る予定の土地がある」といった未公開情報が手に入ることも。ネットには出ない情報こそ、現場に足を運んだ人だけが知る“リアル”です。
土地探しは、パソコンの前だけで完結するものではありません。ネット検索、現地調査、人との会話。その全部を並行して動かしてこそ、道は開けていきます。ひとつの方法にこだわるのをやめたとき、思わぬ方向からチャンスが舞い込んでくることもあるのです。
焦りを力に変えて、探し方に“幅”を持たせてみてください。可能性は、思っているより広がっています。
では、どの方法が効率的かつ効果的な方法なのか?できれば無料で簡単に、ネットでもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
希望条件の優先順位を明確にして整理する
土地が見つからないとき、多くの人が見落としがちなのが「条件の整理不足」です。理想を並べるのは簡単ですが、現実はそんなに都合よくいきません。
たとえば「駅近・南向き・予算以内・閑静な住宅街」——この全部を満たす土地は、正直ほとんど出てきません。だからこそ、まずやるべきは「譲れない条件」と「妥協できる条件」を紙に書き出してみることです。
たとえば、「駅からの距離は徒歩15分までならOK」「日当たりよりも学区を重視したい」といったように、自分たちにとって本当に必要なものが何かを整理するだけで、選択肢は一気に広がります。不動産会社も具体的な条件が明確になれば、提案の精度がぐっと上がります。
理想を100点満点に保ったままでは、時間ばかり過ぎて焦りも膨らむばかり。7割満足できる土地との出会いを大切にする視点が、スムーズなマイホーム計画への第一歩になります。現実を見据えつつ、自分たちにとっての“暮らしやすさ”を言葉にしていきましょう。
理想の暮らしをイメージして土地を絞り込む
土地探しに行き詰まったとき、まず立ち止まって考えてほしいのが「どんな暮らしがしたいのか」という問いです。条件を並べていくうちに、いつの間にか本来の目的が見えなくなってしまう人は少なくありません。駅からの距離や日当たり、周辺環境——もちろん大切ですが、それがあなたの理想に本当に必要な要素か、振り返ることが大事です。
たとえば、週末は家族でバーベキューを楽しみたい、子どもが庭で自由に遊べる場所が欲しい、朝は静かな場所でコーヒーを飲みたい。そういった“暮らしのシーン”を具体的に描くことで、求める土地の条件もはっきりしてきます。実際に、住宅情報サイトのコラムでも「まず暮らしを描くことが、納得のいく土地選びへの近道」と紹介されています。
条件が厳しすぎて選べないのではなく、暮らしのイメージが曖昧だから選べないことも多いのです。理想を丁寧に言葉にする。それが、迷路のような土地探しに風穴をあける一歩になります。
住みたい場所に土地がない時に検討したい5つの代替案

「どうしてもこのエリアがいいのに、土地が出てこない」
そんな壁にぶつかったとき、視点を変えることが突破口になるかもしれません。
その「住みたい場所に土地がない時に検討したい代替案」を知っておくことで、選択肢の幅がぐっと広がります。
理想の住まいを実現するために、いま取れる現実的なアプローチを整理してみましょう。
希望する地域以外のエリアも視野に入れて探す
「ここに住みたい」と心に決めた場所があっても、思ったような土地が見つからないことはよくあります。そんなときは、一度その“こだわり”を少しだけ緩めてみることをおすすめします。
たとえば、希望していた駅から2~3駅ほど離れたエリアに目を向けるだけで、驚くほど選択肢が広がることもあります。実際、不動産ポータルでも「人気エリアの周辺駅や隣町に目を向けることで、条件に近い土地に出会いやすくなる」と紹介されているほど。
筆者の体験談ですが、私の知人は都心にアクセスしやすい沿線で探していたものの、候補を隣接エリアに広げたことで、希望していた広さと予算を両立した土地に巡り会いました。
最初に描いていた場所に固執しすぎると、時間も気持ちも疲弊しがちです。土地探しは“一点集中”より“周辺拡大”の視点が鍵になることもあります。「住みたい場所に土地がない」と感じたら、まず一歩だけ外へ目を向けてみてください。その視点の転換が、意外にも理想の暮らしへの近道になるかもしれません。
中古住宅や古家付き土地を購入して建て替えを検討する
「土地が見つからない…」と頭を抱えている方に、ぜひ知っておいてほしいのが“古家付き土地”という選択肢です。意外かもしれませんが、この方法なら人気エリアでも現実的な予算で土地を確保できることがあります。
実際、中古住宅を含む土地は、新築に比べて価格が3~4割も安くなるケースが多いのです(出典:不動産流通市場活性化に向けて)。
たとえば、建物は使わずに解体してしまい、その場所に新たに家を建て直すというプラン。これなら立地も妥協せず、間取りも自由に設計できます。最近では「築古でも土地の場所さえ良ければ即検討」という人が増えており、思い切って建て替え前提で探すのは、土地不足の今こそ現実的な戦略だといえるでしょう。
もちろん、解体費や上下水道の再整備、仮住まいなど、見落としがちな費用もあるため、購入前に必ず工務店や不動産会社とすり合わせを。うまく活用すれば、「住みたい場所に土地がない」という悩みに対して、状況を打開する強力な手段になります。
そして、中古住宅や古家付き土地を効率よく探すなら、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用するのがおすすめです。
「タウンライフすまいリクエスト」は、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
狭小地や旗竿地など個性ある土地も候補に入れて検討する
「土地が全然見つからない…」そんな焦りのなかで、つい見落としがちなのが“少しクセのある土地”です。たとえば狭小地や旗竿地。形が不規則だったり、通路が細かったりするため敬遠されがちですが、実は魅力もたっぷりあるのです。
旗竿地のような変形地は、同じエリアの整形地よりも20~30%ほど安く手に入ることが珍しくありません(出典:参考資料)。予算の限られた中でも「場所は妥協したくない」という人にとって、価格面のメリットは大きな支えになるはずです。また、通路の奥にある旗竿地は人目につきにくく、静かな環境を手にできることも魅力のひとつです。
もちろん、いいことばかりではありません。日当たりや風通しに工夫が必要だったり、重機が入らないため工事費が高くつく可能性もあります(出典:敷地細分化抑制のための評価指標マニュアル)。でも、だからこそ設計の工夫が活きる場面でもあるのです。
たとえば2階リビングや天窓を設けて自然光を確保する。細長い通路部分をうまく使って駐車スペースや小道にする。そんなふうに、一般的な土地ではできない発想が活きてきます。
“住みたい場所に土地がない”と行き詰まったように感じた時こそ、こうした「個性のある土地」にも目を向けてみてください。一見クセの強い土地が、実は暮らしの楽しさを広げてくれる可能性を秘めているかもしれません。大事なのは、「普通の土地」だけにこだわらないこと。視野を広げて探せば、予想もしなかった好物件に出会えることもあるのです。
建築条件付き土地で価格を抑えつつ理想に近づける
「希望の場所に土地がない」と悩んでいるなら、視点を変えて建築条件付き土地を探してみるのも一つの方法です。これは、あらかじめ決められた建築会社と家を建てることを前提に販売される土地のこと。
いわゆる“建物とのセット販売”に近い形ですが、その分、土地価格が相場よりも数百万円ほど安くなるケースも少なくありません(出典:不動産情報ライブラリ)。
たとえば首都圏では、坪単価が相場より3~5万円程度下がっている例も見受けられ、総額で見るとコスト削減効果は大きめです。しかも建築会社とのやり取りが一本化されるため、打ち合わせの負担が少なく、スケジュールも比較的スムーズに進む傾向があります。
もちろん、自由設計を重視したい人には向かないかもしれません。間取りの融通が利きにくかったり、施工の仕様がパッケージ化されていたりするからです。ただ、「手が届く範囲で理想の家に近づけたい」「住みたい地域から離れたくない」という人にとっては、検討する価値のある現実的な選択肢だといえるでしょう。
マンション購入も選択肢に加えて柔軟に検討する
「土地が見つからない」と嘆く前に、マンションという選択肢に目を向けてみる価値はあります。なぜなら、理想のエリアで暮らしたいという希望を、マンションなら意外とすんなり叶えられることが多いからです。
分譲マンションは、駅近や都市部など“良い場所”に建っているケースが圧倒的に多く、国土交通省の調査でも、マンション購入者の72.3%が「住宅の立地環境が良かったから」と回答しており、「立地の満足度」が購入理由の上位に挙げられています。戸建て用地では手が届かないようなエリアでも、マンションなら予算内で購入できる可能性がぐっと高まります。
たとえば、都内で駅から徒歩5分圏内の場所に住みたいとします。戸建てでは到底かなわなくても、中古マンションなら現実的な価格帯で選べる物件があります。しかも宅配ボックスやセキュリティなど、暮らしの便利さも備わっている点は見逃せません。
土地が見つからず、心が疲れてしまう前に──。“戸建て一択”という思い込みを一度手放して、視野を広げてみるだけでも、暮らしの選択肢は驚くほど広がります。マンションも「住みたい場所で暮らす」という夢に近づく、ひとつの有効な道です。
そして、理想のマンションを効率よく探すなら、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用するのがおすすめです。
「タウンライフすまいリクエスト」は、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
住みたい場所に土地がないからといって買わない方がいい土地の特徴

住みたい場所に土地がない状況が続くと、つい焦って「今ある土地」で妥協してしまいがちです。
しかし、条件をよく見極めないまま契約してしまうと、後悔の残る住まいになりかねません。
そこで「住みたい場所に土地がないからといって買わない方がいい土地の特徴」を知っておくことが大切です。
ここでは、その避けたほうがよい土地の具体例を整理しています。焦りを手放し、冷静に判断するための参考にしてください。
日当たりが悪く湿気がたまりやすい土地
日当たりが悪い土地は、見た目では分かりにくい“暮らしのストレス”を生む原因になります。たとえば、朝から部屋が薄暗い、洗濯物が乾かない、冬場は窓がビッショリ結露……。そんな毎日が当たり前になると、気づかないうちに心も家もじわじわ疲弊していきます。
実際、日照不足の土地では、湿気がこもりやすく、結果としてカビやダニが発生しやすい環境になってしまいます(出典:参考資料)。家の構造に悪影響が出たり、家族の健康を害するリスクもあるため、「建てれば終わり」では済まないのが現実です(出典:健康・快適居住環境の指針)。
とくに住宅密集地では、隣家の影の影響で日照が大きく変わることも少なくありません(出典:建築基準法(集団規定))。
「この場所しかない」と焦って妥協してしまうと、あとから後悔することも。土地選びの段階で、時間帯ごとの陽の入り方や風通し、周囲の建物の高さなどをしっかり確認することが、快適な住まいづくりの第一歩です。
交通量が非常に多く騒音や排ガスが気になる土地
家づくりにおいて、立地は最も重視したいポイントのひとつです。とくに、交通量が多いエリアは見た目以上に注意が必要です。朝晩の通勤時間帯は車の流れが途切れず、車の走行音が窓越しに響き続けます。窓を閉めていても低周波音が気になり、静かな暮らしを求めている方にはストレスになるかもしれません。
さらに問題なのは空気の質です。幹線道路沿いでは排ガスによる空気汚染が懸念され、特に小さなお子さんや高齢の方がいる家庭では健康への影響が無視できません(出典:沿道における大気汚染の現状と対策)。洗濯物がすぐに黒ずんだり、窓のサッシが排気で汚れるといった現象もよくある話です。
実際、国交省の資料によれば、交通量が多い道路周辺ではPM2.5などの微小粒子が基準値を上回る例もあり(出典:沿道における大気質の現況把握及び対策の検討)、特に子どもや高齢者がいる家庭には慎重な判断が求められます。
もし気になる土地がこうした場所にある場合は、現地を平日・休日・時間帯ごとに見て回るのがおすすめです。音や空気の状態は数字だけで判断できません。最終的に暮らし始めてから「思っていたよりうるさい」「外に洗濯物が干せない」と感じないよう、事前のチェックが何より重要です。
接道義務を満たしておらず建築不可の土地
どんなに立地が良くても、「道路にしっかり接していない土地」は、実は家を建てられない可能性があります。これを「接道義務」と言い、建築基準法では、幅4メートル以上の公道に2メートル以上接していることが新築の条件です(出典:接道規制のあり方について)。
たとえば、周囲を他の家に囲まれた旗竿地で、通路部分が細すぎると、建て替えすらできません。こうした土地は一見安く見えても、実際には「建てられない=価値がつかない」ケースも多く、後悔する人が後を絶ちません。
土地を見つけたら、「この土地はどこに、どれだけ道路と接しているのか?」という視点をまず持ってください。不動産会社任せにせず、役所で接道状況を確認することも忘れずに。不安があれば建築士に相談するのも手です。家を建てたいなら、土地選びは慎重すぎるくらいでちょうどいいのです。
境界があいまいで隣地トラブルが起きやすい土地
土地を選ぶとき、つい見落としがちなのが「境界の明確さ」です。見た目ではわからなくても、境界がはっきりしていない土地は、のちのち厄介なトラブルを招くことがあります。たとえば、「ここまでがうちの敷地」と思っていた場所に、隣の人が物置を置いてきた──そんなとき、境界の根拠がなければ話し合いも難航しがちです。
境界線には「所有権界」と「筆界」という2つの考え方があり、どちらが問題になっても建築トラブルや近隣トラブルの火種になり得ます(出典:参考資料)。民法234条1項では隣地境界から50cm以上離して建てる必要がありますが、境界があいまいなままだとこの距離が守れない場合もあります(出典:民法の相隣関係の規定)。
購入前に、土地家屋調査士による測量を依頼し、「筆界特定制度」などを使ってしっかり確認しておくと安心です。杭や鋲で明示すれば、万が一の誤解やトラブルもぐっと減ります。将来の安心を買うという意味でも、境界が確定しているかどうかは見逃せないチェックポイントです。
災害リスクが高くハザードマップに注意が必要な土地
「ようやく見つけた土地。でも、災害リスクの文字を見て不安になった」——そんな声は決して珍しくありません。実際、土地探しでは立地や価格に目が向きがちですが、災害への備えも見過ごせない大切な要素です。
国や自治体が公開しているハザードマップには、洪水・土砂崩れ・津波などの被害想定がエリアごとに詳しく示されています。2020年以降、不動産取引の場でも、重要事項説明としてそのリスクの提示が義務づけられています(出典:参考資料)。
たとえば川の近くの住宅地では、浸水の深さが「3m以上」と表示されるケースもあります。これは、2階まで水が届く可能性を意味しており、住まい方にも大きな影響を与えます(出典:参考資料)。土砂災害警戒区域であれば、追加の工事費や構造強化が必要になることも(出典:土砂災害防止法の概要)。
後悔しない土地選びのためには、「安全性」を最優先に。価格や立地に心が揺れるときこそ、ハザードマップをじっくり確認し、家族の暮らしを守れる場所かどうか、冷静に判断していきましょう。
【Q&A】住みたい場所に土地がない状況に関するよくある質問

最後に住みたい場所に土地がない状況に関するよくある質問についてです。
実際によく寄せられる疑問とその答えをまとめました。焦らず次の一歩を踏み出すヒントにしてみてください。
土地探しに何年くらいかかりますか?
「土地がなかなか見つからない…」と感じたら、焦りたくなる気持ちはよくわかります。でも現実には、土地探しには数ヶ月から1年ほどかかることが珍しくありません。
とくに都市部や人気エリアは物件の回転が早く、好条件の土地はすぐに買い手がついてしまうのが実情です。実際、あるご家庭では希望エリアに絞った結果、土地探しに約3ヶ月、建築準備を含めるとトータルで1年かかったという例もあります。だからこそ、焦らず地道に情報を集めながら、条件を少しずつ調整していく姿勢が大切です。
土地なしで注文住宅を建てる場合の流れは?
家を建てたいのに、肝心の土地が決まっていない。そんなときは「どこから手をつければいいの?」と戸惑うかもしれません。
基本的には、①土地を探す → ②資金計画とローンの仮審査 → ③住宅会社と打ち合わせ → ④土地の購入契約 → ⑤建築スタート、という順序で進みます。土地と建物のローンを同時に組む場合も多いため、金融機関との調整も大切になります。だからこそ、土地探しの段階からハウスメーカーや工務店に相談しておくと、設計や費用感の目安が見えやすくなり、後の工程がスムーズになります。
土地を探すときまずやることは?
「さあ土地を探そう」と意気込んでも、最初にやるべきことを間違えると、迷路に迷い込むような気分になってしまいます。
まずやるべきことは、“何を重視するか”の優先順位を決めることです。駅からの距離なのか、日当たりなのか、学校までの通学距離なのか…。条件を並べるだけでなく、家族で「これだけは譲れないね」と共有しておくと、検索や相談もスムーズに進みます。その上で、複数の不動産サイトをチェックしながら、地元の不動産会社や市の住宅課に問い合わせてみるのが具体的な一歩になります。
マイホームの土地が決まらないときの対処法は?
条件にぴったりの土地がどうしても見つからない。そんなときにやってしまいがちなのが、「もうちょっと待てば完璧な物件が出るかも」と延々と探し続けることです。
でも、100%理想通りの土地はまず現れません。現実には、70~80%を満たす物件に出会えたら“選ぶ”判断が必要です。たとえば駅から少し遠いけれど日当たりは抜群、そんな土地ならライフスタイルに合う工夫ができるかもしれません。完璧を求めるよりも、“納得できる選択肢”に出会ったときが、決断すべきタイミングかもしれません。
土地が見つからないのはスピリチュアルなサイン?
結論、土地が見つからないのはスピリチュアルなサインではありません。
「土地が見つからないのは、もしかして運命の流れ?」と感じてしまうのは無理もありません。理想の土地に出会えず迷走していると、思考がスピリチュアルに傾く人もいます。ただ、実際には、情報収集の手段が限られていたり、選択肢が狭まっていたりするのが大きな原因です。
特に人気エリアでは、一般に出回らない未公開物件が多く、地域の不動産ネットワークに入っていないとチャンスすら巡ってきません。「運」より「縁」を作る努力が必要です。神頼みも悪くはないですが、確実に成果に近づけるのは地道な行動の積み重ねです。
見つからないときの土地の探し方の裏ワザはないの?
実はあります。ちょっと面倒でも「現地を歩く」が最強の裏ワザです。
ネットに出ていない空き地を見つけ、法務局で登記簿を確認し、所有者へ手紙でコンタクトする——これが意外と効くんです(出典:参考情報)。不動産屋も把握していない空地が住宅地のすき間にポツンと残っていることも多く、直接交渉に応じてもらえるケースも。
手間はかかりますが、そのぶん競争率は低く、掘り出し物に出会える可能性が高くなります。「掲載されていない土地」こそ、狙い目なんです。
土地が見つからずイライラしたときどうすればいいの?
「もう探すのやめたい…」と投げ出したくなる気持ち、よくわかります。でも、イライラの正体は「行き詰まり感」。つまり、手探り状態で進んでいるせいなんです。
そこでおすすめなのが、探し方の棚卸し。どのエリアを何件見たのか、どんな条件を譲れないのか、紙に書き出してみましょう。優先順位が整理されると、冷静さも戻ってきます。そして、視野を少し広げるだけで、意外とあっさり見つかることもあります。行動を“見える化”すると、心のモヤモヤもすっと晴れてきます。
売りに出てない土地は本当に購入できる?その方法は?
結論から言えば、「売りに出ていない土地」でも購入は可能です。
方法は、まず土地の住所(地番)をもとに法務局で登記簿を取得し、所有者を調べる。そして手紙や電話で意思を確認した上で、不動産会社を介して交渉を進めます。もちろん、交渉がまとまるとは限りませんが、驚くほどスムーズに進むことも。
中には「売ろうと思っていたけど面倒だった」という地主さんもいます。ネットに出ている土地だけが市場ではないということ。見えないところにこそ、チャンスは潜んでいます。
まとめ:住みたい場所に土地がない時の対処法と探し方のコツや代替案
住みたい場所に土地がない時の対処法と探し方のコツや代替案をまとめてきました。
改めて、住みたい場所に土地がない時の対処法をまとめると、
- 複数の不動産会社に同時に問い合わせて情報量を増やす
- ハウスメーカーや工務店と連携して土地を一括提案してもらう
- 地域密着型の不動産会社に相談して隠れ物件を紹介してもらう
- 条件の7~8割を満たす現実的な土地を候補に入れる
- 自治体や市役所の未公開土地情報をチェックする
そして、住みたい場所に土地がないときに知っておきたいポイントもまとめると、
- 複数の不動産会社や地域密着型業者に問い合わせて情報量を最大化することが有効
- ハウスメーカーや工務店と連携し、土地と建物を一括で提案してもらう方法が効率的
- 希望条件を整理し、完璧を求めすぎず7~8割で折り合いをつけることが現実的
- 代替案として中古住宅や建築条件付き土地、マンション購入も柔軟に検討する
- ハザードマップや接道義務など、安全性と法的条件を満たした土地を優先して選ぶ
住みたい場所に土地がないと感じたときは、ただ諦めるのではなく、視野を広げることが大切です。
土地の探し方を見直したり、希望条件の優先順位を整理したりすることで、選択肢はぐっと広がります。焦らず、柔軟な姿勢で向き合いましょう。