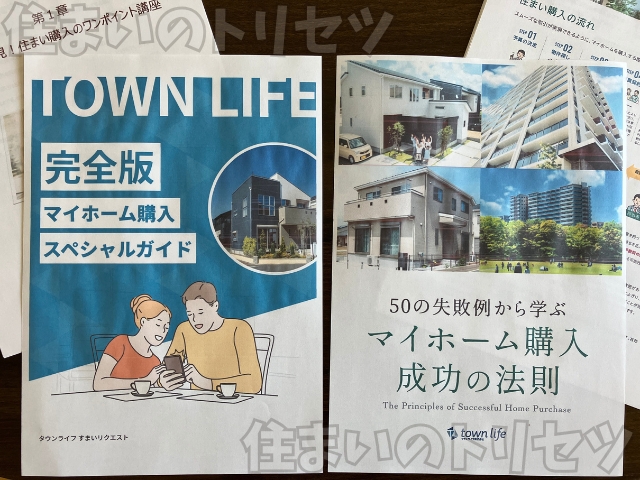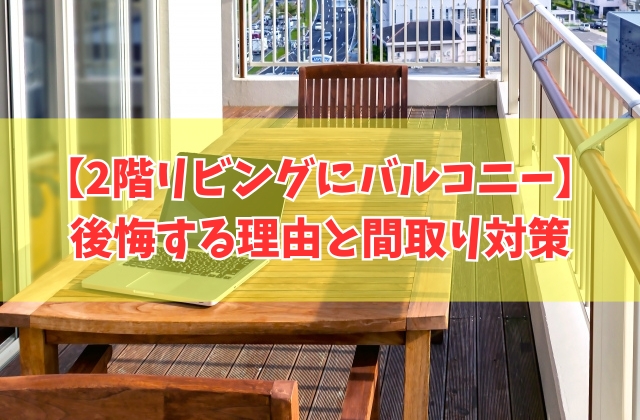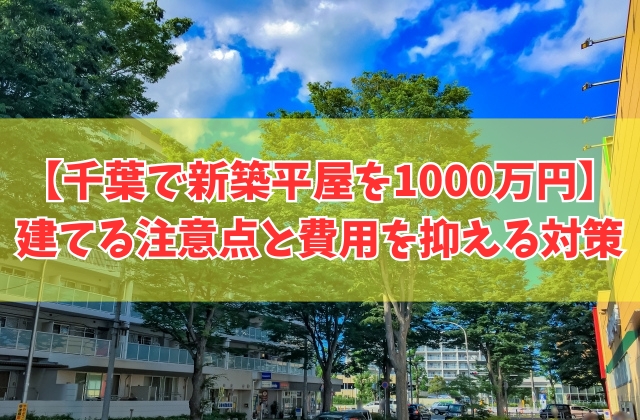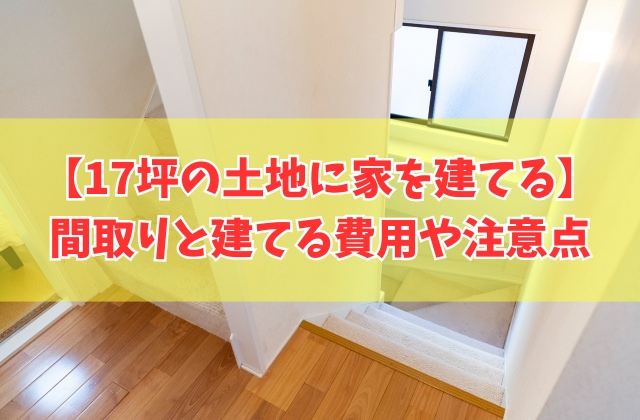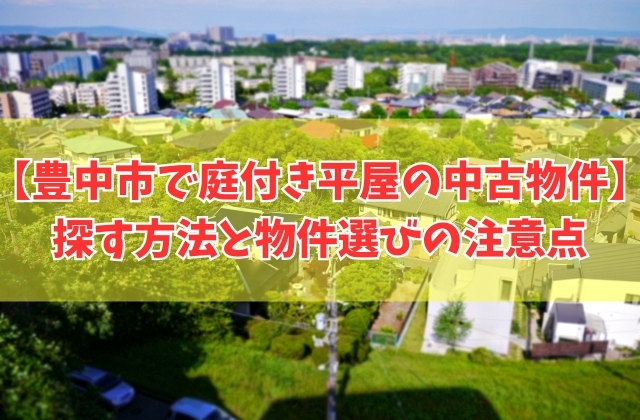「土地を買ってキャンピングカーに住むことは可能?」
「住む場合のメリット・デメリットは?土地はどうやって探せばいい?」
「好きな場所で、自由に暮らせたら…」そんな思いから、土地を買ってキャンピングカーに住むことを考え始めた方も多いのではないでしょうか。
毎月の家賃に縛られず、自然の中でのんびりとした時間を過ごす生活は魅力的です。
その一方で、「本当に現実的に可能なのか?」「どんな手続きや費用がかかるのか?」といった不安も尽きません。
この記事では、実際に土地を買ってキャンピングカーに住む場合のメリットや注意点、必要な費用などを分かりやすく解説しています。
自分らしい暮らしを本気で考えている方に、役立つ情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。
- 土地を買ってキャンピングカーに住むことは法的に可能だが条件を満たす必要がある
- 維持費やライフライン整備費などの初期コストやランニングコストに注意が必要
- 移動の自由や家賃ゼロなど、従来の住まいにはないメリットも多くある
土地を買ってキャンピングカーに住むという選択肢は、自由度の高い暮らしを実現できる一方で、行政手続きや設備費用などの現実的な課題も伴います。
情報をしっかり集めて、自分に合ったライフスタイルを見極めることが大切です。
では、どうやって理想の土地を効率よく探せばいいのか?できればネットで簡単に、情報がもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフすまいリクエスト』を活用する方法です。
「タウンライフすまいリクエスト」とは、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
- 非公開物件&値下げ物件の情報がもらえる!
複数社への一括依頼により、広告掲載前や値下げ前の“掘り出し物件”に出会える可能性が高まる - 物件探しの手間・時間を大幅に削減できる!
60秒の簡単入力だけで、複数の不動産会社から資料・提案が一括で届くので、自分で探す手間が省ける - 信頼できる複数の不動産会社の中から選べる!
登録企業は全国170社以上、独自基準をクリアした優良な不動産会社に限定。安心して比較・選択ができる
さらに!タウンライフすまいリクエスト利用者限定で2つの特典が必ずもらえるプレゼントを実施中!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、40ページを超える読み応えありの内容で、今後の物件探しのヒントが満載でした。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
【結論】土地を買ってキャンピングカーに住むことは可能?

土地を買ってキャンピングカーに住むことは可能なのかどうか。
気になる結論ですが、「住めないことはないけれど、想像以上にハードルは高め」です。土地を手に入れて、そこにキャンピングカーを停めて暮らす──そんな自由なライフスタイルは確かに魅力的ですが、現実はもう少し複雑です。
たとえば、キャンピングカーは“住宅”ではなく“車両”として扱われます(出典:道路運送車両法・第2条)。そのため、住民票をその場所に置こうとしても、ほとんどの自治体では認められていません。実際に生活していても、法律上は「そこに住んでいる」とは見なされないわけです。
また、トレーラーハウスのように地面に固定するタイプの場合は、建築物と判断される可能性が出てきます(出典:参考資料)。そうなると、建築確認申請が必要になったり、地域によってはそもそも設置が認められていないケースもあります(出典:裁判例結果詳細)。都市計画法や用途地域の制限に引っかかることもあり、法的な確認を怠ると後々トラブルになりかねません。
そのため、キャンピングカー生活をしている人の中には、実家の住所を使って住民登録をしたり、郵便物の受け取りを代行サービスでカバーしている人もいます。「土地を買えばすぐに暮らせる」というほど単純ではないのが実情です。
つまり、「土地+キャンピングカー=家になる」とは限らないということ。夢を実現させるには、法的な下調べや行政への相談が欠かせません。自由な暮らしを目指すなら、まずはその自由を成立させるための準備が必要です。
土地を買ってキャンピングカーに住む5つのメリット

土地を買ってキャンピングカーに住む生活には、思っている以上に多くのメリットがあります。
住まいにかかる費用をぐっと抑えられるだけでなく、暮らし方そのものを柔軟に変えていける点も大きな魅力です。
特に、自由な時間や場所を大切にしたい方にとって、このスタイルは理想に近い選択肢となるかもしれません。
ここでは、実際に注目されている「土地を買ってキャンピングカーに住む5つのメリット」について詳しく紹介していきます。
自由に移動してその日の気分で居住場所を変えられる
キャンピングカーで暮らす一番の魅力は、「どこに住むかを自分で決められる自由さ」かもしれません。土地を所有して拠点を持ちつつ、気分次第で風景を変えられるというのは、今の日本の住まい方ではかなり贅沢です。
実際、キャンピングカーは車両なので、道の駅やRVパーク、キャンプ場など、各地に整備された場所へ簡単に移動できます。住まいに“定位置”がないということは、暮らしそのものに“流れ”が生まれるということ。天気が良ければ海のそばへ。気分が変われば山の中へ。そんなふうに、自然と調和した生活が実現できるのです。
たとえば、朝は木々に囲まれた静かな場所で目を覚まし、夜は星空の下で眠る。都会ではなかなか味わえないこのリズムが、心にもゆとりを与えてくれます。
「今日はどこで寝ようか」と考えながら暮らす毎日は、想像以上に刺激的で、自分らしい人生を取り戻したい人にはぴったりの選択肢です。
家賃や住宅ローンなしで経済的な自由が増す
もし毎月の家賃や住宅ローンに追われない生活ができたら——。そんな想像をしたことがある方にとって、キャンピングカー暮らしは思った以上に現実的な選択肢になります。
住宅のように高額なローンを組む必要はなく、キャンピングカー自体も購入後の固定資産税が基本的にかかりません(出典:【フラット35】ご利用条件)。土地を所有しながらも、住まいの維持費は最小限に抑えられるという点で、経済的な負担は大きく違ってきます。月にかかる維持費も人によっては3万円程度に収まることが多く、従来の住居スタイルとはコスト感がまるで違います。
実際に住宅を手放して“バンライフ”に移行し、月々の生活費を約6万円ほど落とせたという例もあります。自由と引き換えに多少の不便はあるかもしれませんが、無理なく暮らせるという安心感は、何にも代えがたい価値です。
一歩踏み出す勇気さえあれば、経済的なストレスに縛られない、もっと柔らかい暮らし方がそこに待っているかもしれません。
固定資産税がかからず維持コストを抑えられる
キャンピングカーで暮らす最大のメリットのひとつが、「家」としての税金がかからないことかもしれません。固定資産税——つまり、土地や建物にかかる税負担がゼロになるだけで、長期的に見ても支出はかなり軽くなります。
なぜかというと、キャンピングカーやトレーラーハウスは、法律上「不動産」ではなく「車両」として扱われるためです。特に、地面にしっかりと固定されておらず、いつでも移動できる状態を保っていれば、住宅とみなされることがなく、課税対象から外れます(出典:参考資料)。
とはいえ、所有する土地には固定資産税がかかる点には注意が必要です。住宅用地としての減税措置が使えない場合、税額は満額で請求されます(出典:住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)。
それでも、家を建てるより維持コストをぐっと抑えられるのは間違いありません。無理なく暮らすための住まい方として、こうした選択肢がもっと広がっていってもいいはずです。
多拠点生活や移動拠点として使いやすい
「一つの場所に縛られない生き方がしたい」──そう思ったことがあるなら、キャンピングカーという選択肢は決して突飛ではありません。むしろ、今の時代に合った新しい“暮らしのカタチ”といえるかもしれません。
たとえば、週の前半は都心近くで仕事に集中し、週末はそのまま車を走らせて、山や海のそばで過ごす。そんなライフスタイルが現実のものになります。実際、近年ではキャンピングカーを拠点に、季節ごとにお気に入りの土地を巡る「移動生活」を選ぶ人も増えています(出典:二地域居住等の最新動向について)。
必要なのは、暮らしをしっかり支えてくれる“拠点の一つ”としての土地。そこにキャンピングカーを停めることで、どこへでも動けるベースができあがります。移動できるのに、帰ってくる場所がある。そんな柔らかさが、心を自由にしてくれるのかもしれません。
災害時の避難拠点としても活用できる
万が一のとき、頼れる場所があるかどうかで、人の不安はずいぶん変わってきます。キャンピングカーは、ただの移動手段ではなく、非常時には「動く避難所」として心強い存在になります。
実際に、災害時にキャンピングカーが役立ったという声は多く、ある調査では98.3%の人が「避難時に役立つ」と回答し、91.2%が“プライバシーの確保”を特に評価していました。
たとえば、大規模停電が続いた地域では、自家電源付きのキャンピングカーが暖房や冷蔵庫の代わりとなり、寒さや食料管理の不安を軽減したケースもあります。家族単位で過ごせる空間が確保されていることは、避難所では得がたい安心感につながります(出典:参考資料)。
災害は、待ってはくれません。でも、自分で用意した「小さな拠点」があるだけで、守れる日常のかけらが増える。そんな備えのかたちとして、キャンピングカーという選択肢は、静かに価値を持ち始めています。
土地を買ってキャンピングカーに住む7つのデメリット

キャンピングカー生活には自由や柔軟性といった魅力がありますが、良い面ばかりではありません。
土地を買ってキャンピングカーに住むという選択肢には、実際の暮らしの中で直面しやすい「7つのデメリット」も存在します。
憧れだけで進めてしまうと、後悔につながるリスクも。ここでは、事前に知っておくべき注意点を具体的に掘り下げていきます。
住民票を取れず行政手続きに支障が出る
キャンピングカーに暮らすこと自体は自由ですが、住民票をそこに置くことはできません。ここが大きな落とし穴になります。
日本の制度では「住民票=固定された住居」に限られており、移動できる車両は登録先として認められていません(出典:住民基本台帳法)。もし住所がない状態になると、免許の更新や健康保険、年金、銀行口座の手続きなど、日常生活に直結する部分で不都合が次々と出てきます。
実際にバンライフを続けている人の多くは、実家や知人宅を“書類上の住所”として借りる形で解決しています。郵便物はコンビニ受け取りや営業所止めを利用するケースも少なくありません。
つまり、土地を買ってキャンピングカーに住むと決めても、「住民票をどこに置くか」を真剣に考えておかないと、想像以上に生活が回らなくなります。これは避けて通れない現実です。
法的規制や条例により居住が制限される場合がある
キャンピングカーを買って、自分の土地に停めて、そこでのんびり暮らす——想像するとちょっとワクワクしますよね。ただ、現実はそう甘くありません。思わぬところに、法律の壁が立ちはだかります。
たとえば、「建築物かどうか」という線引き。知られていないことが多いのですが、キャンピングカーやトレーラーハウスでも、設置の仕方次第で“建築物扱い”になることがあります。地面に固定された階段を設置したり、電気や水道を直結したりすると、法律上はもはや「動かせる車」ではなく「定着した建物」と見なされるのです(出典:参考文献)。
そうなると、建築基準法の対象になり、建築確認申請が必要になったり、違反建築物として指導を受ける可能性も出てきます(出典:参考資料)。
さらに、自治体ごとの条例も侮れません(出典:トレーラーハウス条例)。「景観を損なう恐れがある」「用途地域にそぐわない」と判断されると、そもそも設置を許可してもらえないケースもあります(出典:景観法および景観法施行令)。たとえ自分の土地でも、です。
このあたりの事情、実際に生活を始めてから気づいても遅いです。場合によっては、撤去を命じられたり、住民トラブルに発展することさえあります。ですから、土地を買ってキャンピングカーに住むというライフスタイルを選ぶなら、購入前に必ず市町村の建築課や都市計画課に相談しておくことを強くおすすめします。
社会的に居住が認められず追い出されるリスク
たとえ土地を購入してキャンピングカーを置いたとしても、「ここに住みます」と胸を張って言える環境ばかりではありません。法律が許しても、周囲の目や地域の空気まではコントロールできないのが現実です。
実際、SNSや掲示板では「変な人が住み着いた」「キャンピングカーがずっと止まってて不安」といった声が時折見られます。特に住宅街や人目につきやすい場所では、近隣住民からの苦情が出て、最悪の場合、自治体から立ち退きを勧告されることもあります。道の駅や公園でのトラブルも過去に報道されています。
つまり、物理的には住めても、地域に「受け入れられるか」は別問題です。自由な暮らしを選ぶ代わりに、周囲との摩擦や孤立を覚悟しなければならないかもしれません。
キャンピングカーの維持費が高くなりやすい
キャンピングカー生活に憧れているなら、ひとつ覚悟しておきたい現実があります。それが「維持費の重たさ」です。
もちろん、車ですから税金や保険料、車検費用などは当然として、それに加えてガソリン代、メンテナンス費、時には駐車場代まで積み重なっていきます。例えば、ある程度しっかり装備された車両を持っていると、年間30万~60万円前後は当たり前。中には100万円近くかかる人もいます。これは、使い方によって大きく差が出る部分です。
特に見落とされがちなのが、修理費やタイヤ交換などの“突発的な出費”。キャンピングカーは構造も複雑で、エアコンや冷蔵庫、サブバッテリーなど普通車にはないパーツも多く、ちょっとした故障でも出費がかさみがちです。
自由気ままな暮らしの裏には、そうした「想定外のコスト」も潜んでいます。キャンピングカーは確かに家賃のいらない住まいかもしれませんが、維持にかかるお金のことは、甘く見ない方がいいと実感しています。
水道電気などインフラ整備に多額の費用がかかる
キャンピングカーで自由気ままな暮らしを描いていたはずが、いざ“生活拠点”として土地に落ち着こうとすると、意外な落とし穴が見えてきます。その代表が、水道や電気といったインフラの整備費です。
たとえば、電気の引き込み工事には約10万円~、水道と排水の整備には30万円以上が目安とされており、地域や土地の状況によっては50万円を超えるケースも珍しくありません。しかも、田舎で安く土地を手に入れた場合ほど、インフラの整備費は高くつく傾向があります。
もちろん、タンクやソーラーパネルで工夫して暮らす人もいます。ただ、手間や不便さはどうしても避けられません。「今日は水をどこで補充しよう」「曇りが続いてバッテリーが心配」と、自由の裏に“暮らしの重み”がのしかかってくるのです。
憧れのキャンピングカー生活を現実にするためには、こうしたインフラの整備費をあらかじめ計算に入れておくことが、失敗しない第一歩と言えるでしょう。
土地の整備や準備に時間と手間がかかる
キャンピングカー生活の自由さに憧れて土地を購入しても、いざ住む段階になると、思った以上に「整える工程」が待ち構えています。山林や原野のような安価な土地ほど、その傾向は強まります。
たとえば、ただ車を停めるだけならまだしも、雨水が溜まらないよう地面を均す「整地」、そして電気や水道といったライフラインの整備が必要です。特に電柱のない土地だと、電気の引き込みに20~30万円、水道工事に関しては井戸を掘る選択をすると50万円以上の出費になるケースもあります。
しかも、それらはお金だけでなく“時間”も食います。役所に何度も出向き、法的な条件や条例の確認をしたうえで業者とやりとりしなければなりません。「買ったらすぐ住める」と思っていた理想と現実のギャップに、疲れを感じてしまう人も少なくないのが実情です。
収納や生活空間が狭く快適性に欠ける
「自由な暮らし」に憧れてキャンピングカーでの生活を始めたものの、最初にぶつかるのが“モノの多さ”です。普段意識していなかった日用品や服が、わずか数畳の車内では急に存在感を放ち始めます。「これ、置き場所どこにしよう?」そんな悩みは、ほぼ毎日起きます。
実際、キャンピングカーの車内面積はおおよそ4~8㎡程度が一般的で、ベッドやテーブル、収納棚を置けばすぐに足の踏み場もなくなります。さらに、ファミリーで暮らすとなると、プライベートの確保はほぼ不可能です。空間の狭さは、物理的な不便さだけでなく、心の余裕にも直結してくるのが正直なところです。
ただ、すべてがマイナスというわけでもありません。収納をシビアに見直すことで「本当に必要なものだけに囲まれて生きる」という選択肢も見えてきます。ミニマルな生活は、想像以上に気持ちを軽くしてくれるものです。とはいえ、その「心地よさ」にたどり着くまでは、少しの覚悟と試行錯誤が必要になるのもまた事実です。
土地を買ってキャンピングカーに住むのに向いている人の特徴

キャンピングカーでの暮らしは、すべての人にとって理想的とは限りません。
とはいえ「土地を買ってキャンピングカーに住むのに向いている人の特徴」を理解しておくことで、自分がこのライフスタイルに合っているかを見極めやすくなります。
ここでは、実際にどんな価値観や生活スタイルの人が快適に続けられるかを具体的に紹介していきます。
いろんな地方を旅してまわりたい人
「いつか日本中を旅しながら暮らしたい」──そんな想いを胸に抱いてきた人には、キャンピングカー生活はまさに理想のかたちです。自由な移動手段を手に入れることで、春は桜の名所へ、夏は高原の避暑地へ、冬は温泉地へと、気候や気分に合わせて住む場所を変えられるからです。
現に、近年では“バンライフ”というライフスタイルが注目を集めており、2024年時点でキャンピングカーの保有台数は全国で16万台を超えました(出典:参考データ)。週末に短期の旅を楽しむ人もいれば、四季に合わせて全国を巡る“遊牧型”の生活を実践する人も増えてきています。
実際、ネット環境さえ整えばどこでも働ける職種も増えており、都会に縛られない新しい暮らし方として、このスタイルを選ぶ人が静かに増えているのです(出典:令和6年度 テレワーク人口実態調査)。旅を暮らしに変えるという選択肢は、今や夢ではなく、現実として手に届く時代に入ってきたと言えるでしょう。
他人と違う自由な生活を求める人
「みんなと同じじゃ、つまらない」——そんな思いを胸に抱く人にこそ、キャンピングカーで暮らすという選択は刺さるかもしれません。決まった場所に住まないというのは、まさに“住まいの常識”に風穴を開ける生き方。どこに拠点を置くかさえ、自分で決められるのです。
実際、ネット上ではキャンピングカーで暮らす人たちの暮らしが多数発信されています。たとえば大学生の青年が自作したキャンピングカーで日本各地を巡りながら生活していた例や、夫婦でフルリモートワークをしながら山間の土地で自立した暮らしを送る姿も見られます。そこには、型にハマらない自由がありました(出典:バンライフ女子大生、自由な車上生活を選んだ訳)。
だからこそ、周囲の目を気にせず、自分の価値観を大切にして生きたい人には、「土地を買ってキャンピングカーに住む」という選択が、単なる移動手段や住まい以上の意味を持ってきます。誰かの「正解」ではなく、自分の「納得」で生きる。そんな人生を望むなら、これは挑戦する価値のあるライフスタイルです。
リモートワークなど場所に縛られず働ける人
「今日は湖のほとりで、明日は山の麓で」。そんな働き方が現実になった今、キャンピングカーで暮らすという選択肢は、単なる夢ではなくなりました。
テレワークが定着した今、会社に毎日出勤しなくても成り立つ仕事がぐっと増えました(出典:テレワークの導入状況)。Wi-Fiさえ確保できれば、どこにいても仕事ができる──その自由を最大限に活かせるのが、キャンピングカー生活です。
たとえば広めのダイネット付きのモデルなら、椅子に腰かけてノートPCを開けば、そこはもう立派なマイ・オフィス。ソーラーパネルやポータブル電源を装備すれば、電力の心配もぐっと減ります。
実際に「キャンピングカーでリモートワークをしている人」の事例は着実に増えており、メーカーや専門サイトでも“働ける車内空間”に関する特集が組まれています。自然に囲まれた静かな環境で仕事をすれば、集中力も高まり、生産性の向上も期待できます。
もちろんすべてが快適というわけではありませんが、「どこで働くか」を自分で選べるという感覚は、都会のマンションでは得られない解放感があります。場所に縛られずに働くスタイルをすでに実践している人にとって、「土地を買ってキャンピングカーに住む」という暮らしは、理にかなった次のステップかもしれません。
生活をシンプルにして物を減らしたい人
物に囲まれていると、なぜか心まで窮屈になりますよね。思い切ってキャンピングカーで暮らし始める人の多くは、「持ちすぎていた」と気づくことで、暮らし方そのものを変えていきます。
実際、ある女性は服を300着から40着にまで減らし、スーツケース1つで暮らすようになったそうです。スペースに限りがあるからこそ、本当に必要なものと向き合うことになるのです。毎日使うもの、大切にしたいものだけを残していく感覚は、単なる“片づけ”ではなく、生き方の棚卸しに近い体験です。
そして不思議なことに、モノを手放すほど、心は軽くなっていきます。何を捨てて、何を残すか。その判断を重ねていくうちに、自分の価値観がクリアになる感覚が生まれてきます。大げさではなく、「自由になった」と語る人が少なくありません。
もし、モノを減らして、もっと軽やかに暮らしたいと考えているなら。キャンピングカー生活は、その一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。物理的にも精神的にも、「足るを知る暮らし」を体験できるライフスタイルです。
チャレンジ精神があり困難も楽しめる人
「誰かと同じ生き方じゃ、どうしても落ち着かない」。そんな気質を持つ人にとって、キャンピングカーでの暮らしはただの手段ではなく、自分らしく生きるための選択肢になり得ます。
たとえば、全国を巡るバンライファーたちの多くは、炎天下の駐車場や静まり返った道の駅で夜を越えています。エアコンなし、狭い空間、時には虫も出る。それでも、朝一番に車窓から見える景色や、静かな森の中で飲む一杯のコーヒーに救われる。そんな日々を「ちょっと不便な贅沢」と捉えられる人は、きっとこの生活に向いています。
実際、バンライフ情報サイトでは、「バンライフの現実は虹ばかりではない」と正直に記されています。ですが、同時に「心構えさえできていれば、たいていの困難は問題にならない」とも述べられています。
設備の不便さ、天候への対応、インフラの問題など、乗り越えるべき壁は多いかもしれません。ただ、そうした「ひとクセある日常」をポジティブに変換できる人にとって、キャンピングカー暮らしは“冒険”そのものです。自分で選んだ不自由だからこそ、そこには妙な誇りと面白さがあるのかもしれません。
【参考情報】土地を買ってキャンピングカーに住む場合の価格
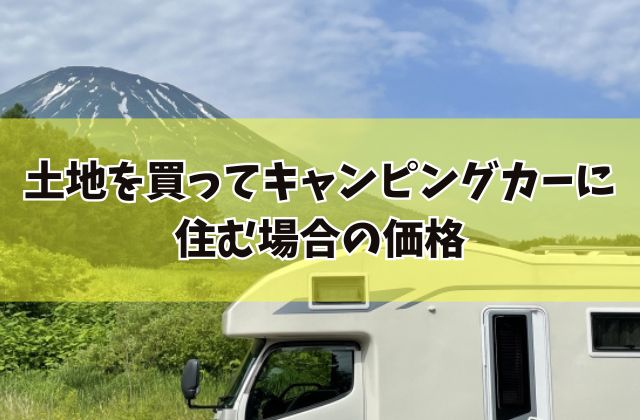
キャンピングカーでの生活を現実的に考えるなら、「土地を買ってキャンピングカーに住む場合の価格」は避けて通れない重要なポイントです。
土地の広さや立地条件によって購入費用は大きく変わりますし、車両そのものの価格やインフラ整備にかかる費用も見逃せません。
ここでは、必要な土地の広さと相場、キャンピングカー本体の価格帯、さらに初期費用や毎月かかる維持費まで、具体的な金額を交えて詳しくご紹介します。
実際に土地購入・キャンピングカー購入前の具体的な計画を立てる情報として、ぜひ役立ててください。
必要な土地の広さと価格
キャンピングカーで暮らすなら、まず考えるべきは「どのくらいの土地があれば安心して停められるか?」という点です。実際のところ、最低限のスペースとしてよく目安にされるのが、幅4メートル×奥行き7メートル=約28㎡。この広さがあれば、ドアを開けて出入りできるし、ちょっとした荷物の出し入れにも不便しません(出典:RVパーク開設説明資料)。
でも実際に生活するとなると、それだけじゃちょっと窮屈かもしれません。たとえばトレーラーハウスの上位モデルでは、40㎡(約12坪)ほどのスペースが必要とされています。室内での動線を考えたら、このくらい余裕があると快適に暮らせます。
肝心の土地価格については、都心部では現実的でない額になる一方で、郊外や地方に目を向ければ、数十万円~数百万円で手が届く場所もあります。特に用途地域が「市街化調整区域」などに当たれば、価格はグッと下がりますが、住宅用に使えないケースもあるので注意が必要です。
結論としては、「最低28㎡、できれば40㎡以上」がひとつの目安。そして、場所選びによって価格帯は大きく変動します。キャンピングカー生活を始めるなら、土地探しは“安さ”よりも“使いやすさ”を基準にするのが後悔しないポイントです。
キャンピングカーの価格
キャンピングカーに住む暮らしを本気で考えはじめたとき、最初にぶつかるのが「いくらかかるのか?」という現実的な壁です。ロマンだけじゃ走り出せません。
結論から言えば、キャンピングカーの価格はピンからキリまで。軽自動車ベースのいわゆる“軽キャン”なら、200万円台から新車で手に入ります。手頃で取り回しもラクなので、はじめての一台として選ばれることも多いです。
一方で、車内にシャワーやベッド、キッチンなどを備えた本格派の「キャブコン」タイプになると、500万円~1,000万円ほどは見ておいたほうがいいでしょう。さらにその上、バスのような大型キャンパーになると1,000万円超えも普通にあります。
たとえば、2025年時点での実際の相場を参考にすると、バンコンタイプは300万円~800万円程度、キャブコンタイプは450万円~1,100万円台が目安とされています。もちろん中古車市場を探せば、もっと安く手に入ることもありますが、状態によってはメンテナンス費用がかさむ場合もあります。
重要なのは、「家代わり」として本気で使うなら、最低限の装備では物足りなくなるかもしれないという点です。日常生活に必要な快適さを求めるなら、300万では足りない、と感じることもあるはずです。
価格を見ると少し尻込みするかもしれませんが、「動く家」を持つという自由さは、お金には代えがたい価値をくれるはずです。
その他必要経費を総額および毎月で算出
キャンピングカーで暮らすと決めたとき、真っ先に気になるのは「どれくらいのお金がかかるのか」という現実的な話。土地代や車両代に目が行きがちですが、実際に生活を始めてみると、それ以外にも毎月じわじわと出費はあります。
たとえば、すでにバンライフを実践しているご夫婦の事例では、月の生活費は約15万円(2人分)というデータがあります。この中には、ガソリン代や食費、キャンプ場や駐車場の使用料、車のメンテナンス代なども含まれています。つまり、住む場所が車に変わっても「日々の暮らし」にかかるお金はそれなりに発生するということです。
もう少し現実的に比較するなら、都市部でワンルーム(20~40㎡)を借りた場合、家賃の相場は月5~7万円ほど。つまり、「キャンピングカーに住めば固定費がゼロになる」とは言い切れないのが実際のところです。逆にいえば、生活コストが劇的に下がることを期待しすぎない方が、後々のギャップに悩まされずに済みます。
初期費用を抑えたい人は、中古のキャンピングカーや安価な土地を選ぶなど工夫の余地があります。ただし、目に見えない維持費も含めて、月々10~15万円前後は生活費として見積もっておくと安心です。自由な暮らしを手に入れるためには、経済的な「リアル」から目を背けず、しっかりと計画を立てることが欠かせません。
【無料】住むのに必要な理想の土地を効率良く探せる方法

「キャンピングカーで住むために最適な土地の選び方が分からず迷っている」
「住める土地の条件や法的な制限について調べても情報がバラバラで不安になる」
「費用を抑えつつ、インフラ環境が整った土地を効率よく見つけたい!」
あなたも、上記のように悩んではいませんか?
理想の土地を探すのは至難の業。まして、人生で一番高い買い物で失敗なんて、笑えませんよね。
でも実は、そんな悩みを解決する住むのに必要な理想の土地を効率良く探せる方法があります!
それが、540,000人以上が利用した“一番いい”物件情報がもらえる『タウンライフすまいリクエスト』です。
「タウンライフすまいリクエスト」とは、物件の希望条件を入力するだけで、複数の不動産会社から最適な物件提案や資料が一括でもらえる無料の比較サービスです。
- 非公開物件&値下げ物件の情報がもらえる!
複数社への一括依頼により、広告掲載前や値下げ前の“掘り出し物件”に出会える可能性が高まる - 物件探しの手間・時間を大幅に削減できる!
60秒の簡単入力だけで、複数の不動産会社から資料・提案が一括で届くので、自分で探す手間が省ける - 信頼できる複数の不動産会社の中から選べる!
登録企業は全国170社以上、独自基準をクリアした優良な不動産会社に限定。安心して比較・選択ができる
さらに!タウンライフすまいリクエスト利用者限定で2つの特典が必ずもらえるプレゼントを実施中!
筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、40ページを超える読み応えありの内容で、今後の物件探しのヒントが満載でした。
少しでも効率良く“一番いい物件”を探したい方は、ぜひプロが選んだ物件提案を一括で受け取って、後悔しない住まい選びを今すぐ始めてみてください。
【Q&A】土地を買ってキャンピングカーに住むことのよくある質問

最後に土地を買ってキャンピングカーに住むことのよくある質問をまとめました。
実際によくある疑問にわかりやすく答えていきます。判断材料としてぜひ活用してみてください。
キャンピングカーで暮らす場合に税金はどうなるの?
キャンピングカーでの生活に憧れる方が増えている一方で、気になるのが「税金ってどうなるの?」という疑問。実は、家のように暮らしていても、税の扱いは「車両」としての課税になります。
つまり固定資産税はかかりませんが、自動車税(種別割や軽自動車税)、車検ごとの自動車重量税、それに自賠責保険などが毎年・数年ごとに必要になります。東京都では排気量に応じて年額で課税され、重量税は車検時に納める仕組みです。「家の代わり=家の税金」とはならないので、毎年かかる維持費を事前に把握しておくと安心です。
キャンピングカーで生活したら住所はどうすればいいですか?
キャンピングカー暮らしを始める際に、多くの方がつまずくのが「住民票はどこに置くの?」という問題です。法律上、住所は「生活の本拠」である場所に置く決まりになっています(出典:民法|第22条「住所=各人の生活の本拠」)。
たとえば、一年の大半をある場所で過ごしているなら、そこを住所として届け出るのが基本。ただ、キャンピングカー生活は移動が前提となるため、特定の土地に安定して住んでいるとは言いにくいのが現実です。ですから、行政手続きや郵便の受け取りのことを考えると、家族の実家や知人の住所を借りるなど、実務的に対応できる「拠点」をひとつ確保しておくのがベストです。
キャンピングカーをはじめ車に住むことは違法ですか?
「車に住むって、そもそも違法なの?」と心配になる方も少なくないでしょう。結論から言うと、私有地や許可された場所でのキャンピングカー生活自体は、法的に問題ありません(出典:民法206条「所有権の内容」)。
ただし、公道や道の駅の駐車場など、公共の場所での長時間滞在や宿泊となると話は別。特に道の駅では、休憩目的に限った利用が前提で、車中泊はマナー違反とされることもあります。トラブルを避けるためには、あらかじめRVパークやキャンプ場など、滞在を認めている場所を選んでおくと安心です。
土地だけ買ってトレーラーハウスを置けるの?
「家の代わりにトレーラーハウスを置いたらどうか」と考える方も増えています。結論としては、条件さえ整えば土地にトレーラーハウスを設置することは可能です(出典:参考文献)。
国の通達では、車輪が付いていて移動可能であること、水道・電気などの接続が工具なしで簡単に外せること、そして地面に固定されていないことなど、いくつかの要件を満たしていれば「建築物」とは見なされません。ただし、ウッドデッキなどを追加して固定してしまうと、法律上は建物扱いになってしまい、建築確認申請が必要になる可能性があります。自由さを活かすなら、設置方法には細心の注意が必要です。
なぜキャンピングカーはやめとけと言われるの?
SNSなどで「キャンピングカーはやめとけ」との声を見ると、不安になる方もいるかもしれません。実はこの言葉の背景には、想像以上の維持コストがあります。
毎年の自動車税、定期的な車検とその費用、任意保険、燃料代…車としての経費は意外とバカになりません。さらに、泊まれる場所が限られているため、常に駐車場や宿泊場所を確保しなければならず、その手間も無視できません。自由で魅力的なライフスタイルである一方、維持面の現実をしっかり把握しないと、理想とのギャップに苦しむことになります。
キャンピングカーは家代わりになるの?
「家がわりにキャンピングカー」という発想は魅力的ですが、法的にはあくまで“車”として扱われます。そのため、住宅ローン控除や住宅に関する固定資産税の軽減など、住まいとしての恩恵は一切受けられません(出典:参考資料)。
また、土地に据え置いて電気や水道を常時接続するような使い方をすると、「建築物」として扱われ、建築基準法の適用対象になることもあります。気軽に始めたつもりが法律に抵触してしまう可能性もあるため、「どこまでが車」「どこからが建物」という線引きは事前に確認しておくべきポイントです。
まとめ:土地を買ってキャンピングカーに住むメリット・デメリット
土地を買ってキャンピングカーに住むメリット・デメリットをまとめてきました。
改めて、土地を買ってキャンピングカーに住むメリット・デメリットをまとめると、
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
そして、土地を買ってキャンピングカーに住むために押さえておきたい5つの結論もまとめると、
- 土地を買ってキャンピングカーに住むことは法律上は可能だが、地域ごとの条例や用途制限に注意が必要
- 自由な移動や住宅ローン不要といった大きなメリットがある一方、行政手続きや社会的な認知には課題が残る
- 土地代は地域により大きく差があり、キャンピングカー設置には最低でも10坪(約33㎡)以上は確保したい
- キャンピングカー本体の価格は新車で500~1,000万円、中古なら300万円前後が相場
- ガソリン代、保険、駐車場代など維持費を含めて毎月10~15万円ほどの生活費が必要
土地を買ってキャンピングカーに住むというライフスタイルは、固定観念にとらわれない自由な暮らしを求める人にとって魅力的な選択肢です。
経済面や法的条件をしっかり確認しつつ、現実的な生活設計を立てることが成功のカギになります。夢を現実に変えるには、情報と準備がなによりの味方です。