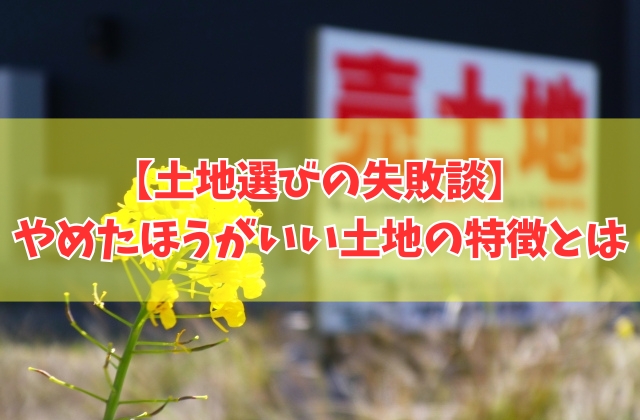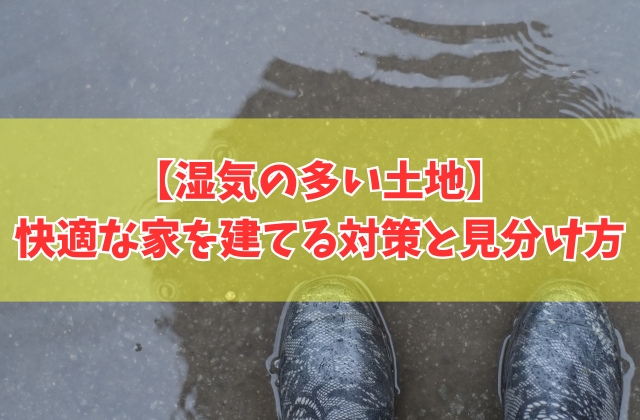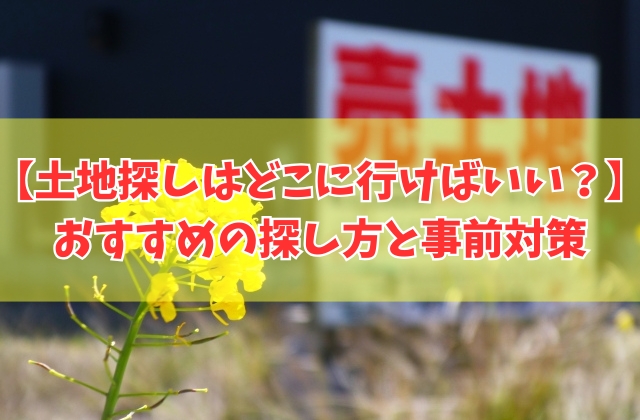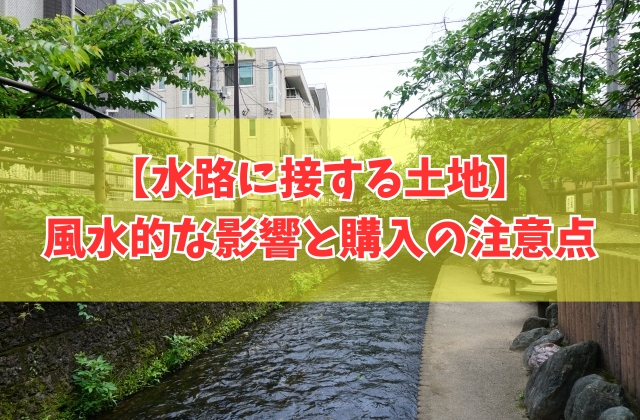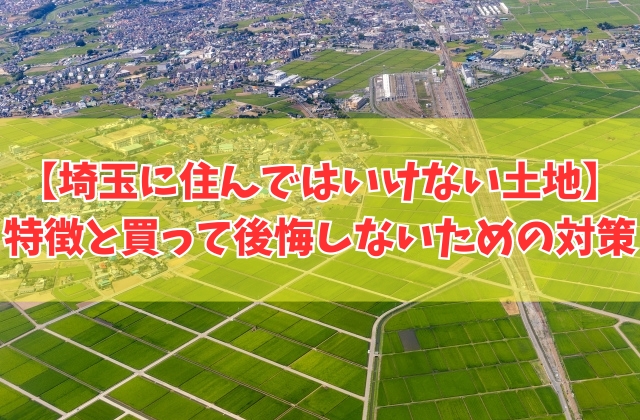「二筆の土地に家を建てるメリットデメリットは?」
「合筆する注意点は?理想の土地を効率良く探す方法はあるの?」
家づくりを始めるとき、土地の形や登記の状態が思った以上に重要であることに気づく方も多いのではないでしょうか。
特に「二筆の土地に家を建てる」ケースでは、建築基準や登記、将来の相続や売却を見据えた判断が必要になります。
安易に進めると後で思わぬトラブルや費用が発生することもあるため、事前の確認が欠かせません。
この記事では、二筆の土地に家を建てる際に押さえておきたいメリットと注意点を、わかりやすく丁寧に解説します。
- 二筆の土地は合筆・分筆どちらも可能だが、目的や将来設計に合わせた選択が必要
- 登記や抵当権など権利関係の確認を怠ると手続きに支障が出る可能性がある
- 固定資産税や建ぺい率など税制・法規面の影響も考慮して計画を立てることが大切
二筆の土地に家を建てるには、法的・登記的な手続きに加え、将来の使い方や相続まで見越した判断が求められます。建築や税制面での影響も含めて、事前にしっかりと準備することが後悔しない土地活用の第一歩です。
では、どうやって土地情報を集めればいいのか?できればネットで簡単に、情報がもらえる方法があれば楽ですよね。
そんな忙しい方におすすめなのが、累計540,000人以上が利用する人気の『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
「二筆の土地に家を建てる」とは

地番が2つに分かれている土地でも、ひとつの家を建てることは可能です。つまり「二筆の土地に家を建てる」とは、登記上では2筆に分かれていても、建築上はひとつの敷地として扱い、家を建てることを指します。
なぜそれが可能なのかというと、建築基準法では「筆数」が問題になるわけではなく、敷地が一体となっていれば建築可とされるからです。ただし、これは2筆の土地が隣接していて、かつどちらも同じ所有者名義であることが前提になります。
たとえば、相続で得た土地がもともと2筆に分かれていた場合でも、両方が自分名義なら、特別な手続きをしなくても住宅は建てられます。ですが、もし一方に抵当権が設定されていたり、共有名義だったりすると、建築確認の審査でつまずく可能性があります。
不動産登記と建築法の「考え方のズレ」を知っておくことが、後々のトラブル防止にもつながります。家を建てる前には、土地の状態をきちんと確認しておきましょう。
二筆の土地に家を建てる場合の方法
隣接した二筆の土地に家を建てたい場合、もっとも安心でスムーズな方法は「合筆登記」をして一筆の土地にまとめてから建築することです。
建築基準法では、原則として「1つの敷地に1つの建物」が求められます。つまり、登記簿上で土地が2つに分かれているままだと、役所の審査でストップがかかるケースもあるのです。とくに住宅ローンの審査や建築確認申請では、土地の筆数が引っかかることがあります。
たとえば、親から相続した土地が2筆に分かれていた場合でも、地続きで名義が自分ひとりなら、合筆して一筆にすれば、土地全体を「1つの敷地」として扱えるようになります。このひと手間をかけるだけで、建築の手続きもスムーズに進みやすくなります。
まとめると、二筆の土地で家を建てたい場合は、土地が隣同士で所有者が同じなら、合筆してしまうのがもっとも確実な方法です。無駄なトラブルを避けて、安心して家づくりを始められるようになります。
二筆の土地に家を建てる際の注意点
二筆の土地に家を建てる際にまず気をつけたいのは、「登記の状態が建築に影響する」という点です。見た目はつながっていても、登記内容がバラバラだと後々トラブルの元になります。
というのも、合筆や建築確認を行うには、両方の土地が同じ所有者名義で、地目や用途地域などの条件も揃っていないと申請が通らないケースがあるためです。とくに注意したいのが、片方の土地に抵当権や地役権がついていた場合。こうした権利関係が引っかかると、思わぬ足止めを食らうことになります。
たとえば、2筆の土地のうち1筆だけが農地だったり、異なる用途地域に属していたりすると、建ぺい率や容積率の制限が変わってきます。これに気づかず計画を進めると、希望の間取りが建てられないということにもなりかねません。
だからこそ、家づくりの第一歩として、登記簿や用途地域、所有権の状況などを細かくチェックすることが欠かせません。安心して家を建てるためには、土地の中身を「書類ベース」で把握しておくことが何より大切です。
二筆の土地に家を建てるメリット6選

二筆の土地に家を建てると聞くと、手続きが煩雑で不利に思えるかもしれませんが、状況によってはむしろ大きな利点になることもあります。
所有や相続、税金面など、工夫次第で有利に働くケースが多々あるため、まずはその具体的な利点を知っておくことが大切です。
ここでは、二筆の土地に家を建てるメリット6選として、代表的なポイントをわかりやすくご紹介します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 土地を別々に登記できる | 所有者や持分を明確にでき、将来の売却や相続トラブルを防ぎやすくなる。 |
| 抵当権を必要な土地だけに設定できる | 住宅ローンの担保範囲を限定することで、他の土地の自由度を確保できる。 |
| インフラ整備の費用を節約できる | 二筆を一体利用すれば、水道・電気などの引き込み工事を一本化でき、費用負担が軽減される。 |
| 相続での土地の扱いがしやすくなる | 土地を分けておけば、相続人ごとに明確に分配でき、手続きや税務処理もスムーズになる。 |
| 土地の形状を整理して使いやすくなる | 形の悪い土地を分筆で整えれば、建物配置や庭の設計がしやすくなる。 |
| 固定資産税の評価額が下がる可能性 | 形状や利用方法によっては評価額が抑えられ、税負担の軽減につながる。 |
土地を別々に登記できることで所有関係を明確にできる
二筆の土地をあえて別々に登記することには、大きな意味があります。最もわかりやすいのは、「誰がどの土地を持っているのか」が書類上ではっきりと区分される点です(出典:登記 -不動産登記-)。
たとえば、兄弟や親子で将来的に土地を分けて相続したいという場合、分筆して登記しておけば、あとから所有割合で揉めるリスクをぐっと減らせます。登記簿を見れば一目で分かるので、話し合いがスムーズになるのです。
実際、ひと筆のまま所有していると、「売るのはこの部分だけ」というやり取りが複雑になりますが、登記が分かれていれば、片方だけを売却することも可能になります。登記の分離は、資産管理の柔軟性を高めてくれる手段でもあります。
つまり、土地を二筆に分けて登記することは、単に形式上の問題ではなく、将来にわたるトラブル回避や資産運用の自由度に直結する、大切な準備とも言えるでしょう。
ローンの抵当権を対象の土地だけに設定できる
土地が二筆に分かれている場合、住宅ローンを組む際に必要な筆だけに抵当権を設定できることがあります。これは資産を守るうえで、実はかなり大きなメリットです。
たとえば、家を建てるのはAの土地だけ。隣接するBの土地には駐車場や家庭菜園をつくりたい、あるいは将来的に売却や貸し出しを考えている。そんなとき、Aの土地だけに抵当権を設定できれば、Bの土地の自由度は保たれます。
実際、土地が一筆だと、ローンの担保に土地全体が自動的に組み込まれてしまいますが、筆が分かれていれば「どこまでを担保にするか」が選べる余地が出てきます。これは将来の売却、建て替え、相続の柔軟性を確保するうえでも重要な判断材料になります。
住宅ローンを利用する際、二筆のまま登記しておくと、このように不動産の一部を守る選択肢が残せるという点で、資産管理の戦略としても非常に効果的です。
インフラ整備の費用を節約できる可能性がある
二筆の土地に家を建てると聞くと、費用が増えそうな印象を受けるかもしれません。ところが、インフラの整備に関しては、むしろ費用を抑えられるケースもあるのです。
たとえば、上下水道や電気の引き込み工事を考えるとき、2筆の土地をあえて一体として扱えば、申請や工事が一本化できます(出典:参考資料)。これによって、複数回に分けた工事が不要になり、施工費や手続きの手間を削減できるのです。
実際、まだインフラが通っていないエリアでは、引き込みのたびに数十万円単位の費用が発生します。一度で済ませられれば、そのぶんコストは明らかに軽くなります。
土地が二筆あっても、それをどう活用するかで支出は大きく変わります。インフラにかかる初期費用を抑えたいなら、「まとめて整備する」という視点は見逃せないポイントです。結果的に、家づくり全体のコストパフォーマンスにもつながってきます。
将来の相続で土地の扱いがしやすくなる
土地の相続は、ただでさえ親族間で揉めやすいもの。とくに1筆の土地を複数人で分けるとなると、「誰がどこを使うのか」「売るのか、残すのか」で話がこじれるのは珍しくありません。
けれども、あらかじめ二筆に分けて登記しておけば、状況はぐっとシンプルになります。たとえば「Aの土地は長男、Bの土地は次男」といった具合に、物理的にも登記上も明確に分けられるため、相続の手続きが格段に楽になります。
また、評価額が分かれて算出されることで、相続税の計算がしやすくなるケースもありますし、不要な土地だけを単独で売るといった柔軟な選択も取りやすくなります。
土地をどう残すか、どこまで家族に負担をかけないか。そう考えると、登記の段階から“分けておく”という選択は、将来の相続に備えた立派な準備と言えるかもしれません。
土地の形状を整理して使いやすくなる
土地がいびつな形をしていると、建物の配置や外構の計画がどうしても制限されてしまいます。そんなときに効果的なのが、二筆の土地をうまく分筆・活用して形を整えるという方法です。
たとえば、L字型や極端に細長い土地の場合、そのままでは建てられる建物に限りが出てきます。しかし、不要な部分を切り離す、もしくは別の目的に活用するように分けて登記すれば、住宅スペースはぐっと使いやすくなります。
具体的には、自宅を建てるためにメインの筆を確保し、隣の小さな土地は駐車場や家庭菜園用として活用する。そんな使い分けができるようになれば、敷地全体に無駄がなくなり、結果的に生活動線もスッキリします。
「形の悪い土地だから…」とあきらめる前に、形状の整理で土地のポテンシャルを引き出す。そんな考え方が、理想の住まいづくりには大切です。分筆によって土地を「整える」という視点が、活用の幅を広げてくれます。
固定資産税の評価額が下がる可能性がある
土地の税金は、形や使い方で思いのほか変わってくるものです。実は、二筆の土地をそのまま分けて使うことで、固定資産税の評価額が下がるケースもあるのをご存じでしょうか。
というのも、土地の評価額は、広さや形状、接道状況などに応じて決まります(出典:土地家屋の評価)。たとえば、分筆によって一部が細長くなったり、不整形な土地になった場合、その分「使い勝手が悪い」と評価され、評価額が抑えられる可能性があるのです。
これは、整形地よりも市場価値が下がると見なされるためで、結果的に課税額にも影響が出ます。
実際に、旗竿地や間口の狭い土地などでは、評価が1?2割下がることもあるといわれています。その影響で、年間の固定資産税が数万円単位で軽減されることもあるのです。
もちろん、すべての土地が当てはまるわけではありませんが、「土地の分け方ひとつで税金が変わる可能性がある」と知っておくだけでも、後の選択肢に大きな差が出てきます。土地活用を考える際は、評価額の視点も忘れずにチェックしたいところです。
二筆の土地に家を建てるデメリット5選

二筆の土地に家を建てる選択は、柔軟な活用ができる一方で、見落としがちな落とし穴も存在します。
たとえば、敷地の制限により建物の設計が希望どおりに進まないことや、税金や登記手続きの負担が増すケースもあります。
事前に「二筆の土地に家を建てるデメリット5選」を知っておくことで、後悔のない土地活用がしやすくなります。
ここからは、その代表的なデメリット(注意点)について、順番に解説していきます。
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 土地が狭くなり建物が制限される可能性がある | 建築可能な範囲が限られることで、間取りや建物の大きさに制約が出る場合があります。 |
| 建ぺい率や容積率の制約で希望の家が建てにくい | 二筆にまたがる場合、建ぺい率や容積率が厳しくなり、理想の家が建てづらくなります。 |
| 分筆後に土地評価が上がり固定資産税増の可能性がある | 分筆によって土地の評価額が上がり、結果として固定資産税が高くなることがあります。 |
| 境界トラブルが起きやすくなるリスクがある | 隣接地との境界が不明確だと、所有権をめぐるトラブルや立ち合いの手間が発生しやすくなります。 |
| 分筆手続きや登記の際に費用負担がかかる | 登記費用や測量費、調査士への報酬などが発生し、合計で数十万円になる場合があります。 |
土地が狭くなり建物が制限される可能性がある
二筆の土地に家を建てる計画を立てる際、どうしても気をつけたいのが「建てたい家が本当に建つかどうか」という点です。分けた土地が狭くなりすぎると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
実は、建物を建てられる面積には法律でしっかりと上限が設けられており、「建ぺい率」や「容積率」によって制限されます(出典:建築基準法第2条および第52条)。たとえば、住宅地の建ぺい率が50%で、1筆あたりの面積が100㎡なら、建物は最大でも50㎡までというわけです。
仮に分けた土地が50㎡になってしまった場合、建てられる家の面積は25㎡。この広さで理想のマイホームを形にするのは、正直、かなり難しいはずです。この点が「二筆の土地に家を建てる」最大のデメリットだといえます。
だからこそ、土地を分筆して使う場合は「登記上の分け方」だけでなく、家の設計にどう響くかまで視野に入れておくべきです。図面だけでは見えてこない部分に、後悔の種が潜んでいることも少なくありません。
建ぺい率や容積率の制約で希望の家が建てにくい
「二筆に分かれた土地に家を建てたい」と考える方が、意外と見落としがちなのが建ぺい率と容積率の壁です。これが案外やっかいで、建てたい家の広さが思うように確保できない…ということが起こりえます。
たとえば、1筆が100㎡で建ぺい率が50%だった場合、1階は最大でも50㎡までしか建てられません。2階建てでも、容積率の制限があるため、合計100㎡を超えるとアウト(出典:参考資料)。こうした制限は、用途地域によって異なり、住宅地なら建ぺい率はおおよそ30~60%、容積率も100~200%が相場です。敷地が狭くなればなるほど、この制限はシビアに響いてきます。
「せっかくの注文住宅、リビングを広くしたい」「将来は子ども部屋も必要」といった希望があっても、法的に建てられるサイズに限界があるとなると、理想に届かないことも。仮に緩和措置があっても、地域や建築条件によっては利用できないケースも少なくありません。
土地の分け方次第で、家の間取りや快適さが左右される現実があります。設計に入る前に、まず建ぺい率と容積率をじっくり確認すること。それが後悔しない家づくりへの第一歩です。
分筆後に土地評価が上がり固定資産税増の可能性がある
土地を二筆に分けると、意外な落とし穴があるのをご存知でしょうか。分筆によって、これまで適用されていた小規模住宅用地の特例から外れてしまうことがあり、その結果、固定資産税が跳ね上がるケースが実際に起きています(出典:土地についての特例)。
たとえば、もともと「一体の住宅用地」として評価されていた広い土地を分けて登記した場合、それぞれの筆が住宅用の要件を満たさないと判断されれば、特例は適用されません。その瞬間、評価額は通常水準に戻り、税額も比例して増加します。
実際に「固定資産税が倍近くに増えた」と悩む声も珍しくありません。分ければ節税になると思い込んで進めると、かえって損をする結果になりかねません。分筆前には、税務署や不動産の専門家に評価基準や特例の適用条件をしっかり確認しておくことが大切です。
境界トラブルが起きやすくなるリスクがある
二筆の土地に家を建てようと考えたとき、意外と見落とされがちなのが「境界」にまつわる問題です。土地を分けて使うこと自体は自由ですが、その境目が曖昧だと後々やっかいなトラブルを引き起こします。
例えば、隣地との間に昔からあったブロック塀が、本当に境界線上にあるのかはっきりしない──そんな状況、実は珍しくありません。現地の杭がズレていたり、古い図面と実際の土地の形が一致していなかったりと、思わぬ誤差が出ることも。測量をやり直した結果、隣地の所有者と見解が食い違い、話し合いが長引くケースもあります。
分筆登記を行うには、土地の正確な境界を示す測量と、それに対する隣地所有者の同意が必要です(出典:参考資料)。ですが、もし相手が不在だったり、関係がこじれていたりすれば、手続きがストップする可能性も否定できません。
境界問題は「起きてからでは遅い」と言われる理由がここにあります。これから二筆の土地で家を建てようと考えているなら、まずは境界を確定させてから。できれば、経験豊富な土地家屋調査士にも相談して、慎重に準備を進めることをおすすめします。時間も費用もかかるかもしれませんが、その分、将来の安心につながります。
分筆手続きや登記の際に費用負担がかかる
「二筆の土地に家を建てる」という選択肢には、思わぬ落とし穴があります。それが、分筆登記や境界確定にかかる費用です。手続き自体はシンプルに見えても、実際に動き出すと想定以上の出費が発生するケースが珍しくありません。
まずかかるのが登録免許税で、これは土地1筆あたり1,000円程度とごくわずか。しかし、本当に負担が重いのはそこではありません。問題は、土地家屋調査士に依頼する境界確定や測量作業です。すでに隣地との境界が明確であれば10~50万円ほどで収まることもありますが、もし境界が曖昧だったり、立ち合いが必要な場合には、60万~100万円近くまで跳ね上がることもあります。
実際、分筆を進めたものの、近隣との境界確認に時間を取られ、追加測量や書類のやり直しが発生した結果、予定より30万円以上オーバーしたというケースもあるほどです。
家を建てるための第一歩が、いきなり想定外の出費になるのは避けたいところ。分筆を前提にするなら、測量費や調査士報酬など実務コストの把握を早めに行い、複数の専門家に見積もりを取っておくことを強くおすすめします。最初の一手でつまずかないためにも、計画段階から慎重に費用を見極める姿勢が肝心です。
二筆の土地を合筆して家を建てるメリット5選
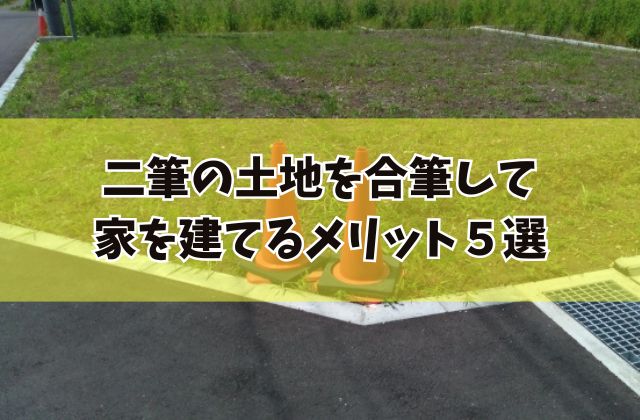
二筆の土地に家を建てる前に、合筆という方法を選ぶ方も増えています。
土地を一体化することで管理がしやすくなり、将来の相続や売却にも備えやすくなる点が大きな利点です。
ここでは、その具体的な二筆の土地を合筆して家を建てるメリット5選をわかりやすく紹介します。
選択の参考になるよう、実用的な視点から解説していきます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 土地をまとめて管理が楽になる | 複数の地番を一つにすることで管理が一元化され、将来的な手続きや管理負担が軽くなります。 |
| 登記識別情報が一つになり手続きが簡単になる | 合筆によって登記識別情報が統一されるため、売買や相続の手続き時に書類が少なく済みます。 |
| 固定資産税評価額が下がり税負担軽減の可能性がある | 土地の形状や面積によっては、合筆によって評価額が調整され、結果的に税負担が軽くなる場合があります。 |
| 契約や売買のときに書類作業が簡略化される | 合筆により地番が一つになるため、売買契約書や登記申請書類が簡潔になり、説明や手続きもスムーズになります。 |
| 将来の土地活用や売却がしやすくなる | 土地が一筆にまとまっていれば、活用の自由度が高まり、不動産会社からも資産価値が評価されやすくなります。 |
土地をまとめて管理が楽になる
「登記簿が一つで済む」──この違い、地味に見えても日々の管理では大きな差になります。たとえば二筆の土地を別々に所有していると、登記情報の取得や名義変更のたびに書類は2倍、費用も2倍。固定資産税の納税通知も別々に届きますし、ちょっとした手続きでもその都度手間がかかってしまいます。
ですが、合筆すれば話は変わります。登記識別情報(いわゆる「権利証」)は1通で済みますし、税金の納付書も一体化。手続きのたびに複数の地番を確認したり、管理表を作り直したりする必要がなくなるため、実務的なストレスが大幅に軽減されます。
特に将来的に相続や売却を見据えている場合、土地がまとまっている方が扱いやすく、買い手や相続人にとってもわかりやすい資産になります。手続きの効率だけでなく、資産価値という面でもメリットがあるのが合筆の大きな魅力です。
登記識別情報が一つになり手続きが簡単になる
二筆の土地を一つにまとめる“合筆”には、書類の管理がグッと楽になるという、見逃せない利点があります。というのも、登記識別情報(いわゆる権利証)は、土地一筆ごとに個別に発行されるため、二筆のままだとそれぞれ別々に保管し、手続きのたびに両方を用意する必要が出てきます。
ところが、合筆して登記を一本化すると、新しく発行される登記識別情報は1通のみ。つまり今後の売却や名義変更などの場面で「どっちの土地の書類だったっけ?」と探す手間がなくなり、何かと煩雑な手続きを一枚の書類で済ませられるようになるのです。
実際、司法書士や不動産実務の現場でも「合筆しておいてよかった」と実感されるポイントの一つがこの登記識別情報の簡素化。特に相続や売却の際、手続きがスムーズに進むかどうかは、この1通の書類にかかっているといっても過言ではありません。
土地を一つにまとめることは、面積が変わらない以上、ぱっと見ではわかりづらいメリットかもしれません。ただ、見えにくいからこそ後になって効いてくる──それが、登記識別情報を一本化できる合筆の真価です。
固定資産税評価額が下がり税負担軽減の可能性がある
土地を合筆すると管理がシンプルになる反面、分筆のまま所有することが節税につながるケースもあるというのは、あまり知られていません。
たとえば、二筆のうち一方が変形地だったり、道路と接していなかったりすると、その土地の評価額は低く見積もられやすくなります。形が悪い土地や接道条件の悪い土地は、使いにくい分だけ価値が下がる。これは、不動産の評価基準として当然の話です。実際に、旗竿地のような細長い形状になった結果、評価額が減額された事例も確認されています。
つまり、土地を分けたままの状態で維持しておくほうが、結果として固定資産税の負担が軽くなる可能性があるのです。ただし、この効果を狙って分筆する場合は、税理士や土地家屋調査士など専門家への相談は欠かせません。
「分けるか」「まとめるか」で迷ったときは、節税という視点も持って、土地の形状や立地条件を一度じっくり見直してみると良いでしょう。それだけで毎年の税負担が変わってくるかもしれません。
契約や売買のときに書類作業が簡略化される
土地を二筆から一筆に合筆すると、あとあとラクになる場面が意外と多いです。とくに売買契約や相続など、「土地にまつわる書類手続き」でその効果を実感することになります。
たとえば、不動産の売却時には登記情報を確認する機会が必ず出てきますが、二筆のままだと、それぞれの地番について登記事項証明書を取り寄せたり、抵当権の有無を調べたりと、ひとつずつ確認作業が必要です。その点、合筆しておけば、手続きは一筆分で済むので、書類の枚数もチェック項目もグッと減ります。
司法書士や不動産会社に頼む場合も、筆数が少ない方が当然スムーズですし、ミスや手戻りのリスクも抑えられます。実務の現場では「合筆されていて助かった」と安堵するケースが多いのも事実です。
つまり、目に見えるコストだけでなく、“後々の煩雑さ”を未然に防げるのが、合筆の隠れたメリットなのです。
将来の土地活用や売却がしやすくなる
「この土地、あとでどう使うかはっきり決まっていないけれど…」とお考えなら、合筆は一つの有効な選択肢です。土地を一筆にまとめておくことで、将来的に活用や売却を検討する際に“扱いやすい資産”として機能するからです。
合筆しておけば、登記の情報もすっきり一枚にまとまり、契約時に必要な資料や説明がグッと簡単になります。不動産会社からの評価も、バラバラの小さな土地より、一体になった土地の方がスムーズに進む傾向があります。面積や形状が整っていれば、それだけでも買い手の印象は良くなるものです。
たとえば相続が発生したとき、合筆済みの土地であれば、遺族が混乱することなく処理できますし、いざ手放すとなったときも話が早いです。資産としての見せ方が整っていると、売却のタイミングでも有利になりやすいのです。
将来を見据えたとき、「管理しやすい=売りやすい・活用しやすい」に直結します。家を建てる前に少し手間をかけてでも、長い目で見ればその価値は十分にあるはずです。
二筆の土地を合筆して家を建てるデメリット5選

土地をまとめる「合筆」は管理や活用の面で多くの利点がありますが、良いことばかりではありません。
実際には合筆によって将来の選択肢が狭まる場面もあります。
そこで、二筆の土地を合筆して家を建てるデメリット5選をまとめました。
よく見落とされがちな落とし穴や後悔につながるポイントについて、具体的に解説します。
家づくりを進める前に、判断材料として一度目を通しておくことをおすすめします。
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 合筆後は元に戻せない | 合筆してしまうと、分筆に比べて元の状態に戻すには手間や制限が多く、再分筆が困難になるケースが多いです。 |
| 土地を一部だけ売却しづらい | 合筆した土地は一体として登記されるため、一部分だけを切り離して売却する際に新たに分筆が必要となり、手続きや費用が発生します。 |
| 担保にできる範囲が限定される | 合筆後は1筆の土地として扱われるため、土地の一部だけを担保に設定することが難しくなります。 |
| 手続き費用や時間がかかる | 合筆には登録免許税や司法書士報酬などの費用が必要で、手続き完了までに数週間を要する場合もあります。 |
| 固定資産税の変動リスクがある | 評価基準が変わることで、想定外に固定資産税が上がる可能性があり、事前に予測しにくい点がネックです。 |
合筆後は元に戻すことが難しくなる
土地を一筆にまとめてしまうと、後から「やっぱり分けておけばよかった」と思っても、そう簡単には戻せません。合筆は確かに管理が楽になりますが、一度まとめた土地を再び二筆に分けるには、分筆登記という厄介な手続きが必要になります。
具体的には、土地家屋調査士に依頼して測量をやり直し、必要なら隣地との境界確認も再度行わなければなりません。時間も費用もかかる上に、手間も少なくないのが現実です。仮に一部を売却したいとなった場合でも、合筆済みだと身動きが取りづらくなってしまいます。
もちろん、将来的にも土地をまとめたまま使うのであれば問題はありません。ただし、「将来のことはまだ分からない」と思っているなら、安易に合筆してしまう前に、一度立ち止まって検討してみる価値はあります。合筆とは“戻れない道”になりかねないという点は、頭の片隅に置いておきたいところです。
土地を一部だけ売却しにくくなる
合筆登記をすると、土地全体がひとつの“まとまり”として扱われるようになります。その結果、もし将来一部分だけを売却したくなっても、そう簡単にはいきません。実際には、再び分筆登記を行う必要があり、そのためには専門家による測量や境界確定といった手続きが避けられません。
「とりあえず一筆にまとめておけばスッキリするし楽」と思いがちですが、あとから「この端の土地だけ売れたら助かるのに…」という状況になっても、分けるために費用と時間がかかってしまいます。測量費や登記費用などで数十万円かかるケースもあるため、軽くは考えられません。
土地を合筆するかどうかは、今の管理のしやすさだけでなく、将来どんな使い方をする可能性があるかまで見据えて判断する必要があります。「後から切り分ければいいや」と考えるのは危険です。先を見越した計画を立てた上で、合筆するかを慎重に選ぶことが大切です。
担保提供できる土地が限定される
合筆した土地を担保に出す予定があるなら、少し立ち止まって考えてみてください。一見、土地がひとまとめになってスッキリするように思えますが、将来、部分的に担保に入れたいときに柔軟な対応ができなくなる可能性があるからです。
たとえば、複数の筆を合筆して一筆にすると、その土地全体に一つの登記情報が適用されます。このとき、もし過去に設定された抵当権が一部の土地だけにある場合でも、登記の内容(受付番号や原因など)が一致していれば合筆できてしまい、その抵当権が全体にかかるという形になってしまうことがあります。
結果的に、「この部分だけを担保にしたい」「一部だけ売却したい」と思っても、それが難しくなるのです。土地の使い道に自由度を残したい場合や、融資時にフレキシブルな対応を望むなら、合筆がかえって足かせになることもある。だからこそ、合筆の前には、将来の計画や担保の必要性を見越して、専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。
合筆にかかる手続き費用や時間の負担になる
土地を二筆から一筆にまとめる「合筆登記」。確かに管理は楽になりますが、その裏には見えにくい手間と費用の負担が潜んでいます。
まず費用の話から。合筆には登記手続きが必要で、土地家屋調査士に依頼すると、おおよそ5万~6万円程度が相場です。加えて、登録免許税として1,000円がかかります。これだけなら「まあそんなものか」と思うかもしれませんが、実際はこれだけで終わりません。公図や地積測量図の取得費用、申請時の書類作成代、さらに郵送や交通費まで含めると、合計で数万円単位の出費になることも珍しくありません。
さらに、時間も意外とかかります。スムーズにいって2週間程度ですが、必要書類がそろわなかったり、地番の確認に手間取ったりすると、1ヶ月以上かかるケースもあります。現地調査が必要になれば、さらに日数がのびる可能性もあります。
つまり、合筆は「ただまとめるだけ」の簡単な作業ではなく、費用・時間ともにそれなりの負担を伴う工程です。思いつきで動くよりも、まずは専門家に相談して見積もりを取り、自分の計画にとって本当に必要な手続きかどうかを見極めてから動くのが賢明です。
税評価や固定資産税への影響が予測しにくい
土地を合筆すれば管理が楽になる——たしかにそれは事実です。ただ、合筆によって思わぬ“見えないコスト”が出てくることもあります。その代表格が、税評価や固定資産税の変動リスクです。
たとえば、もともと単価の違う2つの土地を一つにまとめた場合、評価額の計算がややこしくなります。合筆前はそれぞれ個別に評価されていたものが、合筆後は一体として扱われ、評価の基準や方法が変わることがあるからです。自治体によっては、面積が広がった分、接道条件や形状などが変わり、結果として税額が上がる可能性もあります。
実際に、「合筆したら税金が下がると思っていたのに、逆に高くなった」という声も少なくありません。
なぜこんなことが起きるのかというと、固定資産税の評価方法は必ずしも単純な「面積×単価」ではなく、道路への接し方や土地の奥行き、形のバランスなど、さまざまな要素が組み合わさって決まるためです。そして、その“さじ加減”は市町村ごとに異なるのが現実です。
結局のところ、合筆すれば得か損かというのは、ふたを開けてみないとわからない部分も多いです。だからこそ、不動産の専門家や税理士に相談してから進めることを強くおすすめします。税金の話はあとから気づいても遅いことが多いので、慎重に判断したいところです。
二筆の土地に家を建てる前に合筆登記する注意点
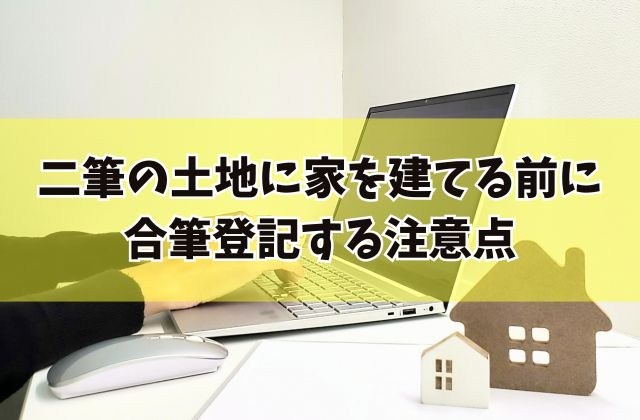
二筆の土地に家を建てる場合、事前に合筆登記を検討する人も少なくありません。
ただし、土地の状態や所有関係、権利の有無などによっては、スムーズに手続きが進まないこともあります。
事前に「二筆の土地に家を建てる前に合筆登記する注意点」を押さえておけば、予期せぬトラブルを防ぎ、より安心して家づくりを進められます。
ここでは、合筆登記する際に確認すべきポイントを5つ紹介します。
土地が隣接しているか確認する
二筆の土地を合筆したいと考えたとき、まず最初に確認すべきなのが「本当に隣り合っているかどうか」です。たとえ登記上は並んで見えていても、わずかでも他人の土地や道路を挟んでいると、法律上は合筆できないのです。
実際、法務局では“隣接していること”を合筆の必須条件としています(出典:参考資料)。極端な例ですが、角と角が「点」で接しているだけではダメです。接しているようで接していない——そんな微妙なケースが現場では珍しくありません。
判断に迷うときは、公図や現地を目で見て確認し、さらに境界杭が見つからない場合には測量を依頼しましょう。登記手続きをスムーズに進めるためには、ここを見落とさないことが肝心です。結果的に、後のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
所有者や持分が全て一致しているか確認する
土地を合筆するとき、意外と見落とされがちなのが「誰がどのくらいの割合で持っているか」という点です。合筆は、ただ地続きであればできるという話ではありません。所有者が同じで、しかも持分の割合まで完全に一致していなければ、法務局で手続きを受け付けてもらえないというルールがあるのです(出典:不動産登記法第41条)。
たとえば、隣り合う2筆の土地があって、どちらもAさんとBさんの共有名義だったとします。一方はAさんが半分、もう一方はAさんが6割持っている…という状況では、登記上「別の人が所有している土地」と判断され、合筆はできません。
このトラブルを避けるためにも、手続きに入る前に登記事項証明書を確認し、所有者の名前と持分割合がすべての土地で揃っているかを細かくチェックしておきましょう。もしズレがあるなら、持分を調整する登記を事前に済ませる必要があります。
あとで慌てることがないように、書類の段階で一致しているかをしっかり確かめておくこと。それが、スムーズな合筆の第一歩です。
抵当権など権利付き土地かどうか確認する
合筆登記を進める前に、ひとつだけ見落としてはいけないポイントがあります。それは「土地に抵当権などの権利が付いていないかどうか」。意外と忘れがちですが、ここを無視してしまうと手続きが途中でストップしてしまう可能性もあるのです。
実際のところ、抵当権が設定された土地は原則として合筆できません。ですが例外もあります。たとえば、二筆の土地にまったく同じ内容の抵当権が設定されていて、登記の受付番号や原因日付も一致していれば、合筆が認められるケースもあるのです。これは「不動産登記規則」によって細かく定められています。
ただし、この条件を自力で判断するのはハードルが高いです。だからこそ、登記事項証明書を取り寄せて、権利関係の記載をしっかり確認すること。そして、少しでも不明な点があるなら、迷わず司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。後になってトラブルになるくらいなら、最初の一歩で慎重すぎるくらいがちょうどいいのです。
登録免許税や手数料の負担に注意する
合筆登記は見た目にはシンプルな手続きに思えますが、実際に動き出すと意外と費用がかさむことがあります。とくに注意したいのが、登録免許税や申請時に発生する各種手数料です。
合筆の登録免許税は、土地一筆あたり1,000円と定められています。たとえば二筆の土地を一筆にまとめる場合でも、まとめたあとの一筆分1,000円が課税対象です。これだけ聞けば「大した金額じゃない」と思いがちですが、登記所での窓口申請には1件につき600円、オンライン申請でも500円前後の手数料が加わります。
さらに忘れがちなのが、公図や地積測量図、印鑑証明書などの取得にかかる実費。書類1通で数百円でも、何通も必要になればまとまった金額になります。もし境界があいまいで測量士に依頼するとなると、報酬が数万円かかることも珍しくありません。
費用は「ちょっとずつ」増えていき、気づけば数万円単位の出費になることも。後で慌てないためには、事前に必要な書類と費用を洗い出し、できれば専門家にも相談して見積もりを取っておくことが安心です。
合筆には共有者全員の同意が必要か確認する
土地を合筆する際にひっかかりがちな盲点が、「誰の同意が必要か」という点です。特に共有名義の土地では、話がスムーズに進むかどうかはここで決まるといっても過言ではありません。
以前は、合筆するには共有者全員の合意が大前提でした。ですが、2023年の法改正により、合筆や分筆といった軽微な変更に関しては、持分の過半数を押さえれば手続きできるようになりました(出典:参考資料)。つまり、全員の印鑑がなくても登記が進められるケースがあるということです。
ただし、誤解してはいけないのは、これはあくまで「登記上」の話。現実には、のちのちのトラブルを避けるためにも、全員に内容を説明し、きちんと理解と納得を得ておくのが理想です。たとえば相続人が複数いるケースなどでは、同意の取り方一つで信頼関係が崩れることもあります。
登記事項証明書を確認して、持分割合や所有者を事前にしっかり洗い出しておく。そして必要に応じて司法書士などの専門家に相談する。これが、後悔しない合筆手続きの基本です。
【無料】家にいながら理想の土地を効率良く探す方法

「理想の土地がなかなか見つからず、そもそもどこから探せばいいのか分からない」
「二筆の土地を購入するべきか、合筆するべきか、判断の決め手がなくて迷っている」
「費用や手続きの不安が多く、どの段階で専門家に相談すべきかタイミングが分からない」
あなたも、上記のように悩んではいませんか?
条件に合う土地を探すのは至難の業。しかも土地は“見えないリスク”が多く、買ってから失敗に気づいても手遅れ。
でも実は、そんな悩みを解決する家にいながら理想の土地を効率良く探す方法があります!
それが、540,000人以上が利用した“複数社から一括で”土地情報をもらえる『タウンライフ家づくり』です。
「タウンライフ家づくり」とは、土地の希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや不動産会社から土地情報や間取りプランが無料でもらえる一括依頼サービスです。
- 土地+間取り+資金計画をまとめて受け取れる!
間取りや資金計画の希望に沿った土地情報を一括で受け取れるので、効率的に家づくりを進められる - 非公開・未公開の土地情報も手に入る!
ネットに出ていない掘り出し物件や、ハウスメーカー独自の好条件土地情報まで、比較検討の選択肢が広がる - ネット完結だから手間も時間も大幅節約!
スマホやPCから3分の簡単依頼で、自宅にいながら複数社の資料を比較できるから、住宅展示場に通う負担を軽減できる
さらに!タウンライフ家づくりを利用すれば、土地情報だけでなくハウスメーカーから住宅カタログと間取りプランも届く!
筆者も実際にサンプルを受け取りましたが、図面を眺めながら「家族の動線はこうかな」「家具の配置は?」と、家づくりのイメージが一気に膨らみました。
家を建てる第一歩は“いい土地探し”から。今すぐ無料で、プロが選んだ土地情報と間取りプランを比べてみてください。
【Q&A】二筆の土地に家を建てることに関するよくある質問
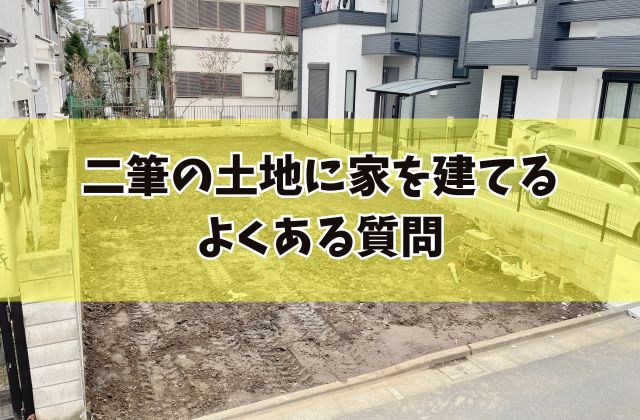
最後に二筆の土地に家を建てることに関するよくある質問をまとめました。
よくあるポイントをわかりやすく解説します。少しでも不安を減らし、スムーズに準備を進められるようお役立てください。
土地を2筆売却できますか?
2筆ある土地、それぞれを別々に売ること自体は可能です。ただし注意点があります。もし2筆のうちどちらか、あるいは両方が共有名義になっている場合、勝手に売ることはできません。必ず全員の同意が必要です。
さらに、売却前に「分筆登記」などを行って、所有関係や境界を明確にしておくと、トラブルを避けられます。自分の名義であっても、土地の評価や法的な制限によってスムーズに売れないケースもあるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
2筆の土地の評価はどうなりますか?
評価は土地ごとに異なり、2筆を合わせたからといって単純に足し算で終わる話ではありません。道路との接道状況、形の良さ、面積の広さなど、様々な条件が複雑に絡み合って評価額が決まります。
時には「合筆したらむしろ評価額が上がって、税金が増えた」なんてケースもあります。つまり、損得は一概に言えないんです。固定資産税や相続税にどう影響するのか、事前に役所や税理士に確認しておくと安心ですよ。
2筆にまたがる土地で建ぺい率の計算はどうなる?
2筆の土地にまたがって家を建てる場合、建ぺい率や容積率の扱いがどうなるかは重要なポイントです。合筆して一筆にすれば、全体面積に対して計算できますが、用途地域が異なれば「加重平均」での扱いになります。
つまり、思っていたほど建物の大きさが取れない可能性があるということ。特に狭い土地や変形地では、わずかな違いが設計に影響するので注意が必要です。建築士や不動産会社と早い段階で相談しながら進めるのが賢明です。
2つの地番にまたがって家を建てることは法律上問題ない?
結論から言えば、2つの地番にまたがる土地に家を建てること自体は、法律で禁止されているわけではありません。
とはいえ、実務上は合筆して一つの地番にしてから建てるケースが圧倒的に多いです。そのほうが、登記手続きや建築確認申請などもスムーズに進みます。
もし合筆せずに進めたい場合でも、隣接状況や権利関係の整合性を取っておかないと後々トラブルの原因になります。建てる前に必ず専門家にチェックしてもらいましょう。
個人が分筆した土地は2つ以上売り出すことができないのはなぜ?
「土地を分けたのに、なんで自由に売れないの?」と疑問に思う方も多いですが、理由は主に法規制やインフラ整備の制限にあります。
特に私道にしか接していない土地や、再建築できない土地を分筆して売ろうとすると、買い手が見つからないだけでなく、行政からの指導が入ることも。
さらに、税務上の問題や固定資産税の増額など、予期せぬコストがかかることもあります。売る前に、「この土地は法的に“売っていい土地”かどうか」を、必ずチェックしておくことが大切です。
まとめ:二筆の土地に家を建てるメリットデメリットと注意点
二筆の土地に家を建てるメリットデメリットと注意点をまとめてきました。
改めて、二筆の土地に家を建てる際に押さえておきたいポイントをまとめると、
- 二筆の土地は建築前に登記や所有権の確認が必要
- 土地が隣接していなければ合筆できないので事前の現地確認が重要
- 共有名義の場合、持分の過半数で合筆登記は可能だが、全員の理解が望ましい
- 抵当権が設定されている土地は、金融機関の承諾など登記時に手続きが煩雑になる
- 合筆には登録免許税や手数料などのコストがかかるため資金計画を立てておく
「二筆の土地に家を建てる」という選択には、手続きや登記の面でいくつかのハードルがあります。
しかし、正しい知識を持って備えれば、スムーズに進めることができます。特に登記や所有者の確認、抵当権の有無などは後回しにせず、早めに整理しておくことが成功への近道です。